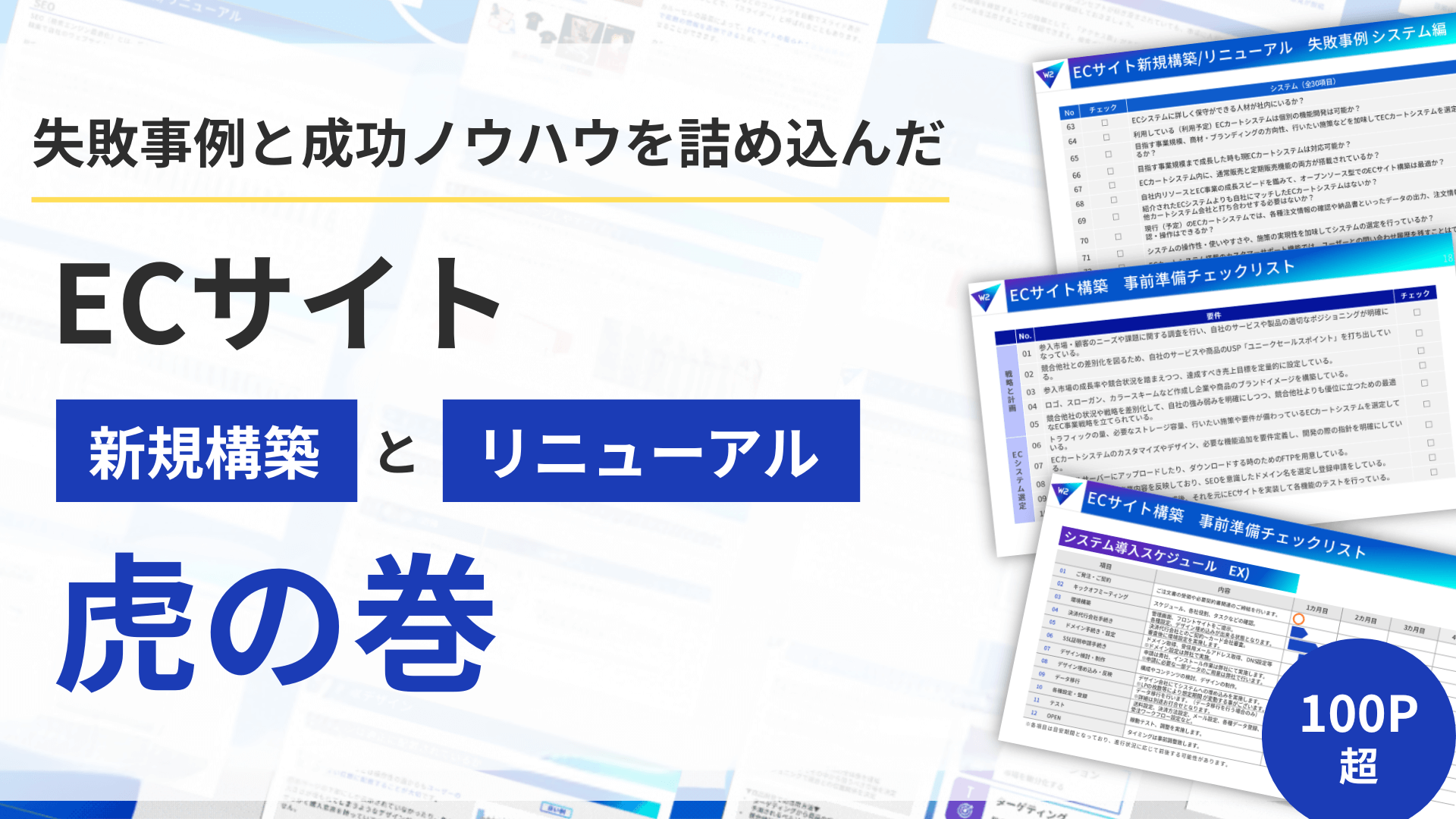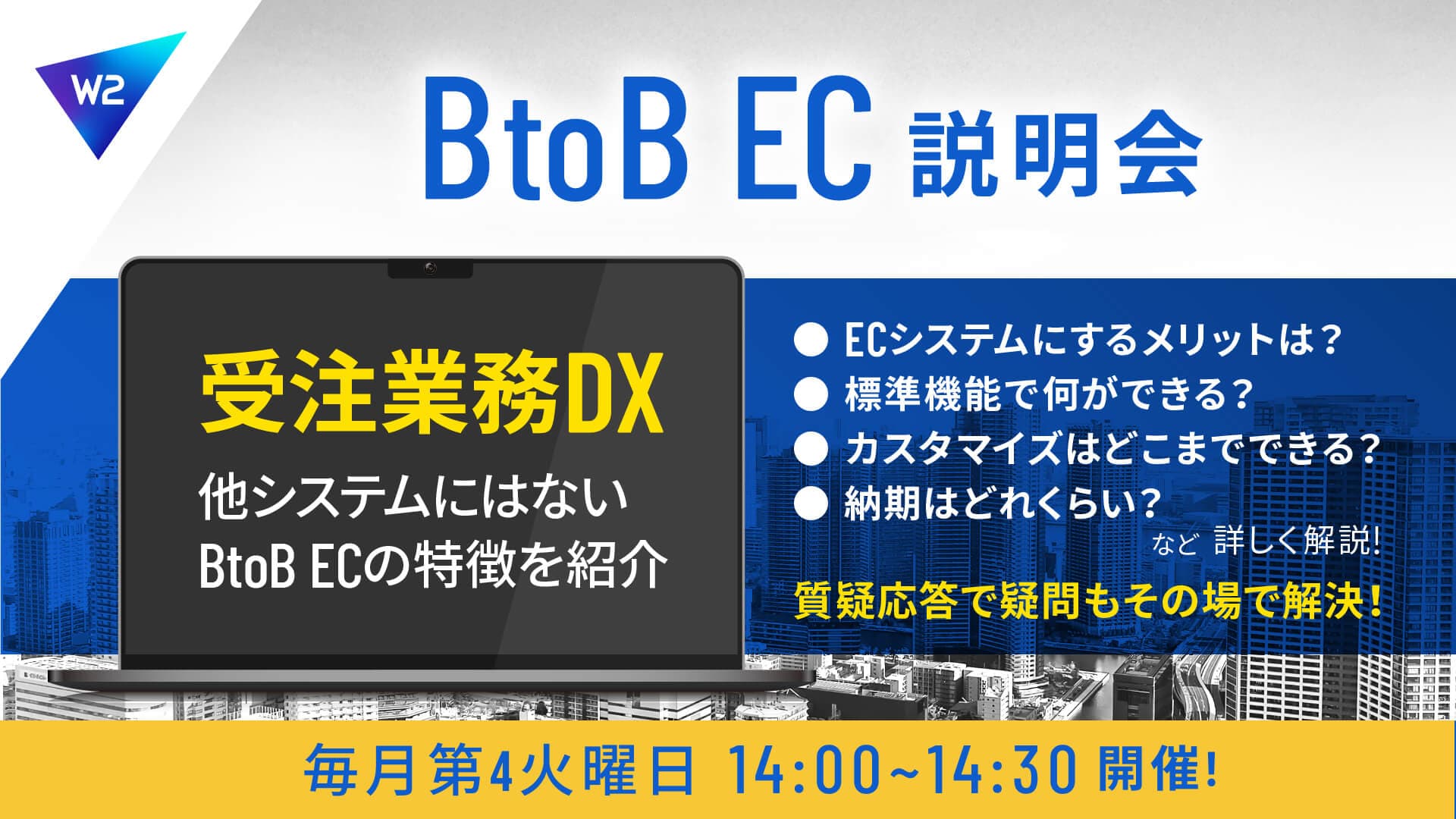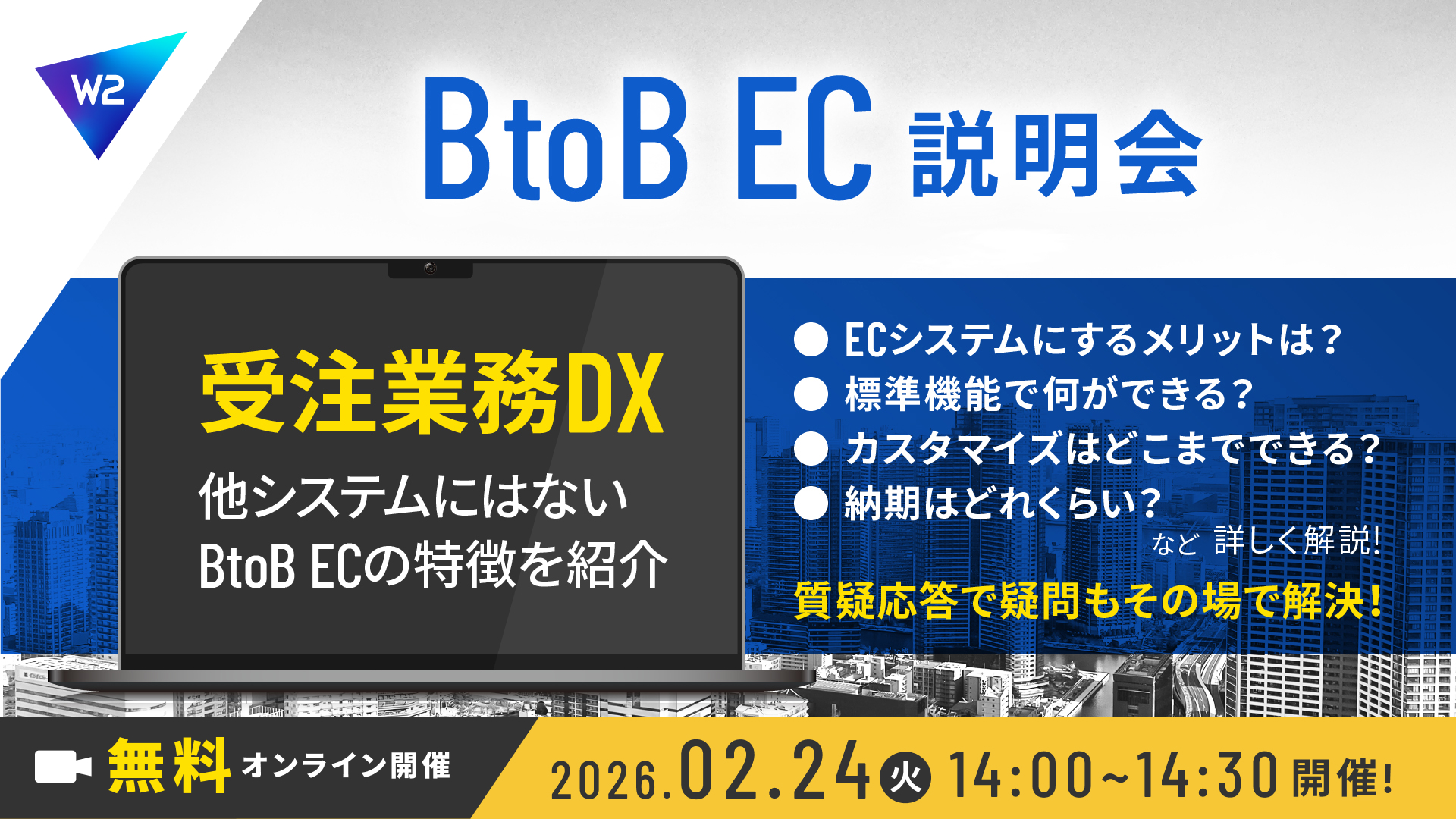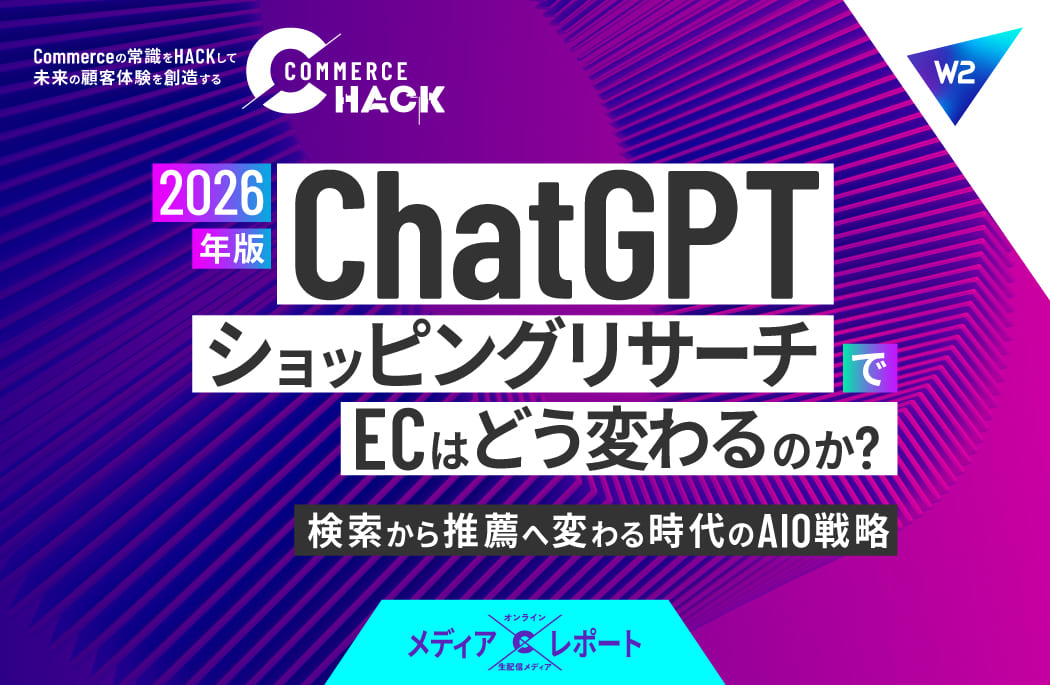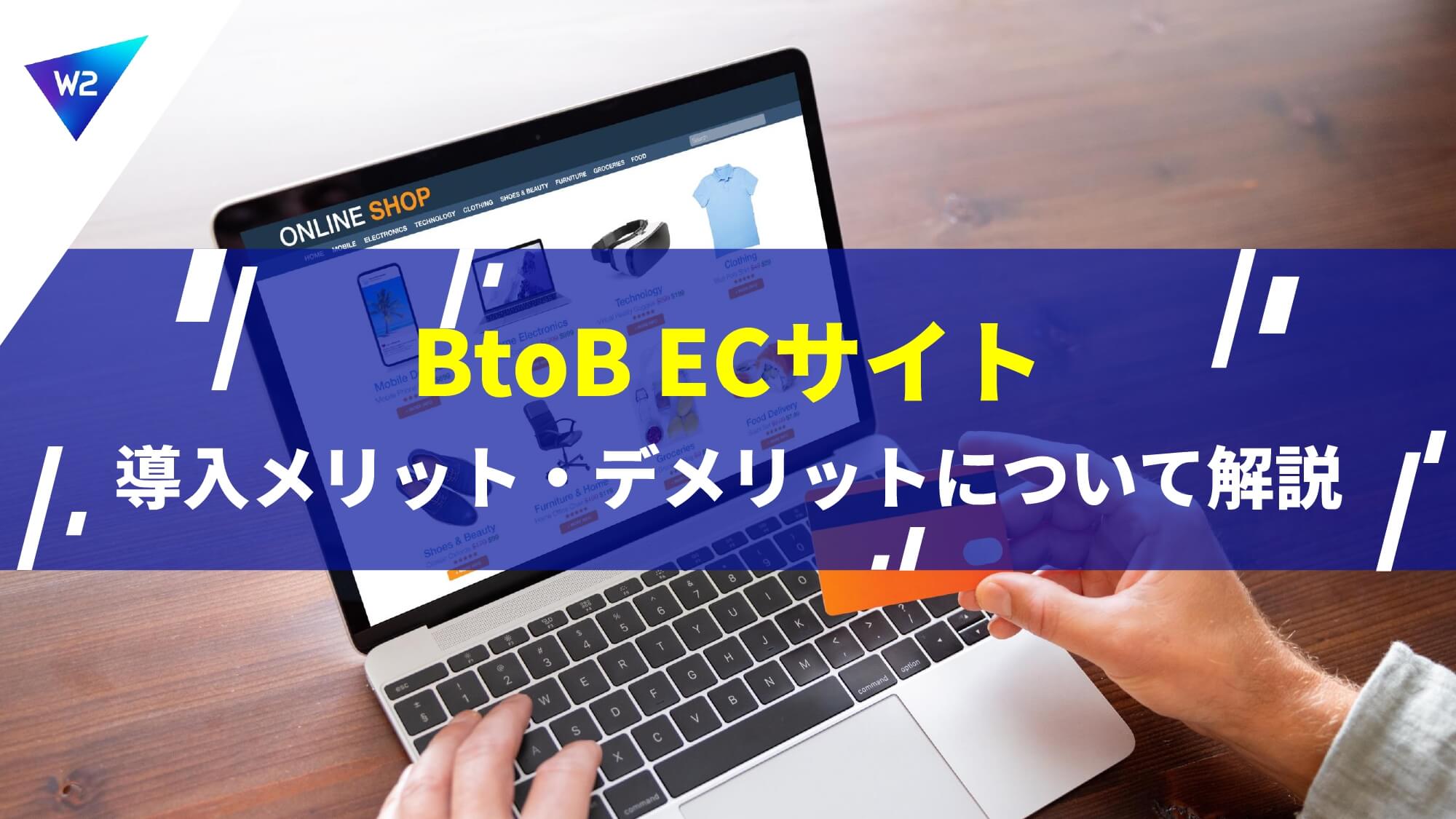
BtoB EC(企業間電子商取引)のニーズは年々高まり、市場規模も急速に拡大しています。特に受発注業務の効率化や売上拡大といったメリットから、多くの企業がBtoB ECの導入を進めています。
一方で、BtoB ECシステムには「ASP型」「パッケージ型」など複数の種類があり、自社に合ったシステムを選ぶには、BtoB ECの基本的な特徴や種類ごとの違いを理解することが不可欠です。
本記事では、BtoB ECの基本知識に加え、2026年最新の市場規模や導入のメリット・デメリット、必要な機能、主要な構築方法、そしておすすめのBtoB EC構築プラットフォームまでをわかりやすく解説します。
受発注業務の効率化を目指す方や、BtoB ECサイトの導入を検討中の方はもちろん、新規導入やリプレイスを検討している企業の担当者の方も、ぜひご一読ください。
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
- 01|BroB EC(企業間取引EC)とは?基礎知識を5分で理解
- 02|BtoB ECとその他ECとの違い
- 03|BtoB ECにおける最近のトピック
- 04|【2026年最新】BtoB ECの市場規模とEC化率の動向
- 05|BtoB ECの市場規模と業種別EC化率
- 06|BtoB EC成長を支える4つの要因
- 07|BtoB ECサイトの種類
- 08|BtoB ECサイトの導入メリット4選
- 09|BtoB ECサイトの導入デメリットと対策
- 10|BtoB ECサイトに必要な機能
- 11|BtoB ECサイトの主な構築方法5選
- 12|BtoB EC導入前のチェックリスト
- 13|BtoB ECサイト構築を構築するなら「W2 BtoB」
- 14|W2システム導入で成功したBtoB ECサイトの事例
BroB EC(企業間取引EC)とは?基礎知識を5分で理解

BtoB(Business-to-Business)EC(Electronic Commerce)とは、企業間取引をオンライン上で行う電子商取引のことを指します。
従来の電話やFAXによる受発注業務を、インターネット上のWebサイトやシステムを通じて行うデジタル化された取引形態です。企業が他の企業に対して製品やサービスを販売する際に活用されるシステムで、「Web受発注システム」 と呼ばれることもあります。
BtoB ECの基本的な仕組みは以下の通りです:
- 商品カタログの公開:取引先企業向けにWebサイト上で商品情報を掲載
- オンライン受発注:Web画面から注文・見積もり依頼が可能
- 価格・在庫連携:基幹システムと連携したリアルタイム情報提供
- 承認ワークフロー:企業内の承認プロセスをシステム化
- 決済・請求処理:掛け払いや請求書発行の自動化
BtoB ECの特徴として、取引量が大きく、契約内容が複雑であることが挙げられます。さらに、価格交渉や納期調整など、対人でのやり取りが必要となるケースが多く見受けられます。
そのため、BtoC ECやCtoC ECと比較して、取引に関わるプロセスが多岐にわたり、質の高いサービスが求められることが特徴です。
EDI(電子データ交換)との違い
EDI(Electronic Data Interchange) は、企業間で標準化されたフォーマットを用いて文書やデータを電子的に交換するシステムです。
注書や請求書などの書類を紙でやり取りすることなく、迅速かつ正確な情報交換を実現します。
| EDI | BtoB EC | |
| 主な目的 | 既存取引の効率化 | 販売拡大・新規顧客獲得 |
| 利用方法 | 専用ソフト・システム間連携 | Webブラウザからアクセス |
| 導入コスト | 高額(専用システム構築) | 比較的低額(クラウド活用可) |
| 柔軟性 | 取引先ごとに個別対応が必要 | 統一されたWeb画面で対応 |
| マーケティング機能 | 限定的 | 商品検索・レコメンド等が可能 |
EDI活用におけるISDN回線終了への対応
EDIは従来、NTTのISDN回線を使用することが一般的でしたが、NTT東西によりISDN回線(INSネット)の新規販売は2024年8月31日に終了し、サービス提供も2028年12月31日に完全終了する予定です。
そのため、多くの企業でWeb-EDIやインターネットEDIへの移行、またはBtoB ECシステムへの切り替えが急務となっています。
BtoB ECへ移行する企業が増加している背景については、その対価が挙げられます。
- 汎用性の高さ:特定の取引先に依存せず、幅広い企業との取引が可能
- マーケティング活用:商品検索や販促機能により新規顧客開拓が可能
- 運用コストの削減:クラウド型サービス活用による保守費用の軽減
- ユーザビリティ:直感的なWeb画面で取引先の習熟コストが低い
このように、BtoB ECは企業間取引のデジタル化と効率化を進める重要な手段として、今後さらにその重要性が高まる と考えられます。
BtoB ECとその他ECとの違い
ECシステムには、BtoB ECの他にもBtoC ECやCtoC ECなどがあります。それぞれの違いを「対象」と「取引の特徴」で整理しました。
| 取引主体 | 代表例 | |
| BtoB EC | 企業⇔企業 | メーカーと卸、卸と小売店 |
| BtoC EC | 企業⇔消費者 | Amazon、楽天市場、企業公式サイト |
| CtoC EC | 消費者⇔消費者 | メルカリ、ヤフオク!、ラクマ |
BtoB EC は「メーカーと卸問屋」「卸問屋と小売店・飲食店」などの商取引が主で、提供者・対象ともに企業・法人です。
BtoC ECは、いわゆるオンラインショップや通販サイトを指します。企業から一般消費者を対象に商品・サービスを提供します。独自ECサイトやAmazon・楽天市場などのECモール出店があります。
CtoC ECは、個人間取引や消費者間取引のことを指します。「シェアリングエコノミー」とも呼ばれ、不要品売買や個人スキル提供サービスが含まれます。
また、BtoE ECは、Business to Employeeの略で、自社従業員向けの販売を行います。社内販売や職域販売とも呼ばれます。
BtoB ECにおける最近のトピック
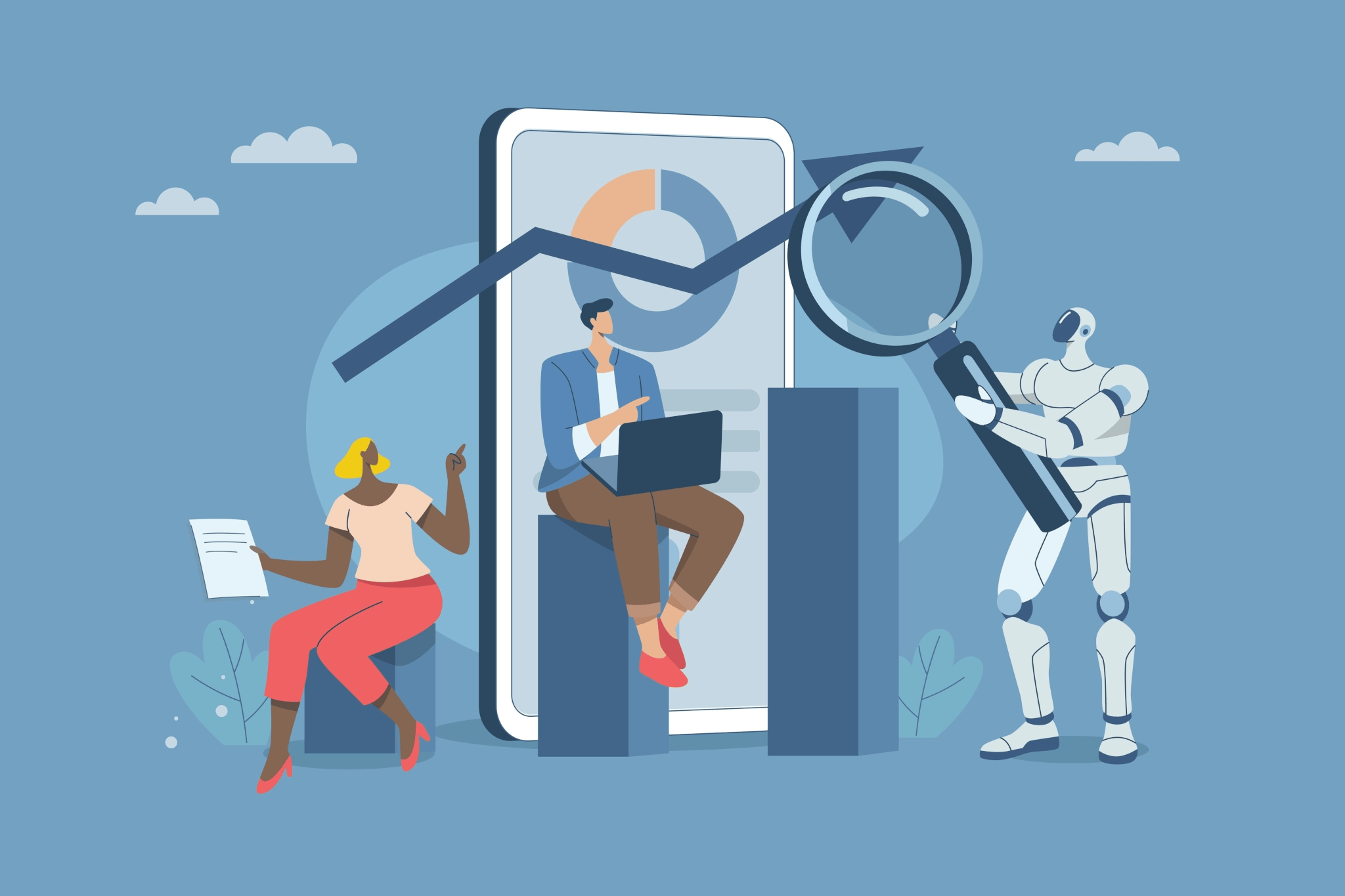
近年、企業間取引のWEB化を取り巻く環境は制度面・技術面の両方で大きく変化しています。
インボイス制度や電子インボイスの普及、DX推進による受発注のデジタル化、さらにはPSTNのIP網移行などが企業のEC導入を後押ししています。
ここから、BtoB ECの普及に影響を与える主要なトピックを3つ解説します。
インボイス制度への対応
2023年10月から開始されたインボイス制度により、BtoB ECシステムには適格請求書の自動発行機能や登録番号管理が必要となりました。
効率化の一環として、国際規格「Peppol」に準拠した日本版標準仕様「JP PINT」による電子インボイスの活用が推進されています。
DX推進とEC化率の向上
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、多くの企業で受発注プロセスのデジタル化が進んでいます。
特に製造業ではEC化率67.2%に達するなど、競合他社との差別化や業務効率化を目的としたBtoB EC導入が加速しています。
PSTN(固定電話網)のIP網移行
固定電話網(PSTN)のIP網への移行が進んでおり、これに伴いEDIシステムからBtoB ECへの移行も加速しています。
総務省の方針により、クレジットカード端末やPOSシステムなどの移行が順調に進んでいることが報告されています。
これらの制度的・技術的変化により、BtoB EC導入の重要性がますます高まっています。
【2026年最新】BtoB ECの市場規模とEC化率の動向
BtoB ECの市場規模と最新動向
経済産業省が2025年8月26日に発表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」によると、日本国内のBtoB-EC市場は著しい成長を遂げています。
2024年には市場規模が514.4兆円に達し、前年比10.6%の成長を記録しました。
EC化率も前年から3.1ポイント上昇して43.1%となり、企業間取引の電子化が急速に進展していることが明らかになりました。
この伸びは、2023年の市場規模465.2兆円、EC化率40.0%(2023年度調査)と比較すると顕著です。
また、2024年度のBtoC EC市場規模は約26.1兆円であるため、BtoB ECはBtoC ECと比較して十数倍以上の市場規模があるといえます。
BtoB ECの市場規模と業種別EC化率
| 業種 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 建設 | 15.2% | 16.9% | 18.3% |
| 製造 | 58.3% | 62.1% | 72.5% |
| 情報通信 | 22.3% | 23.4% | 24.2% |
| 運輸 | 20.9% | 22.5% | 24.9% |
| 卸売 | 34.9% | 37.5% | 40.3% |
| 金融 | 23.8% | 25.2% | 26.1% |
| サービス | 15.9% | 16.8% | 18.6% |
| 合計 | 37.5% | 40.0% | 43.1% |
※参考引用元:経済産業省『令和6年度 電子商取引に関する市場調査』
特に「食料品製造業」の総売上高は2024年に51兆1,341億円となり、BtoB-EC市場規模は41兆5,859億円(前年比17.0%増)を記録しました。 インバウンド需要の回復を背景に外食やホテルの利用が拡大したことに加え、原材料価格の高騰に伴う販売価格の引き上げが全体の市場規模を押し上げたことが要因と考えられます。 その結果、業務用食品の取引量が増加するとともにEC化の流れも一層加速し、EC化率は81.3%という非常に高い数値を示しました。
BtoB EC成長を支える4つの要因
BtoB ECの市場規模が成長している背景には、以下の要因が挙げられます。
- BCPの推進
- 働き方改革
- ITインフラの整備
- デバイスの普及
それぞれ詳しく解説していきます。
BCP推進による取引の安定化
近年、パンデミックや紛争、自然災害が発生したことによる資材調達難や原材料高騰、ライフラインの停止などが頻発しています。
これらの影響を受ける企業は少なくなく、ビジネスのグローバル化や気候変動が背景にあります。
このような不確実性の高い現代において、BCPの策定が推進されています。
BCPとは、災害や事故、パンデミックなどの緊急事態においても、企業活動を継続し、早期に正常な業務運営を回復させるための計画です。
BCPが推進されていることで、何か問題が発生して商談や取引が困難な状況下になった場合でも、BtoB ECが安定した供給網の維持や迅速な情報共有を可能にし、事業の継続性を確保するための有効な手段となっています。
その結果、BtoB EC市場の成長に大きく貢献しているのです。
働き方改革によるデジタル化促進
BtoB EC市場の成長において、働き方改革は重要な役割を果たしています。
働き方改革とは、2019年4月1日から順次施行されている政策で、従業員の労働環境を改善し労働生産性を向上させるための取り組みです。
この働き方改革がBtoB EC市場の成長に影響を与えています。
具体的にはテレワークの普及です。テレワークが普及したことでオフィス以外の場所でも業務を行うことが増えています。
これにより、オンラインでの商取引の需要が高まり、BtoB ECの利用が増加しています。
また、働き方改革が推進されていることで業務負担を軽減できるような仕組みが求められるようになりました。BtoB ECは受注プロセスを自動化し、紙ベースの書類を削減することができるので需要が高まり市場規模の成長に繋がっています。
ITインフラの整備
ITインフラの整備や普及は業務効率化を目指す企業にとって注目されており、結果的にBtoB EC市場規模の成長に繋がっています。
BtoC・CtoC EC では、ITインフラが整備されているにもかかわらず、BtoBビジネスにおいては業務工数がかかるアナログなやり取りが主流であったため、業務工数を削減できてデジタルを用いているBtoC EC市場の需要が高まったことで市場規模が成長する要因となっています。
加えて、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進などがBtoB ECの市場拡大を後押ししています。
これらの要因により、BtoB EC市場はより効率的でスムーズな取引が可能になり、市場規模の成長に寄与しています。
デバイスの普及
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどのデバイスが普及したことで、ビジネスパーソンが場所を選ばずにインターネットにアクセスしてWebサイトを操作できるようになりました。
これにより外出先や移動中でもBtoB ECサイトを利用できることで取引の機会が増加して市場規模の拡大に繋がっています。
また、モバイルアプリを活用した決済や受注システムや、リアルタイムで在庫情報を共有するサービスなど、新たなビジネスモデルが登場しています。
さらに、デバイスの普及により中小企業や地方の企業もBtoB EC市場に参入しやすくなり、市場全体が活性化し、成長が加速しています。技術の進化とともにデバイスの役割は今後さらに大きくなることが予想されます。
その他、様々なEC業界の市場規模を詳しく知りたい方は以下の記事で詳細に解説しています。この機会に是非ご一読ください。
BtoB ECサイトの種類
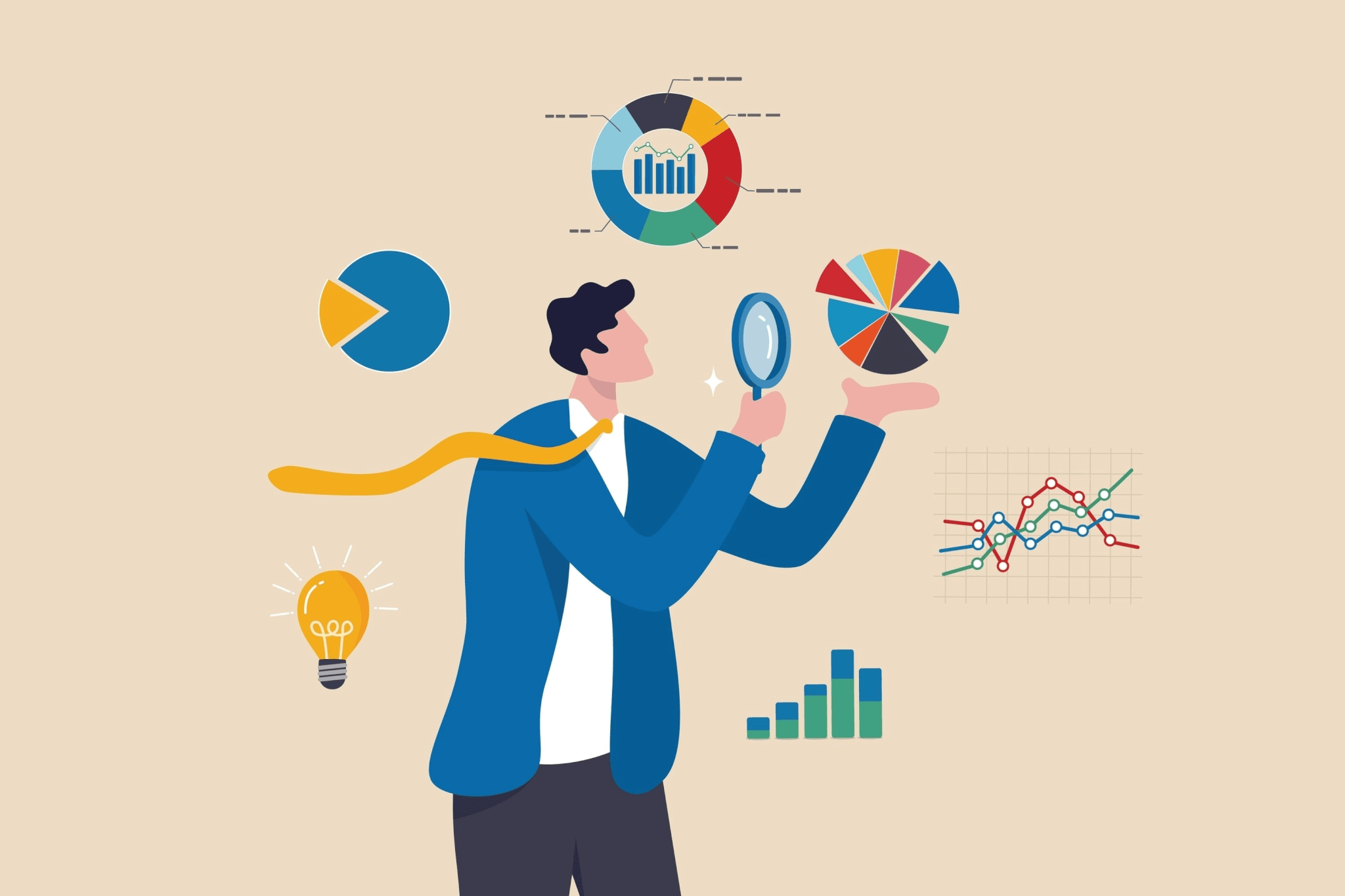
BtoB ECサイトには様々な種類がありますが、以下の代表的な3つのECサイトの種類について解説します。
- クローズド型BtoB ECサイト
- スモール型BtoB ECサイト
- マーケットプレイス型BtoB ECサイト
それぞれ詳しく解説していきます。
クローズド型BtoB ECサイト【既存取引先向け】
クローズド型BtoB ECサイトは、特定の企業や取引先のみがアクセスできる閉じられたECサイトです。アクセスには会員登録や認証が必要で、一般の消費者や非会員企業は利用できません。
このECサイトの特徴は、取引先ごとに異なるサービスや価格設定を提供できることです。また、セキュリティが高く、情報漏洩のリスクを抑えられるため、機密性の高い取引に適しています。
総じて、クローズド型BtoB ECサイトは、特定の業界やベンダー、サプライチェーン内での取引を円滑に行いたい企業に最適です。
スモール型BtoB ECサイト【新規開拓向け】
スモール型BtoB ECサイトは、中小企業やスタートアップ向けの小規模なECサイトです。
低コストで簡単に導入できることが特徴で、主に小規模な取引先との商取引や営業の効率化に利用されます。このタイプのECサイトは、基本的な受発注機能や在庫管理機能、出荷作業の簡素化といった必要最小限の機能に絞ることで、運用コストを抑えることができます。
また、利用者が少ないため、企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
ただし、事業が拡大するにつれて、ECシステムが大量のアクセスに耐えられず、サイトがダウンするリスクがあります。そのため、長期的な事業戦略を考慮した上で、スモール型BtoB ECサイトを選定することが重要です。
総じて、スモール型BtoB ECサイトは、初期投資を抑えつつBtoB取引のデジタル化を進めたい中小企業に適しています。
マーケットプレイス型BtoB ECサイト【多企業参加】
マーケットプレイス型BtoB ECサイトは、複数の企業が参加し、商品やサービスを提供するプラットフォームです。
多くの企業が参加することで、広範な顧客層にアプローチでき、新規顧客の獲得が容易になるほか、初期投資を抑えて大規模な市場に参入できるというメリットがあります。
さらに、プラットフォームの運営者が取引を管理しているため、セキュリティや信頼性を確保するための仕組みが整っている点も特徴です。
BtoB ECサイトの導入メリット4選
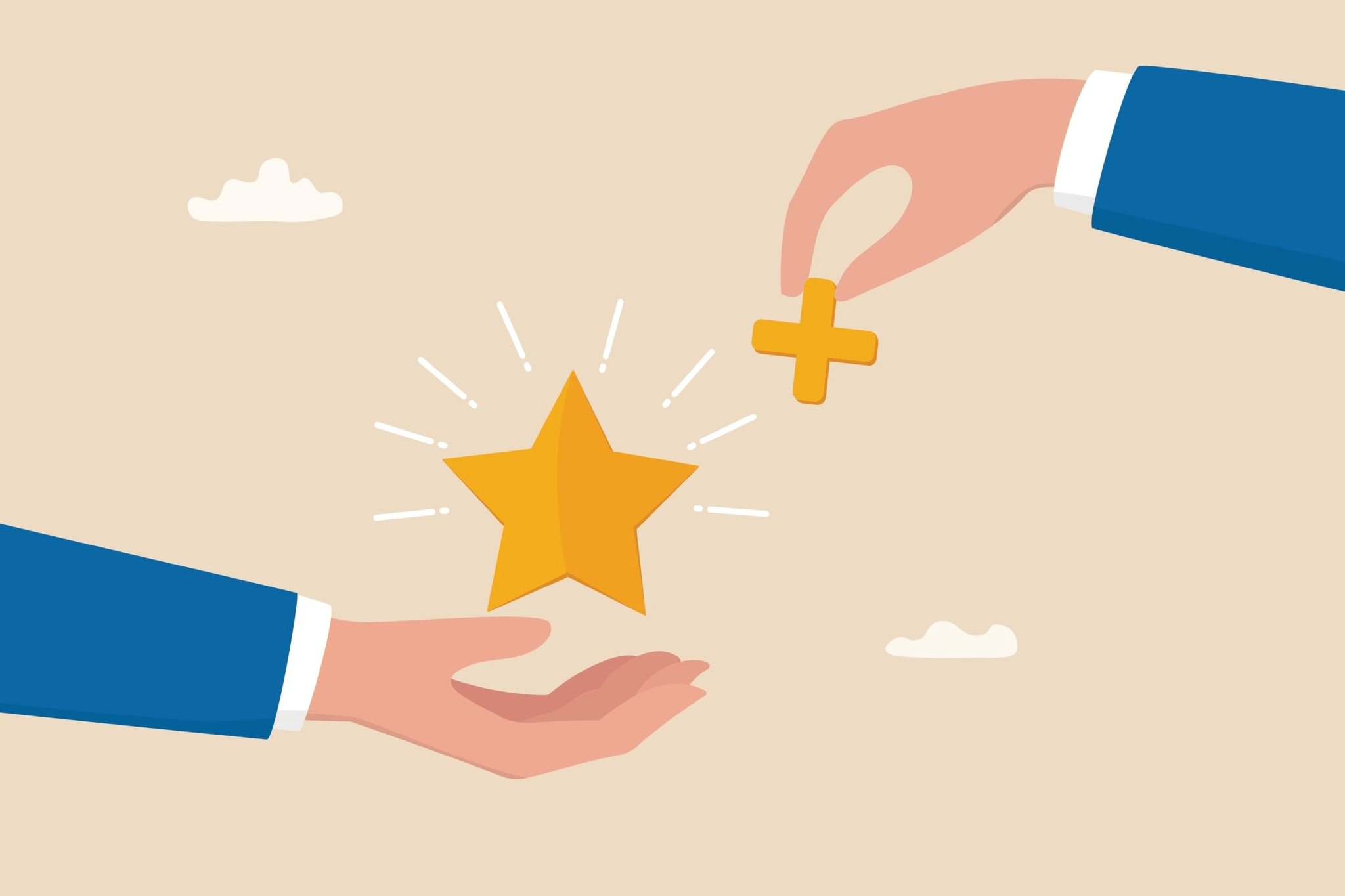
BtoB ECのメリットは、大きく分けて以下の4つに分けられます。
- 受発注業務の効率化
- 人的ミスの削減
- データ分析の活用
- 新規顧客の獲得
詳しく解説していきます。
受発注業務の効率化
BtoB ECに活用されるサイトやシステムは、従来の電話やFAX、メールベースの受発注プロセスを根本的に変革します。
受注から決済、在庫管理までを一元的に自動化することで、業務フローを大幅に簡素化します。
また、24時間365日の発注が可能となり、顧客の利便性を高めながら、企業側の業務効率も劇的に向上させます。さらに、在庫管理システムとの連携により、正確な在庫状況の把握と迅速な対応が可能となります。
人的ミスの削減
手作業による入力作業を自動化することで、転記ミスや入力ミスを大幅に減少させます。
受注データ、顧客情報、請求情報などを自動的にシステム連携することで、人間が介在することによる誤りのリスクを最小限に抑えます。
例えば、注文データの自動取り込み、在庫数の自動更新、請求書の自動生成などにより、従来の人手による作業で発生していた単純ミスを防止します。
これにより、コスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にも直結します。
データ分析による売上拡大
BtoB ECにおいてシステムを活用することで、豊富な受注・顧客データを蓄積し、戦略的意思決定を支援します。
顧客の購買傾向、最適な在庫量、季節変動、人気商品の分析などが容易に可能となります。
高度な分析ツールと連携することで、予測分析や最適な価格設定、マーケティング戦略の立案に活用できます。また、顧客ごとのカスタマイズされた分析レポートの提供や、個別の購買行動に基づいたレコメンド機能の実装も可能となり、顧客との関係性強化にも貢献します。
新規顧客の獲得
オンライン取引の特性を活かし、地理的制約を超えた新規顧客開拓が可能となります。
例えば、SEO対策や効果的なデジタルマーケティングにより、従来のアプローチでは難しかった潜在顧客へのリーチが可能になります。
また、商品情報の透明性、詳細な仕様説明、豊富な画像・動画コンテンツにより、顧客の意思決定を支援できます。
BtoB ECサイトの導入デメリットと対策

BtoB ECサイトの課題と解決策を解説していきます。
- 基幹システムとの連携コストや不具合
- 社内の業務フローの見直し
- 取引先に合わせた購買体験の実現
以下で詳しく説明します。
初期投資・システム構築コスト
BtoB ECの導入には、BtoC向けECサイトよりも高額な初期費用やシステム構築コストがかかる傾向があります。
業界特有の商習慣や企業ごとの個別要件に対応するため、カスタマイズや独自開発が必要になるケースも多く、数百万円〜数千万円の費用が発生することも珍しくありません。
対策: パッケージ型システムの活用やクラウド型サービスを選択することで、初期コストを抑えた導入が可能です。
既存顧客のシステム移行にかかる負荷
BtoB EC導入時には、既存顧客への取引方法変更の説明やフォローが不可欠です。
これまで電話やFAXで取引してきた顧客に対しては、操作マニュアルの作成やデモサイトの案内など、丁寧なサポートが求められます。
対策: スムーズな移行のため、社内外での調整やフォロー体制の構築、段階的な移行スケジュールの設定が重要です。
社内業務フロー変更への対応
BtoB EC導入により、従来の受注プロセスや営業スタイルの根本的な見直しが必要となります。営業担当者の属人的なスキルに依存していた業務のシステム化・標準化には、相応の準備期間と社内調整が求められます。
対策: 社内研修プログラムの実施や、ECサイトと従来営業の併用によるハイブリッド運用が効果的です。
データ整備・セキュリティ対策
BtoB ECでは、顧客情報・価格情報・取引データなど機密性の高い情報を扱うため、情報漏洩リスクへの対策が不可欠です。また、既存データの整備や移行作業にも相当な工数が必要となります。
対策: セキュリティ基盤が充実した信頼性の高いBtoB ECシステムを選択することで、安全な運用を実現できます。大手企業で導入実績のあるパッケージを選ぶことが、セキュリティリスクを最小化する最も効果的な方法です。
BtoB ECサイトに必要な機能
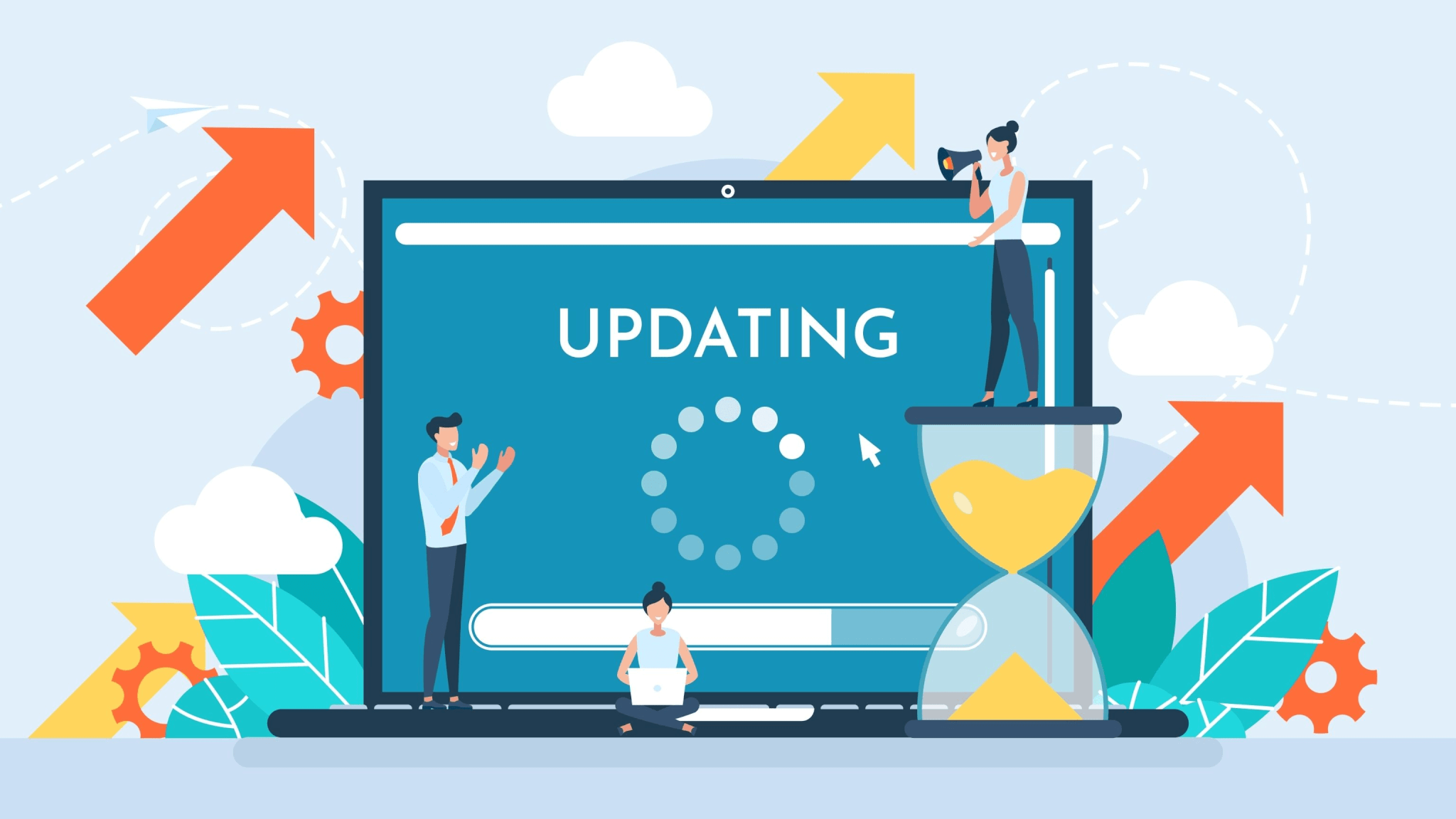
ここでは、BtoB ECサイトを運営する上で、必要になってくる機能をBtoC ECサイト運営と比較しながらご紹介します。
見積もり機能
BtoB ECサイトにおいて見積もり機能が必要な理由は、取引金額が大きく、商品やサービスの構成が複雑になりやすいためです。
BtoCの場合は定価での販売が基本ですが、BtoBでは数量や取引条件によって価格が変動することが一般的です。また、発注前に社内での稟議や承認が必要なケースが多く、正式な発注前に金額を確定する必要があります。
見積もり機能では、商品の選択、数量指定、納期、支払条件などの取引条件を反映させた見積書を作成し、取引先との価格交渉や社内承認のプロセスをサポートします。
掛け払い機能・与信管理機能
BtoB取引では、商品やサービスの提供後に代金を支払う掛け払いが一般的です。これはBtoCのような即時決済とは大きく異なる特徴です。
掛け払い機能では、取引先ごとの与信管理、支払い条件(支払いサイト)の設定、請求締め日の管理、支払い期日の管理などが必要になります。
また、取引先の信用状態を考慮した与信限度額の設定や、未回収リスクの管理も重要です。さらに、複数回の取引をまとめて請求する締め払いにも対応する必要があります。
このように、BtoB ECサイトでは単なる決済機能ではなく、企業間取引特有の複雑な債権管理の仕組みが求められます。
請求書自動発行機能
適切な請求書の発行と管理が法的にも実務的にも重要です。
特に2023年10月からのインボイス制度の開始により、適格請求書の発行が必須となっています。請求書発行機能では、複数の注文をまとめた合計請求や、請求書の定期発行、消費税の適切な計算と表示、源泉徴収の対応など、企業間取引特有の要件に対応する必要があります。
また、電子インボイスへの対応や、請求書の承認ワークフロー、保管・管理機能なども重要です。BtoCでは領収書の発行で十分ですが、BtoBでは取引の証憑として正確な請求書管理が必要不可欠です。
顧客別価格設定機能
BtoB取引では、取引先との契約内容や取引量に応じて、同じ商品でも取引先ごとに異なる価格を設定することが一般的です。
顧客別価格設定機能では、取引先ごとの価格マスタの管理、数量割引の設定、特別価格の期間管理、新価格への改定管理などが必要です。
また、商品のグレードや取引先の規模によって価格帯を分けたり、特定の業界向けの専用価格を設定したりする必要もあります。BtoCの場合は原則として全顧客に同一価格を提示しますが、BtoBでは取引条件に応じた柔軟な価格設定が競争力の源泉となります。
基幹システム連携
BtoB ECサイトでは、受発注データを確実に基幹システムと連携させる必要があります。
これは、在庫管理、生産計画、会計処理、販売管理など、企業の基幹業務と直結しているためです。基幹システム連携では、リアルタイムの在庫確認、受注データの自動取り込み、出荷指示の自動発行、請求データの連携など、様々なデータをシームレスにやり取りする必要があります。
BtoCの場合は比較的シンプルな在庫連携で済みますが、BtoBでは取引先ごとの与信残や取引条件、承認ワークフローなど、より複雑な連携が求められます。また、EDIやERP等の外部システムとの連携も重要な要件となります。
BtoB ECサイトの主な構築方法5選
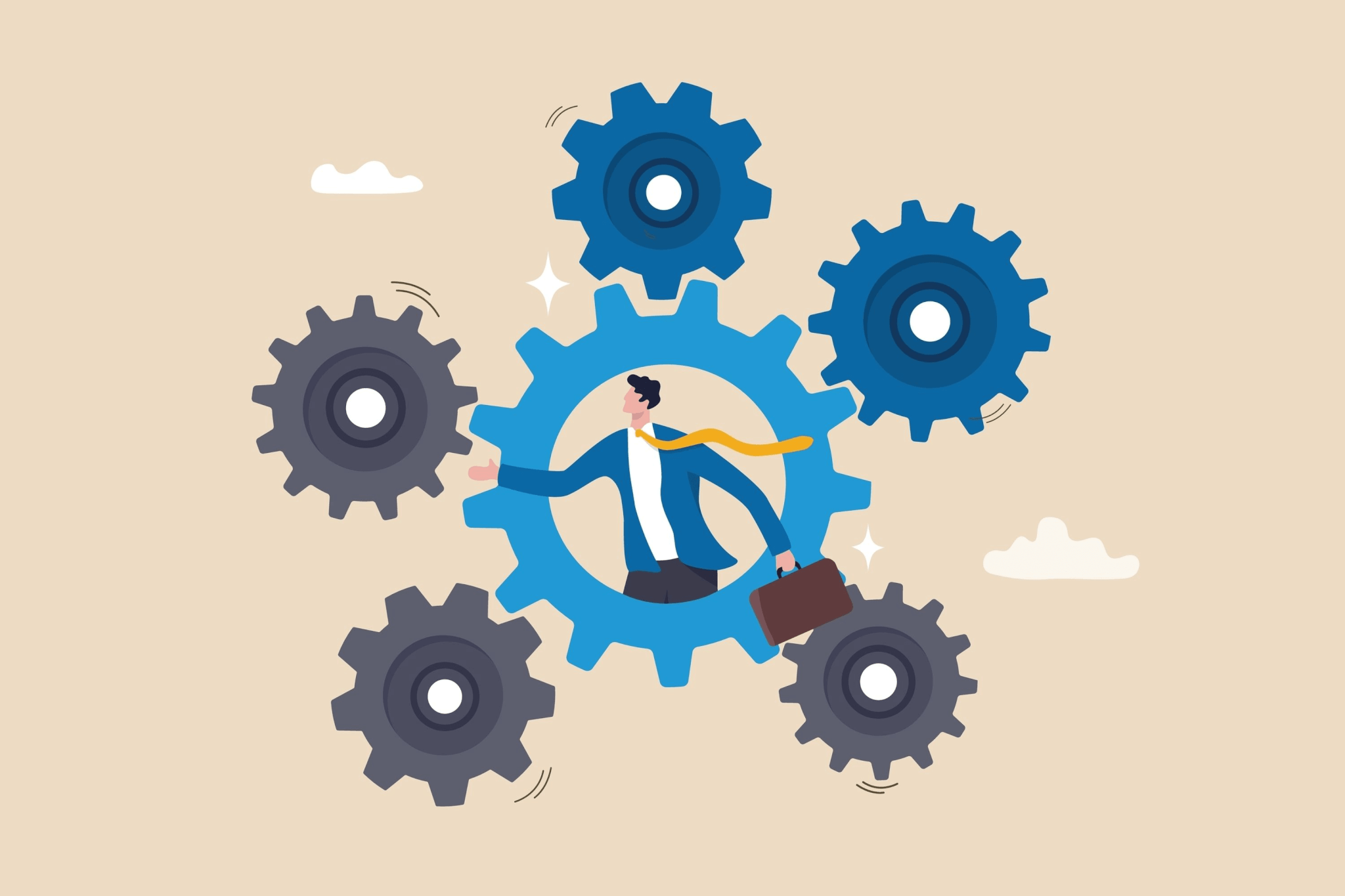
| 構築方法 | メリット | デメリット | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| ASP型 | ・コストを比較的抑えやすい ・構築のハードルが低い |
カスタマイズ性が低い | 初期費用:0円~50万円 月額0~10万円 |
| パッケージ型 | ・サポートが充実している ・カスタマイズ性が高い |
コストが比較的高い | 初期費用:100万円~500万 月額:10万円~50万円 |
| オープンソース型 | ・コストを比較的抑えやすい ・カスタマイズ性が高い |
・高度な知識が必要になる ・セキュリティリスクが高い |
開発費用0円~数千万円 (ライセンス費用は無料) |
| クラウド型 | ・カスタマイズ性が高い ・システムの陳腐化を防げる |
コストがやや高い | 初期費用:500万円~2000万 月額50万円~200万円 |
| フルスクラッチ型 | ・自由度が最も高い ・カスタマイズが無限大 |
時間とコストが特にかかる | 開発費用:3000万円~数憶円 年間保守費用500万円~ |
ASP EC
ASP型とは、ECサイトの構築や運営に必要な機能をクラウド上でレンタルするサービスです。
このサービスの特徴は、比較的短い期間でECサイトを立ち上げることができ、コストを抑えやすい点です。また、システムの保守やバージョンアップは提供元が行うためユーザーは常に最新のシステムを利用できます。
しかし、ASP型ECのデメリットとして、利用できる機能に制限があるためカスタマイズ性や拡張性が低いことが挙げられます。これは、外部システムとの連携や管理画面の拡張が難しいことを意味します。
無料から利用できるASP型ECサービスも存在しますが、無料プランでは機能制限や取引手数料が高く設定されているケースが多いです。一方、有料プランでは、より充実した機能と柔軟性を利用でき、ビジネス規模の拡大にも対応できます。
その他、より詳しくASP型のECサイト構築方法のメリットやデメリットを知りたい方は以下の記事で解説しています。
パッケージEC
パッケージ型とは、ECサイト構築に必要な機能があらかじめパッケージ化されたシステムを購入し、それをベースに企業のニーズに合わせてカスタマイズしてECサイトを構築する方法です。
この手法の特徴は、高いカスタマイズ性と在庫管理や基幹システムとの連携性に優れている点です。また、提供元からのサポートが充実しており、セキュリティ面でも信頼できるサービスが多いです。ただし、他の構築方法に比べて初期費用や月額費用が高くなる傾向があります。
一方で、自社のニーズに合わせてECサイトを構築できるため、大きな成果が期待できるのがメリットです。また、導入から運用までのサポート体制が整っており運営に安心感があります。基本的な必要機能は網羅されているため中規模から大規模のECサイト運営に適しています。
総じて、中長期的に安心して利用できるECサイトを構築できるため、業界や規模問わずBtoB EC事業者全員におすすめです。
以下の記事では、おすすめのパッケージ型のECシステムについて詳しく解説しています。
是非合わせてご覧ください。
オープンソースEC
オープンソース型とは、誰でも閲覧できるソースコードをサーバーにインストールしてECサイトを構築する手法です。特徴として、コストを大幅に抑えてサイトを構築できることとカスタマイズの自由度が高いことです。
ただし、導入・運用には高度なプログラミングスキルが必要で、セキュリティ対策も自社で行う必要があるためリスクも伴います。また、システムの保守や更新、トラブル対応もすべて自社で行う必要があります。
十分な技術力がある企業であれば、自社の要件に完全に合致したECサイトを構築できる点が最大のメリットです。しかし、公式サポートが限定的なため、障害発生時の対応や継続的なメンテナンスは自社の技術力に依存します。
その他、より詳しくオープンソース型のECサイト構築方法のメリットやデメリット、他のECサイト構築方法の違いを知りたい方は以下の記事で解説しています。
クラウドEC
クラウド型とは、クラウド上のシステムを利用してECサイトを構築する手法であり、ASP型と似ていますがカスタマイズ性や初期費用、導入期間に違いがあります。
クラウド型ECは、システムのアップデートが自動で行われるため最新の状態を維持でき、セキュリティも高い安全性が保たれます。また、カスタマイズ性や拡張性に優れており、機能の追加などは比較的低コストで行えます。
ただし、月額費用や保守費用が他の構築方法と比較して高額になる傾向があります。そのため、ある程度の規模と予算を持つ企業で、システムの陳腐化を避けながら継続的な成長を目指す場合に適した構築方法です。
フルスクラッチEC
フルスクラッチ型とは、ゼロからオリジナルのECサイトを構築する方法であり自由に開発ができるので、自社の商材やコンセプト、ターゲットに合わせた最適なECサイトを追求できるのが最大の強みです。
カスタマイズ性が高く、サイト改善やカスタマイズに柔軟に対応できる一方で、サイト構築までに多くの時間とコストがかかります。
大企業が運用する大手ブランドのECサイトにはフルスクラッチ型がよく採用されており、社内の専門部署でシステムの定期的なメンテナンスや調整・拡張業務が行われています。
しかし、中小規模のビジネスを行う企業にとっては予算が合わない可能性もあり、採用する場合は、費用対効果を見込めるか慎重に検討することが重要です。
総じて、フルスクラッチ型は新規でのECサイト構築ではなく、既存のECサイトをリプレイスする方に対しておすすめです。
最近では、BtoB EC特化のパッケージ型のカスタマイズ性が向上しているので、予算が合わずフルスクラッチ型を選択できない場合はそちらも視野に入れてみるとよいでしょう。
その他、より詳しくフルスクラッチ型のECサイト構築方法のメリットやデメリットを知りたい方は以下のお役立ち記事で解説しています。
BtoB EC導入前のチェックリスト
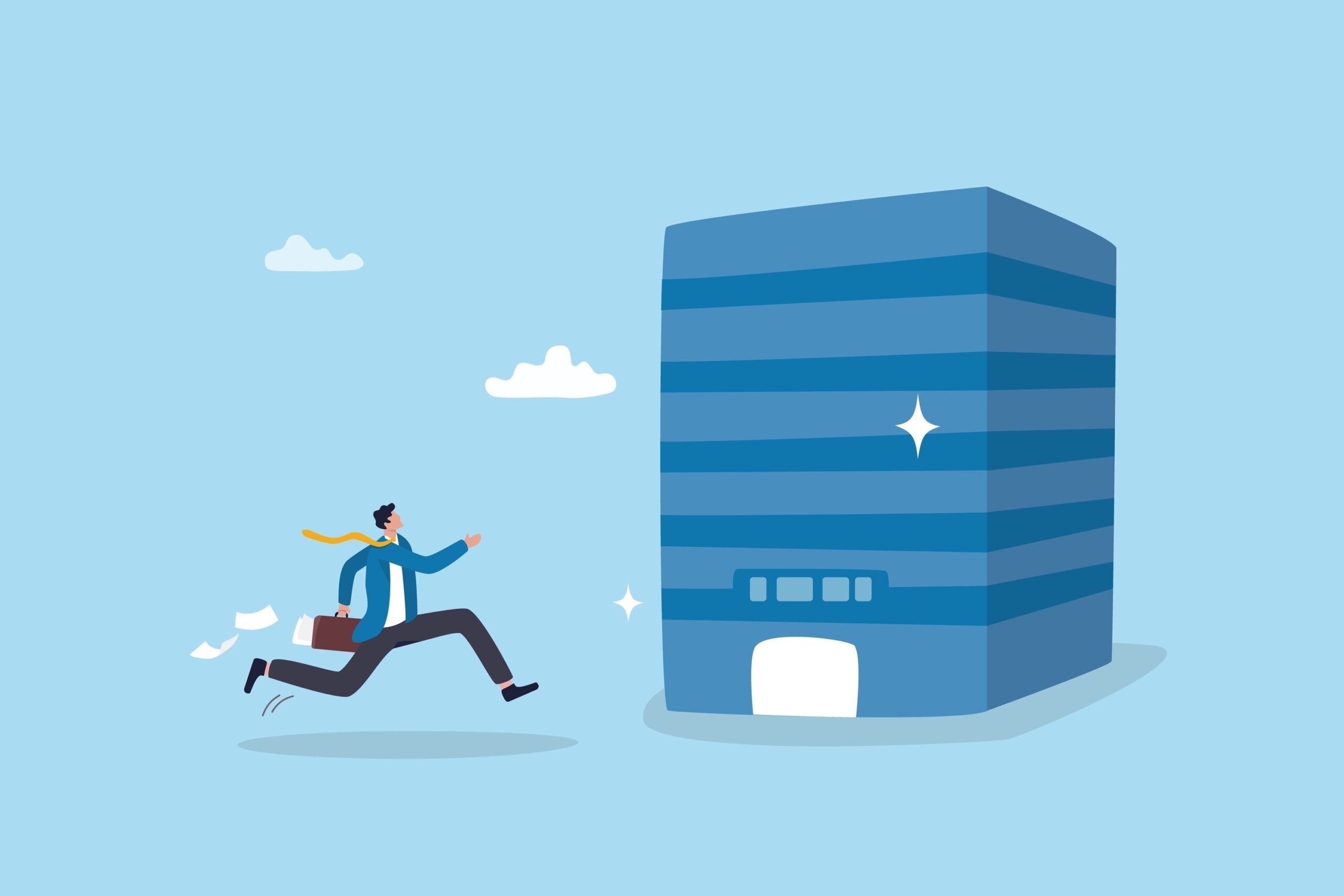
取引条件・価格体系の整理ができているか
BtoB ECを導入する際に最初に確認すべきポイントは、顧客ごとの価格体系や取引条件がどれほど整理されているかという点です。
多くの企業では、掛け率や与信条件、個別値引きなどが長年の積み重ねで複雑化しており、担当者以外には把握しきれないケースが非常に多く見られます。
この状態でEC化を進めてしまうと、実際のオペレーションとシステム設計が噛み合わず、導入後に大きな混乱を招きます。
そのため、導入前の段階で主要顧客の取引条件を棚卸しし、どこまでEC上で標準化するか、逆に例外として扱う部分はどこかを明確に線引きすることが重要です。
値引きルールを整理するのか、承認フローで柔軟性を残すのか、といった判断も欠かせません。
ここを丁寧に行うことで、無駄なカスタマイズを抑え、シンプルで運用しやすい仕組みを構築することができます。結果として、定着スピードも早まり、長期的な運用負荷も大幅に軽減されます。
基幹システム・在庫・受注フローの連携要件を把握しているか
BtoB ECは単体では成立せず、基幹システムや在庫管理システム、受注管理、会計システムなどとの連携を前提に運用されます。
そのため、導入前の段階で「どこまでリアルタイムで連携するのか」「どの処理はバッチで問題ないのか」を整理しておくことが必要です。
リアルタイム連携を過剰に行うと開発コストが急増し、障害発生時のリスクも高まります。
一方で、連携が不足すると在庫差異や出荷ミスが発生し、現場の信頼を失う可能性があります。
また、既存の基幹システムが古く、そもそも連携が困難なケースも少なくありません。
そのため、情報システム部や外部ベンダーと早期に協議し、現在のシステムが持つ仕様や制約を明確にする必要があります。
この準備を怠ると、「構築したものの連携できない」「追加開発が必要になり費用が膨らむ」といったトラブルにつながります。
導入前に連携方針を固めておくことで、運用に適した設計が可能になり、プロジェクト全体の成功率が大きく高まります。
以下の記事では基幹システムに関して詳しく解説しています。
是非合わせてご覧ください。
社内の運用体制と責任範囲は明確化できているか
BtoB ECはローンチ後の運用が成果を左右するため、事前に社内の運用体制を整えておくことが不可欠です。
商品更新や価格変更、取引先からの問い合わせ対応、受注確認、トラブル対応など、EC運用には多くの業務が関わるため、「どの部署が何を担当するのか」を明確にしておく必要があります。
責任範囲が曖昧なままだと、属人化や対応遅延が発生し、EC利用の定着を妨げる原因となります。
さらに、営業部門の理解と協力も重要です。
営業がECを“自分たちの役割と競合する存在”と捉えてしまうと、顧客への案内や利用促進が進まず、利用率が低いまま停滞することがあります。
そのため、導入前に説明会やトレーニングを実施し、ECが営業活動を補完し、業務効率化や売上拡大に貢献する仕組みであることを丁寧に伝えることが大切です。
明確な体制と共通認識が整っていることで、導入後の運用がスムーズに進み、改善サイクルも回りやすくなります。
以下の記事ではEC運営に関して詳しく解説しています。
是非合わせてご覧ください。
取引先への案内・移行計画が設計されているか
BtoB ECの成功は、取引先にどれだけ利用してもらえるかにかかっています。
そのため、導入前に「いつ、どのように案内するか」「どの段階で旧来の注文方法を終了するか」など、具体的な移行計画を立てておくことが非常に重要です。
取引先にとって注文方法の変更は大きな負担となるため、ただ案内を送るだけでは定着が進みません。使い方のマニュアルや動画、よくある質問をあらかじめ用意し、スムーズに移行できる環境を整える必要があります。
また、EC利用のメリットを「取引先の業務改善」という視点で伝えることも効果的です。
例えば、「24時間いつでも発注できる」「納期確認が早くなる」「注文履歴を簡単に見返せる」といった具体的な利点を示すことで、利用する理由が明確になります。
さらに、電話やFAXとの併用期間を設け、段階的に切り替えることで、取引先が安心して移行できる環境をつくることができます。
BtoB ECサイト構築を構築するなら「W2 BtoB」
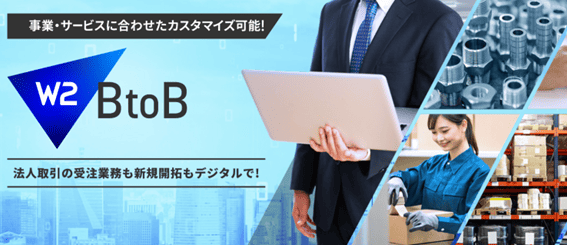
画像参照元:W2 BtoB公式サイト
初期費用:要見積もり
月額費用:要見積もり
導入実績:1100社以上「大東建託株式会社・旭商工株式会社・株式会社ホリ・コーポレーションetc」
W2 BtoBは、1,000以上の充実したEC機能と業務効率化に特化したBtoB機能により、受発注業務から販売施策の実行まで幅広く対応可能です。
具体的には、以下の課題をお持ちの方におすすめです。
- 電話やメールなど、アナログ受注の対応が業務負担になる
- 取引先ごとに価格や商品を変えられず、不便が生じている
- 営業時間外の対応ができず、受注の機会を逃している
- 見積やアカウントの発行に手間がかかっている
- 商品や取引先の情報がバラバラで、管理が面倒
また、W2はBtoBとBtoC ECサイト統合や新規構築に対応可能であり、多様な販売チャネルに加え、BtoBビジネスで重要な取引先・メーカーのデータを全て一元管理することで、複雑な業務プロセスを最適化が可能です。
中小企業から大企業まで幅広い規模の企業で利用されており、豊富な連携サービスや無料API、エンドユーザーの利便性を重視したアップデートが特徴となっています。

W2 BtoBは、法人取引における受注・顧客管理業務をデジタル化し、業務全体を効率化するBtoB向けECソリューションです。FAXや電話での受発注をオンライン化し、業務工数を大幅削減!掛率設定、見積書発行、与信管理など、BtoB特有の商習慣に標準対応しています。
ECを活用した新規顧客開拓にも対応し、BtoBtoBやBtoBtoCなど多様な取引形態・販路を一元管理可能です。
W2システム導入で成功したBtoB ECサイトの事例
この章では、BtoB ECサイトの成功事例について以下の2社をご紹介します。
- 株式会社IL
- 大東建託株式会社
株式会社IL
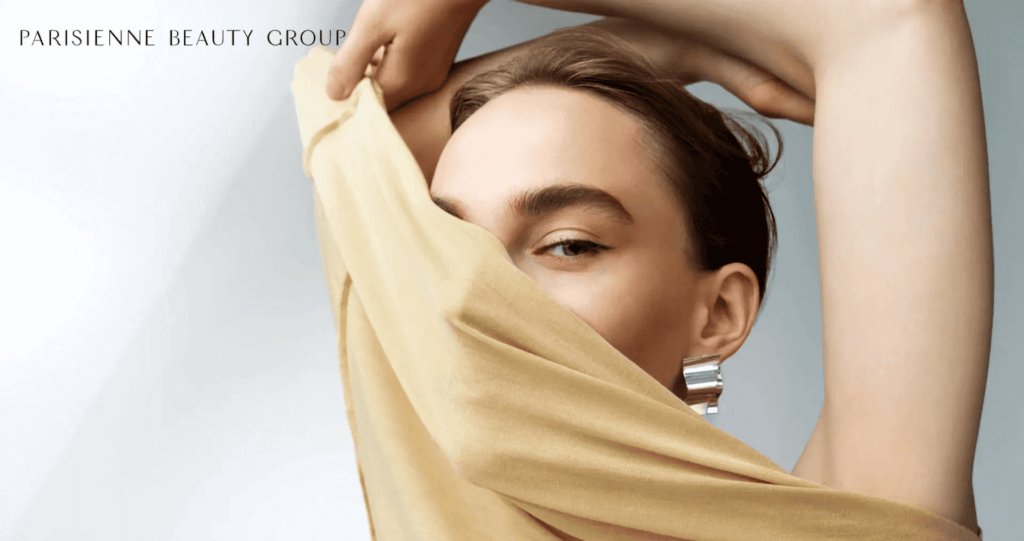
株式会社ILは「素肌美や飾りすぎない自然な美しさを提供すること」をコンセプトに、独自開発した化粧品やスキンケアといった美容商材の生産や代理店向けに販売を行っている会社です。
元々は代理店ごとに価格や掛け率を変化できないことや、代理店ごとの販売管理、受注管理ができない仕様になっており、事業においてどこに課題があるのか可視化することができませんでした。
しかし、BtoB ECのシステムを導入することで、販売先からログインしたお客様ごとで価格の出し分けを可能にすることができたり、ユーザー管理レベル機能を利用して管理画面内で販売先ごとでのお客様管理が可能になっています。
また、クーポン機能を用いて商品を割引価格で販売したことや、お客様を細かな条件でセグメント化して、各セグメントごとに合わせたプレゼントキャンペーンを行ったことで、月間売上が156%増加し、平均の顧客単価も133%向上しています。
詳しい事例は下記よりご一読ください。
売上156%向上と業務工数67%削減を実現!BtoB向け美容商材を販売する 株式会社ILが代理店ごとで価格調整を可能にできることを理由に W2 Repeatを選定!
大東建託株式会社

大東建託株式会社「すまちく建材店」といういわゆるECモール型のサイトを運営していて、お取引のあるメーカー様の商品を会員様限定の特別価格で、企業様やその企業の社員様を対象に販売しているクローズドECサイトを運営しています。
元々はメーカー様の商品登録や在庫確認などを大東建託様が手動作業していたため、業務工数に負荷が生じていました。
しかし、BtoB ECシステムを導入した結果、商品登録や発送は各メーカー様が行うようになり、月に約160時間の工数削減を実現しています。
また、業務効率が改善されたことで、今まで手が付けられていなかった販促やマーケティング活動にも注力することが可能になったことで売上向上を実現しています。
詳しい事例は下記よりご一読ください。
「多機能ECプラットフォーム×柔軟なカスタマイズ」が決め手!大東建託がW2を選定で理想のモール型自社ECサイトを実現/新規出店数4倍を達成!
その他の成功事例を知りたい方は、以下の記事でBtoB EC売上ランキングを基に解説しているのでこの機会にぜひご覧になられてはいかがでしょうか。
なお、下記の資料ではBtoB ECの立ち上げに関する手順と重要ポイントを紹介しています。無料でダウンロードできますので、是非ご活用ください。

以下がこの記事のまとめです。
- BtoB ECは、企業間でのオンライン取引のことを指す
- BtoB EC市場は急成長中で、特に食料品製造業がEC化率81%を超えている
- 成長背景にはBCP推進、働き方改革、ITインフラ整備、デバイス普及などの要因がある
- BtoB ECのメリットはコスト削減、業務効率化、顧客開拓、データ分析の活用などがある
- BtoB ECサイトにはクローズド型とスモール型、マーケットプレイス型がある
- 自社に合わせたECサイトシステムを選ぶことが重要になってくる
BtoB ECサイトの課題は、一朝一夕で解決できるものではありません。しかし、上記の対策を参考に、継続的に取り組むことで、課題を解決し、成功に近づくことができるでしょう。