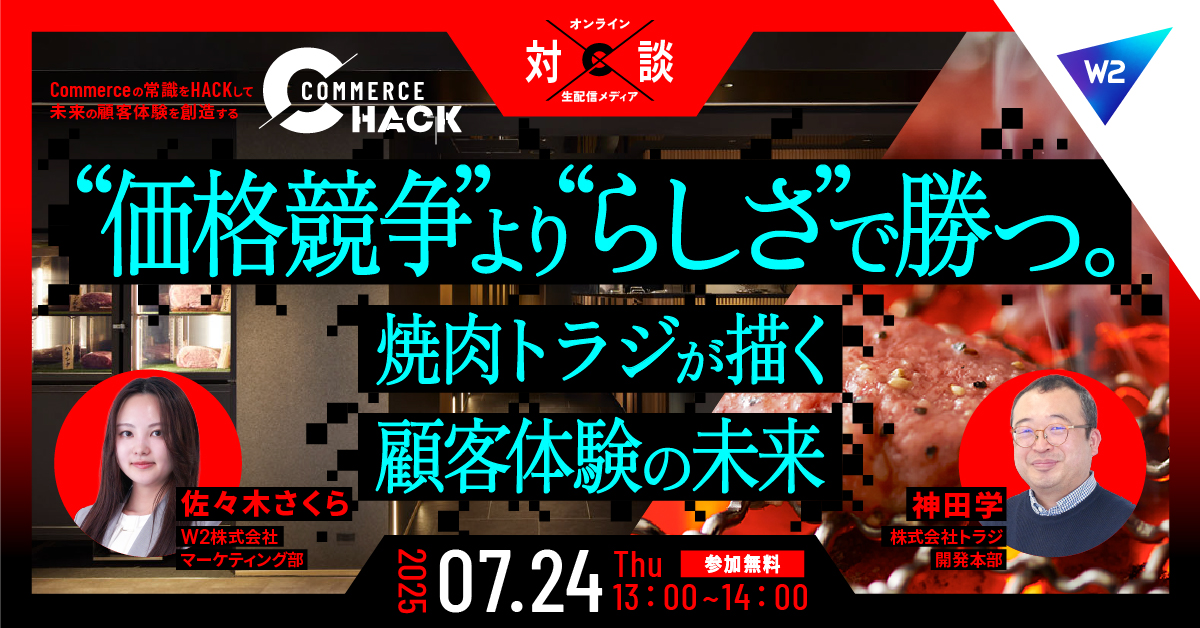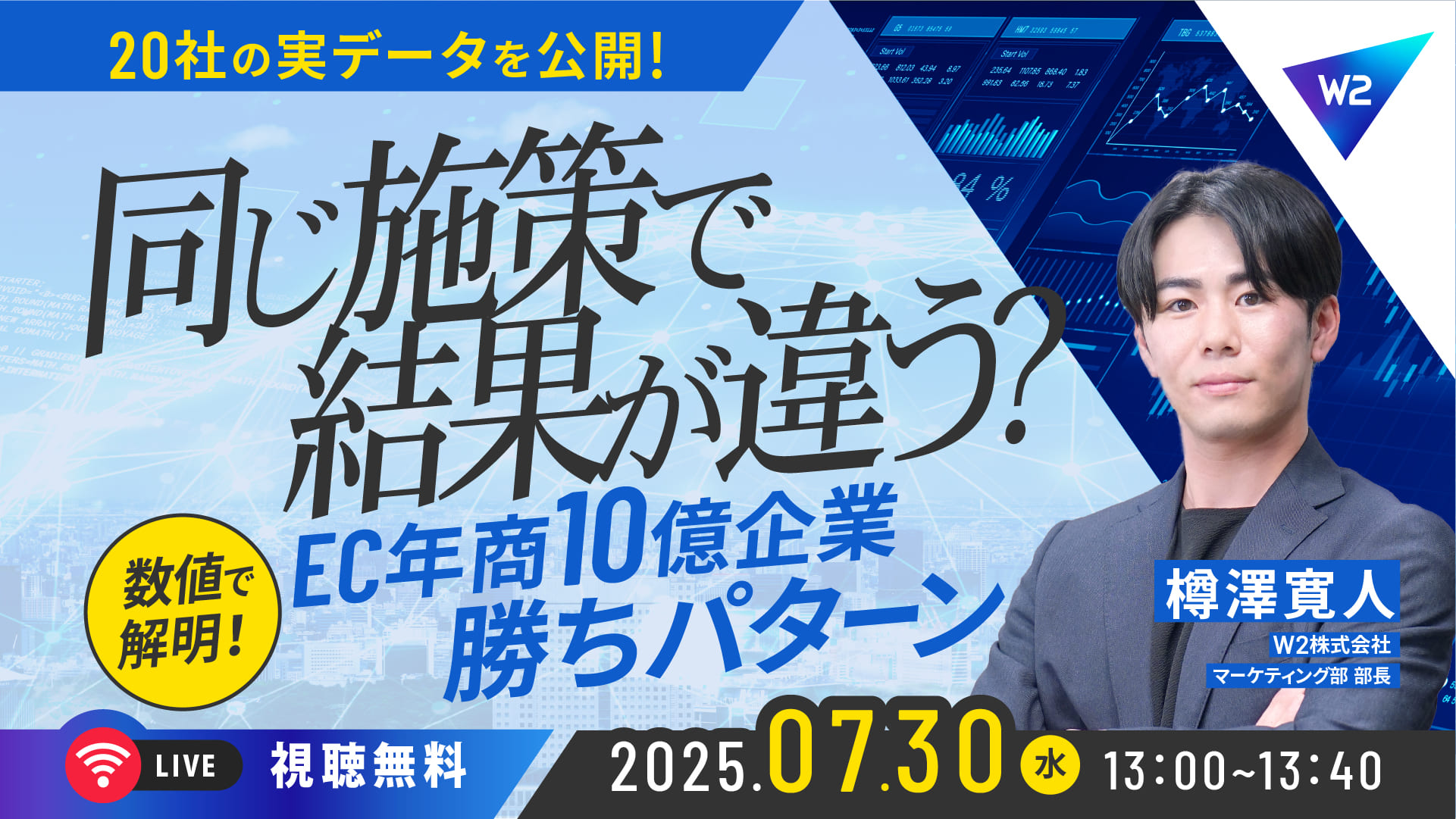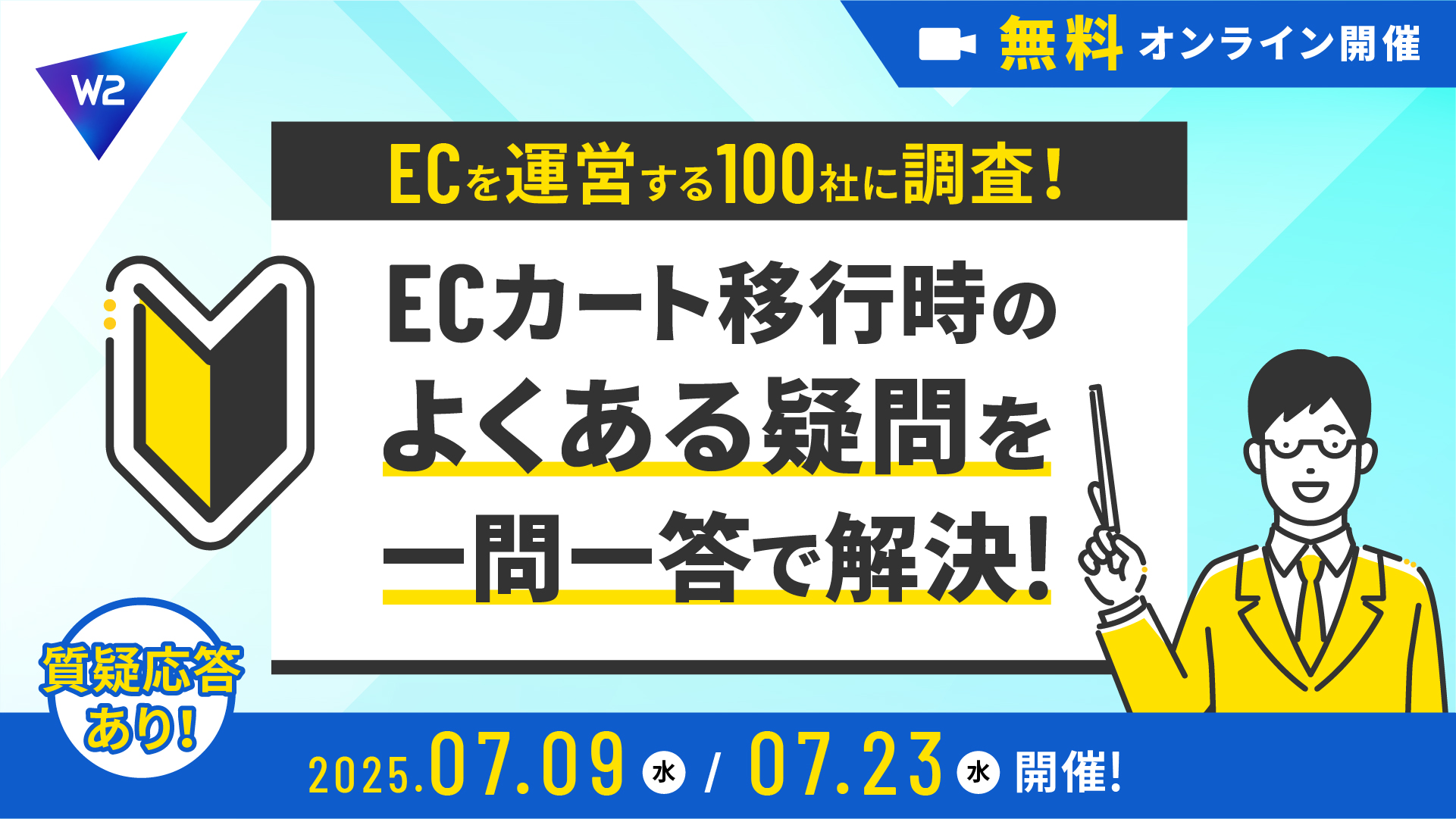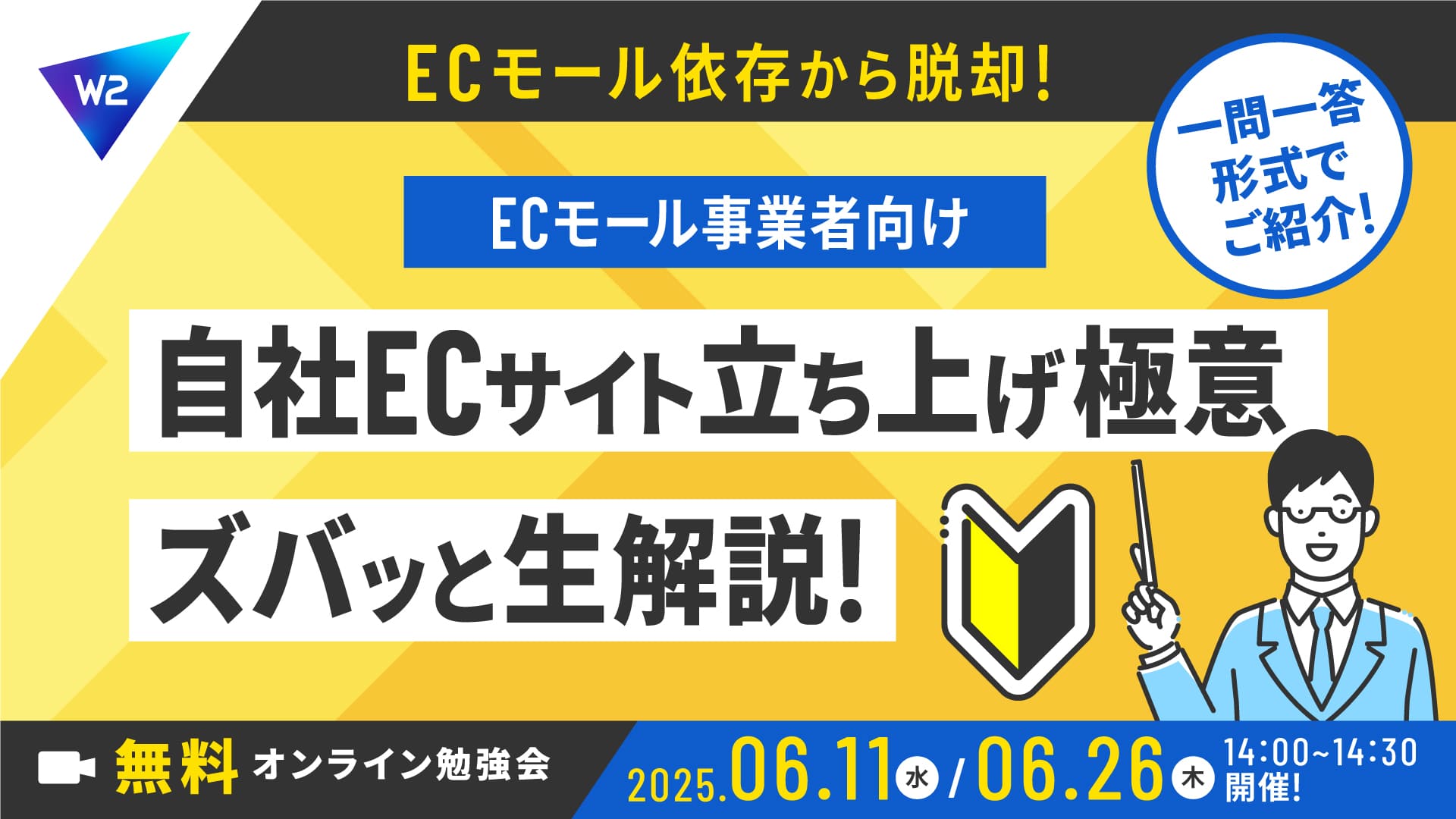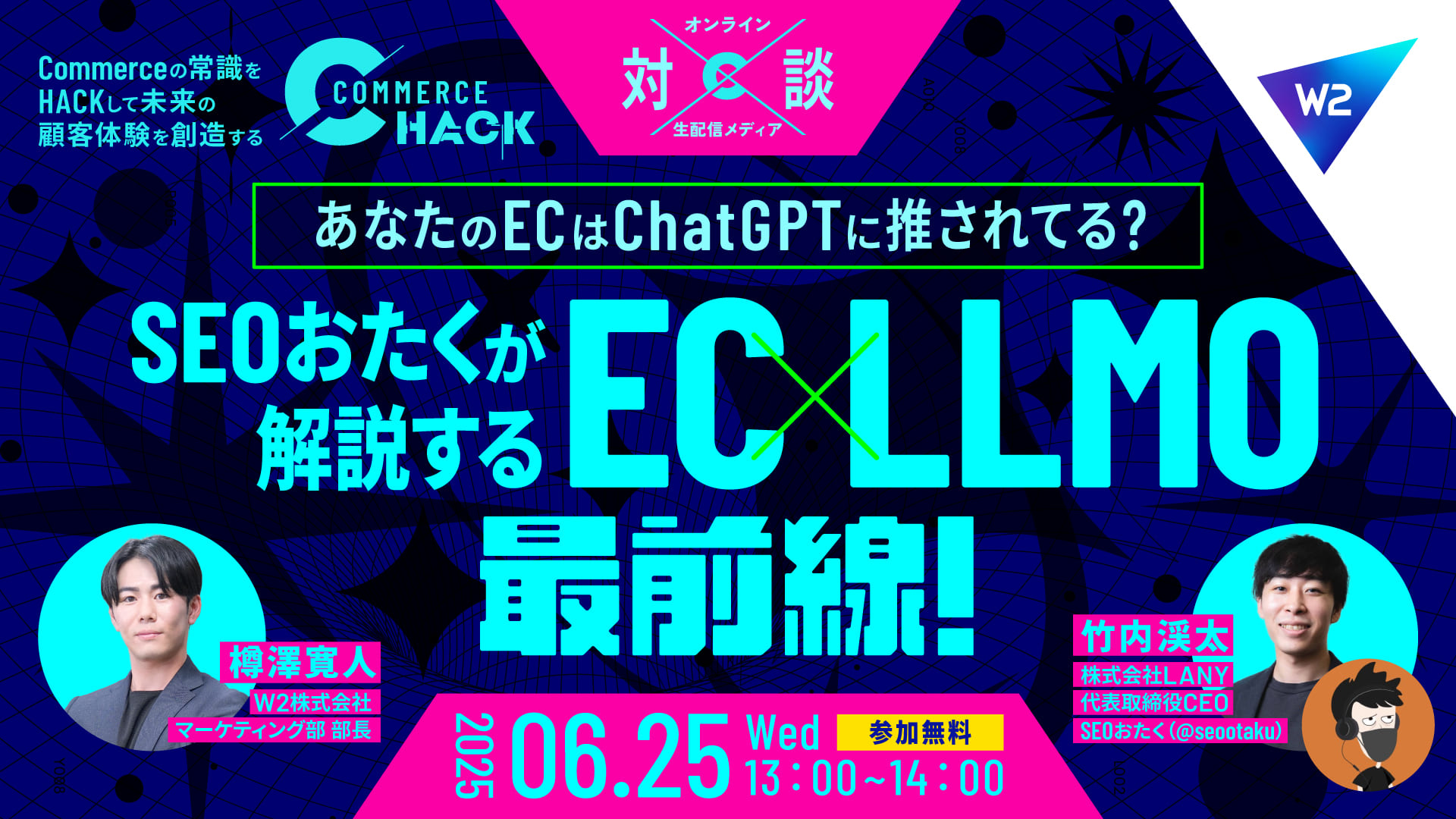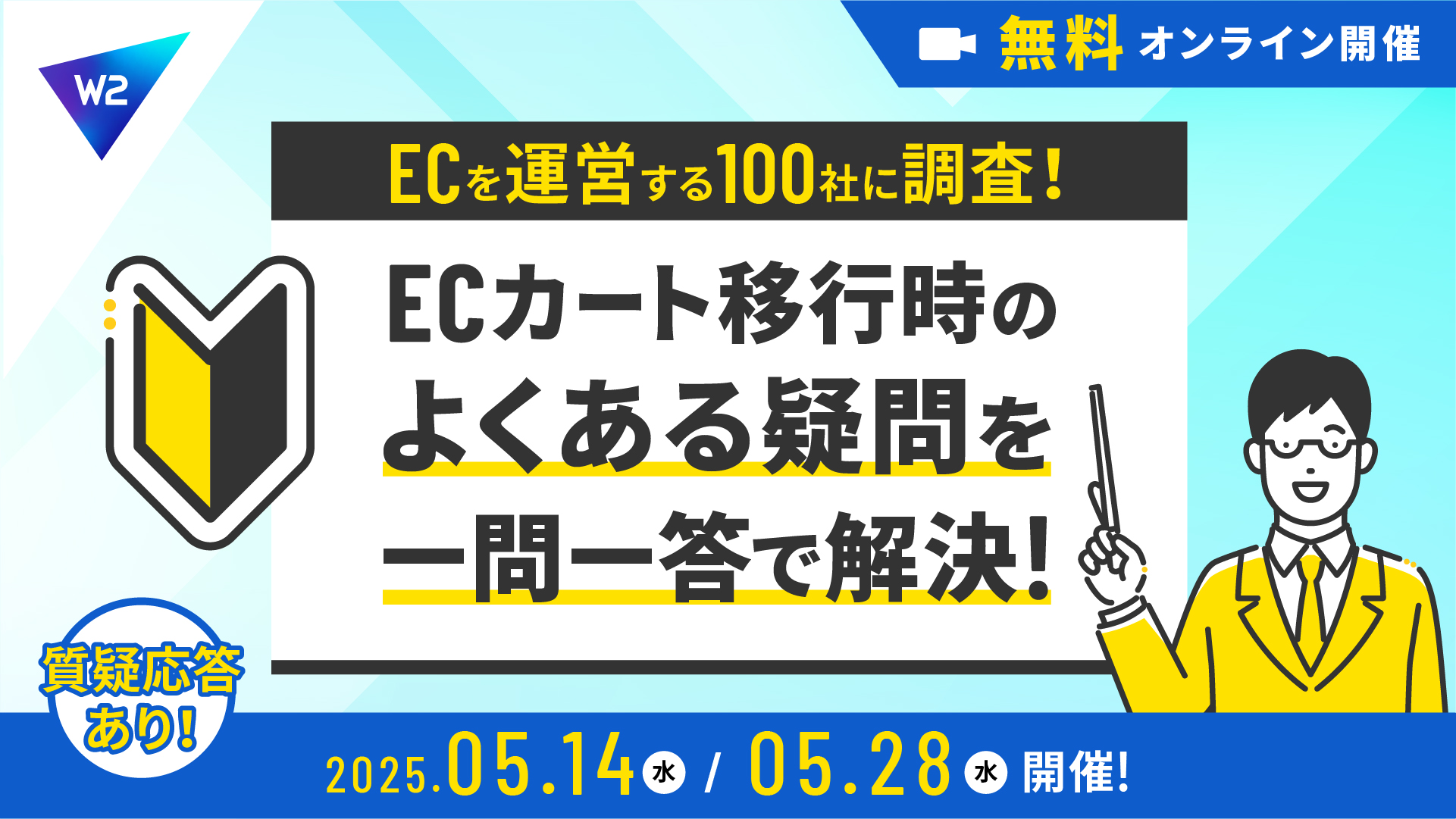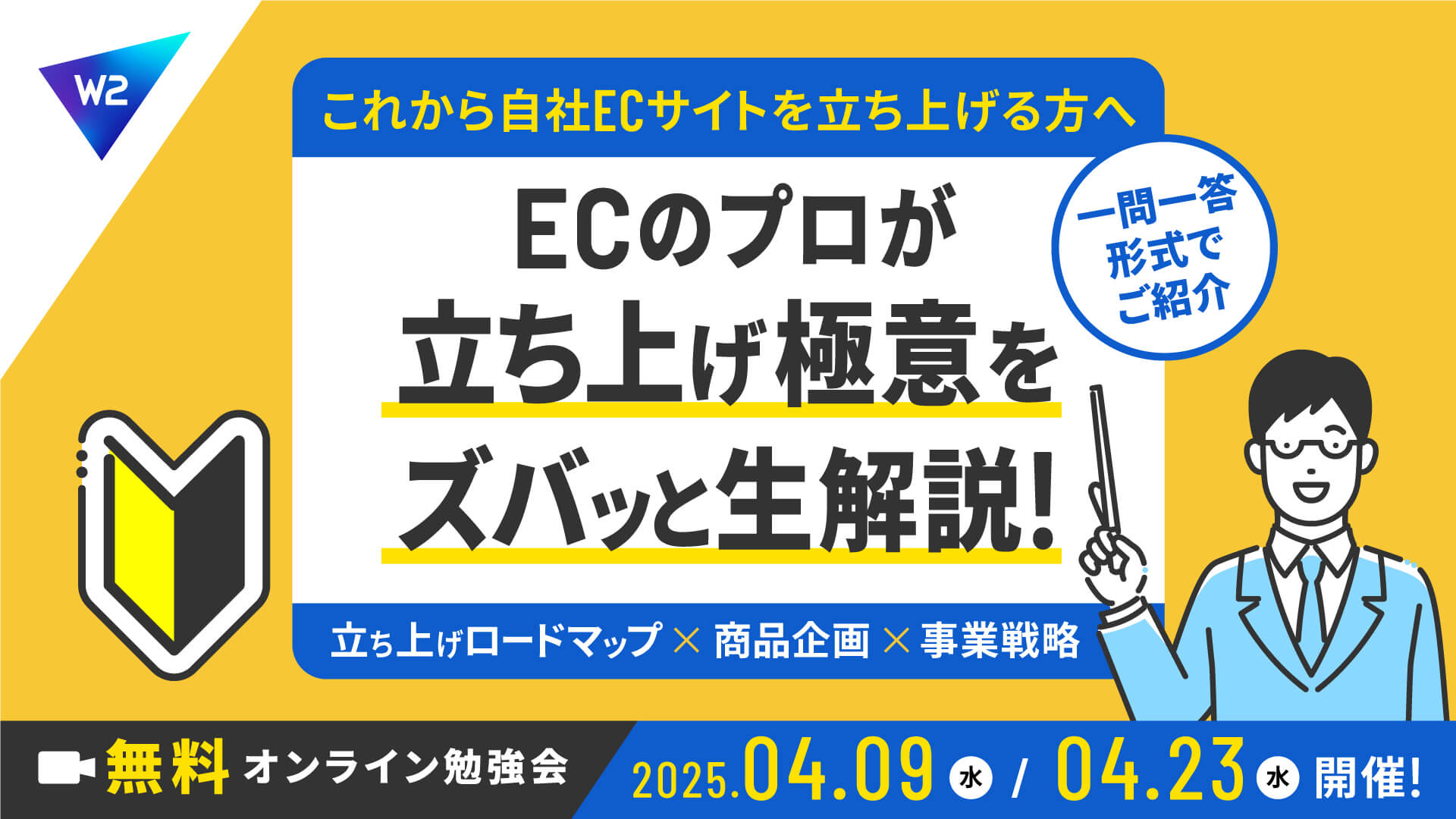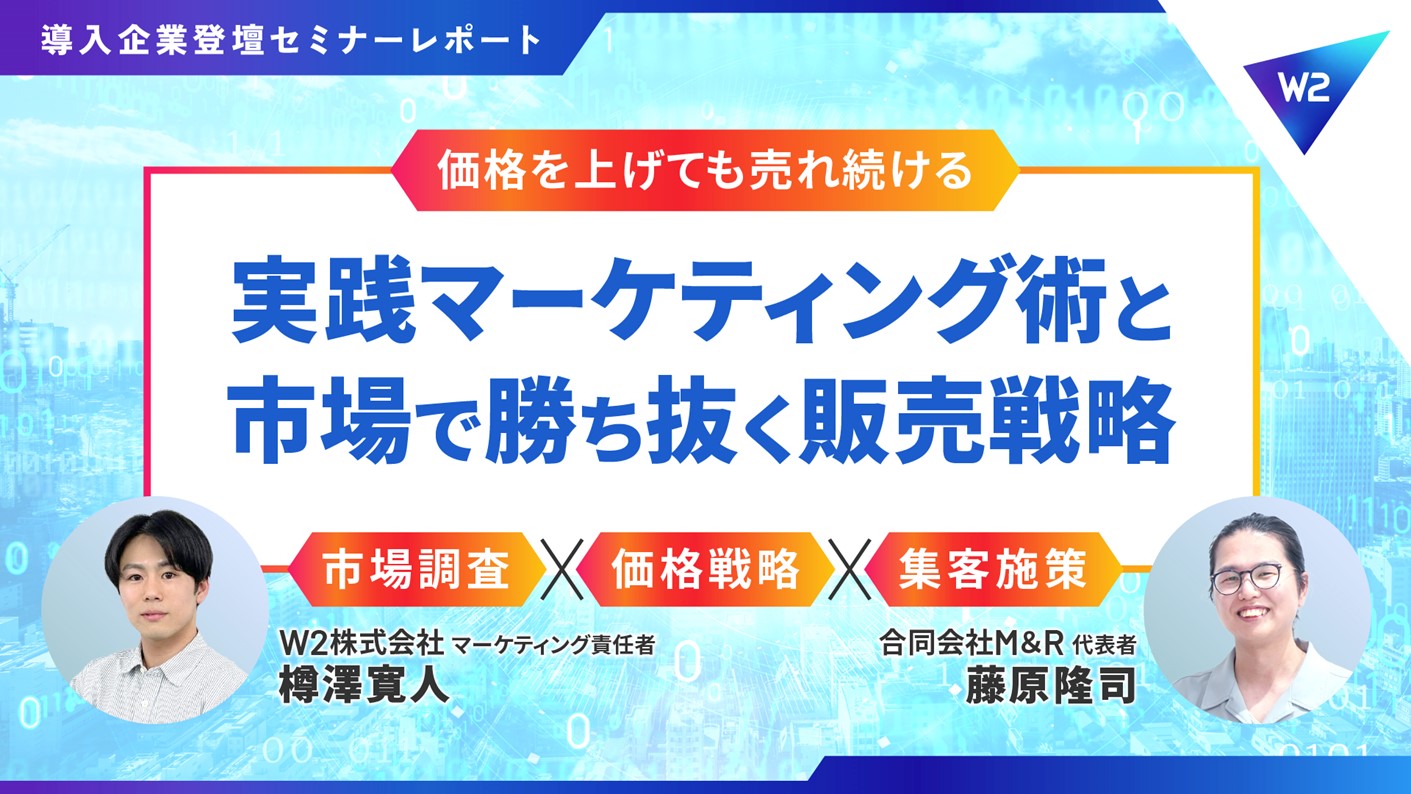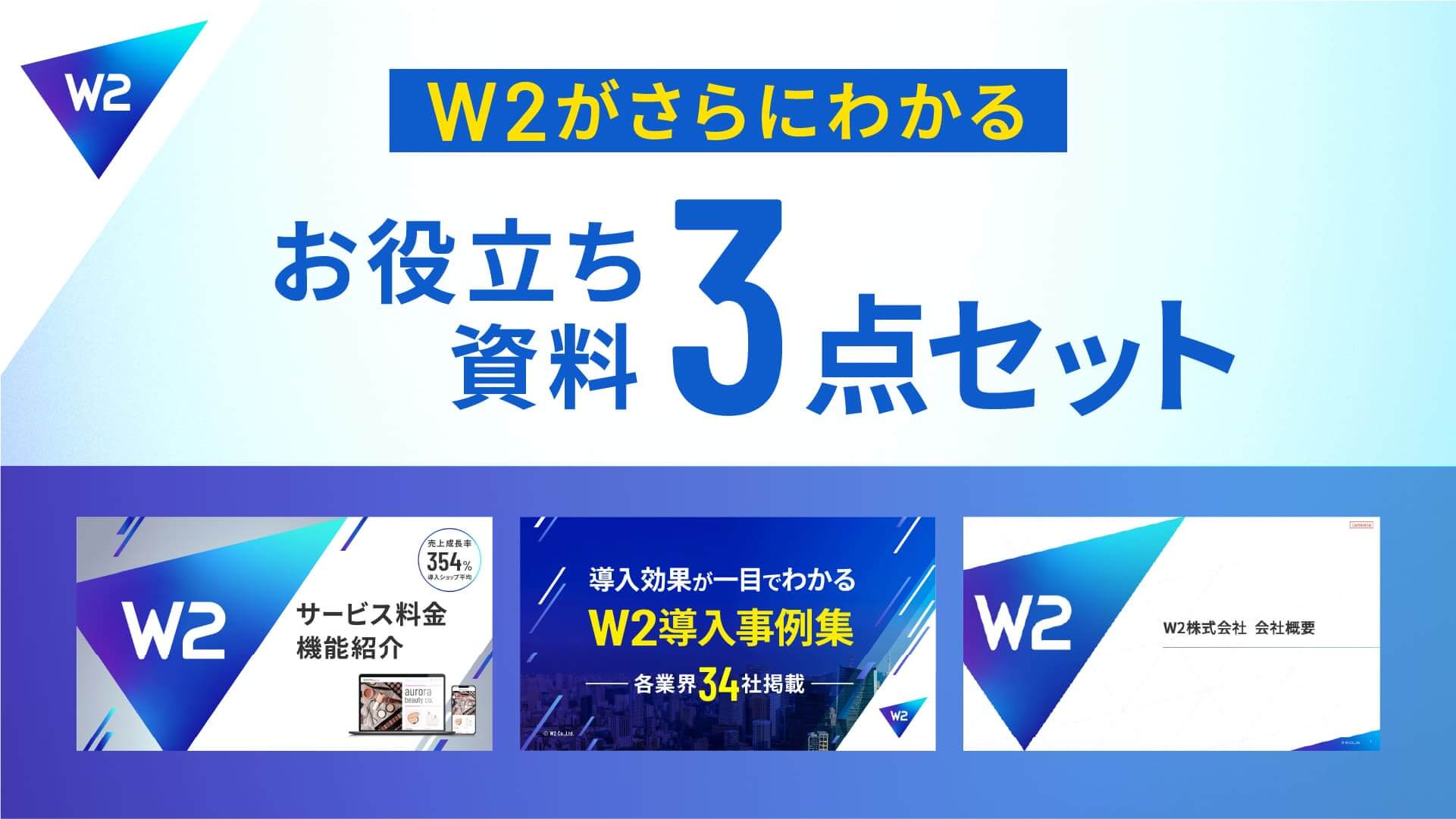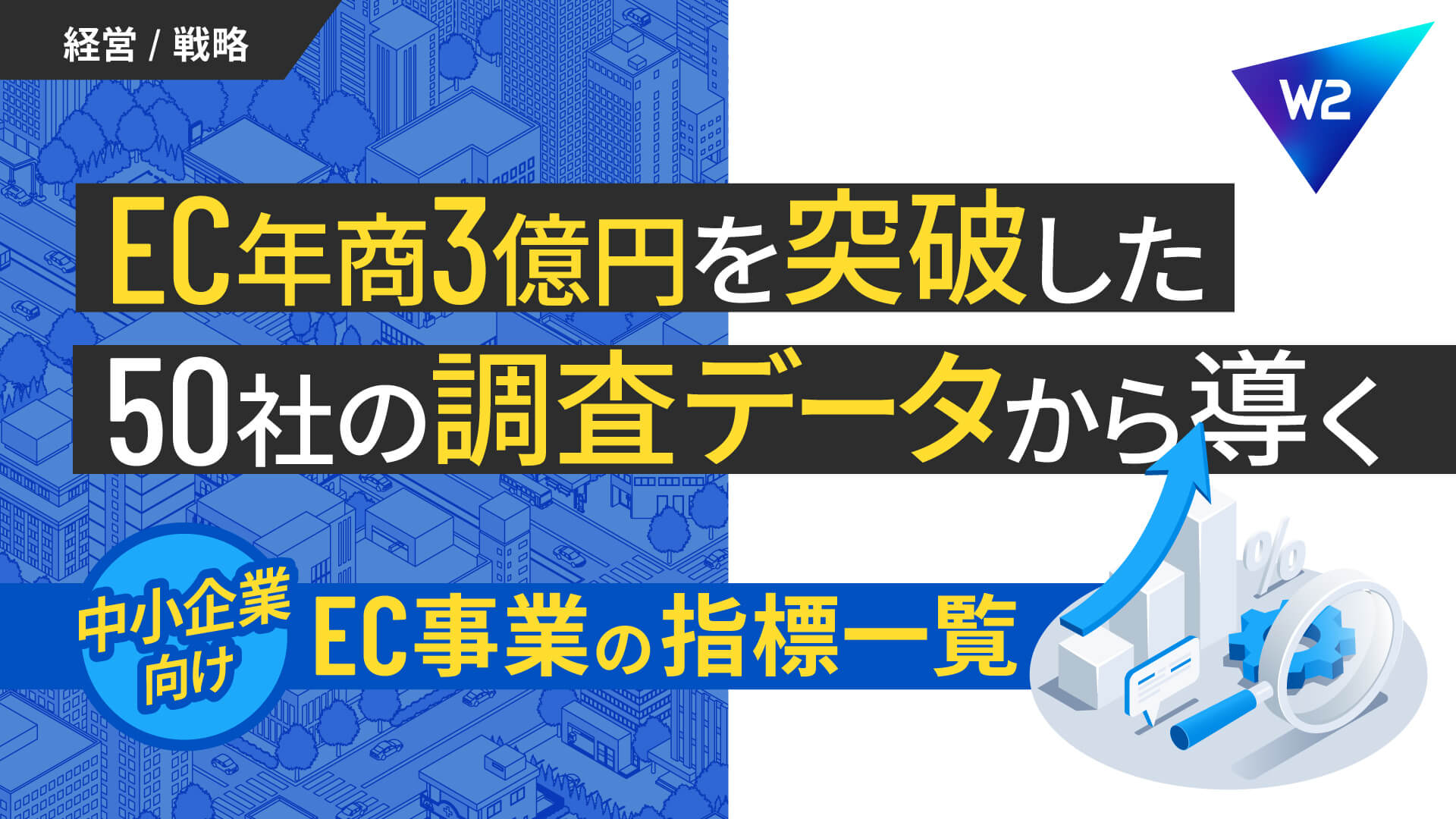【2025年最新版】個人でのネットショップ開業手順とは?必要な手続きや費用相場、仕入れ方法や事例を解説


【2025年最新版】個人でのネットショップ開業手順とは?必要な手続きや費用相場、仕入れ方法や事例を解説
近年、EC市場はますます拡大し、個人でも手軽にネットショップを開業できるようになりました。しかし、その一方で、成功させるためには様々な知識や準備が必要となります。
本記事では、個人事業主向けのネットショップ開業知識から、必要な手続きや費用、売上アップのノウハウまでを網羅的に解説します。
さらには、個人で開業する際の注意点、成功事例や使える補助金情報まで、あなたのネットショップ開業を成功に導くための情報を2025年最新版で徹底解説します。
W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。
数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!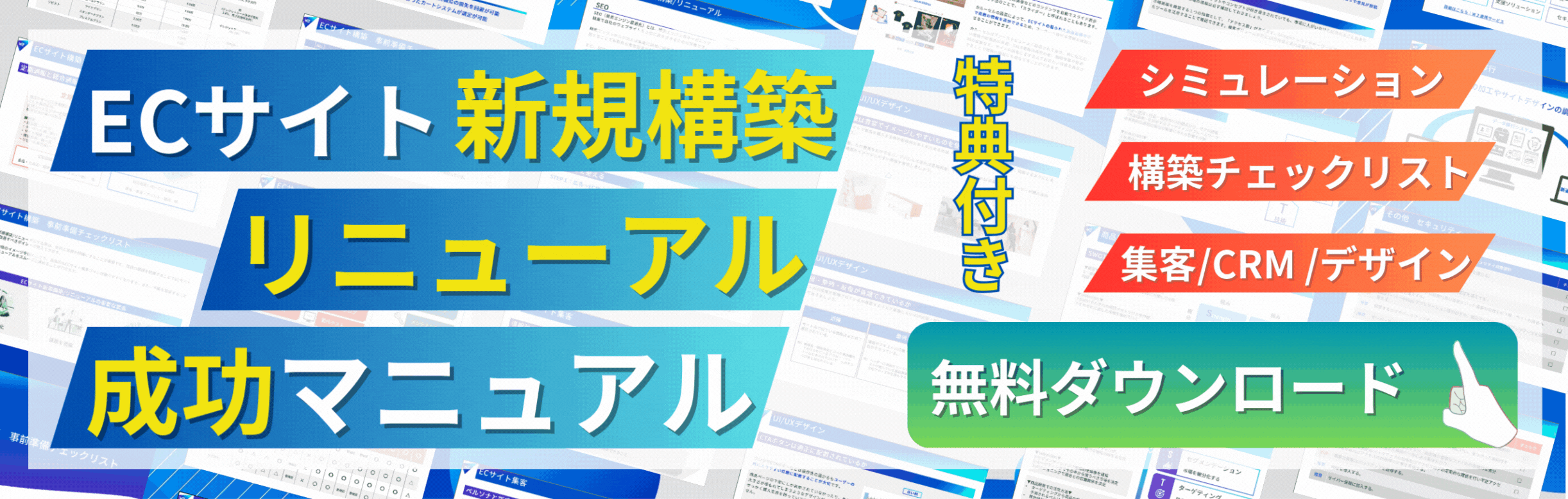
※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。
個人でネットショップを開業するために必要な知識

ネットショップ開業は、まず取り扱う商品と店舗のコンセプト、そして事業としての方向性を考えるところから始まります。
個人でネットショップを始める際、最初に明確化しておきたいのがショップのコンセプトやターゲットとする顧客層です。誰に対してどのような価値を提供するのかを突き詰めると、サイトデザインや商品ラインナップが定まりやすくなります。
また、ネットでの販売が可能かどうか、法律・規制の有無を把握することも欠かせません。商品によっては特定の許可申請が必要な場合があるので、事前に調査を進めましょう。
「自分が売りたい商品が明確」「扱う商材が特定の規制に該当するかどうかを確認済み」といった状態が理想です。これらの基礎を踏まえて、スムーズに事業計画を立てていきましょう。
販売する商品や、お店のコンセプトなど事業計画を立てる
ネットショップを始める前に、商品を通じてどんな価値を提供するのかを明確にすることが重要です。ターゲットとなる顧客層を絞り、彼らのニーズに合った品揃えやサービス、価格帯を検討することで、サイトの方向性が固まります。
商品のコンセプトが曖昧なままスタートすると、集客やブランディングが難しくなり、マーケティング施策の効果も薄くなりがちです。逆に、ユニークなコンセプトを持っていると話題を呼ぶことがあり、広告費をかけなくても自然と集客が生まれる可能性があります。
事業計画を立てる際には、具体的な収支シミュレーションも忘れずに。仕入れにかかるコストや販売価格の設定、月々の運営費用を洗い出し、利益見込みを算出して目標を設定しましょう。
法的な販売可否の確認
ネットショップで扱う商品が法律上販売可能かどうかを確認することは、トラブル回避のために非常に重要です。特に、医薬品やサプリメントなどのカテゴリは、販売に関係する規制や認可制度が存在し、法人化していないと売れない商品というものもあります。
下調べを怠り販売を始めてしまうと、後から行政機関から警告を受けたり、事業停止を余儀なくされる恐れがあります。必ず販売前に、商品ジャンルごとの規制や届け出の有無を確認しましょう。
また、都道府県や市町村によっては独自の規定を設けているケースもあります。ネットでの通信販売に詳しい専門家に相談するなどして、万全の態勢を整えるのがおすすめです。
必要な届出の確認
以下のように、取り扱う商品の種類によって必要な資格は異なります。
| 商品の種類 | 必要な資格・許可・申請 |
| 食品 | ・食品衛生責任者の免許 ・食品衛生法に基づく営業許可 |
| 中古品 | ・古物商許可 |
| 化粧品 | ・化粧品製造販売許可 ・医薬部外品製造販売許可 |
※上記は一例
必要な資格や手続きを済ませていなければ、せっかくネットショップを立ち上げても運営することができません。
どのような資格や手続きが必要なのか、取り扱う商品をもとにぜひ確認してみてください。
また、個人事業主であれば「開業届」を管轄の税務署に提出する必要があります。
開業届を出さなくても罰則や督促があるわけではありませんが、青色申告ができない・屋号を使えないなどのデメリットがあるので、提出しておくのがおすすめです。
ちなみに、法人登録済みの方は提出する必要はありません。
商品・サービスに合ったECプラットフォームを選定する
ネットショップのコンセプトが決まり、必要な機能など要件も固まったら、それらを実現するための「ECプラットフォーム」を選びます。
ECプラットフォームとは、ネットショップの構築・運営に必要な機能(買い物カゴや決済など)を搭載したベースとなるシステムのことです。
大まかな検討のステップとしては、
- 自社ECかモールECか選ぶ
- 自社ECの場合、どの主要プラットフォームにするか選ぶ
- 具体的にどのプラットフォームにするか選ぶ
といった具合に、自社にとって最適なものを絞り込んでいきます。
各ステップについて一つずつ見ていきましょう。
①自社ECかモールECか選ぶ
| 自社EC | モールEC | |
| イメージ | 路面店 | ショッピングモール |
| 初期コスト | △ 安価〜高価 |
◯ 安価 |
| 運営コスト | ◯ 余計なコスト無し |
△ 販売手数料など発生 |
| 利益率 | ◯ 高い |
△ 低い |
| 導入ハードル | △ 低い〜高い |
◯ 低い |
| カスタマイズ | ◯ 自由度が高い |
× 機能やデザインが大幅に制限 |
| 集客力 | △ 自力での集客が必要 |
◯ モール経由での集客が可能 |
| ブランディング | ◯ 「この店で買った」という認識 |
△ 「モールで買った」という認識 |
| リピート購入 | ◯ しやすい |
△ しにくい |
| データ取得 | ◯ 全部 |
× 一部 |
ECプラットフォームは、大きくわけて「自社EC」と「モールEC」の2種類があります。
自社EC:独自ドメインを取得して、サイトを構築・運営する形態
モールEC:Amazonや楽天市場など、モール内に出店する形態
自社ECはいわば「路面店」であり、自分たちで独自のサイトを立ち上げて運営を行うものです。
コストは比較的かかりやすいですが、その分カスタマイズの自由度が高く、
- 競合と差別化がしやすい
- やりたい施策を実行しやすい
などのメリットがあります。
また、モールECによる運営の制限がないため、顧客データを自由に取得・分析して戦略立案に役立てられるのも大きな利点です。
>【初心者必見】自社ECとは?ECモールとの違いやメリット・デメリットについて解説
一方、モールECは「大型ショッピングモール」のようなイメージです。
モール自体の集客力を活かせるのが強みですが、モール内の集客争いに巻き込まれやすいというデメリットもあります。
また、モールの規約に従って運営しなければならず、差別化や独自のブランディングを打ち出すのは難しいです。
>【2023年最新】ECモールの種類とランキングを解説!出店方法や費用比較表も公開
このように、自社ECとモールECはそれぞれ一長一短のため、「どちらが優れている」というのはありません。目的や要件に応じて、最適なほうを選ぶことが大切です(もちろんどちらも併用する方法もあります)。
ただ、自社ECのほうが長期的にみると売上を拡大しやすいため、事業としてしっかり伸ばしていきたい場合は、自社ECを前向きに検討してみるのがおすすめです。
②【自社ECの場合】どの主要プラットフォームにするか選ぶ
| ASP | オープンソース | パッケージ | |
| 構築方法 | 構築に必要なシステムをレンタル | 無償ソースコードをカスタマイズ | 充実したパッケージをもとに開発 |
| 初期費用 | 低 | 低 | 中 |
| 月額費用 | 低〜中 | 低 | 中 |
| 構築スピード | 早 | 早 | 中 |
| カスタマイズ性 | 低 | 中 | 高 |
| メリット | ・コストを比較的抑えやすい ・出店が比較的しやすい |
・コストを比較的抑えやすい ・カスタマイズ性が比較的高い |
・カスタマイズ性が高い ・セキュリティが強固&サポートを得やすい |
| デメリット | ・カスタマイズ性が低い ・外部連携がしにくい |
・高度な専門スキルが必要 ・セキュリティリスクが高い |
・比較的コストがかかりやすい ・システムのアップデートが必要 |
自社ECの中でも、ベースとなるプラットフォームにはいくつか種類があります。その中でも主要なものを3つ紹介します。
- ASP:構築に必要なシステムをレンタルして作成(カスタマイズはほぼ無し)
- オープンソース:公開されているソースコードをもとにカスタマイズ
- パッケージ:充実した機能やシステムが備わったパッケージをベースに開発
※なお、プラットフォームそのものをゼロから作る「フルスクラッチ」もありますが、本記事では既存のプラットフォーム活用に焦点を当てて解説します。
コスト面で見ると「ASP」や「オープンソース」に軍配が上がりますが、ネットショップとして売上の拡大や安定的な運営を目指すなら、カスタマイズ性やセキュリティに優れる「パッケージ」がおすすめです。
コストという一面だけで判断するのではなく、要件と照らし合わせながら総合的・長期的に見て個人に最適なプラットフォームはどれかを検討しましょう。
>主要ECプラットフォームを比較!自社に合った選び方や構築方法も紹介
③具体的にどのプラットフォームにするか選ぶ
大まかな方向性が決まったら、具体的にどのプラットフォームにするかを選びます。
例えば、モールECといっても「Amazon」「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」のようにさまざまな種類があり、それは自社ECにおけるASP・オープンソース・パッケージも同様です。
そのため、個人事業主でも受け入れてもらえるカートシステム会社をいくつかリストアップし、相見積もりを取りましょう。
会社によって初期費用が数十万円違う場合もありますし、機能面やサポート面の条件も異なるので、複数社から話を聞くことがおすすめです。
また、以下の記事ではネットショップを開業する際におすすめのプラットフォームを10選ご紹介しています。
この機会にぜひご覧ください。
【2024年最新版】ネットショップ開業おすすめサービス10選|選定ポイントや注意点を徹底解説
ネットショップのサイト制作を行う
プラットフォームを決めたら、サイトのデザインや決済方法の設定、商品登録などを行います。写真のクオリティや商品説明のわかりやすさは購買意欲に大きく影響するため、手間を惜しまずに作り込みましょう。
プログラミングの知識がなくても、感覚的に操作ができるEC構築サービスやショッピングカートシステムが多数存在します。予算に応じて、テンプレートを利用するのか、デザイナーに依頼してオリジナルサイトを作るのかを選択します。
また、ユーザーがストレスなく購入できる導線設計も重要です。カートに商品を入れてから決済までのステップ数をできるだけ短くするなど、使いやすいサイト設計で購入率アップを狙いましょう。
オープン・集客
オープンしたからといってユーザーがすぐに来てくれるわけではありません。
- 事前にSNSなどで告知する
- プレスリリースを打つ
などして、多くの人に認知してもらえるよう行動することが大切です。
また、実際にネットショップをオープンしてみると、必ずと言っていいほど思わぬハプニングが起こるものです。
その時になってあわてることがないように、
・事前にマニュアルを作成・共有しておく
・カートシステム会社に「過去に起きたトラブル」などを共有してもらう
といった準備を進めておきましょう。
サイトをオープンしてからが本当の勝負です。ユーザーの満足度を高め、売上を伸ばしていくためにも、継続的にサイトの改善を行っていきましょう。
>ECサイトの集客法とは?プロモーションチャネルと運用のコツをご紹介
また、より詳しく成功するネットショップ構築手順を知りたい方は以下の資料でチェックリストと共に解説しているので、この機会にぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
個人ネットショップ開業時の仕入れ方法5選

個人ネットショップ開業時には、商品の仕入れ方法が多数あるため、どの方法が最適か悩まれる方も多いでしょう。
以下では、おすすめの仕入れ方法5選と、それぞれのメリットおよび注意点について解説します。
メーカーから直接仕入れる
メーカーから直接商品を仕入れる方法は、商品の製造元と直接取引を行うことを指します。
この方法では、卸売業者やディストリビューターを介さないため、中間マージンが発生せず、より低コストでの仕入れが可能となります。また、メーカーとの直接的な関係構築により、最新商品情報の入手や専売商品の取り扱いなど、他店との差別化要素を獲得できる利点があります。
ただし、メーカーによっては最低発注数量が設定されていることが多く、初期投資額が大きくなる可能性があります。また、直接取引を行うためには営業許可や古物商許可証などの各種許認可が必要な場合もあり、審査基準も厳しい傾向にあるため、開業初期の小規模ショップにとってはハードルが高い側面もあります。
ドロップシッピングを用いる
ドロップシッピングは、実際の在庫を持たずにネットショップを運営できる仕入れ方法です。顧客から注文を受けた後に卸業者やメーカーから商品を発送してもらう形式で、在庫リスクがなく初期投資を抑えられるため、少ない資金で開業できる点が最大の魅力です。
また、商品管理や発送作業が不要なため、マーケティングや集客などのコア業務に集中できるメリットもあります。特に多品種の商品を扱いたい場合や、商品知識が豊富でなくても始められる点が個人事業主に適しています。
一方で、利益率は一般的に低く設定されており、他店との価格競争に巻き込まれやすい傾向があります。また、在庫状況や配送のコントロールができないため、品切れや配送遅延などのトラブルが発生した際の対応が難しく、顧客満足度に影響を与える可能性があります。
オークションやフリマアプリを用いる
オークションサイトやフリマアプリを活用した仕入れ方法は、個人間取引の場を通じて商品を調達するアプローチです。
ヤフオクやメルカリなどのプラットフォームでは、市場価格より安く商品を入手できる機会が多く、特に中古品や限定品などの特殊な商品カテゴリーに強みを発揮します。
個人が放出する未使用品や新品を狙うことで、低コストで良質な商品を仕入れることも可能です。また、少量から仕入れられるため、商品の売れ行きを確認しながら在庫を増やせる柔軟性があります。
しかし、安定した数量の確保が難しく、継続的な商品展開を計画しづらいというデメリットがあります。また、商品の真贋や状態に関するリスクも伴い、場合によっては偽物や不良品を仕入れてしまう可能性もあるため、商品知識と鑑定眼が求められます。
ネットの仕入れサイトを用いる
ネット上の卸サイトや仕入れサイトを利用する方法は、オンライン上で完結する効率的な仕入れ方法です。国内外の様々な卸業者がオンラインプラットフォームを通じて商品を提供しており、実店舗に足を運ばなくても多種多様な商品を探索・発注できる利便性があります。
また、海外の仕入れサイトを活用すれば、国内では珍しい商品を調達してオリジナリティを出すこともできます。
一方で、実物を確認せずに仕入れることになるため、商品の品質やサイズ感などに関するミスマッチが生じるリスクがあります。特に海外サイトの場合は言語の壁や通関手続き、関税の問題、配送トラブルなどのハードルが存在します。
取引相手の信頼性確認も重要で、レビューや実績を十分に調査してから取引を始めることが望ましいでしょう。
個人店舗や作家から仕入れる
個人店舗や作家、クリエイターから直接商品を仕入れる方法は、他店にはない独自性の高い品揃えを実現できる強みがあります。
ハンドメイド作品やローカルブランド、地域特産品など、大量生産されていない商品を扱うことで、オリジナリティあふれるネットショップを構築できます。
また、小ロットからの発注が可能なケースが多く、売れ行きを見ながらリスクを抑えた仕入れが可能なことも魅力です。
しかし、安定した品質や納期の確保が難しい場合があり、生産キャパシティの限界から急な注文増に対応できないこともあります。
その他、以下の記事では、ネットショップの商品仕入れを成功させるポイントについて詳しく解説しています。
商品仕入れの方法やポイントが分からない人は、ぜひこの記事を参考に実践してみてください。
個人のネットショップ開業に必要な手続き

ネットショップを正式に運営するには、税務署や行政関連の書類提出など、適切な手続きを踏まなければなりません。
個人でネットショップを始める場合、まずは税務署への開業届を提出し、個人事業主として活動をスタートさせます。開業届を出すことで、正式に事業として所得を申告し、税務面でのメリットやデメリットを把握しながら運営が可能となります。
売上や経費の管理をしっかり行うと、確定申告の際にスムーズに書類が作成できます。特に青色申告を選択する場合は、帳簿の作成や決算処理が求められるので、早めに準備を始めましょう。
正しい手続きを踏まないでいると、後から追加の税金や罰則が課される可能性もあります。
開業直後は忙しいものですが、事業者としての責任を果たすためにも行政手続きには十分な時間を割くようにしてください。
個人事業主・開業届の提出
個人事業主としてネットショップを運営する際は、事業を開始する日から1カ月以内を目安に税務署へ開業届を提出する必要があります。開業届を出しておくことで、確定申告時の手続きが円滑になるだけでなく、銀行口座や各種サービスの事業利用をスムーズにできるメリットも生まれます。
届け出手続きは比較的簡単ですが、遅延すると罰則の対象となる可能性があります。郵送や電子申告が可能な場合もあるため、地域の税務署の対応方法を事前に確認しておくとよいでしょう。
また、事業の屋号をどうするかも重要です。将来的に商標登録を考えている場合は、他社の商標と重複しないかなどをリサーチし、法的に問題ないかを確認してから届け出ることをおすすめします。
確定申告(青色申告)の届け出
青色申告をすることで、白色申告に比べて控除額や節税のメリットを享受しやすくなります。
ただし、複式簿記による帳簿付けや定期的な決算作業など、求められる書類作成の手間は増えます。
青色申告を希望する場合、所定の申請書を提出する期限が定められているので、開業初年度から適用を受けたい場合は早めに準備を始めるのが賢明です。提出期限を逃すと、その年の申告が白色扱いになることもあります。
帳簿付けや会計処理に慣れていないと、最初は負担を感じるかもしれません。しかし、日々の取引をベースに記録していく習慣を持つことで、正確な利益把握と経営判断ができるようになり、長期的にビジネスの安定に寄与します。
個人ネットショップ開業に必要な初期費用とランニングコストの相場

個人ネットショップを開業する際の初期費用・ランニングコストの相場は、選択する商品やプラットフォームによって大きく変わります。
主な費用項目と概算を以下にまとめます。
初期費用
- ドメイン取得費::1,000〜3,000円
- ECプラットフォーム導入費用:0円~30万円
- ECサイト構築費用:10万円~100万円
- OEM/ODM製造委託費::最低ロット数×単価(10万〜100万円程度)
- 認証取得費::JIS規格やPSEマークなど、必要に応じて10万円〜50万円
- 外装箱・内装材開発::金型代含め5万円〜20万円
独自商品を開発する場合は、商品企画等のコストが増加し、より初期費用が大きくなります。
一方、既存商品の仕入れ販売を行う場合は、OEM/ODM費用がなくなる代わりに、仕入れ先開拓費用や初回発注量の確保費用がプラスで初期費用として発生します。
商品企画・開発段階では、想定以上の追加コストが発生するケースが多いため、予算の10〜20%程度を予備費として確保しておくことをお勧めします。
ランニングコスト
- ECプラットフォーム月額料金: 0〜50,000円
- 無料プラン: 楽天市場、Yahoo!ショッピング、BASE、STORESなど(販売手数料のみ)
- 有料プラン: 機能充実型で月額5,000〜50,000円
- 決済システム手数料: 売上の3〜7%
- 商品在庫費用: 取扱商品による(0円〜3万円)
- 梱包材: 1件あたり50〜300円
- 発送料: 1件あたり180〜1,000円(商品サイズ・重量による)
- 在庫管理システム: 月額0〜20,000円(家におけない場合)
- 倉庫費用: 自宅保管の場合は0円、外部倉庫利用の場合は月額3万円〜
- 外注撮影: 1商品あたり1,000〜10,000円
- 広告宣伝費: 月額1万〜10万円(Google広告、SNS広告など)
- デザイン料: テンプレート利用で0円、オリジナルデザインで1万〜10万円
上記からわかる通り、個人でスモールスタートし始めた場合は月額運営費約1〜10万円が少なくとも発生します。
EC事業は初期費用、ランニングコストが必ず発生する事業のため、開業初期は必要最小限の投資から始め、売上に応じて徐々に拡大していくことが賢明です。
多くの成功した個人事業主は、初期の半年〜1年は赤字を想定し、その期間を乗り越えるための資金計画を立てています。最低でも6ヶ月分の運転資金を確保した上で開業することをお勧めします。
ネットショップ開業における費用をより詳しく知りたい方は、以下の記事で相場について解説しているので、この機会にぜひご覧になってはいかがでしょうか。
ネットショップ開業を個人でする際の注意点4選
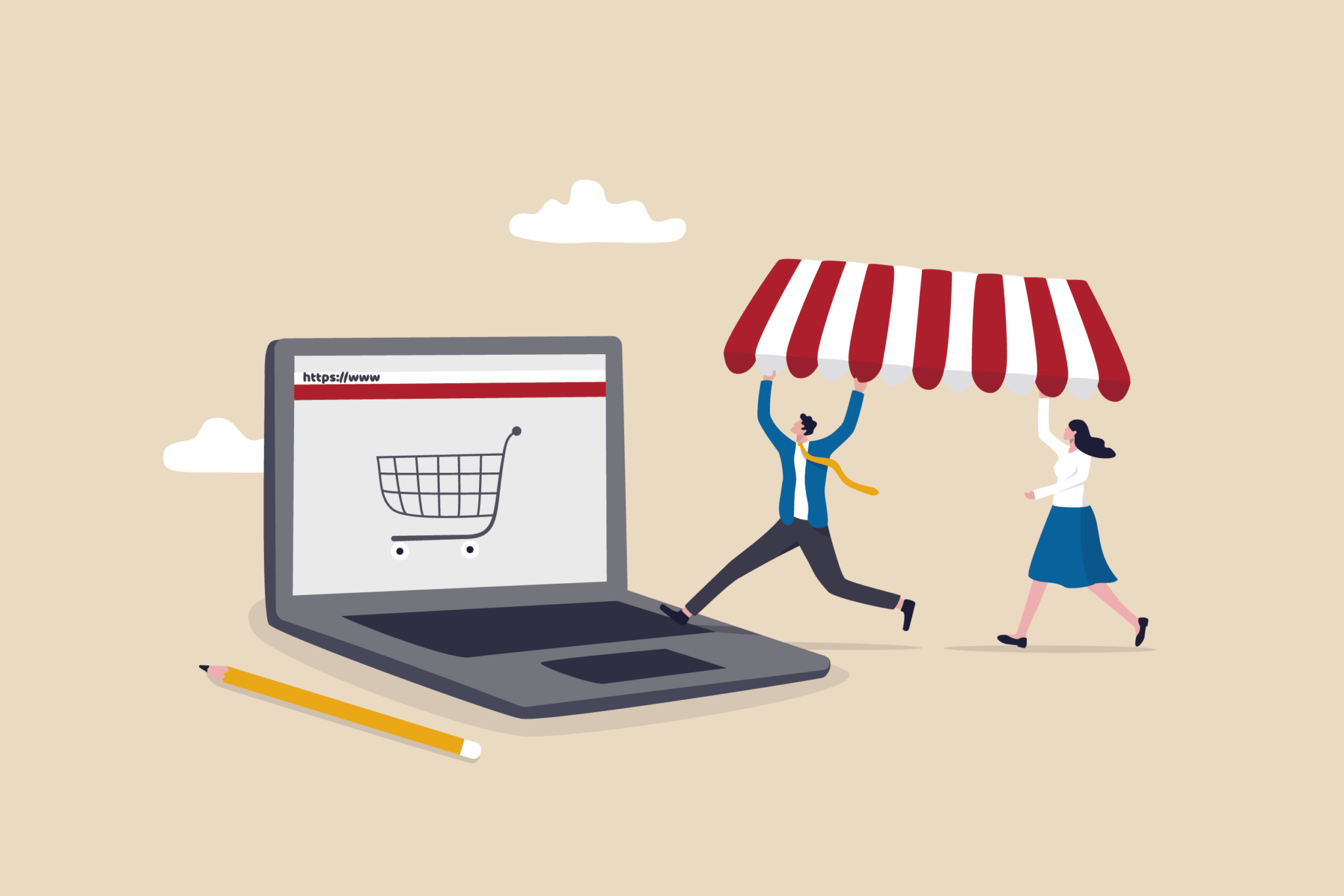
安定して売上を伸ばすためには、賢いコスト管理と適切なプロモーション、そして顧客満足度を意識した運営が鍵となります。
ネットショップを軌道に乗せるためには、コスト管理と集客施策、そして顧客との信頼関係を築くことが不可欠です。経費が増えすぎると利益を圧迫するだけでなく、余裕のない経営状態に追い込まれやすくなります。
また、SNSやSEO対策をはじめとした無料の集客手段を活用して、徐々に知名度を高めていく戦略も大切です。無料施策である程度の売上が見込めるようになったら、広告費を投入してさらなる拡大を目指すというステップを踏むと、リスクを最小限に抑えられます。
顧客からの問い合わせやクレーム対応、レビューへのコメントなど、コミュニケーションの品質がリピーター獲得に直結します。
月々の固定費を抑える
個人でネットショップを開業する際は、固定コストを抑える努力が重要です。
ここでの固定コストとは、広告出稿料金や外部メディア掲載費などの集客コストではなく、倉庫や事務所の賃料、ECカートシステム利用料といったバックエンドに関わるコストのことを指します。
特にカートシステムの月額利用料は、軌道に乗るまでのネットショップの経費を圧迫しやすいため、無料のECカートシステムから始めるのも一つの方法です。
個人での開業時にあるあるなのは、最初から大きな売上をあげたいと考えて、スペックの良い在庫システムやECカートシステムを選定しがちですが、スモールスタートを意識して最初は固定費を抑えながらスタートしたほうが成功しやすい傾向にあります。
無駄な在庫を持たない
個人でのネットショップ開業時は無駄な在庫を持たないように注意しましょう。
もし無駄な在庫を持ってしまうと倉庫スペースを圧迫し在庫管理が複雑になります。
これにより、商品の紛失や遅延が起こり、クレームの原因になることがあるため在庫を最小限に抑えることが失敗を避けるコツの一つです。
また、流行の影響を受ける商品は在庫を過剰に持つと、売れ行きが落ちた時に大きな損失を被る可能性があるため仕入れ量には慎重になる必要があります。
個人でネットショップを開業して間もない時は、どのようなペースで商品が売れるかが検討できない方が多いと思います。よって、少量ずつ商品を仕入れてリスクを抑えながら運営をしていきましょう。
コストと利益の関係性を抑える
ネットショップを始める際はコストと利益の関係性を抑えておきましょう。
コストが少なすぎたら利益が生まれず、コストが大きすぎたら利益が発生するが事業として赤字になる可能性があるので注意が必要です。
一般的には334の法則を基にコスト計算を行います。
334の法則とは、商品原価費用を30%、販売促進費用を30%、その他の経費と利益を合わせて40%に収めることを推奨する法則です。
細分化すると、利益は20%ほどを目指すのが定石とされているので、100万円の費用をかけたら、利益は25万円になるように事業計画を立てましょう。
また、月次・年次の売上目標、損益分岐点の把握も欠かせません。資金計画では自己資金だけでなく、必要に応じた資金調達方法も検討しておくべきです。
こうした数値に基づいた具体的な事業計画があれば、感情や勢いに流されることなく、冷静な経営判断が可能になります。
個人の場合、精密な事業計画を立てることが難しい方もいるかと思うので、その際はEC専門のコンサルタントに依頼することをおすすめします。
その他、EC事業の戦略について詳しく知りたい方は、以下の記事で策定ポイントなどを解説しているので、この機会にぜひご覧になってみてください。
炎上に気を付ける
炎上したら最悪の場合は休店や閉店に追い込まれることもあるため注意しましょう。
炎上しないように顧客対応ルールを定め、適切なオペレーションを行うことが大切ですが、間違った対応をした場合には、真摯に謝罪して適切な対応をすることが重要です。
また、SNSなどと連携する際には過激な表現や誇張し過ぎた言葉を避けて炎上リスクを抑えることが必要です。
炎上によるイメージの損失は取り戻すのに長い時間がかかるため、1人1人の顧客を大切にし、真摯な運営を心掛けることが大切になります。
個人ネットショップ開業で失敗せずに売上を上げるノウハウ3選
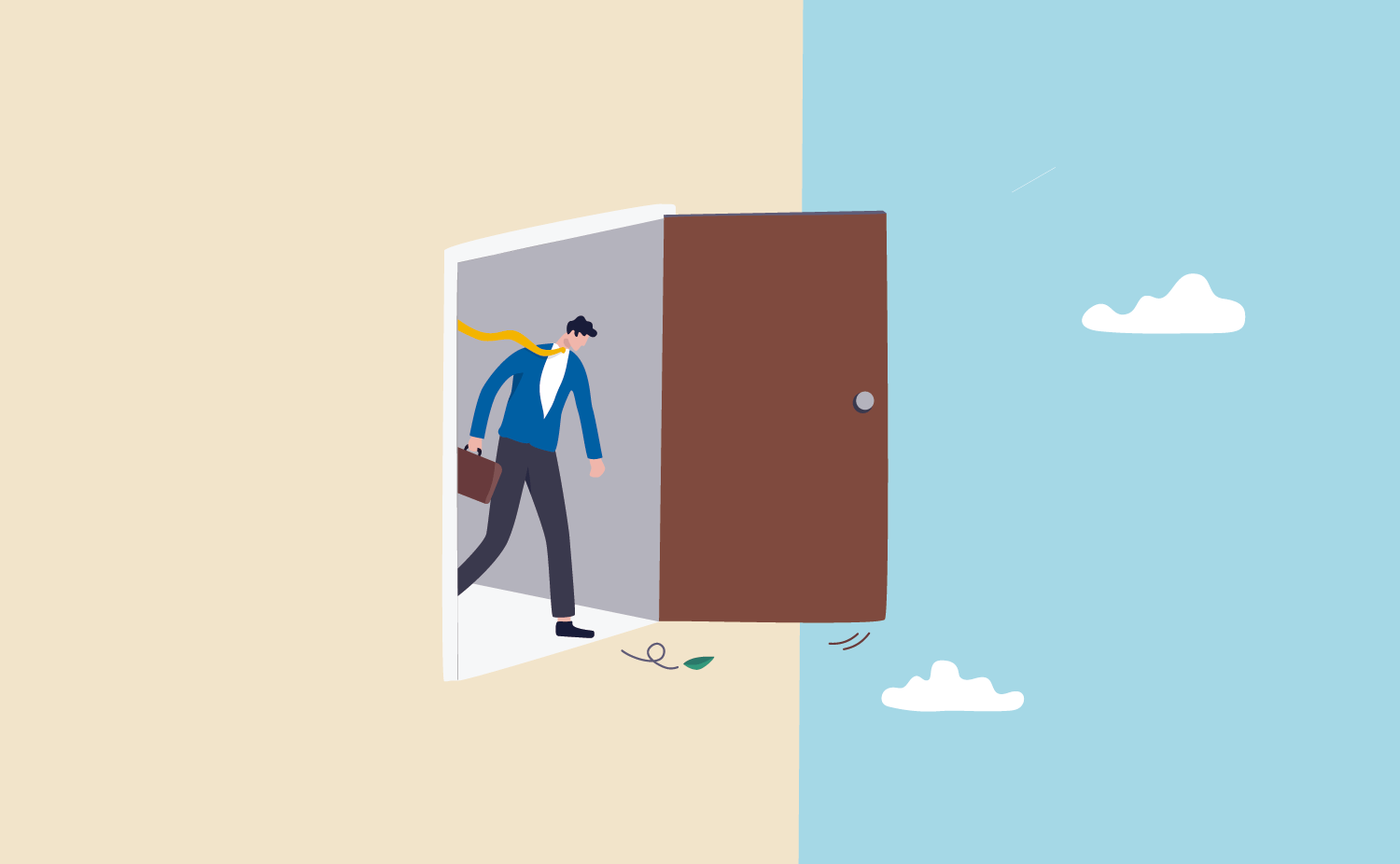
ここまで個人ネットショップ開業のステップや、注意点などをお伝えしました。しかし残念ですが、これらの手順をただこなすだけでは売上を伸ばすのは難しいです。
実際、いつのまにか開業自体が目的になっていたり、目の前のタスクに精一杯になったりするケースは少なくありません。
そこで、個人ネットショップを開業した後、失敗せずに売上を上げ続けるノウハウ3選をご紹介します。
様々な集客チャネルを構築する
ネットショップ開業において安定した売上を確保するには、複数の集客チャネルを構築することが非常に重要です。単一のチャネルに依存すると、アルゴリズム変更や競合激化によって売上が急減するリスクがあります。
また、個人のネットショップ開業初期は、認知度が低く安定顧客も少ないため、多角的なアプローチで潜在顧客との接点を増やす必要があります。各チャネルの費用対効果や相性を早期に把握できれば、限られた予算とリソースを効率的に配分することが可能になります。
主要な集客チャネルと特徴
- SEO対策:長期的に安定した自然流入を生み出しますが、効果が表れるまで時間がかかります。
- SNSマーケティング:Instagram、X(旧Twitter)などで商品の魅力を視覚的に訴求し、ファン層を形成できます。
- リスティング広告:即効性があり、購買意欲の高いユーザーにアプローチできますが、コストがかかります。
- インフルエンサーマーケティング:信頼性の高い第三者からの推薦で認知拡大と信頼獲得ができます。
- メールマーケティング:顧客との関係構築に優れ、リピート購入を促進します。
ネットショップの集客を成功させるためには、まず顧客像を明確にすることが不可欠です。ターゲット顧客の行動特性や好みを理解し、それに合わせた適切なチャネルを選定することで効率的な集客が可能になります。
また、全てのチャネルを一度に展開するのではなく、最初は2〜3のチャネルに注力し、成果を確認しながら段階的に拡大していくアプローチが効果的です。
最初に力を入れるべきチャネルはSNS(Instagramやfacebook)マーケティングです。
他のチャネルと比較して簡単に行えることや、SNSマーケティングは基本的に無料で行えるため、費用を抑えてネットショップ開業を考えている方はSNSマーケティングに注力しましょう。
個人の場合、リソースも少なく、多様な集客チャネルの構築は初期投資と労力を要しますが、長期的な事業の安定性と成長性に直結する重要な基盤となります。
その他、以下ではInstagramマーケティング攻略の定石をまとめた資料を配布しているので、この機会にぜひ閲覧されてみてはいかがでしょうか。
顧客に信頼や安心感を与える
ネットショップで売上を持続的に上げるためには、顧客に信頼や安心感を与えることが不可欠です。顧客が信頼できると感じるネットショップは、リピート購入や口コミによる新規顧客獲得の可能性が高まります。
信頼や安心を築くための施策としては、ページの目立つところに住所や電話番号を記載することや、正確な商品説明と高品質な画像を掲載することが重要です。
さらに、近年では返品や交換ポリシーをはっきりと提示することが求められているため、顧客が商品購入する前後のページ画面で追記しておくとよいでしょう。
ポイントとしては、ただこれらの情報をページに記載するのみではなく定期的に顧客とコミュニケーションを通じて情報を共有しながら、新商品情報やプロモーションも共有することで、顧客の関心を惹きつけ購入に繋げましょう。
豊富に決済種類を用意しとく
近年、決済の種類が増えてきていることから、顧客一人ひとりにあった多様な決済方法を提供することが非常に重要です。
具体的には、クレジットカード決済、デビットカード、電子マネー、後払い、モバイル決済、代金引換を含めることが望ましいです。
また、国際的に販売を行う場合は、地域に応じた決済手段(例えばアリペイやウィーチャットペイなど)を導入することも考慮すると良いでしょう。
これにより、より広い顧客層にアプローチし、国際的な市場での競争力を高めることができます。
ポイントとしてはモバイル決済を含めることが重要です。2024年現在、日本ではモバイル決済の需要が急激に伸びてきています。具体的にはApple PayやGoogle Pay、PayPay、楽天ペイなどです。
SBペイメントサービスが調査した「ECでよく利用する決済手段」の結果では1位がクレジットカード決済で、2位がPayPay、3位が楽天ペイ。という結果になっています。
この結果から分かる通り、顧客がカゴ落ちしないためにもモバイル決済を含めた決済手段を用意しましょう。
ネットショップを開業して成功した事例
それでは実際に、ネットショップを開業して成功した事例を紹介します。
株式会社神戸屋
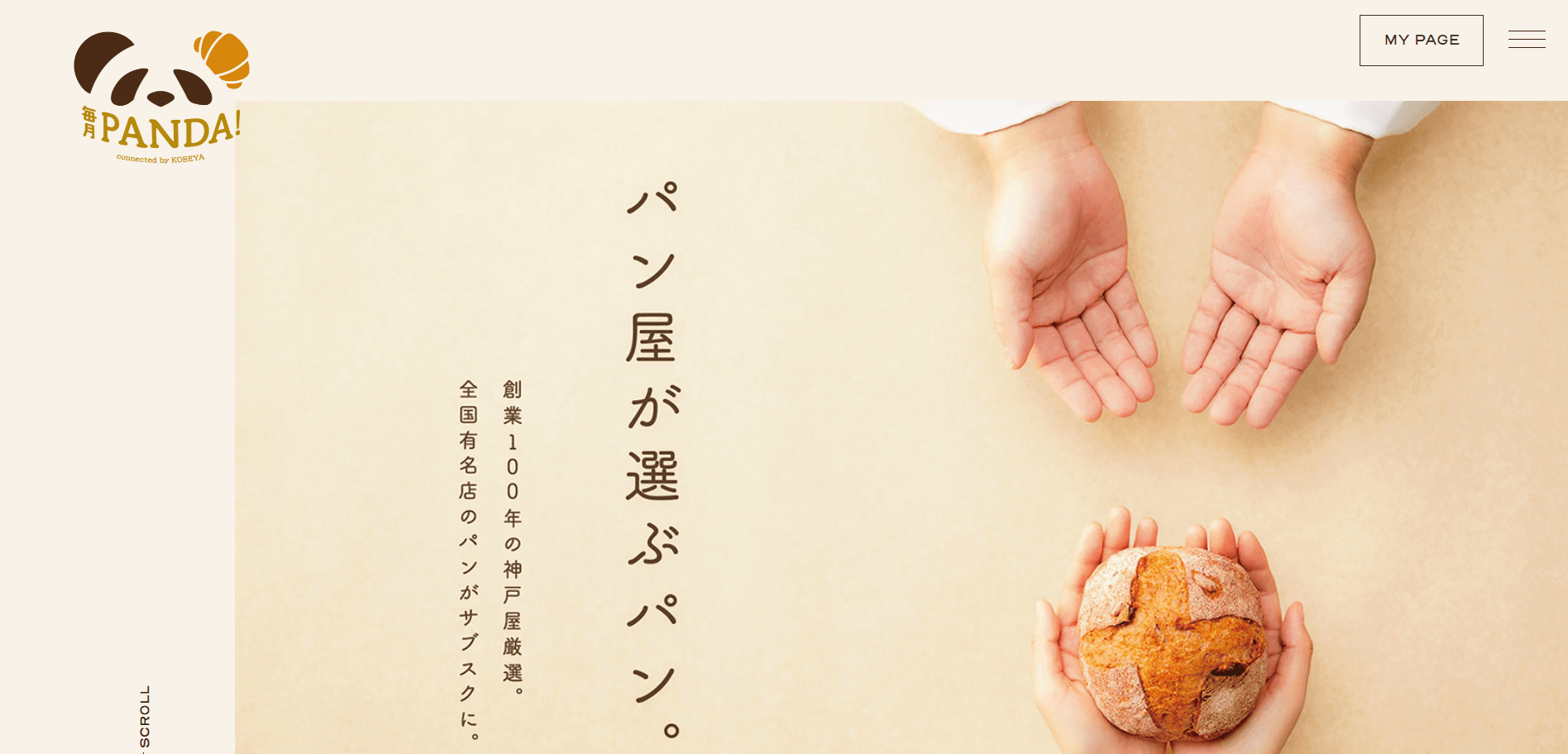
参照画像:神戸屋オンラインストア
株式会社神戸屋が運営しているネットショップ「毎月PANDA!」はネットショップを開業して成功しているといえるでしょう。
まず開業時に、EC業界に初進出ということもあり簡単に操作できて費用が安いECカートシステムを選定し固定コストを低くしてネットショップを開業しています。
また、開業後は頒布会や顧客のマイページに利便性の高い機能を充実させていることで、お客様が信頼してリピートしてくれるネットショップ運営を実現しています。
いまからネットショップの開業をお考えの方は、このように固定コストを低くして顧客の利便性の高い仕様にすることを心掛けましょう。
合同会社M&R
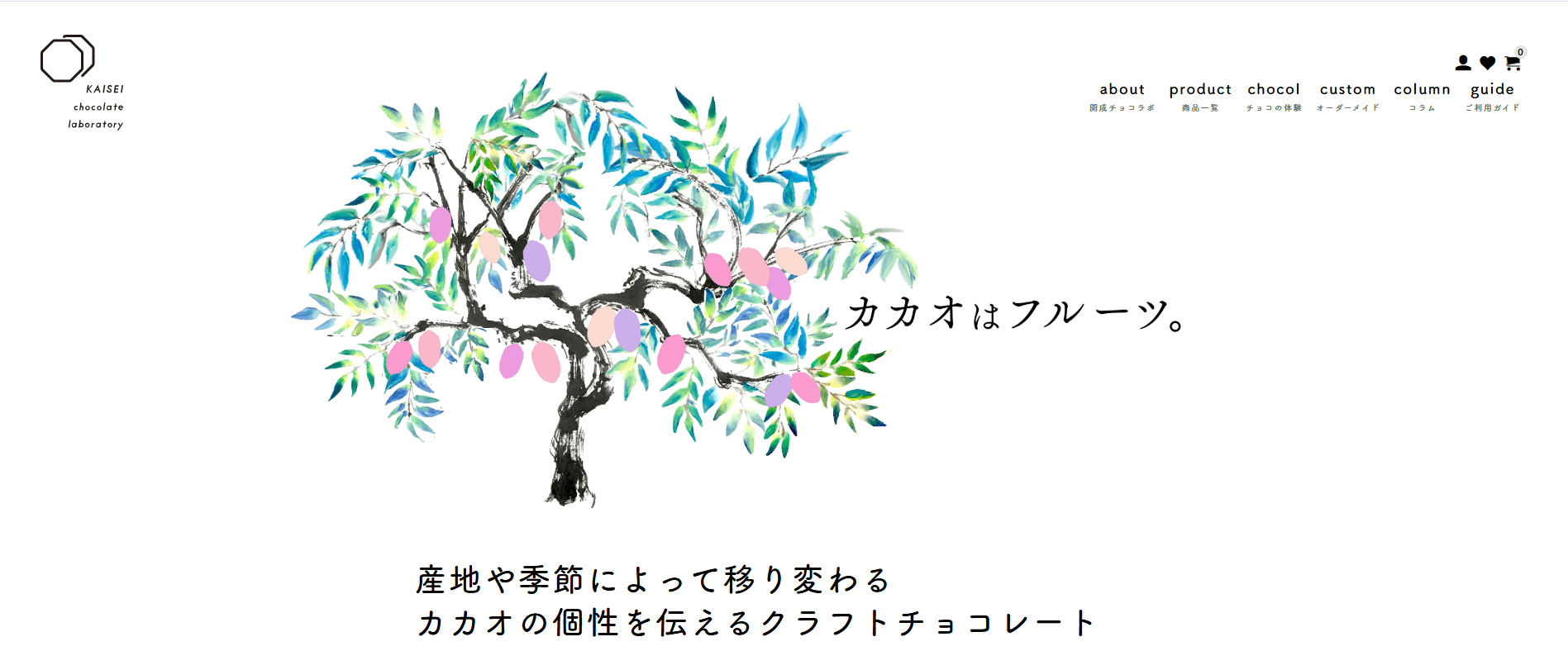
参照画像:KAISEI chocolate laboratory
自社製作の「Origin」ブランドのチョコレート販売に加え、地域食材とコラボレーションした町チョコ「 Yohira」や、オーダーメイドチョコレートのOEM製造を行っている合同会社M&Rは、細かな市場調査やコンテンツ配信で成功を収めています。
市場調査では、チョコレートにおけるオーダーメイド会社がないことや、消費者が自分の好みの味や量に合わして食べたいというニーズを発見して、事業を立案。
その結果、消費者ニーズを捉えながら事業拡大に成功しています。
コンテンツ配信では、ネットショップページ内に、カカオやチョコレートに関する豆知識、コラボや輸入活動の報告、カカオ農園の紹介など、ブランドやチョコレートに関する幅広い情報発信の場として活用した結果、直接商品購入への導線を引くことができ、独自の顧客体験を提供できています。
総じて、チョコレート単体だけでは、大企業が独占している市場になるが、オーダーメイドという価値を組み合わせたことで、小規模でも成功できた事例になっています。
さらに詳しくネットショップを開業して成功している企業を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。ネットショップで成功するためには成功した事例をインプットして、真似することも重要です。
この機会にぜひ合わせてご覧になられてはいかがでしょうか。
その他、成功を収めている他の個人事業主の、ネットショップ事例を知ることも重要です。
以下では、業界別にEC事業で売り上げUPを実現した「成功の秘訣」を下記資料にまとめました。
無料で資料ダウンロードできるのでぜひ一緒にご一読ください。
個人ネットショップ開業に使える補助金・助成金はあるの?

事業拡大や新規開業においては、条件次第で公的な支援制度を活用できるケースがあります。個人ネットショップを立ち上げるにあたり、以下のような補助金・助成金を利用できるケースがあります。
- IT導入補助金(最大450万円、2/3補助)
- 事業再構築補助金(最大6,000万円、2/3補助)
- ものづくり補助金(最大1,000万円、2/3補助)
- 小規模事業者持続化補助金(最大100万円、2/3補助)
- 地元の自治体や商工会議所による補助金
補助金を活用すれば、ネットショップ開業における資金の負担を大幅に減らすことができます。
しかし、補助金を申請する書類の作成には多くの手間がかかるうえに、補助金の枠には限りがあるので、全員が補助金を受け取れるわけではありません。また、同じ案件で国から複数の補助金を受けることもできません。
補助金に頼らず、審査に通らない可能性も視野に入れ、事業計画を立てることをおすすめします。
まとめ:成果が上がるネットショップを個人で開業しよう
ネットショップは少ない資金でも始められる魅力がありますが、成功させるには計画と準備、そして柔軟な運営対応が不可欠です。
また、目先の利益を優先して準備を進めてしまうと、長期的には売上がなかなか伸びず、日々の業務に忙殺されることもあります。
そのような事態を避けるには、「開業」そのものをゴールとするのではなく、その先にある「成果」にフォーカスして判断することが大切です。
ぜひ本記事を参考に、ネットショップ開業を進めてみてください。
なお、EC事業をスタートしたい方・検討している方に向けて、「競合調査と差別化できる調査と分析方法」をまとめました。EC運営を始めるうえで特に「競合他社とどう差別化するか」という点は、ECの成功と失敗に大きく影響します。
資料を無料でダウンロードできるので、ぜひご一読ください。