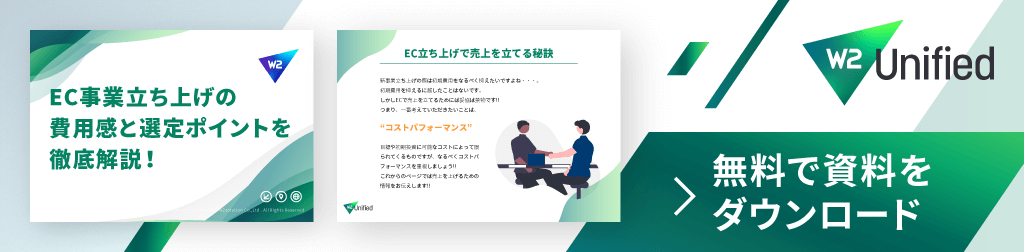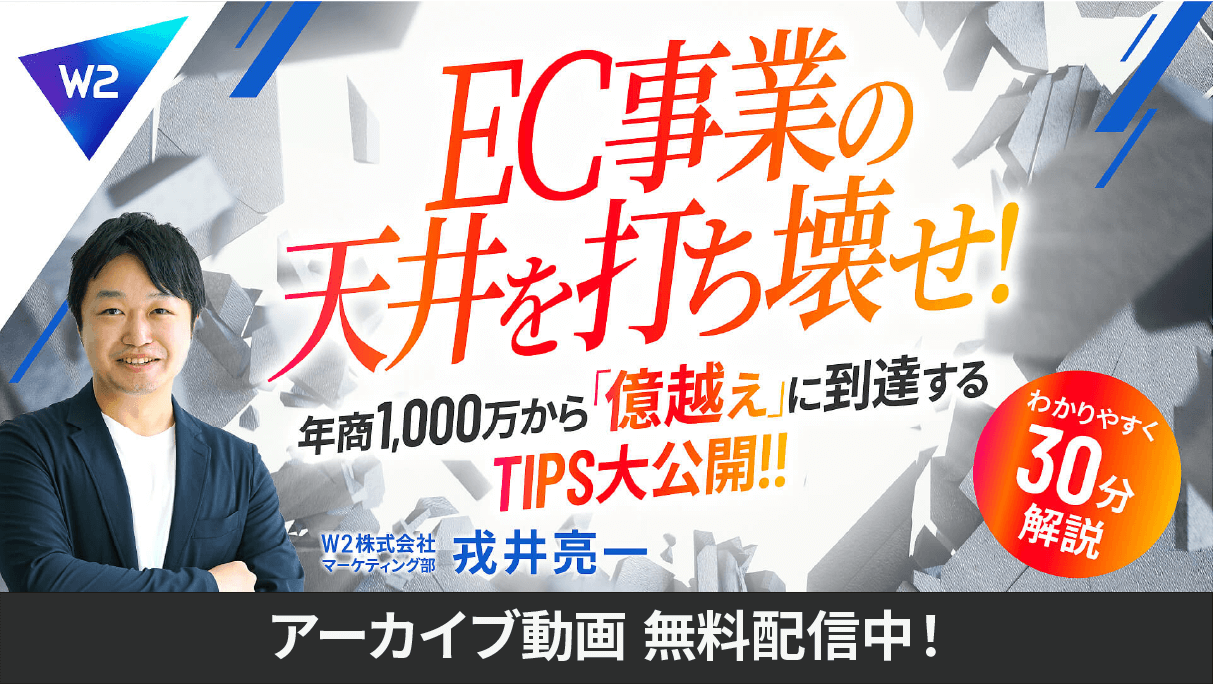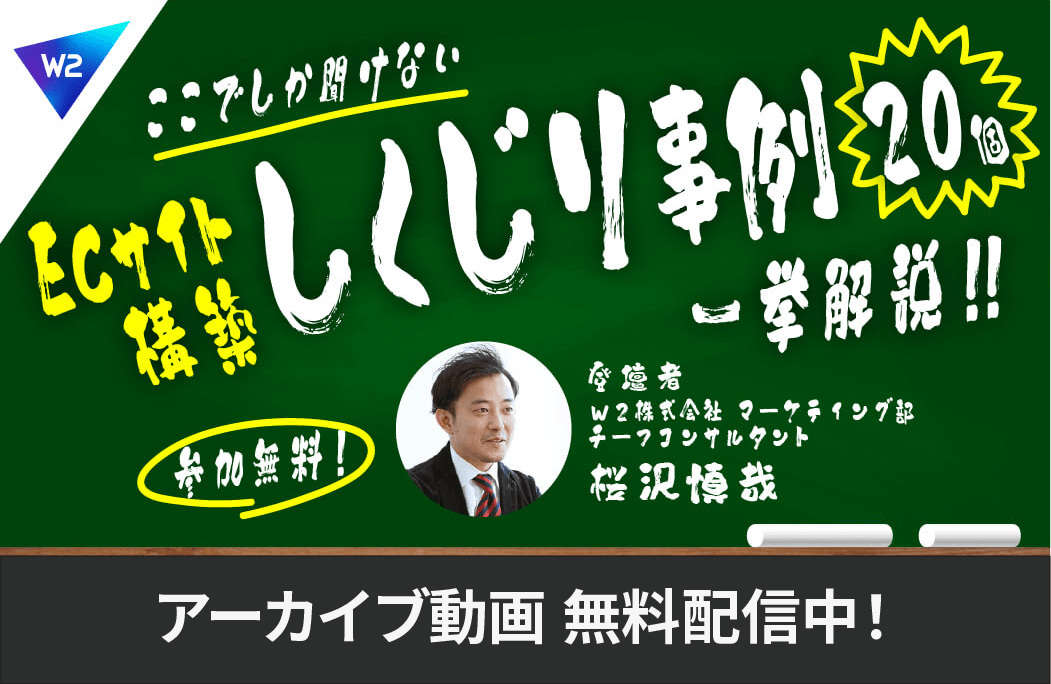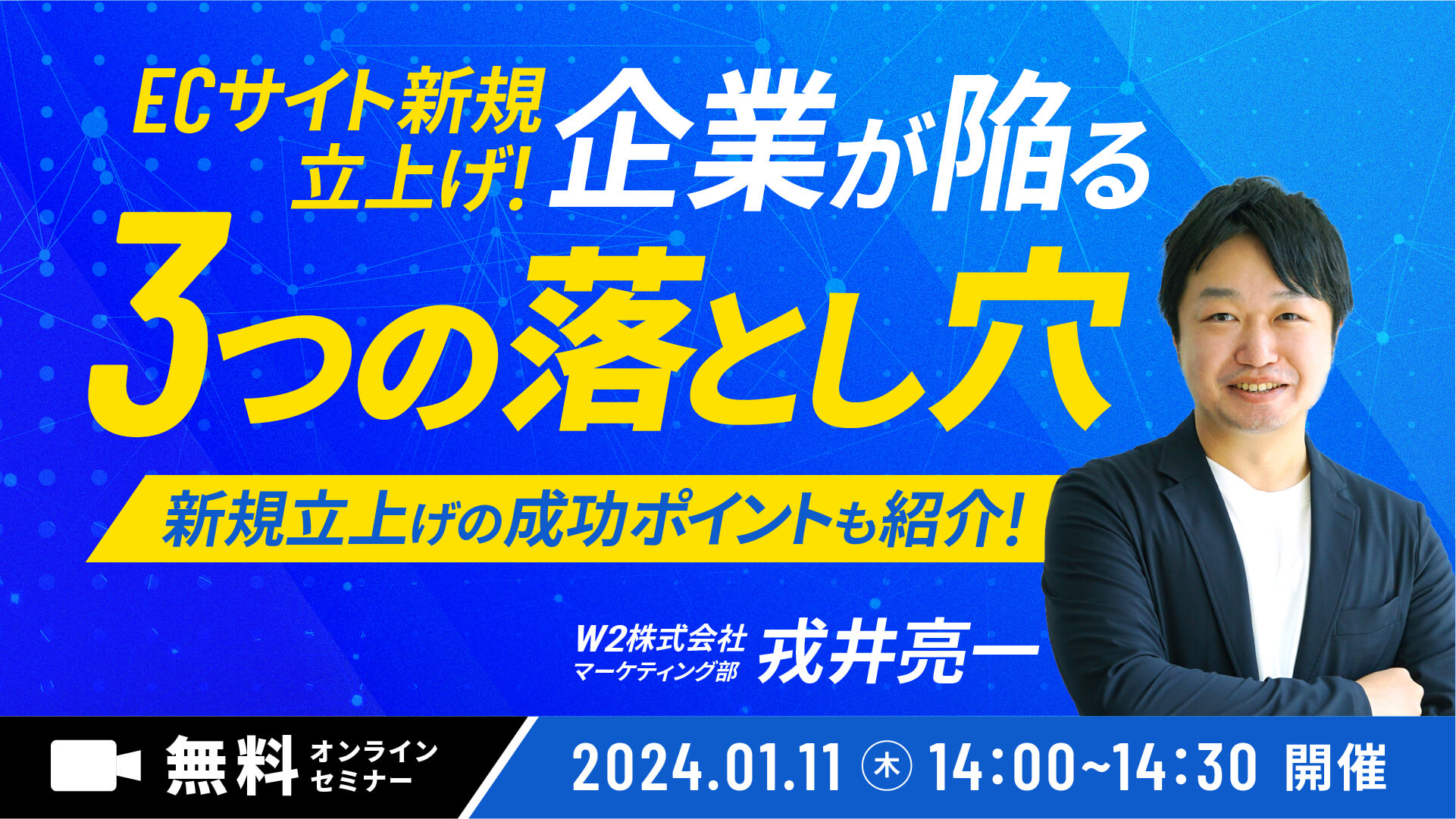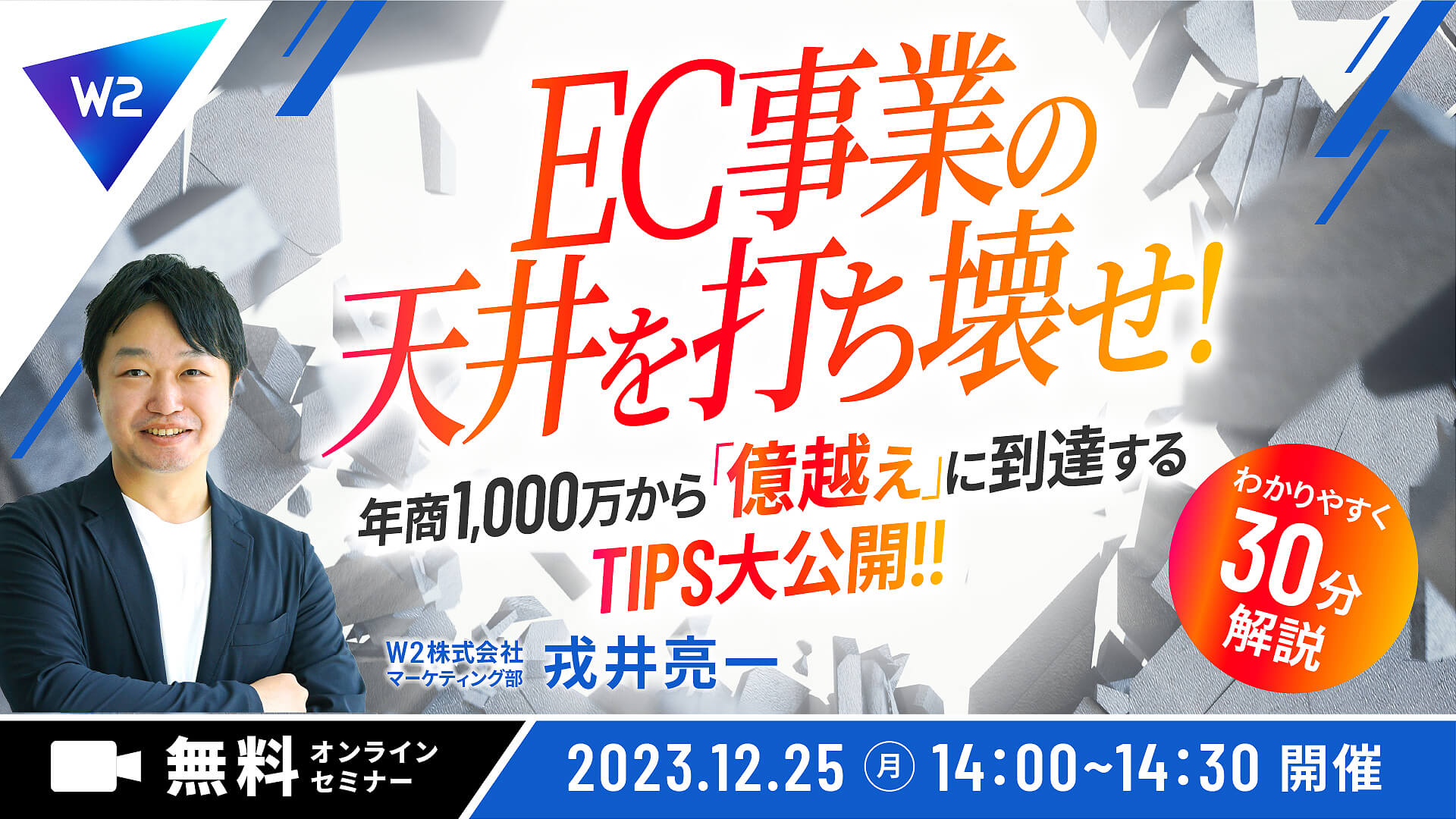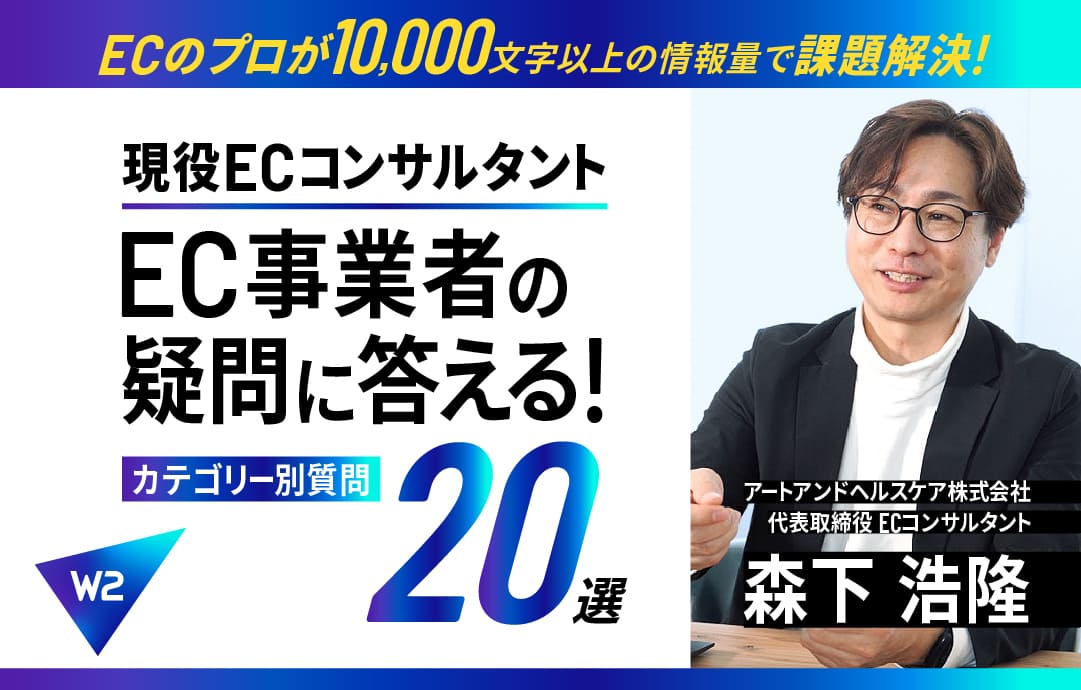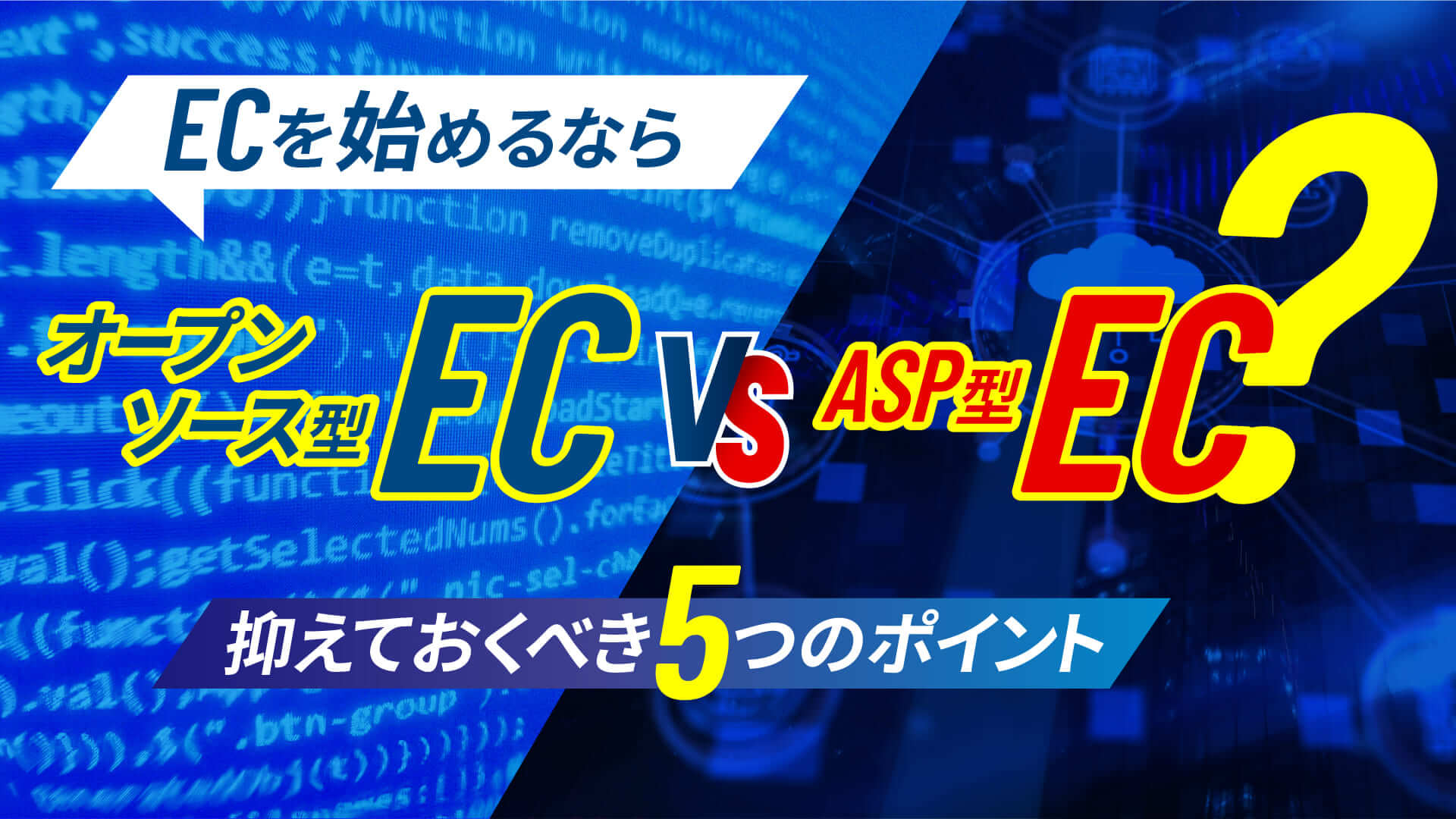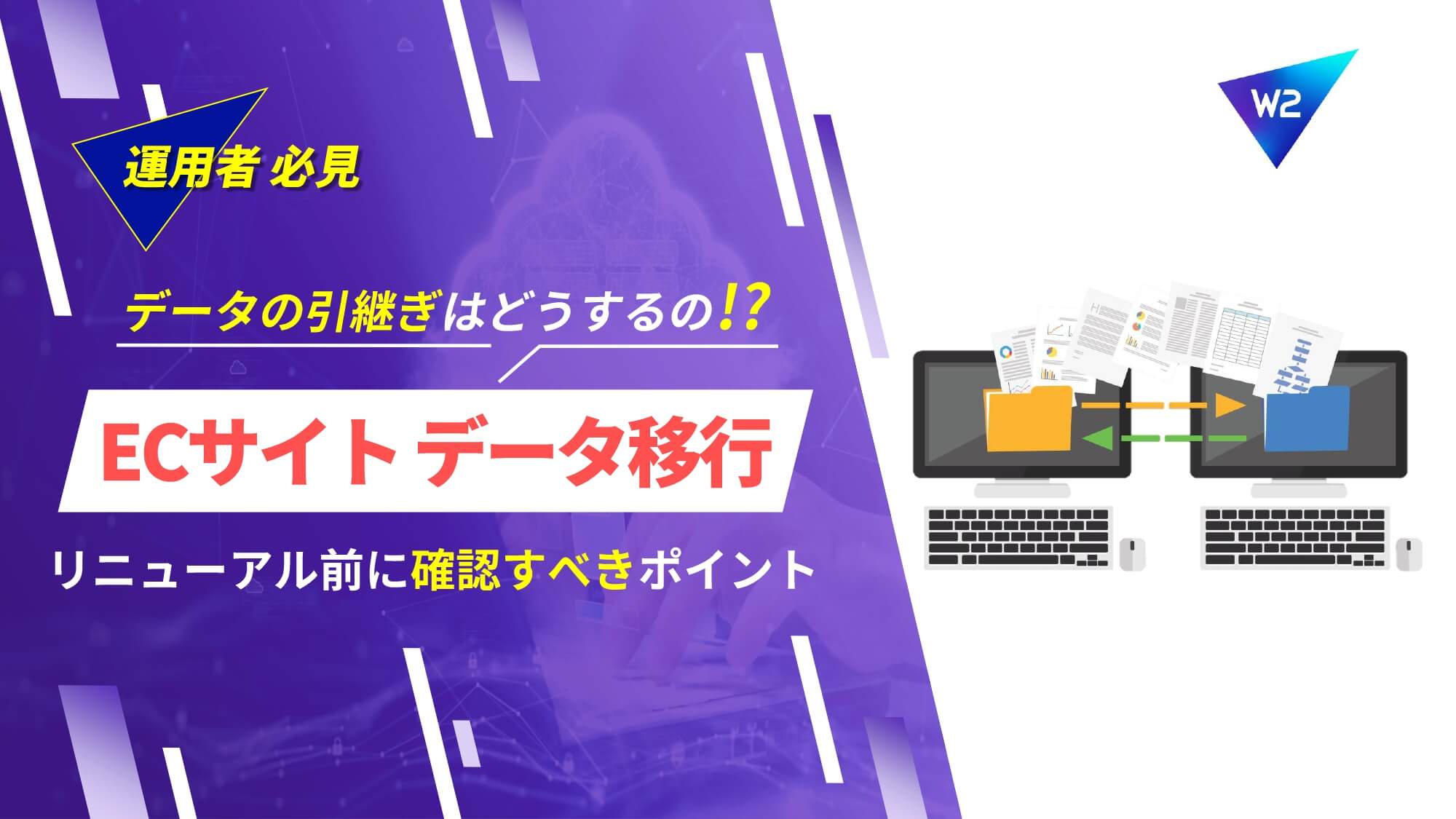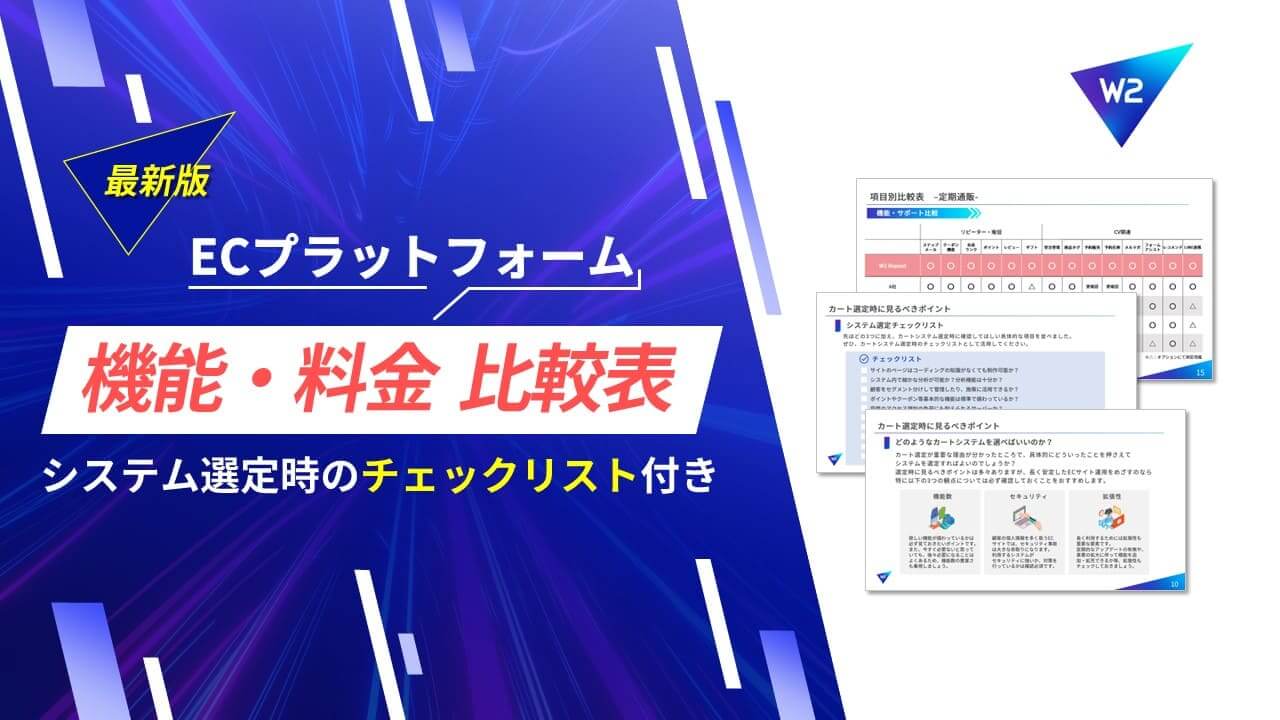EC決済とは?自社ECサイトに導入するべき決済や決済代行サービスの選び方を解説
ECサイトの売り上げは、顧客が選択可能な支払い方法によってある程度左右されます。
決済を導入するのは時間やコストがかかることも多いのですが、その分顧客の決済画面での離脱を防ぐことが可能になります。
GMOペイメントサービスによると、よく利用する支払い方法がない場合、60%以上が離脱し他のサイトで同じ商品を購入するというデータが出ています。
よって、顧客の決済方法に合わせた支払い方法を多く導入することで最大で60%もの離脱を防ぎ、その分売上に繋がるため、豊富な決済方法を導入することは重要になっています。
しかし、決済方法は年々増加しており、どの決済方法を自社のECサイトで採用すべきか迷っているという運営者も少なくないでしょう。
そこで本記事では、ECサイト上の決済の種類やそれぞれのメリット・デメリット、決済方法や決済代行会社の選び方などを詳しく説明していきます。
W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。 数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!
\成功しているEC事業者が確認している資料/  30秒で業界No.1資料を無料ダウンロード
30秒で業界No.1資料を無料ダウンロード
※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。
決済の導入を考える時のポイントや判断基準

上記では、EC決済の現在や将来性について説明してきました。
次に、ECサイトに導入する決済方法を決める際のポイントを説明します。決済方法の導入ポイントは以下の5つです。
・ユーザーの属性
・商品・サービスの価格帯
・セキュリティ
・導入・運用コスト
・決済トレンドやシェア率
以下ではそれぞれ詳しく説明していきます。
ユーザーの属性
自社にどの決済方法が適しているかは、業界や業種のみからではなく年齢や性別などのユーザー属性からも検討することがポイントです。
例えば、10代などの若年層では、クレジットカードの所有率は高くないでしょう。
パソコンよりもスマートフォンからECサイトにアクセスするという人も多いため、携帯電話料金とあわせて支払いができるキャリア決済は相性がよい方法だと考えられます。
一方、50代以上の世代では「Amazon Pay」や「楽天ペイ」などのID決済はあまり利用されず、口座振替などの銀行系決済のほうが好まれる傾向があります。
年齢や性別以外にも、職業や趣味趣向といったユーザー属性が決済方法に関係することもあるかもしれません。
例えば、アパレル関連のECサイトであれば、特定のユーザー層に向けたブランドなのか、より幅広い層をターゲットにしているのかを基準にして考えてみるとよいでしょう。
商品・サービスの価格帯
最適な決済方法は、商品やサービスの価格帯によっても変わってきます。
例えば、高額な商品の支払いでは、ポイントが獲得でき分割払いもしやすいクレジットカード払いを選ぶユーザーが多いでしょう。
反対に、1回限りの少額決済ではクレジットカード番号を入力することが手間だと感じやすいため、キャリア決済のような手軽な手段が選ばれやすくなります。
定期購入(サブスクリプション)による商品・サービスでは、クレジットカード決済を選択できるようにしておくのがおすすめです。
例えば、サプリメント食品や化粧品などを毎月自宅まで届けるサービスが、これに当たります。
クレジットカードなら払い忘れを防ぐことができるので、ユーザーだけでなく運営者側にも一定のメリットがあるでしょう。
また、電子コンテンツのダウンロード販売では、オンラインで完結できる支払い方法が好まれます。この場合は、クレジットカードのほかネットバンキングや電子マネー決済など、複数の選択肢が考えられます。
この場合は、クレジットカードのほかネットバンキングや電子マネー決済など、複数の選択肢が考えられます。
セキュリティ
ECでの決済を導入する際に特に気を付けなければならないのが、セキュリティです。店舗と違い、ネット上での決済は情報が容易く盗まれてしまう可能性が高いためです。また、一度でもセキュリティ問題が起こった際には、再びお客様の信頼を獲得することは極めて困難なことです。
セキュリティトラブルの例としては、健康食品通販サイトで顧客のクレジットカード情報が流出してしまったことや、ペットフード取り扱いサイトで不正アクセスにより個人情報が流出してしまったことなどがあげられます。
いつ何時、不正アクセスやヒューマンエラーでセキュリティトラブルが起こってしまうかわからないため、EC決済を導入する際はセキュリティが万全かしっかりと見極めることが重要になります。
以下の記事では、セキュリティの対策方法を載せています。ぜひ合わせてご覧ください。
導入・運用コスト
決済方法の種類はEC市場の拡大でどんどん増えていますが、導入する際の初期費用や月額費用、手数料などの運用コストにも違いがあります。
一般的なEC決済代行サービスの導入相場は初月・月額がかかることがなく、決済手数料が高くなる傾向にあります。例えばクレジットカードの決済手数料は3.25%~3.75%となっています。
そのため、あるだけの決済方法を導入していくのではなく、自社商品の顧客層に合った決済方法を導入していくことが継続していくうえで重要になってきます。
また、導入する際に「初期費用・月額費用をどれだけ抑えられるか」や「長期的なコストをどれだけとるのか」などを十分に検討していくことが大事です。
決済代行サービスの選び方についてはまた後程詳しく説明します。
決済トレンドやシェア率
EC決済方法を決める際には、決済トレンドやシェア率状況を確認して選択するのもいいでしょう。シェア率の高い決済を優先導入した方が、ユーザー数や売上げが伸びやすくなるからです。
また、今後伸びると推測される決済方法に関しても分析できるとより良いです。近年では、キャッシュレス決済を推進していることもあり、決済トレンドの変化も激しくなっているため、トレンドに敏感になって置くことが大事です。
最近では「○○Pay」というのがEC決済の中でも拡大しています。例えば、PayPayや楽天Pay、メルペイなどが挙げられ、モバイル決済の代表的なものになっています。
最新のEC決済方法を取り入れることで新規ユーザーも獲得できる可能性がでてきます。
それぞれの決済方法のメリット・デメリット

上記では決済方法の選び方をお伝えしてきました。
次に決済方法の種類、それぞれのメリットデメリットについて詳しく説明していきます。
今回取り上げる決済方法は以下の8つです。
・クレジットカード
・コンビニ決済
・代金引換
・銀行決済
・キャリア決済
・電子マネー
・後払い決済
・外部ID決済
以下ではさらに詳しく説明していきます。
クレジットカード
クレジットカード決済は、決済代行会社を介して立て替え払いをし、購入者の講座から後日引き落とされる仕組みになります。
上でも説明したとおり、インターネット上のショッピングではクレジットカードによる支払いを選ぶユーザーが多くを占めています。
そのため、ECサイトでもクレジットカード払いは導入必須になってきます。
【メリット】
・クレジットカードによる即時決済には商品代金の未回収リスクが低く、入金されるのを待つ必要もない
・注文を受けたらすぐに発送作業に移れるため管理もスムーズになる
・ユーザーの手元に商品が届くまでの時間も短縮することが可能
【デメリット】
・クレジットカード番号の盗難などによる不正利用で、チャージバックが発生するリスクがある
・転売などの目的で購入されることの多い商品を扱っている場合には注意が必要
・クレジットカードを所有していない人への配慮も必要
コンビニ決済
コンビニ決済は、最寄りのコンビニエンスストアを利用して手軽に支払いができる決済方法です。予約番号などをもとに代金の支払い後に商品を発送する「前払い」と、商品と同時に振込票を同梱する「後払い」がある。
【メリット】
・クレジットカードの利用に抵抗があるユーザーにも受け入れられやすい
・自宅や職場の最寄りのコンビニで支払えるため、顧客にとっては利便性が高い
・前払い方式は、受付番号を発行するだけなので後払い方式よりも印刷コストを抑えられる
・クレジットカードを作れない高校生などの若年層の購入に繋がりやすい
・前払い方式の場合、商品のキャンセルや代金未払いのリスクが提言する
・後払い方式の場合、顧客は支払い前に実物を試せる
【デメリット】
・提携先のコンビニエンスストアがユーザーの居住地に出店していないと支払いができない
・後払い方式にする場合は、商品代金を回収できないリスクがある
・導入する際に、各コンビニに審査を申請する必要がある
代金引換
代金引換は、注文した商品を発送し、購入者が商品を受けとる際に「商品代金」と「送料」を合わせて運送会社に支払う仕組みのことです。
【メリット】
・顧客に安心感を提供できる
・顧客にとって支払いのための外出の手間が省ける
・顧客は購入した商品を受け取るときに宅配業者を通して代金を支払うため、「支払いをしたのに商品が届かない」というリスクを避けられる
・セキュリティへの警戒心からクレジットカードの利用を敬遠している人や、オンライン決済のリテラシーが低く不安を感じるという人でも気軽に注文できる
・代金の未回収が発生しにくい
・購入者負担額の手数料を事業者が決められるため、コストの調整が可能
【デメリット】
・留守による再配達などの理由で、商品の到着と支払いが遅れてしまうケースがある
・一週間ほど配達不在になると、返送もしくは破棄されてしまう
・商品の返送や代引きにかかる料金は事業者側が負担となるため注意が必要
銀行決済
銀行振り込みは、指定した金融機関の講座に購入者が商品代金や送料を振り込む決済方法のことです。
【メリット】
・リテラシーに関係なく幅広いユーザーに対応できる
・ターゲットとする年齢層が比較的高い商品を扱うECサイトでは、支払いに対する抵抗感を減らせる
・ペイジー(Pay-easy)やネットバンキングにも対応しておくと、番号などの入力が必要なクレジットカード決済よりも手軽な支払い方法を提供できる
・ネットバンキングはログインするだけで支払い情報の入力を完了できるため、金額や振込先を間違えてしまう可能性が低くなる
・手数料が発生しないため、運用コストを抑えられる
【デメリット】
・口座振替であっても、一定の未回収リスクがある点には注意が必要
・入金の消し込み作業に手間がかかる
・15時以降の入金が翌営業日扱いになる
キャリア決済
キャリア決済は、NTTドコモやau、ソフトバンクなどの携帯会社のアカウントにより、商品代金が支払える仕組みです。
【メリット】
・クレジットカードを持てない学生などの若年層の購入に繋がりやすい
・個人情報の入力なども省略できるため、安心感が出て購入率の増加やリピーター獲得に繋がる
【デメリット】
・事業者側にクレジットカードの1.2~1.5倍ほどの手数料がかかってしまう
・キャリアごとに仕様が違うため、導入時に注意が必要になる
電子マネー
電子マネーは、データ化した現金で支払いを行える方法です。「Suica」などの交通系電子マネーや「nanaco」などの流通系電子マネー、「iD」などのクレジット系電子マネーなどが当てはまります。
後払いタイプだけでなく、事前にチャージするプリペイドタイプ、購入時に講座から引き落とされるデビットの決済方法があります。
【メリット】
・ポイントバックがあり、他決済よりも顧客に選ばれる可能性が高い
【デメリット】
・高額商品を取り扱う場合、プリペイド型の電子マネーだと不便性を感じる場合もあるので注意
後払い決済
後払い決済は、購入者が商品を受け取った後でコンビニや銀行で代金を支払うことです。
【メリット】
・商品を確認してから支払えるため、購入者にとって安心して購入できる
・オフライン決済のため、パソコンや携帯電話などに慣れない高齢者やクレジットカードをもたない若年層なども利用しやすい
【デメリット】
・購入者の支払遅延等により、代金未回収のリスクが発生する可能性が高い
・決済後の請求書送付や、代金回収などの手間がかかる
外部ID決済
外部ID決済は、楽天市場やAmazon、LINEなどの他のサービスを利用する際に用いる個人情報を使用して決済を行う仕組みです。
【メリット】
・住所やクレジットカード番号を省略できるため、かご落ちを防ぐことができる
・事業者側にとって、個人情報を自社のサーバーに保存する必要がないため情報漏洩などのリスクを減らすことができる
【デメリット】
・提供企業の増加に比例して導入コストや工数が増えてしまう
決済代行サービスとは?

上記では、決済方法の種類とメリット・デメリットについて解説しました。
決済方法にはさまざまな種類があるため、メリットとデメリットを見極めて自社に最適なものを導入することが大切です。
少しでも機会損失を減らすには、ユーザーが選択できる支払い方法を増やすに越したことはありません。
しかし、対応する決済方法が多ければ、その分だけ管理の手間とコストが余計にかかってしまいます。また、セキュリティや未回収といったリスクへの対応も簡単ではなくなってきます。
このような問題を解決するには、決済代行サービスを利用するのがよいでしょう。
決済代行サービスとは、様々な決済をオンライン上で一括で行えるサービスのことです。一般的にはクレジットカード決済ならクレジットカード会社、キャリア決済ならキャリア会社など各社と契約を結び、サービスを導入する必要があります。
しかし、決済代行サービスを利用すれば複数ある決済方法の導入を代行してもらいながら、手間やコストを削減しリスクも最小限に抑えることが可能になります。
決済代行サービスには主に3つの種類に分かれています。
BtoB向けの決済代行サービス、BtoC ECサイト向けの決済代行サービス、BtoC 実店舗向けの決済代行サービスです。
例えばBtoB向けの決済代行サービスには、法人の掛売り業務を代行してくれる会社もあります。
よって、自社に適した決済代行サービス会社を選ぶことが重要になってきます。
クレジットカード決済の方法

決済代行サービスによるクレジットカード決済では、導入の方式に4つの種類があります。
・リンク型
・トークン型
・データ伝送型
・メールリンク型
それぞれの方式の特徴について紹介します。
リンク型
リンク型は、ECサイトから決済代行サービスの決済ページにリンクすることで支払い処理を行う方式です。
決済時に画面が切り替わるため、画面遷移型とも呼ばれます。
ECサイト内に決済ページを用意しなくてよいため、自前での開発・構築作業は不要です。
また、ユーザーのクレジットカード情報をECサイト側で保管しておく必要がないという特徴があります。
セキュリティについては専門知識のある決済代行サービスに任せればよいので、運営者としても安心できるでしょう。
トークン型
トークン型も、ECサイト側でクレジットカード情報を保管する必要のない方式です。
リンク型とは異なり、クレジットカード情報を「トークン」と呼ばれる特別な文字列に置き換えて通信することで、決済代行サービスのページに遷移することなく情報漏洩のリスクを抑えています。
画面遷移によるユーザーの離脱を防ぎたい場合や、自社のECサイト内で支払い処理を完結させたい場合に適した方法だといえるでしょう。
ただし、専用のJavaScriptプログラムを組み込んだクレジットカード情報入力画面を用意する必要があるため、導入の際にはWebに関する知識がある程度求められます。
データ伝送型
データ伝送型は、ECサイト側がもつクレジットカード情報を決済代行サービスに送ることで支払い処理を行う方式です。
自社システムを決済に用いるためSSL対応サーバーを用意する必要があり、カード情報そのものがネットワークを通過することから十分なセキュリティも求められます。
その分、決済画面の設計については自由度が高い点が特徴です。
注文件数が多い大規模ECサイトなどでは、導入を検討する価値があるといえるでしょう。
メールリンク型
メールリンク型は、商品を申し込んだユーザーにメールで決済方法を案内する方式です。
ユーザーはメールに記載されたURLから決済代行サービスの決済ページを開き、支払いをします。
リンク型と似ていますが、リンク元がメールになるため自社サイトに決済機能をもたせる必要がないのが特徴です。
これは、ECサイトを用意しなくてもネット通販ができるということを意味します。
例えば、電話で注文を受ける場合や、仕入れ量や時価、見積もりなどによって価格が一定ではない商品を扱う場合にも対応可能です。
これからECサイトの出店を考えている場合には、手段のひとつとして知っておくとよいでしょう。
決済代行会社を選ぶ際のチェックポイント

次に、決済代行会社の選び方をご説明します。
選ぶポイントは以下の8つです。
・自社のECカートシステムに各種決済が標準対応しているか
・セキュリティは万全か
・自社のサービスに適した料金形態か
・決済システムの稼働率はどうか
・導入前後のサポートが充実しているか
・入金サイクルが自社に合うか
下記では詳しく説明していきます。
自社のECカートシステムに各種決済が標準対応しているか
一番重要であることで、ECカートシステムで各種決済が導入可能なのか確認をする必要があります。例えば、W2株式会社では、クレジットカード、携帯キャリア決済など幅広い標準対応をしています。
希望している決済に対応していないECカートシステム会社もあります。希望している決済に対応していない場合は自前での開発が必要になってしまうため、コストの面でも手間の面でも決済代行サービスを利用するメリットが薄れてしまいます。
セキュリティは万全か
十分信頼できるセキュリティが確保されているかどうかをチェックすることも大事になります。決済処理では、ユーザーがクレジットカード番号などの個人情報を入力することになるためです。
クレジットカード決済保護の国際基準「PCI DSS」や個人情報保護が適切に行われている証である「プライバシーマーク」、国際基準と同等のセキュリティマネジメント体制があるかどうかを示す「ISMS認証」などのセキュリティの基準がありますので、基準に達している会社かどうかをチェックすることをおすすめします。
自社のサービスに適した料金形態か
決済代行会社にもさまざまな料金形態があり、自社の運用コストに見合っているかを検討することも大事です。一般的には、導入時にかかる初期費用と、利用中にかかる決済手数料などのランニングコストがあります。
短期的なコストだけにとらわれず、数年先までのコストをシミュレーションして長期的に考えることが大切です。
決済システムの稼働率はどうか
セキュリティに合わせて、決済システムの稼働率を考えるのも重要です。システム障害が起きた場合、ECサイト内で購入ができず売上に直接大きな影響が出てしまいます。そういったトラブルを避けるため、高い負荷に耐えられる決済システムなのかを事前に調べておくといいでしょう。
また、サーバーの稼働率は高ければ高いほど高い負荷に耐えられます。例えば稼働率99%の場合、年間のシステム停止時間が4日、99.99%の場合、年間のシステム停止時間1時間となります。できるだけ100%に近い方がリスクを抑えられます。
導入前後のサポートが充実しているか
決済代行サービスを導入する際に、事業者によっては簡単に導入できない場合もあります。
よって、できるだけ導入から導入後まで手厚いサポートをしてくれる会社だといいでしょう。また、導入の時だけでなく、トラブルが発生した際に迅速に解決してくれるかどうかも重要になってきます。
入金サイクルが自社に合うか
入金サイクルとは、どのタイミングで売上を締めて何日後に入金するのかということです。
同じ月末締めでも「翌月10日入金」と「翌々月末日入金」では実際に売上が入金されるまでに50日もの差があります。
特に季節によって売上の変動が大きい商材をもつ事業者では、入金サイクルが遅いと仕入れ・資金繰りに大きな影響がでてしまいます。
事前に自社にどういった入金サイクルがあっているのかを確認してから決済代行会社を選びましょう。
まとめ
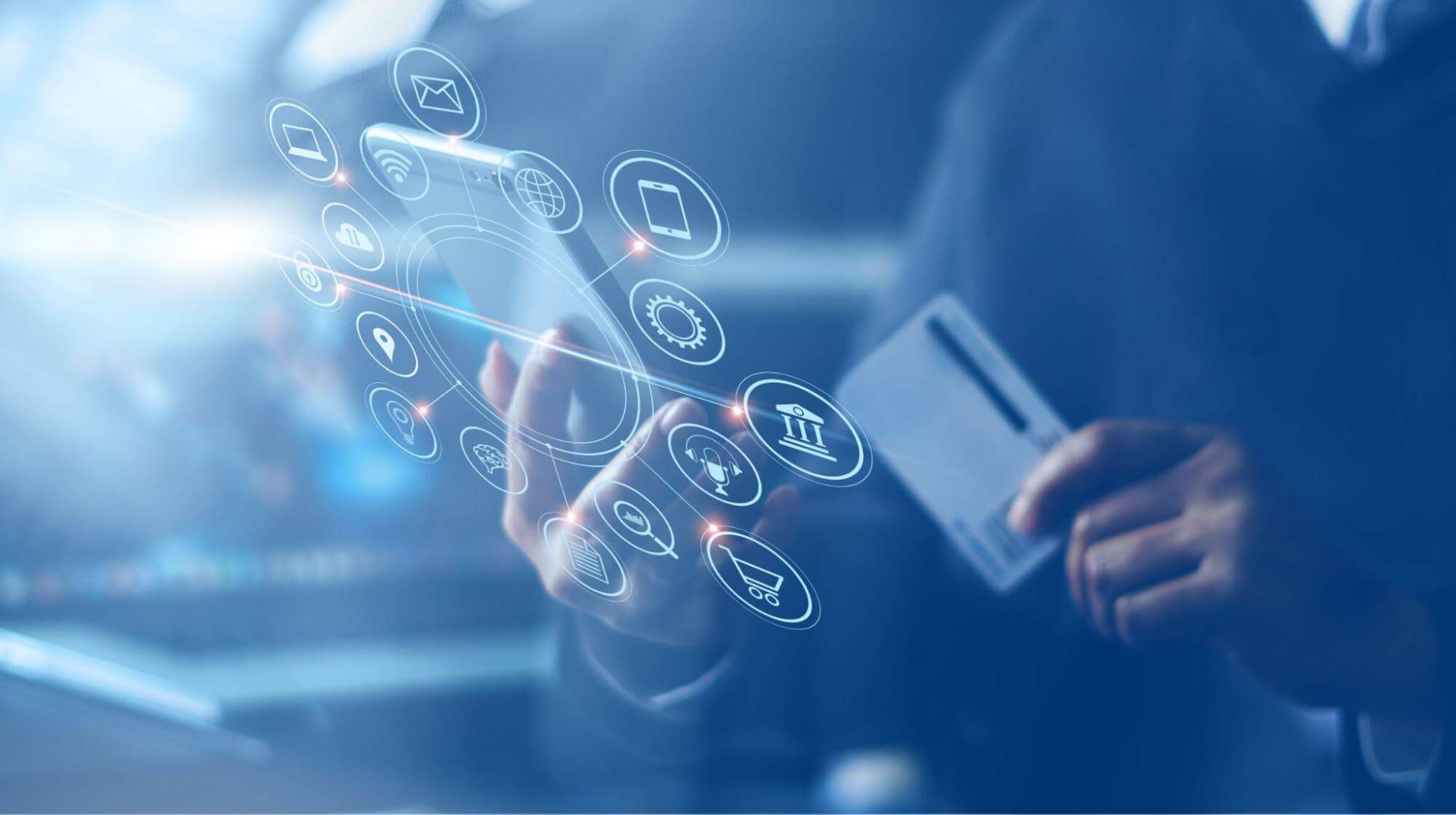
改めて本記事の内容をまとめます。
・EC決済市場は、EC市場に伴い拡大傾向にあり、2026年に40兆円規模へと成長すると予想されている
・決済導入する際には、自社商品を購入する顧客の特徴や、運用コストなどを考える必要がある
・豊富な決済方法があり、それぞれメリットデメリットを考えながら何を導入するか決める
・決済代行サービスは、各決済会社に問い合わせなくても、一括で多くの決済方法が導入可能になる
・決済代行サービスを選ぶ際には、料金や稼働率、サポートの充実性をしっかりと把握する
ECサイトの決済方法には種類があり、それぞれの特徴から自社にあうものを選ぶことが大切です。
決済代行サービスも活用しながら、クレジットカード決済を中心に複数の決済方法を組み合わせて販売機会を増やしていきましょう。