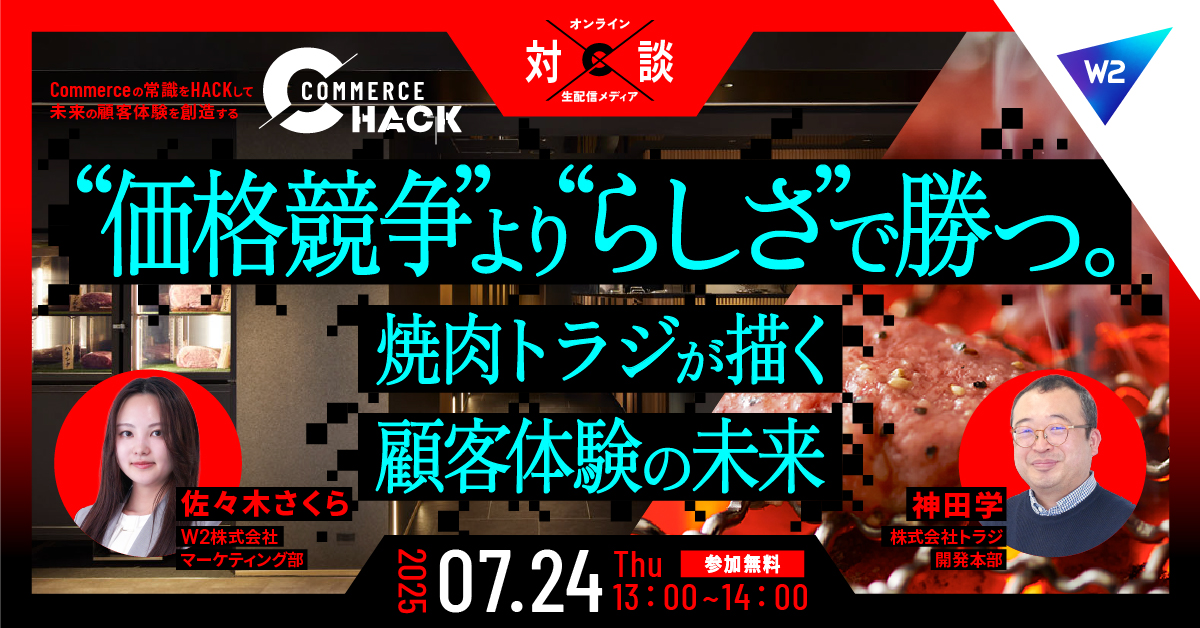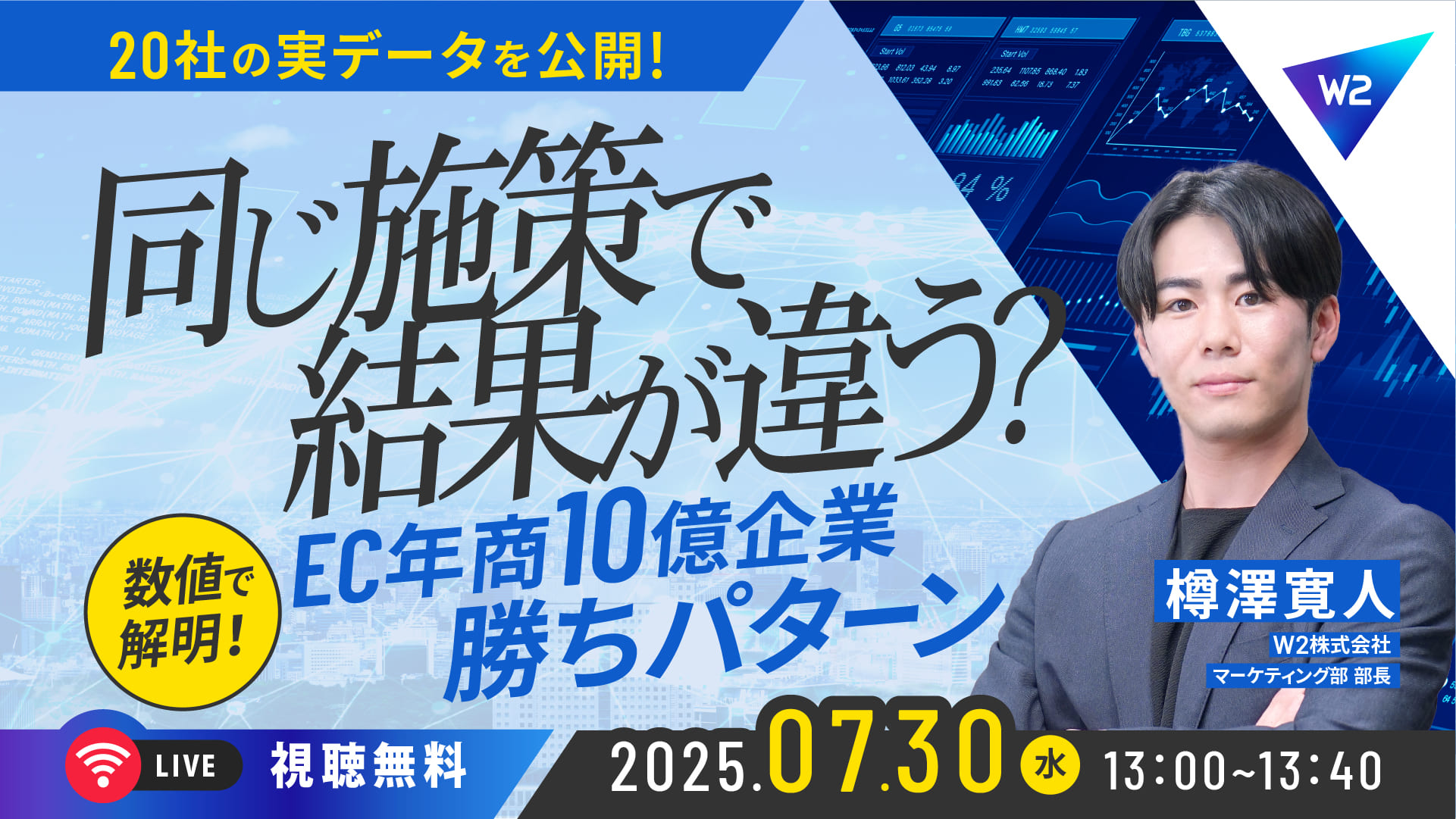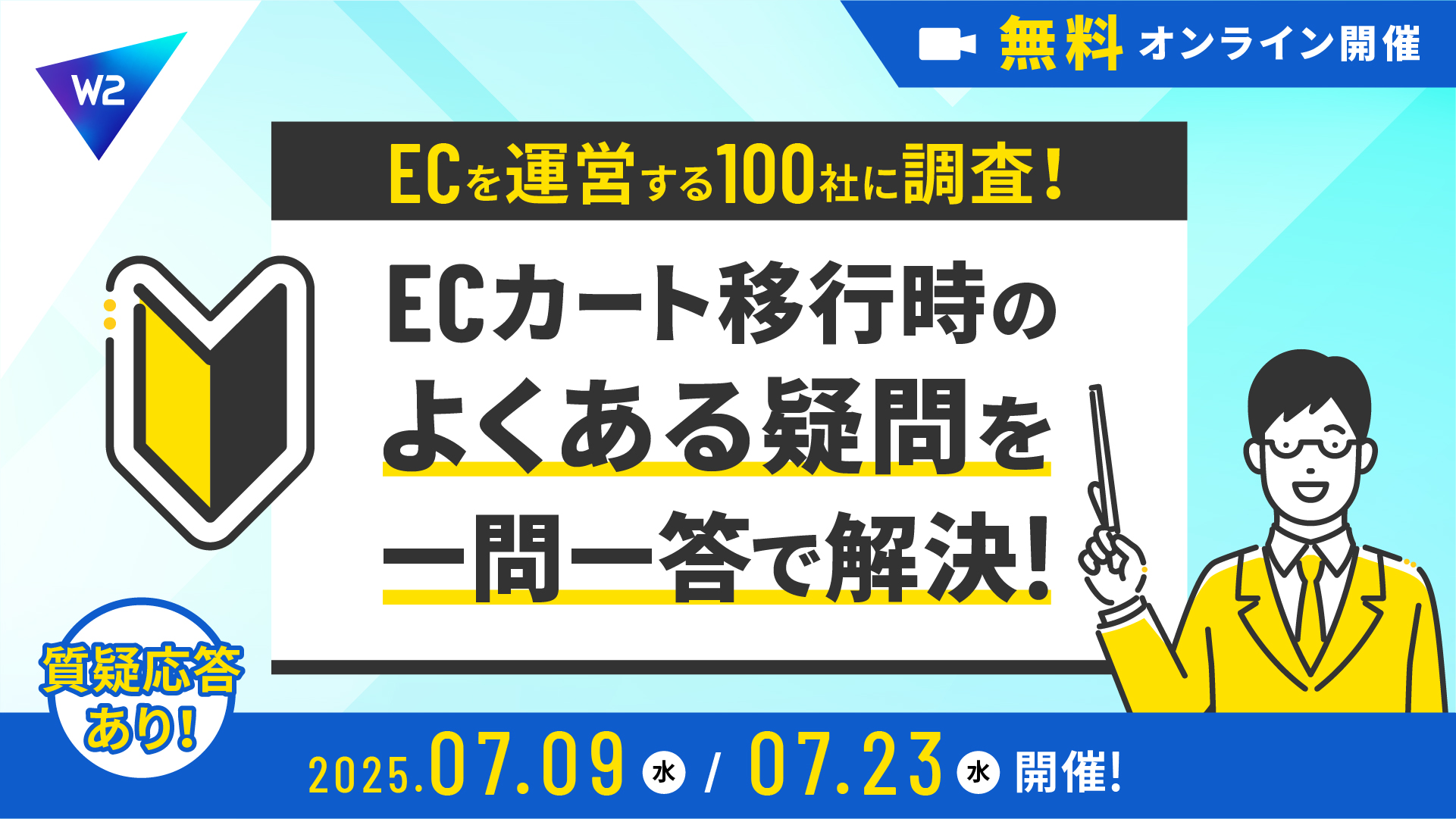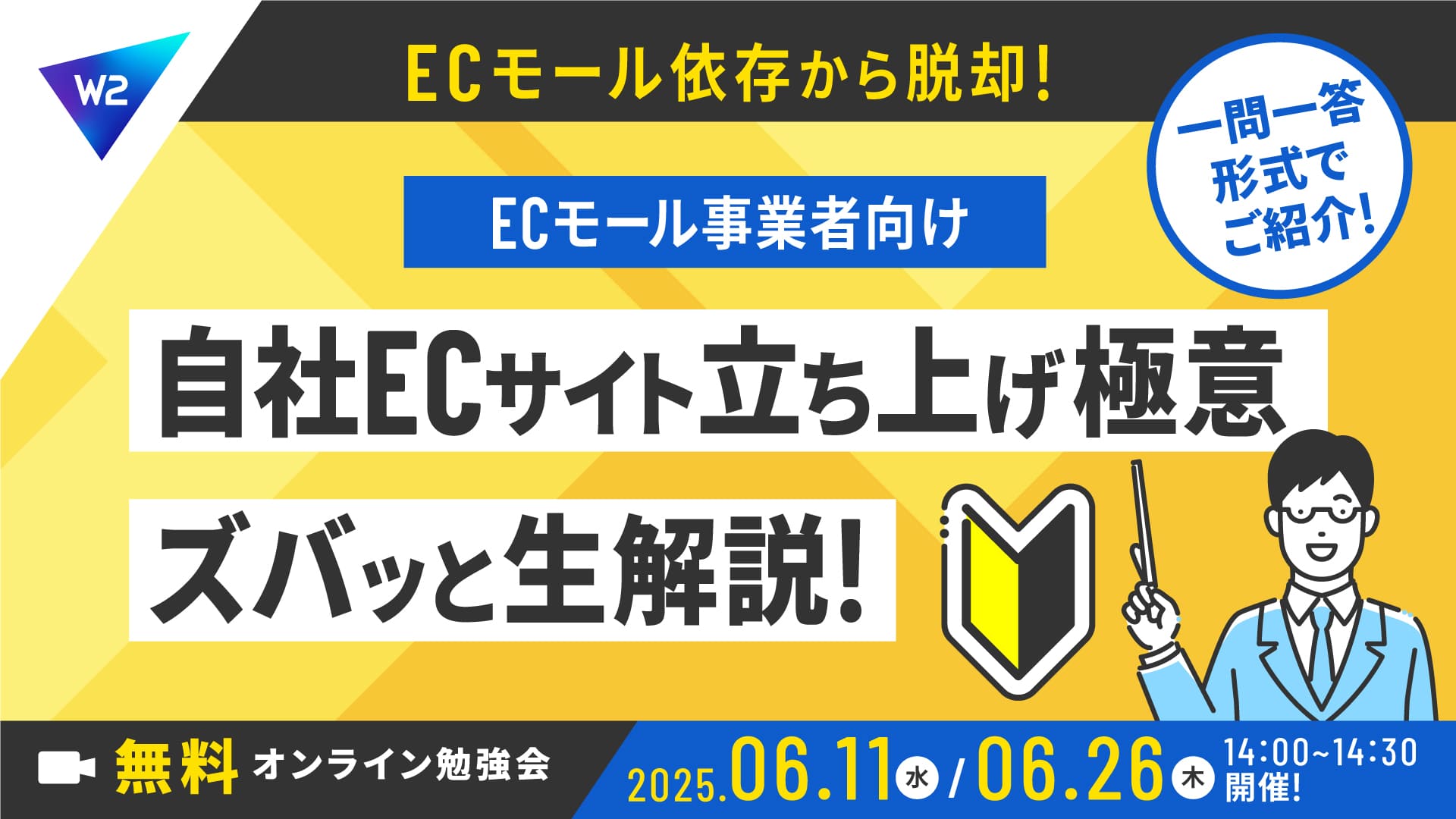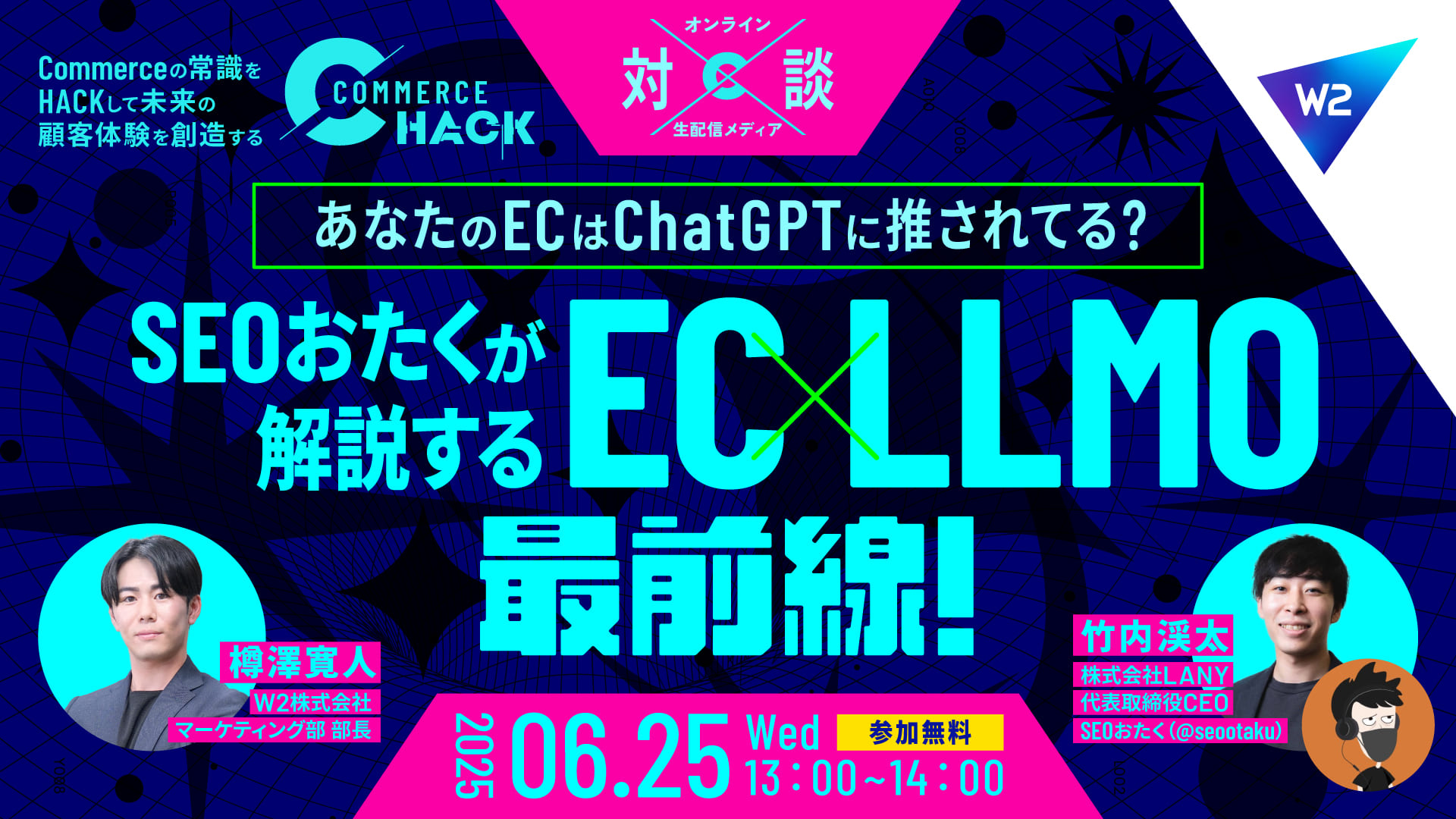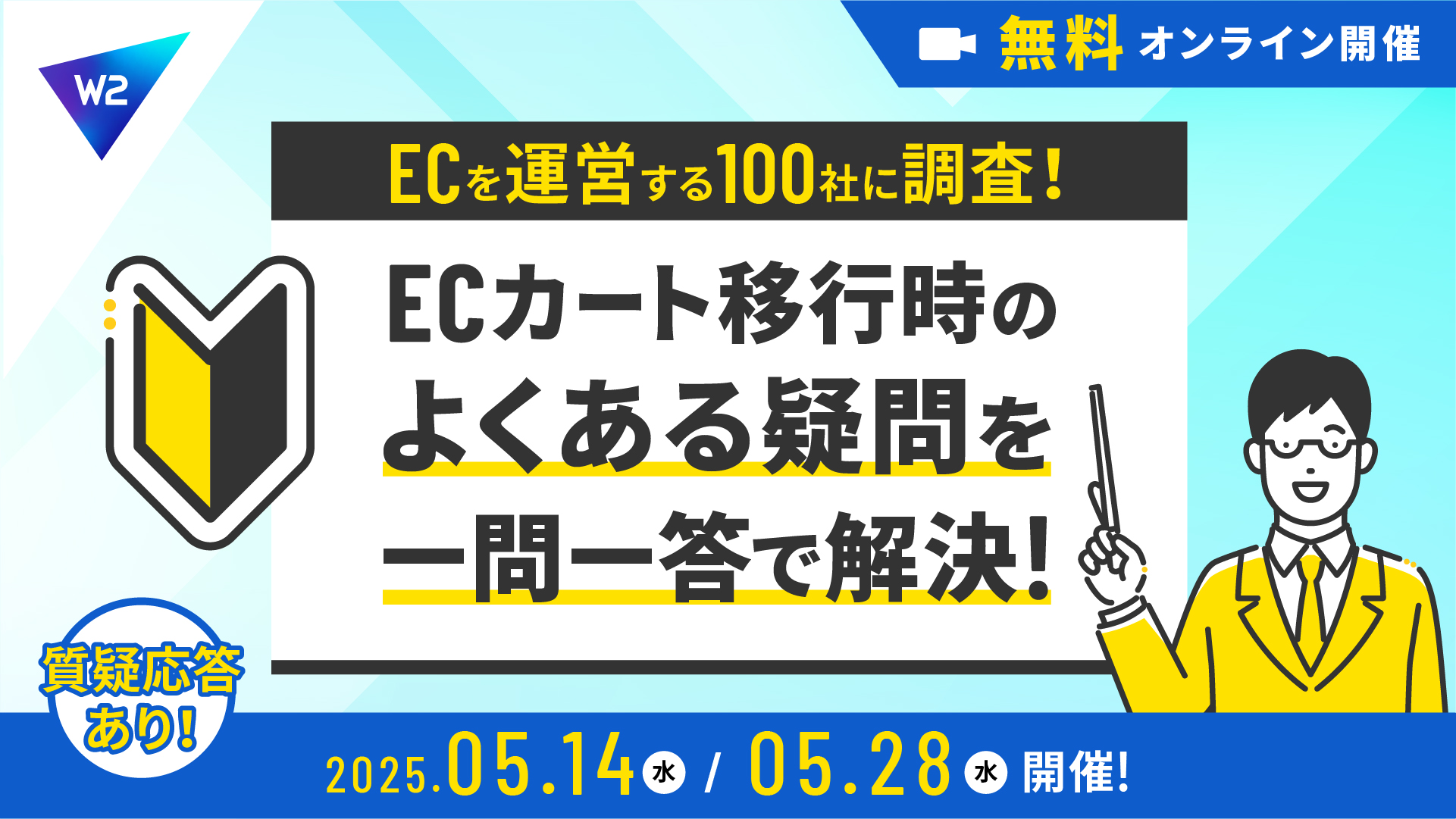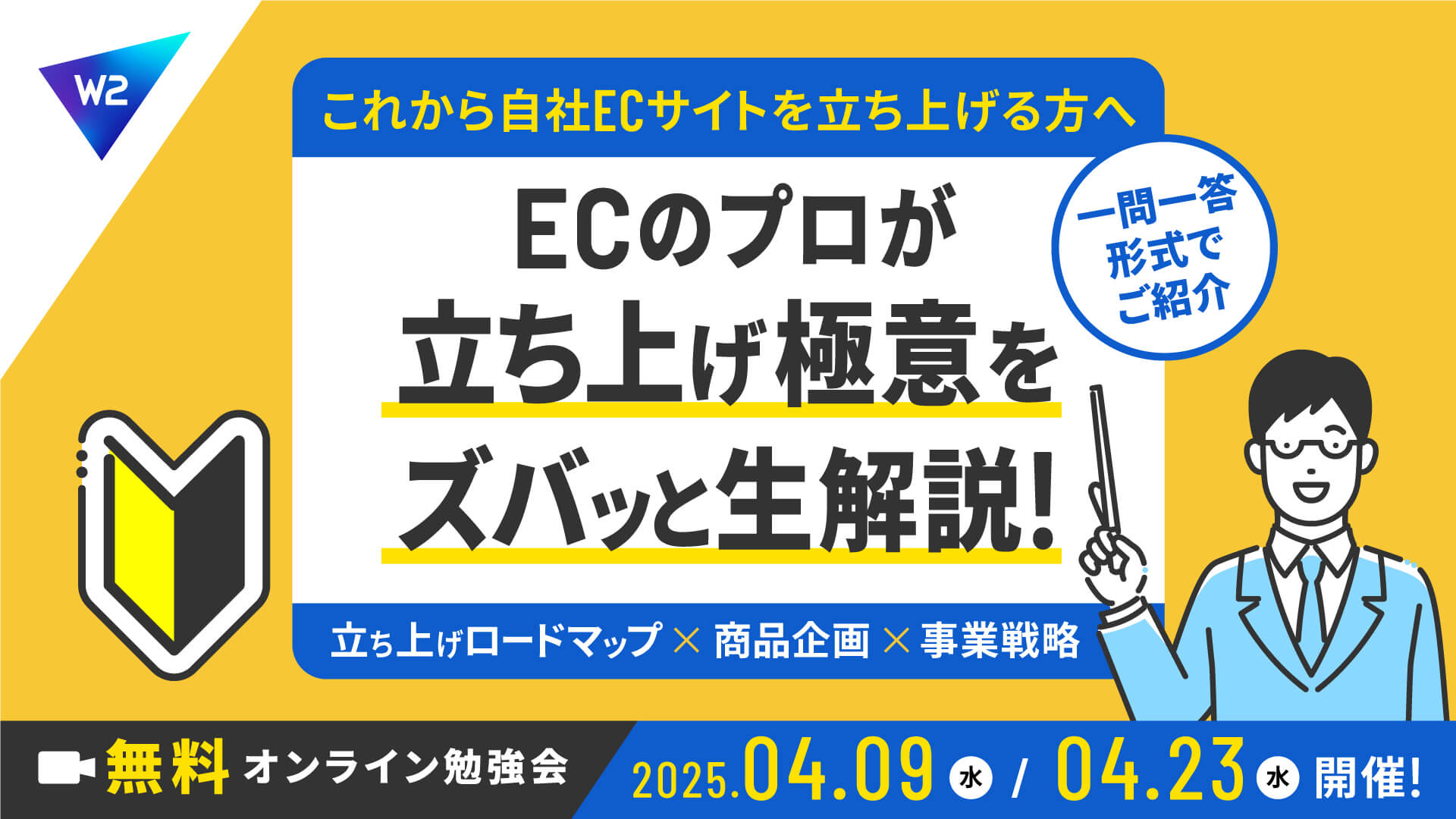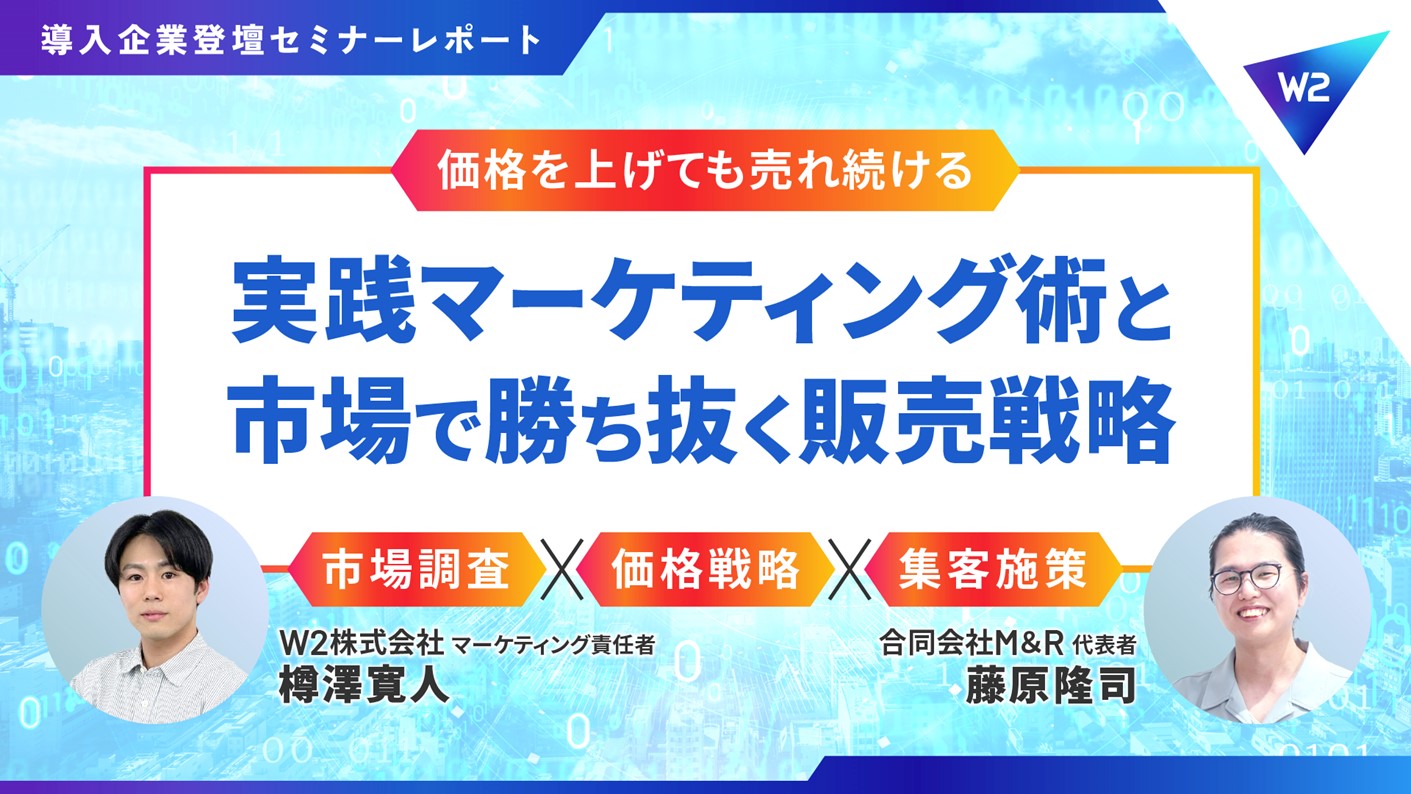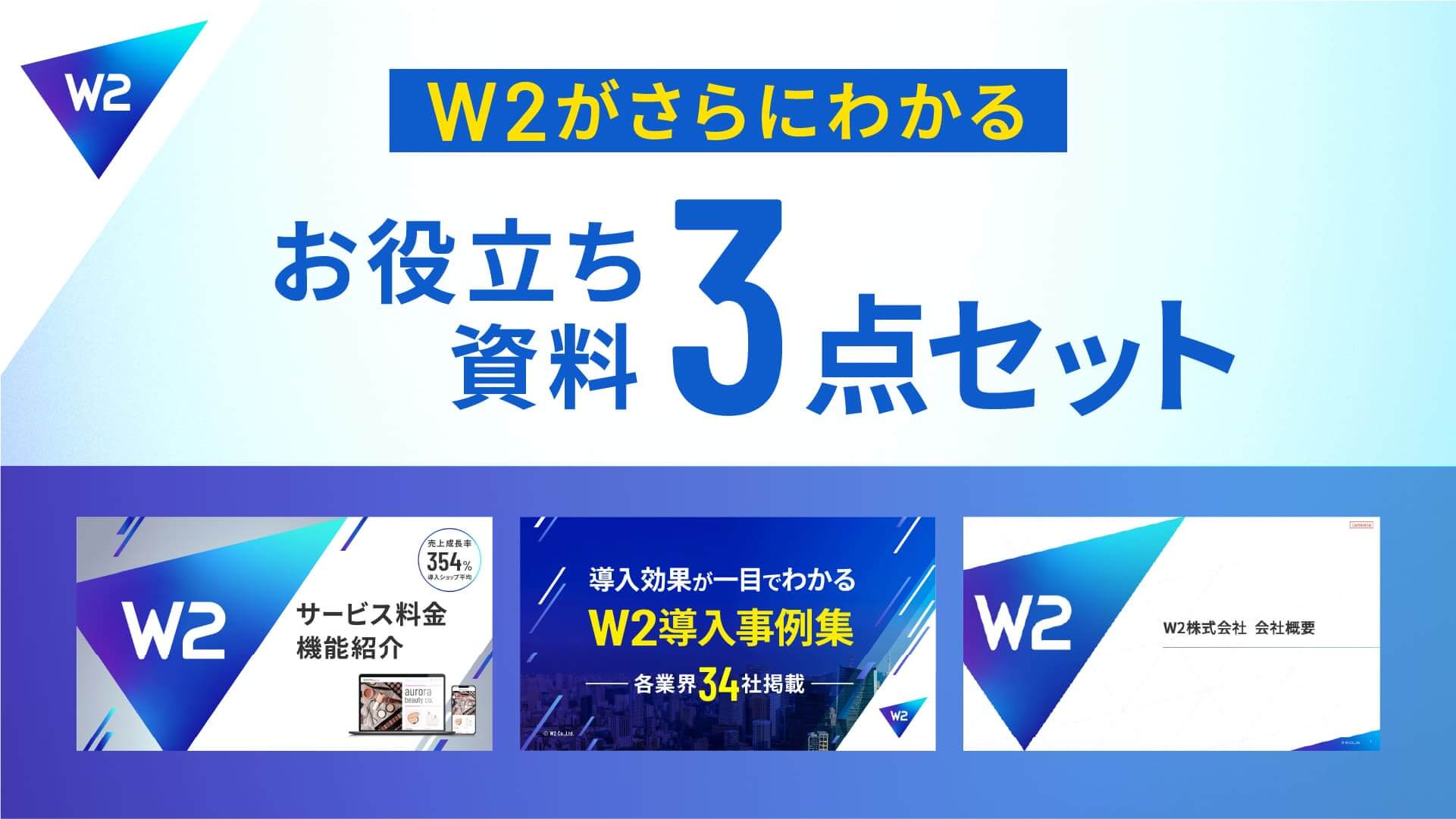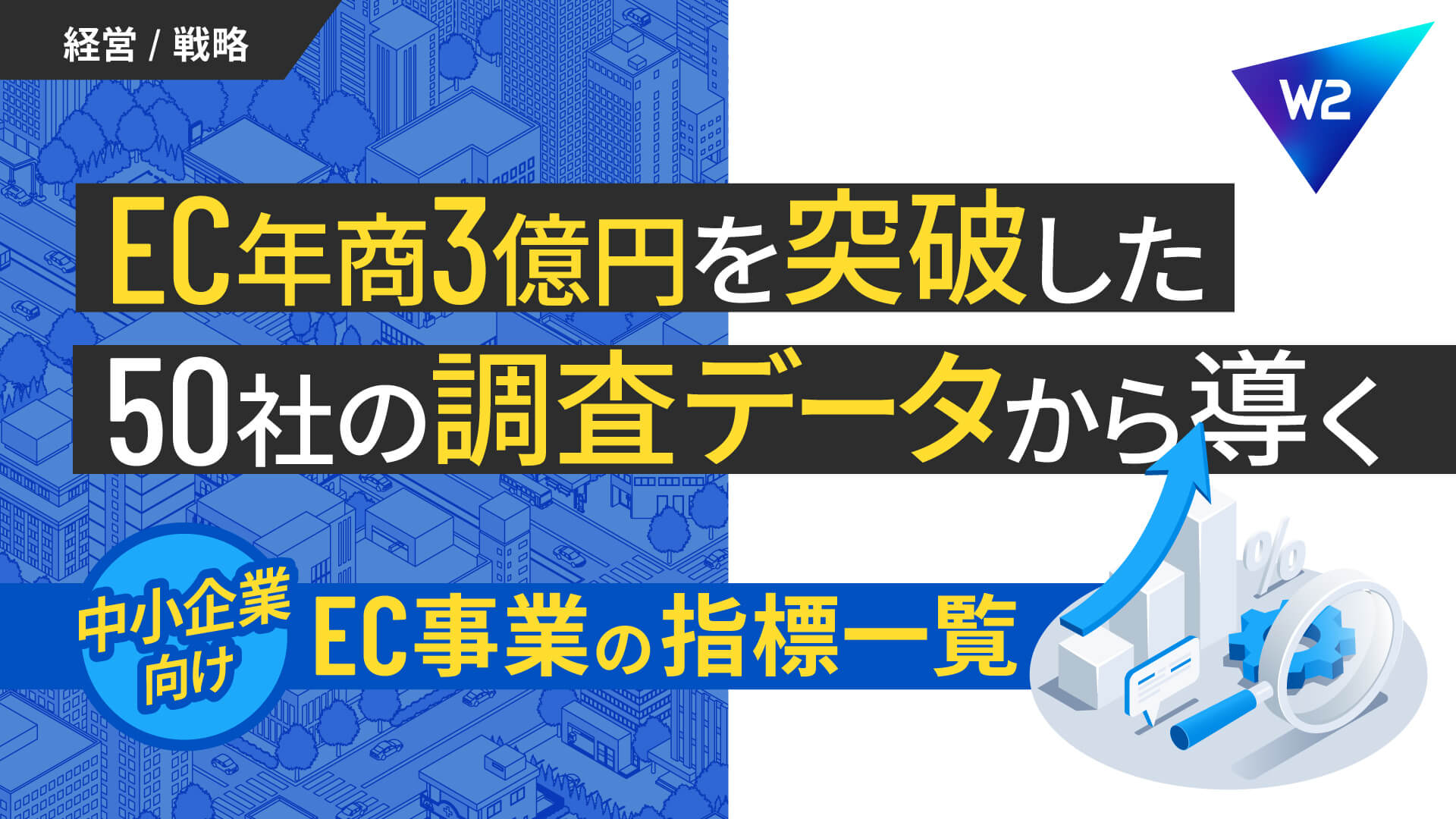ロジスティクスとは?EC事業での役割、物流との違いや仕組み、メリットについて解説


ロジスティクスとは?EC事業での役割、物流との違いや仕組み、メリットについて解説
現在EC市場が拡大し、ネットでの購入が増加しています。それに伴い、荷量も増加している現状があります。また、2024年問題といって、2024年の4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制がかかり、労働時間が短くなることで輸送能力が不足してしまうという問題も起こる可能性が高いです。
経済産業省によると、2024年問題に対して対策を行わなかった場合には、運送能力が2024年には14%、2030年には34%に不足する可能性があると予測しています。
そうした2024年問題やEC市場拡大に伴った荷物の増加により、EC事業を行っている会社は物流などを見直した方がいいとされています。
そこで今回注目したいのが「ロジスティックス」です。
ロジスティクスは、製品やサービスが生産者から消費者に至るまでの流れを管理し、効率的に行うための計画、実施、改善などの活動を指しています。サプライチェーン全体での効率的な荷物の移動をするうえで重要な役割をはたしています。
この記事では、ロジスティクスの定義や、物流とロジスティクスの違い、役割や活用方法、メリット・デメリット、概要などを詳しく解説しています。
「ロジスティクス」とは?

先ほども述べた通り、ロジスティクスは、製品やサービスが生産者から消費者に至るまでの流れを管理し、効率的に行うための計画、実施、改善などの活動を指しています。
商品を生産・調達してからの工程を消費者に合わせて管理することで、現場全体の業務効率化、迅速な出荷、配送を可能にしています。
ロジスティックスはもともと軍事用語で、戦地に置ける人員や兵器などの物資の供給をあらわす言葉でもありました。時代を経て、物流現場に転用されて現在の意味を持つようになりました。
ロジスティクスの重要性
消費社会は大きな転換期を迎え、個々の消費者の要望が多様化しています。
モバイル端末の普及により、EC市場が拡大し、オンラインショッピングが一般化したため消費者は限られた予算内で高品質かつ迅速な配送を求めるようになりました。
この変化に対応するには、市場動向を的確に分析し、戦略的な生産計画と販売戦略を立てることが重要になってきます。
しかし、効率的な物流システムが整っていない企業では、生産のタイミングや配送プロセスが最適化されておらず、結果として製造コストの上昇や配送の遅延につながり、顧客の不満を招く可能性があります。
効果的なロジスティクス戦略を導入することで、企業全体の業務効率が向上するだけでなく、正確かつ迅速な商品配送によって顧客満足度を高めることができます。
物流とロジスティクスの違い
物流とロジスティクスの違いは、その目的や範囲にあります。
物流は、商品を生産地から消費者まで効率的に運送するための包装、荷役、保管、運送の仕組みを指しており、作られた商品を消費者に届けるまでの活動全般をカバーしています。
商品の流れを効率化し、適時に適切な場所に商品を届けることを重視します。
一方、ロジスティクスは、物流を含む広範なプロセスを一元管理することを目的としており、生産から物流までのすべてのプロセスを統合的に管理します。
必要な原材料の調達から始まり、生産、在庫管理、販売に至るまでの一連の活動を効率的に行うため、全体のサプライチェーンが最適化され、コスト削減と効率向上を実現します。
また、ロジスティクスは、物流の上位概念としても用いられています。
物流が商品の物理的な移動に焦点を当てているのに対し、ロジスティクスは戦略的な視点で全体のプロセスを管理し、企業全体の競争力を高めることを目指しています。
例えば、需要予測を行い、必要なタイミングで適切な数量の原材料を調達し、在庫レベルを最適化したり、生産スケジュールを調整し、商品が消費者に届くまでの時間を短縮することにも貢献します。
さらに、顧客満足度の向上にも繋がります。
効率的なロジスティクス管理により、商品の納期が短縮され、品質が保証されるため、顧客の信頼を得ることができます。
このように、物流とロジスティクスは、異なる目的と範囲を持ちながらも、密接に関連しています。企業が持続的に成長し、競争力を維持するためには、ロジスティクスの戦略的な導入と運用が不可欠になっています。
以下の記事ではEC物流を重要視すべき理由について詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
EC物流を重視すべき3つの理由とは?仕組みやよくある課題・解決策も紹介
ロジスティクスの最新トレンド
ロジスティクスにはいくつかトレンドがあります。
例えば、AIと自動化技術の導入やサステナビリティを考えた技術、リアルタイムでの追跡とシミュレーションを可能とするデジタルツイン技術などが挙げられます。
最新のロジスティクス技術は、AIと自動化技術の導入が進み、自動運転車やドローン、ロボットが活用されています。
自動運転車は効率的な配送と安全性向上に繋がり、ドローンは遠隔地への迅速な配送を行っています。また、倉庫内ではロボットが作業を自動化し、人手不足解消と効率向上に貢献しています。
サステナビリティへの取り組みに関しては、電動トラックの導入・リサイクル可能な梱包材の使用・配送ルートの最適化などにより、二酸化炭素排出量の削減と持続可能な物流を行っています。
また、デジタルツイン技術は、物流プロセスを仮想空間で再現し、リアルタイムでの追跡とシミュレーションを可能にしています。
運行状況や在庫レベルのリアルタイムな把握、予期せぬトラブルや需要変動への迅速な対応を行えます。
ロジスティクスの構成要素

次に、ロジスティクスを構成している要素について解説します。
ロジスティクスの主な構成要素の一覧は以下の5つです。
- 供給管理
- 倉庫管理
- 在庫管理
- 受注処理・配送管理
- アフターフォロー
上記の5つについてこの章では詳しく解説していきます。
供給管理
供給管理とは、商品を生産するための原材料の仕入れや、商品自体の仕入れの管理業務全般のことを指しています。仕入れ先の選定や、価格・納期・品質等に関する交渉、仕入れた原材料や商品の管理などが該当します。
サプライヤーの選定や交渉、購買、在庫管理、サプライヤーとの強固な関係の維持などの活動も含まれることで、スムーズで効率的な物資や資材の流れを確保するための重要な役割をはたしています。
具体的には、サプライヤーとの調達戦略、交渉と契約管理、需要予測と計画、リードタイムの短縮、リスク管理、技術とデータの統合などです。これらでサプライチェーンの性能を最適化し、顧客満足を高める役割を果たしています。
計画的なアプローチと改善、他の関連会社との連携が必要になります。
倉庫管理
倉庫管理は、原材料や商品を保管するための倉庫に関する管理のことを指しています。
仕入れた材料や商品をどの倉庫に保管するためのスペースの確保から、倉庫内のレイアウトの決定、在庫の品質管理、配送の準備、貨物の集約と分割などさまざまな機能を果たしています。
在庫管理、保管施設の選択、スペースの最適化、クロスドッキング、在庫品質管理、バーコードやRFID技術の導入、クロスチャネル対応、倉庫自動化など、スムーズな物流に欠かせず、正確なピッキングと配送、顧客満足の向上に繋がります。
仕入れや配送などの工程とも連携させて物流の品質を高められるように管理することも重要です。
在庫管理
在庫管理は、効率的な物流運用を行うために重要な要素です。例えば、カスタマーサービスの向上、在庫コストの最適化、余剰在庫の回避を行います。
他にも、ABC分析、在庫の可視・レベル最適化・寿命管理、ストックアウト回避、リバースロジスティクス、運用コストの削減などに繋がります。
適切な計画と運用を行い、適時に在庫を供給することで競争力のあるビジネス運営を実現できます。
受注処理・配送管理
受注管理は、ECサイトの注文から商品をピッキング、梱包、出荷をして届けるまでのプロセスを指します。
オーダー受注と処理、ピッキング、オーダーの正確性と精度、迅速な注文処理など、顧客の要求に迅速に答えることで、リードタイムの削減ができ、顧客満足の向上、競争力の強化に繋がります。
近年では、技術の進化により受注処理・発送管理の自動化が進んでいて、より正確な処理が可能になっています。
アフターフォロー
アフターフォローは、商品を顧客に届けた後に行う修理や、返品、ECサイトや電話からのお問い合わせに対応することを指します。商品の品質や顧客満足度を向上させたり、長期的な顧客関係などに重要な役割をはたしています。
製品保障と修理サービス、返品・交換ポリシー、保守契約、定期点検などが当てはまります。
効果的なアフターフォローは、企業の信頼性やブランド価値の向上にも繋がります。
ロジスティクスのメリット

次に、ロジスティクスのメリットについて解説します。ロジスティクスのメリットは以下の5つです。
- 生産・調達の最適化
- 環境負荷の低減
- 在庫管理の最適化
- コスト削減
- 生産不足・過剰の回避
上記の5つについてこの章ではさらに詳しく解説していきます。
生産・物流の効率化
ロジスティクスは、生産、管理、配送を一元的に管理することで、企業の業務全体を最適化し、効率を大幅に向上させる重要な手段です。
例えば、ロジスティクスシステムを活用することで、注文データをリアルタイムで収集・分析し、迅速に生産計画を調整することが可能になります。
無駄な在庫を減らし、適切な商品数を効率的に生産することができ、コスト削減にも繋がります。
また、物流拠点の集約や最新の配送管理システムの導入により、配送ルートの最適化が図られ、配送効率を大幅に改善することができます。
ロジスティクスを通じて生産から配送までの各工程を可視化することで、業務効率を妨げる要因を明確にし、問題解決に向けた具体的なアクションを迅速に取ることも可能です。
環境負荷の低減
ロジスティクスは、生産、管理、配送の各プロセスを効率化することで、環境負担を大幅に減少させる重要な手段となります。
例えば、従来は10台のトラックで行っていた配送業務を、ルートや積載方法の最適化を行うことで8台に削減できれば、それに伴い二酸化炭素の排出量も削減されます。
また、効率的な生産管理により、必要な商品数を正確に生産することで、過剰在庫を防ぎ、エネルギーや資源の無駄を減らすことが可能です。
こうした物流の効率化に伴う二酸化炭素削減は、国土交通省も積極的に取り組んでおり、これは社会全体の持続可能な発展に直結する課題とされています。
企業単位でのロジスティクスの最適化は、環境保護への貢献だけでなく、コスト削減や競争力強化にも繋がります。
在庫管理の最適化
ロジスティクスの活用により、ECサイトからの注文数をリアルタイムで集計することが可能となり、適切な商品量を適切なタイミングで生産することができ、欠品や過剰在庫を防ぎます。
倉庫内の在庫状況もリアルタイムで可視化されるため、商品の出荷がスムーズに行われているかを監視でき、在庫の回転率を向上させることが可能です。
さらに、在庫が見つからないというトラブルや、先入先出が徹底されずに商品の劣化が生じるといった問題も未然に防ぐことができます。
コスト削減
ロジスティクスを導入することで、生産量の過不足をリアルタイムで可視化できるようになります。
必要な商品を必要なタイミングで、必要な数だけ効率的に生産できるようになるため、過剰な材料の仕入れコストや過剰在庫の保管コストを大幅に減らすことが可能です。
さらに、不良在庫が減少し、商品不足による販売機会の損失も大幅に削減できるため、企業の収益性が増し、ビジネスの安定性が向上します。
加えて、業務のシステム化による人的コストの削減や、配送効率の向上による輸送コストの削減も期待できます。
生産不足・過剰の回避
重要性でも記載したように、ロジスティクスを取り入れることで、生産から保管までの全プロセスを最適化し、供給のバランスを取ることが可能となります。
ロジスティクスを活用することで、必要な量を適切なタイミングで生産できるようになり、余剰在庫や過剰生産などの無駄を回避できます。
また、イベントや季節商品における需要の変動に対しても、ロジスティクスを導入することで柔軟に対応できます。
受注予測が上振れし、欠品が続出するような場合でも、ロジスティクスの効率的な運用により、機会損失を極小化することが可能です。
適切な在庫管理と配送計画の立案により、無駄なコストを削減し、より効率的な物流網を構築することができます。
ロジスティクスの効果的な活用方法

ロジスティクスの効果的な活用方法は以下の4つです。
- プラン・システムの構築
- ニーズの把握と需要予測
- 物流の各データ連携
- アウトソーシングを活用する
この章では4つについて詳しく解説していきます。
プラン・システムの構築
実際にロジスティクスのためのシステムを導入する前に、計画を立てることが重要になります。例えば以下のことを確認しましょう。
- 自社にとって最適なサプライヤーはだれか
- コストパフォーマンスがいい物流システムはなにか
- 各種在庫を誰がどこで管理するのか
- ロジスティクスの各フェーズで自動化できるものはあるか
- ロジスティクスの各フェーズでアウトソーシングできないか
また、物流においては輸送手段に加えて緊急時のプランも用意しておきましょう。
ニーズの把握と需要予測
ロジスティクスを効率的に活用するには、ニーズの把握と需要予測が重要です。
過去の販売データや市場トレンドを分析し、将来の需要を予測することで、最適な在庫レベルを維持できます。在庫過剰や不足による無駄を防ぎ、コスト効率の高い運営が可能です。
季節商品やイベントに合わせた在庫調整も、需要変動に柔軟に対応するために重要になってきます。
特定の時期に需要が高まる商品については、事前に在庫を増やして販売機会を最大化、需要が低下する時期には在庫を減らし、保管コストを削減。
このように、需要予測と在庫管理を連携させることで、供給チェーン全体の効率が向上します。
物流の各データ連携
ロジスティクスを効果的にするためには、物流の各プロセスのデータを連携させることも重要です。
生産から保管、購買データなど、さまざまなデータを一元管理することで、各工程の生産性を向上させることができます。
例えば、生産データと保管データが連携されていれば、在庫状況をリアルタイムで把握し、適切なタイミングで必要な数量を生産することができ、過剰在庫や在庫不足を防いで効率の良い運営が行えます。
また、購買データを連携させることで、材料の調達から生産、出荷までの一連の流れを最適化できます。
購買部門が正確な在庫状況と生産計画を把握していれば、必要な材料を適時に調達し、生産の遅延を防ぐこともできます。
各プロセスのデータがバラバラに管理されていると、情報の共有が滞り、意思決定が遅れる原因となり、リードタイムが長期化・顧客への納期が遅れるリスクが高まります。
そのため、物流の各プロセスのデータを連携させることが重要になってきます。
アウトソーシングを活用する
ロジスティクスを効果的に活用するには、様々な視点の計画や管理が求められます。
ロジスティクスの運営に関する知識と経験を持つ人材が社内に不足している場合、アウトソーシングを活用することは非常に有効な手段です。
その代表的な方法が、3PL(サードパーティー・ロジスティクス:Third Party Logistics)です。
3PLは、企業が自社のロジスティクス機能を専門の第三者に委託する仕組みであり、物流の運営を外部の専門業者に任せることによって、効率的かつ効果的なロジスティクス管理が可能になります。
また、物流のプロセスを専門的に管理し、最新の技術やノウハウを活用でき、在庫管理・配送計画・リードタイムの短縮など、ロジスティクス全体のパフォーマンスを最適化することができます。
ロジスティクスの将来と課題

この章では、ロジスティクスの期待されている将来性について解説します。
- SCMの強化
- 最新技術の活用
- 労働力人口不足の解決
SCMの強化
ロジスティクスを強化するうえで、併せて学びたいのが「SCM(サプライチェーンマネジメント)」です。
SCMとは企業の枠を取り払い、情報を一元化していこうとする考え方です。ロジスティクスとはあくまで社内だけにあてはまる考え方であり、「自社の利益を守る」という目的が根底にありました。
それに対し、SCMは同業他社の協力が不可欠です。
原材料納品から部品、小売にいたるまで、さまざまな分野の企業が連携し、業務効率を高め合っていきます。
SCMの狙いは、現場での「スピード感向上」です。
生産や物流をスムーズに行うためには、作業を分け合っている他社との関係が肝心です。
お互いに情報を報告し合い、役割分担や指揮系統を明確にしておかなければ少しずつ作業に遅れが出ていきます。
多様化する顧客のニーズに応じるためには、わずかな作業の停滞すら命取りになりかねません。
異なる企業がまるでひとつの組織のように手を組み、連携を図るのがSCMの本質です。
企業の垣根に縛られず、指示を出したり受けたりできるのでトラブルの処理速度も改善されます。
労働力人口不足の解決
ロジスティクスの背景としても挙げましたが、物流業界では労働者不足の問題が挙げられます。
自動運転やロボットの導入により、人手不足の解決だけでなく、より効率的かつ安全な輸送が実現できます。
それにより、人件費の削減や業務効率化の効果も期待できます。
ロジスティクス4.0
ロジスティクスには段階があり、もうすぐ「ロジスティクス4.0」を迎えるようになります。
各段階について簡単に解説します。
【ロジスティクス1.0】
19世紀に入り、モノの内陸輸送に大きな革命が起こりました蒸気機関、すなわち「鉄道」の発明です。
蒸気機関車によって、輸送力を飛躍的に高めることに成功し、大量輸送時代が始まりました。
この時期を「ロジスティクス1.0」と呼んでいます。
【ロジスティクス2.0】
蒸気機関の登場によって、内陸輸送は大きな変化を遂げました。しかし荷降ろしや運搬、仕分けは手作業で行っていました。
1950年代になると、フォークリフトとパレットの登場で「荷役の機械化」が訪れます。
それに加えて海上コンテナの普及も相まって、積み込みに要する時間は10分の1まで減少し、人員も大幅に減少することとなりました。
この機械化の変革を「ロジスティクス2.0」と呼びます。
【ロジスティクス3.0】
「荷役の機械化」によって、物流業界に大きなイノベーションが訪れたものの、荷物の入出管理や在庫管理の業務は全て書類と台帳で管理されていました。
1980年代に入ると、コンピューターの普及に伴い、管理・処理業務に「WMS」導入され、システムが普及するようになります。
WMSは、入荷~梱包まで業務を管理するシステムで、管理・処理業務の電子化というイノベーションを起こしました。
物流管理がシステム化された時期を「ロジスティクス3.0」と呼びます。
WMSについては以下の記事ではさらに詳しく解説していきます。
ぜひ合わせてご覧ください。
WMS(倉庫管理システム)とは?導入のメリットや選ぶポイントを解説!
【ロジスティクス4.0】
物流管理がシステム化された時期「ロジスティクス3.0」を経て、IoTやAI等による省人化の「ロジスティクス4.0」が訪れようとしています。
自動運転の実用化やドローンによる宅配、ロボットによる庫内作業の実現が挙げられます。
また、IoTやAIで情報を共有することによる標準化も行われます。
例えば、輸送手段や配送ルートなどの最適解をAIが導き出したり、交通網や気象・災害情報といった物流を超えたプラットフォームが形成されたりして
情報の可視化がされるようになります。
記事のまとめ

この記事のまとめをこの章では行います。
この記事の重要なポイントは以下になります。
- EC市場の拡大に伴い、ロジスティクスが注目されている
- ロジスティクスは、製品やサービスが生産者から消費者に至るまでの流れを管理し、効率的に行うための計画、実施、改善などの活動のことを指している
- ロジスティクスの主な構成要素は、供給管理・倉庫管理・在庫管理・受注処理・配送管理
- アフターフォローで構成されている
- 労働者不足や物流コストの高騰化でロジスティクスは求められている
- ロジスティクスは、コスト削減や生産・調達の最適化など多くのメリットがある
- これからロジスティクス4.0を迎え、さらなる物流の効率化が進む
売上を短期間で伸ばすのは難しくても、コストを削減すれば利益増加につながります。
そしてロジスティクスは、その効果的な手法として今注目を集めています。
物流だけにとらわれるのではなく、大きな視点でロジスティクスにも目を向けましょう。
また物流以外にも日々の業務をかしこく効率化しながら売上を伸ばす方法は下記資料で詳しく紹介しています。
資料は無料ダウンロードできるので、ぜひあわせてご一読ください