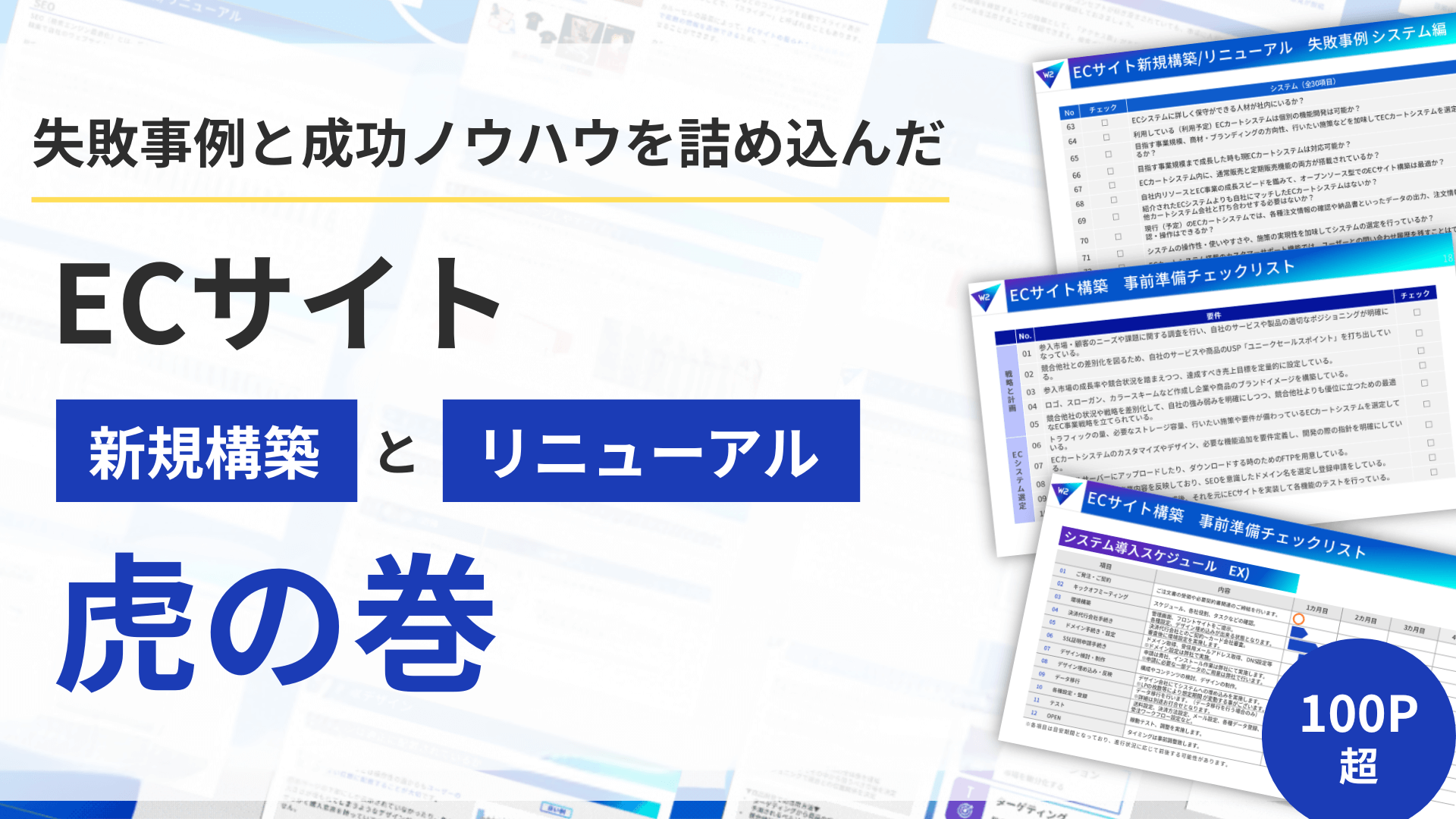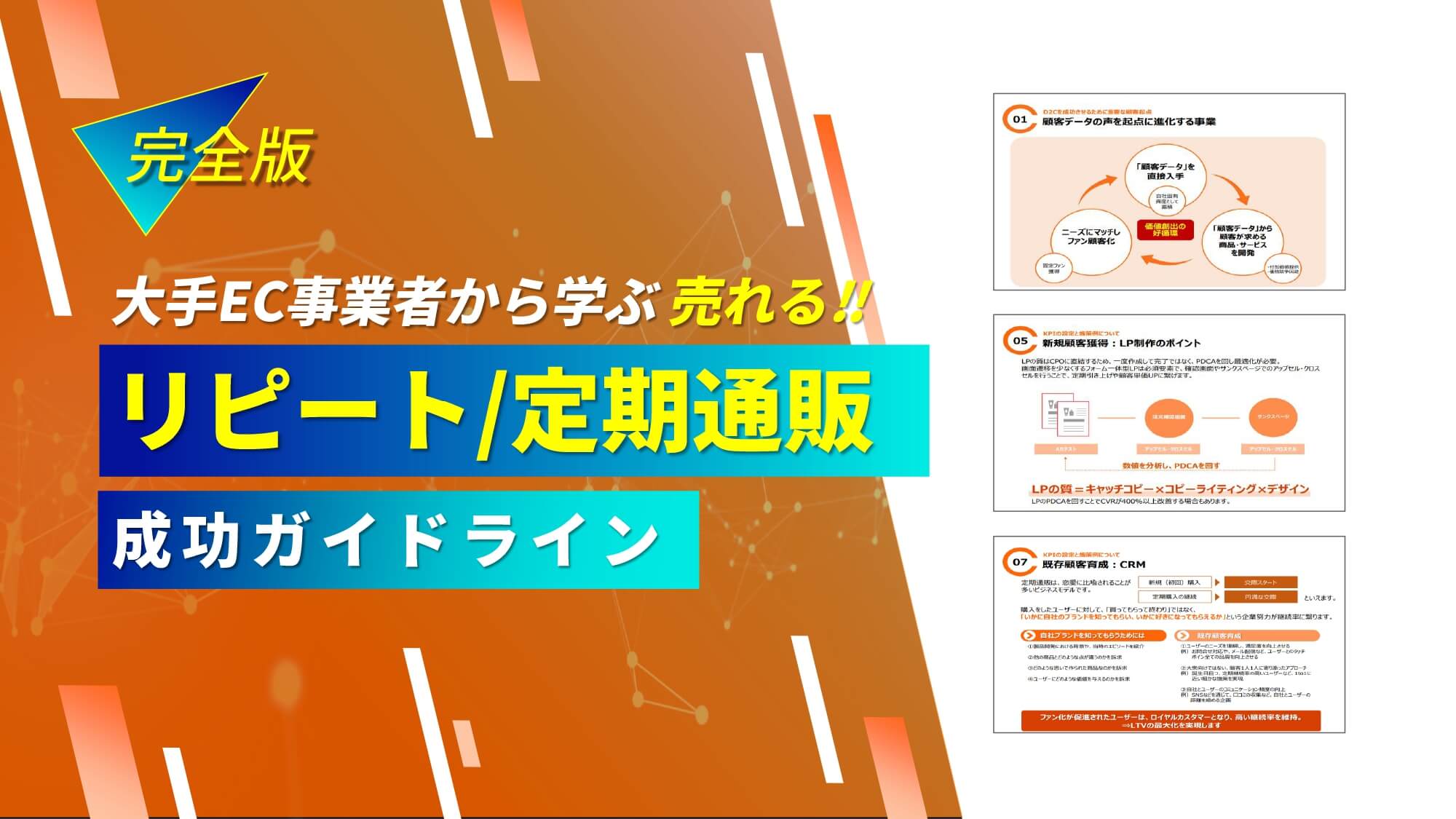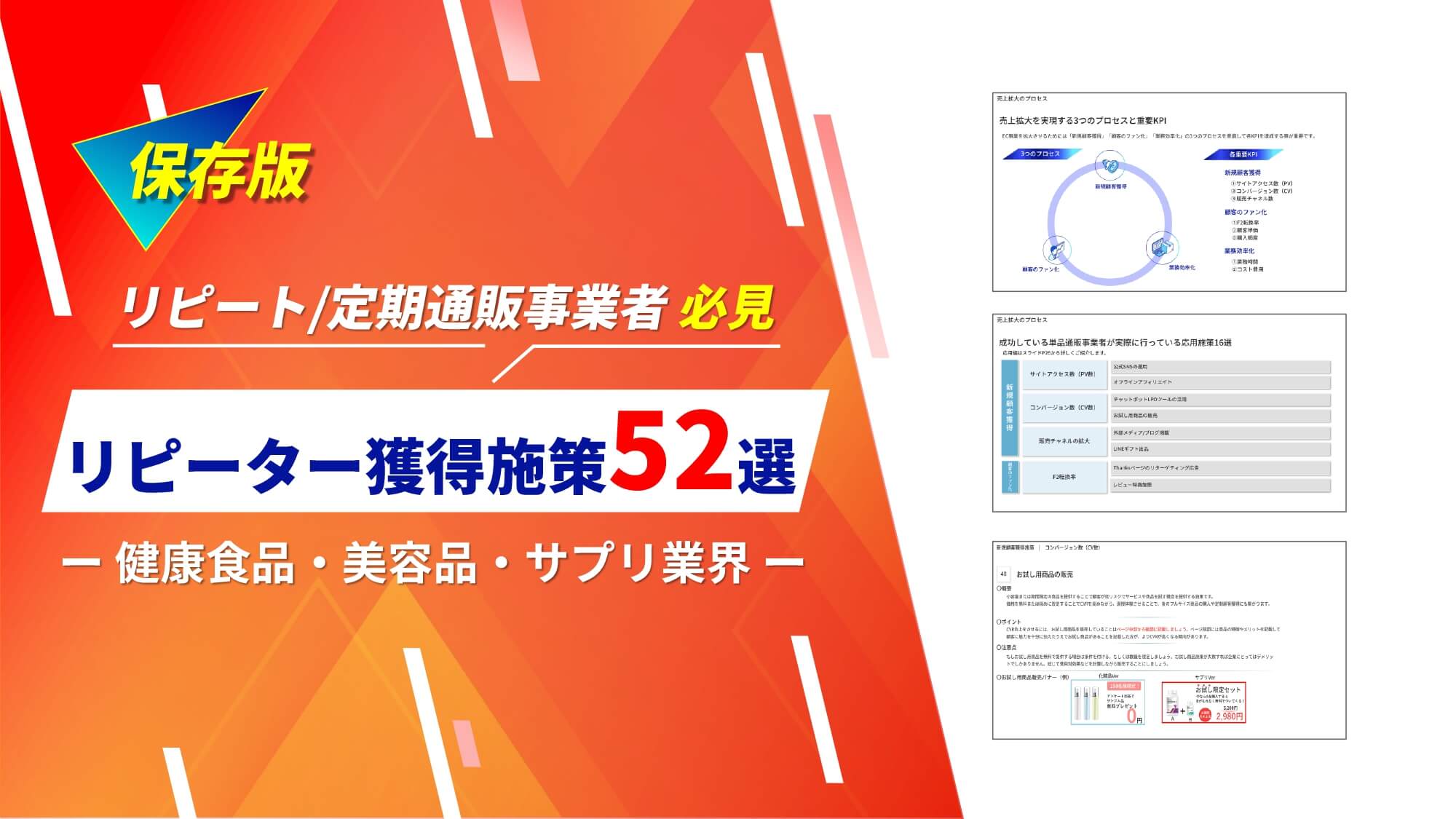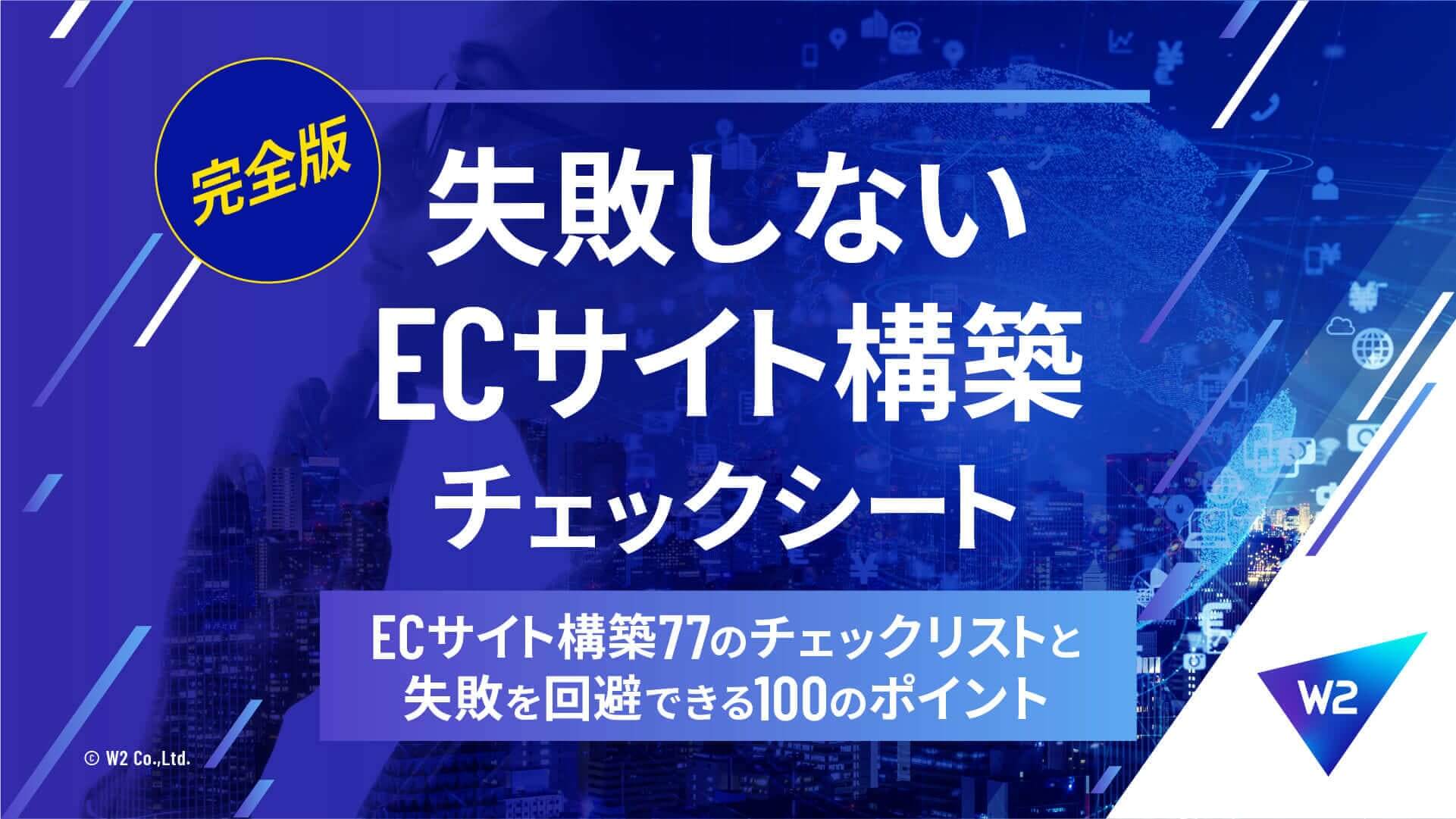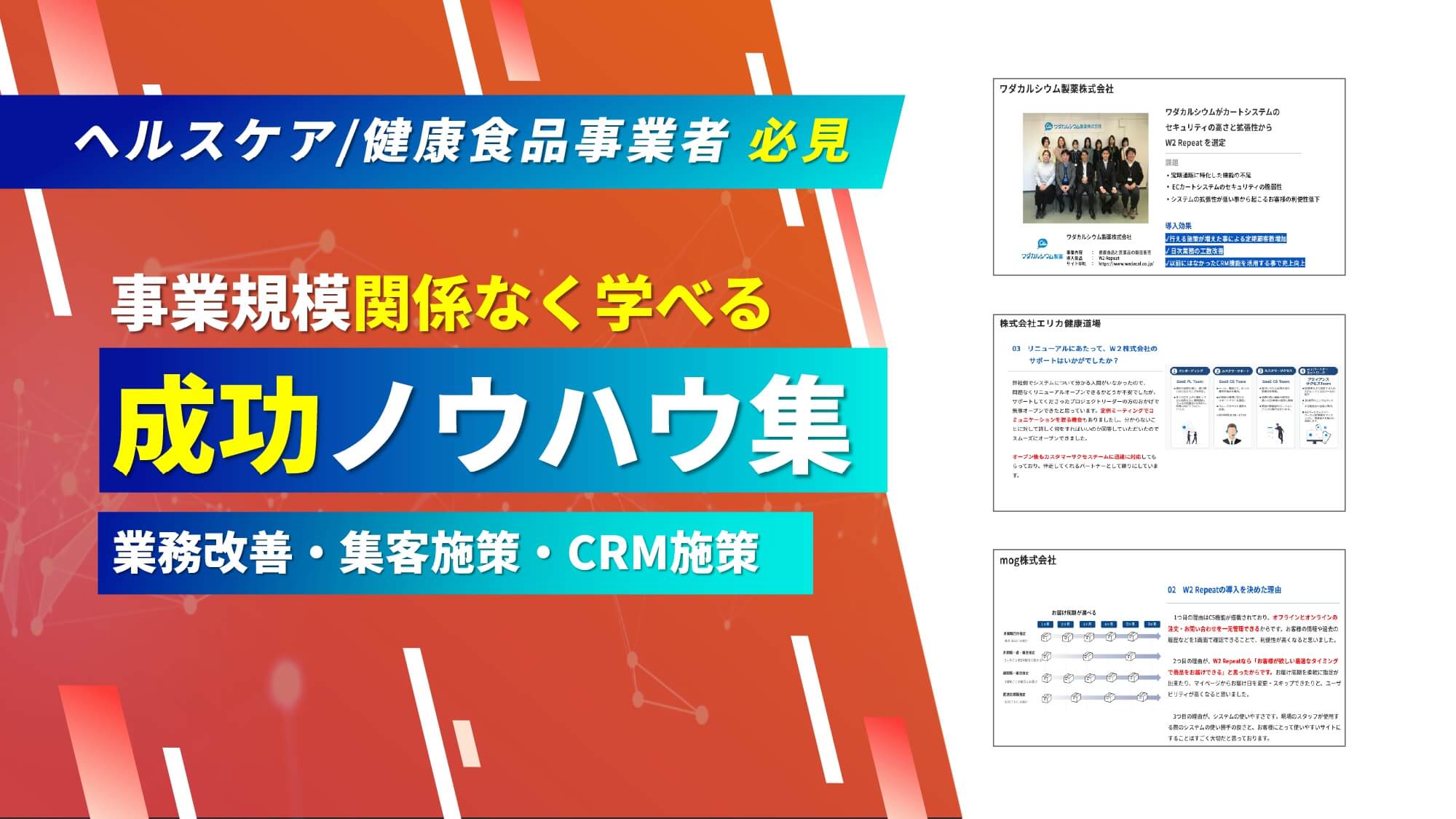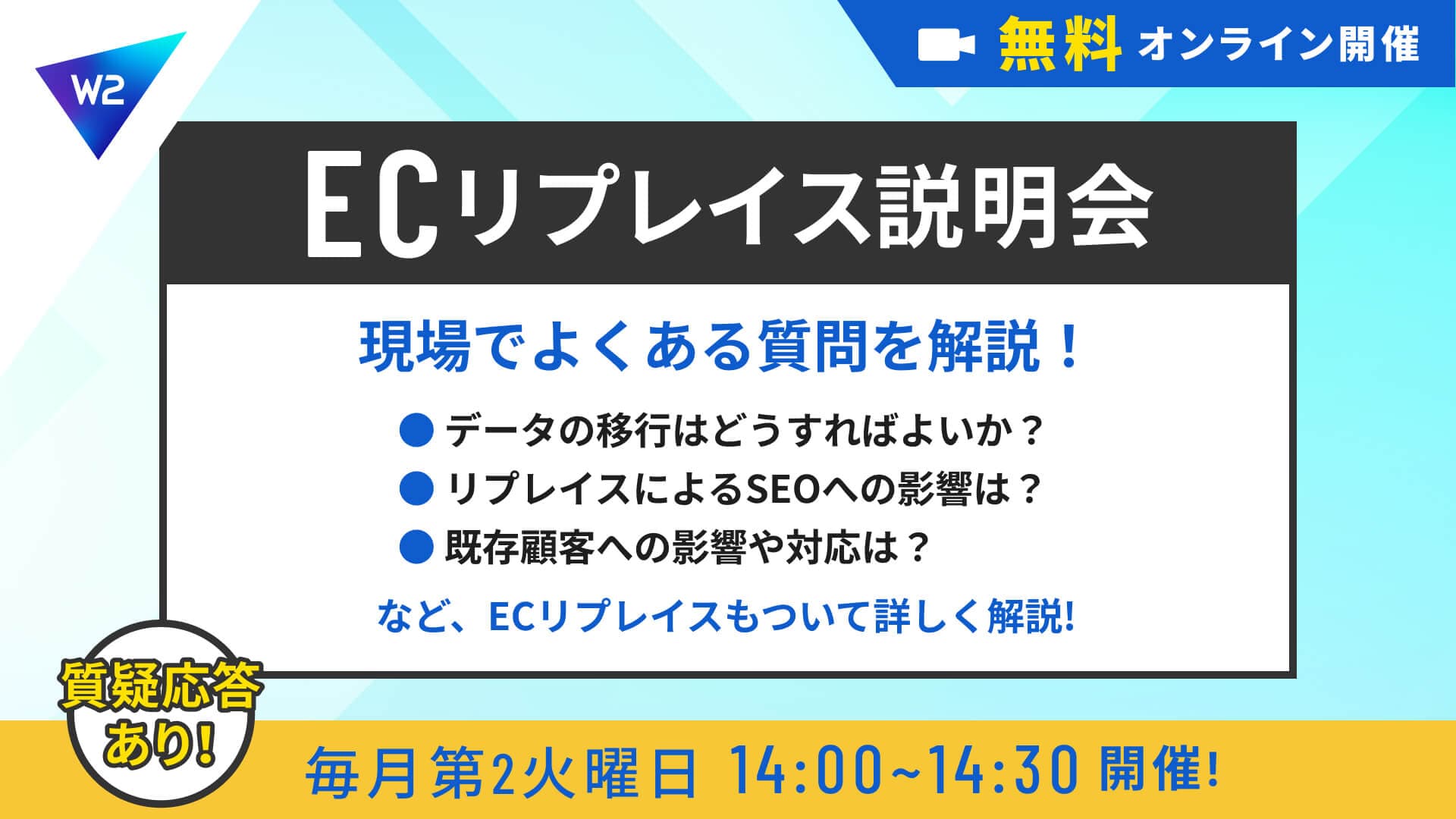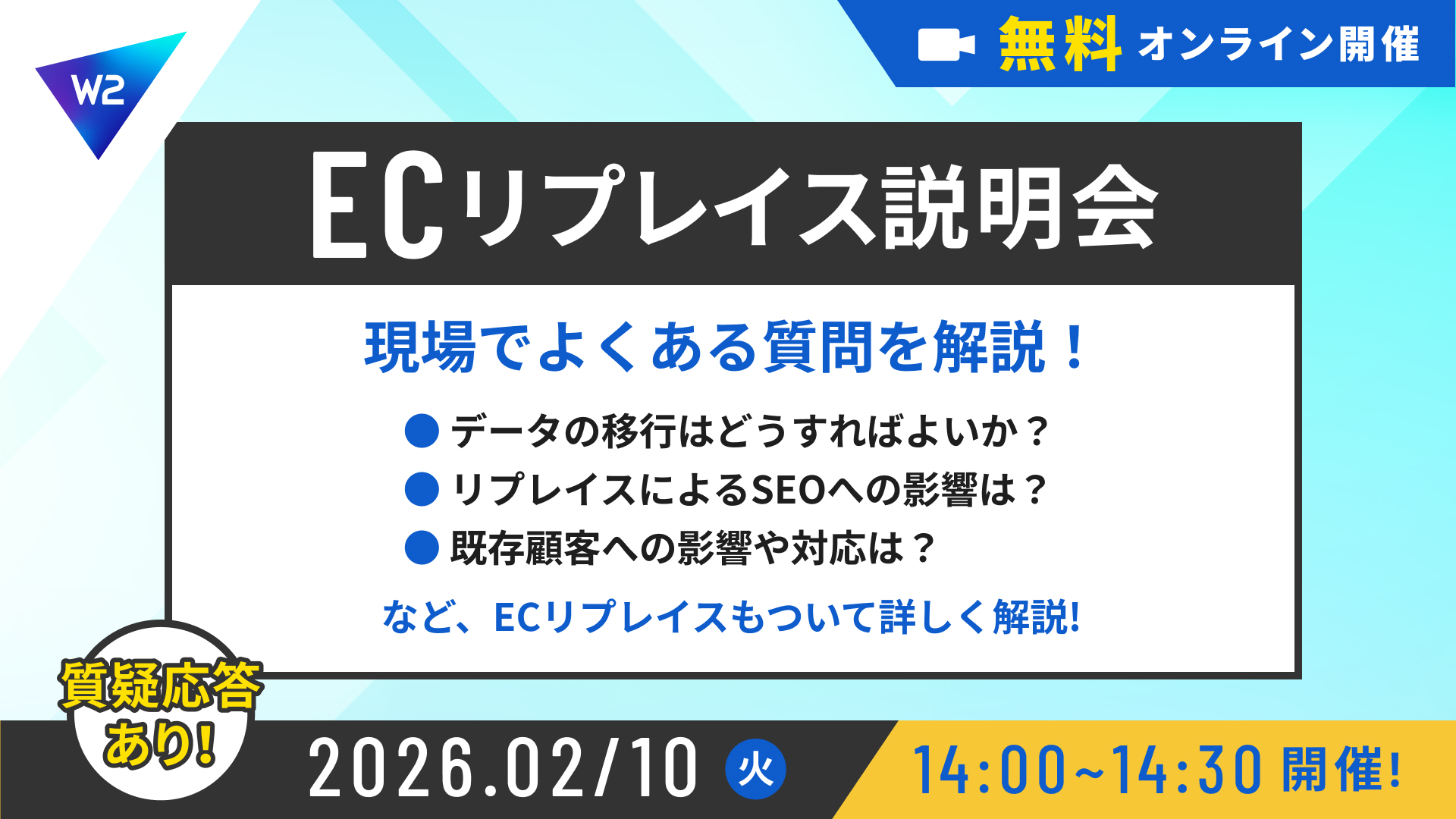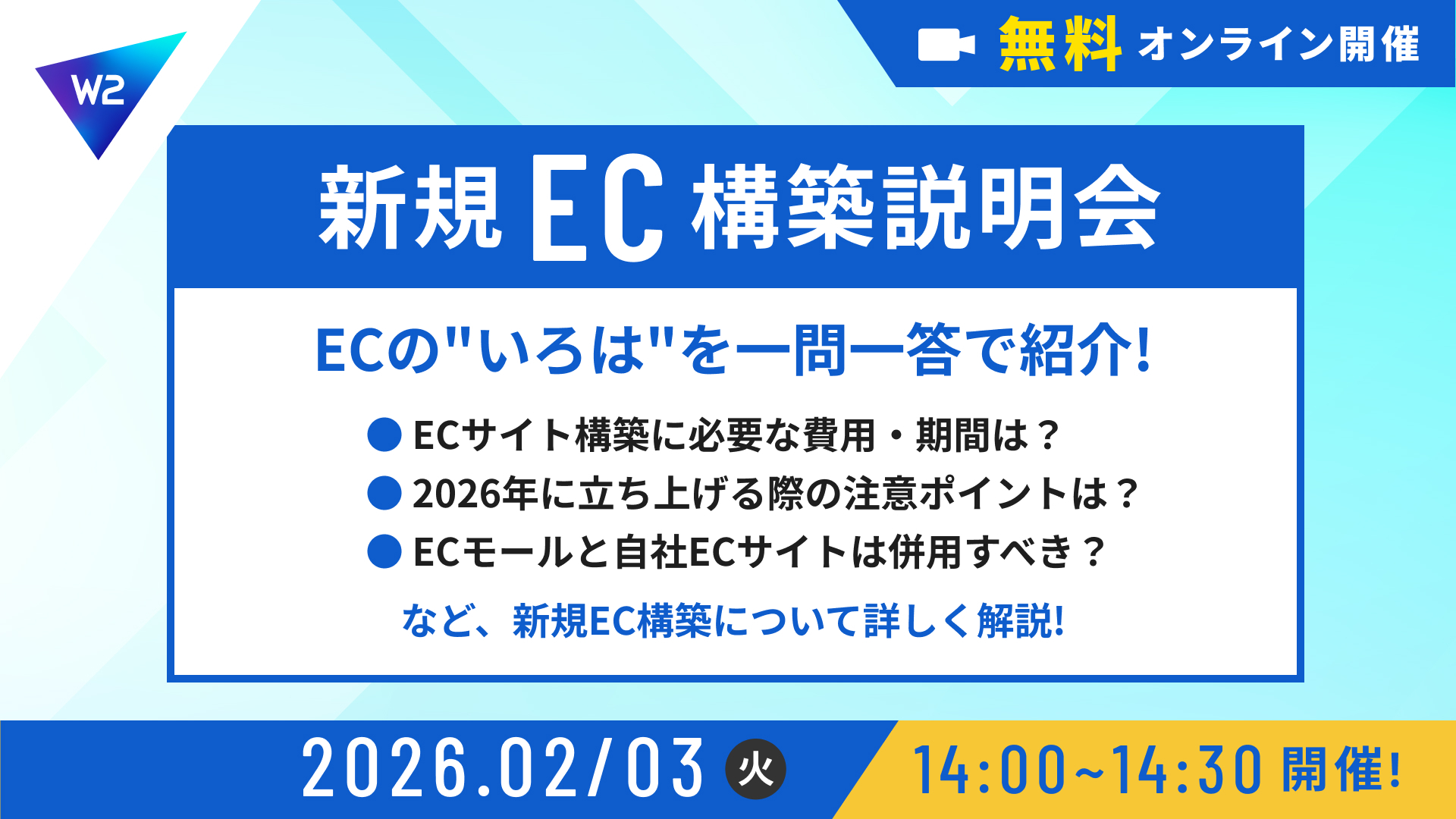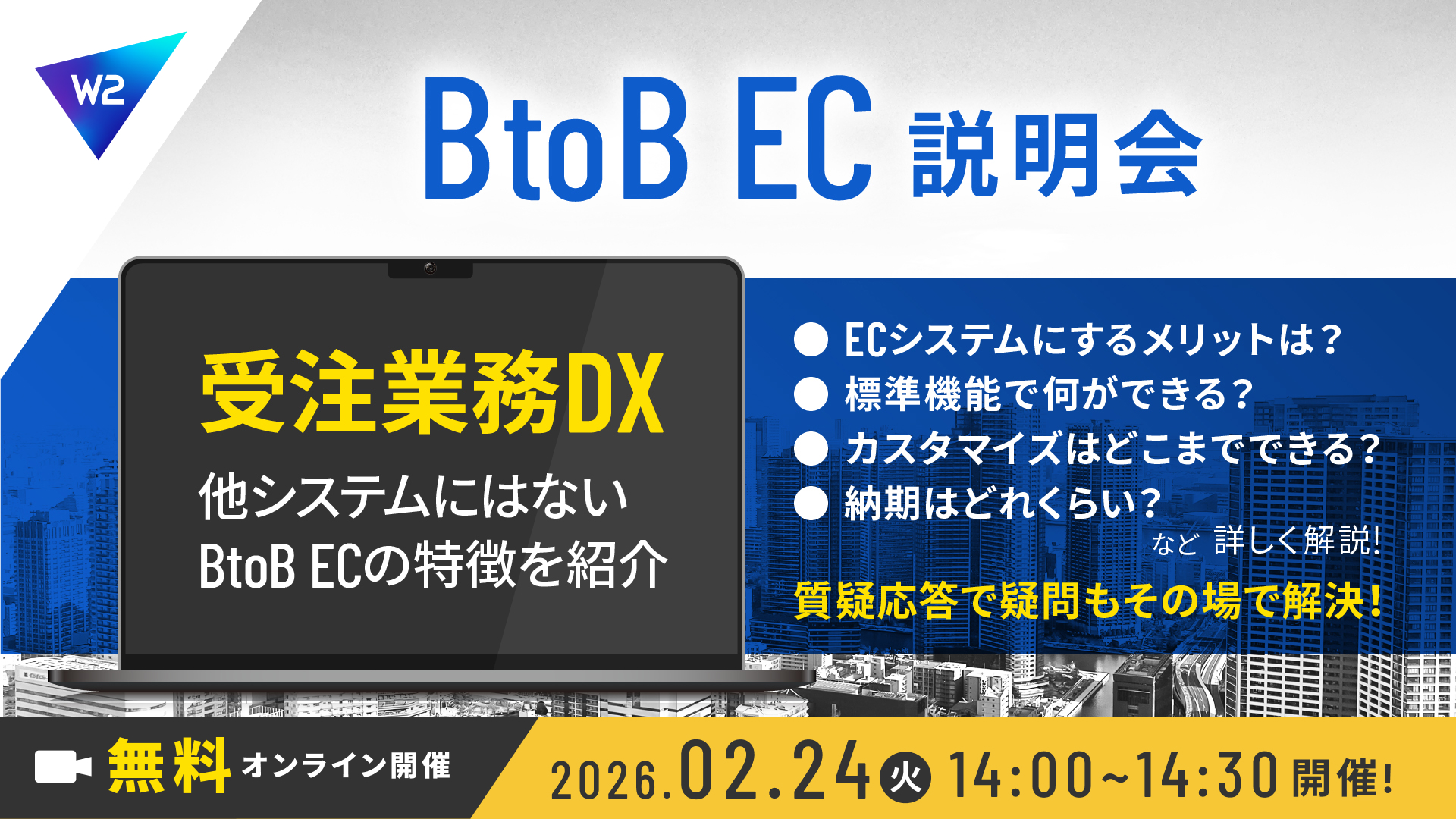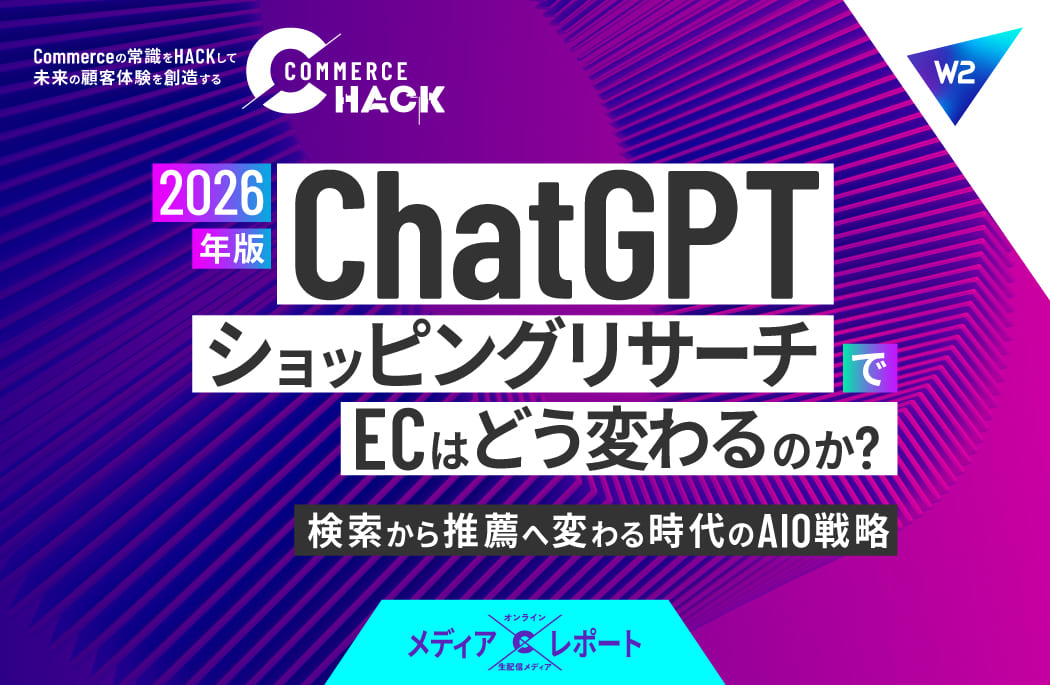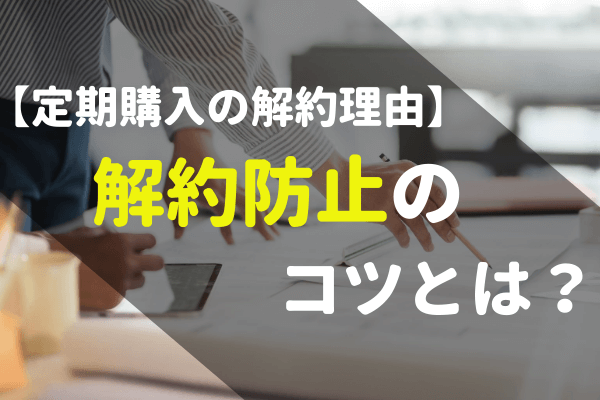
定期通販を運営する中で、「思ったよりも継続率が伸びない」「初回購入で解約されてしまう」と悩む担当者は多いのではないでしょうか。
定期購入モデルは、一度の販売で終わらずLTV(顧客生涯価値)を最大化できるビジネスモデルとして注目されています。しかし、その一方で解約率の高さが収益を左右する大きな課題です。
定期購入の解約には、「商品に対する不満」だけでなく、「サポート体制」や「購入体験」「訴求内容」といった多角的な要因が関係しています。
そこで本記事では、
- よくある定期購入の解約理由・事例
- 「効果がない」の解約対策・施策
- 「余っている」の解約対策・施策
- 「高い」の解約対策・施策
などを紹介します。
また、どのECカートシステムを選べば良いかわからないとお悩みの方に向けて、おすすめの定期購入カートシステム5選を以下の記事で解説します。この機会にぜひ一緒にご覧になられてはいかがでしょうか。
関連記事:定期通販を始めたい!定期通販のカートシステムを選ぶコツは?
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
よくある定期購入の解約理由・事例
効果がなかった・実感しない
健康食品やダイエット関係の商品でよくある例です。
宣伝文句では「効果あり」「すぐに実感できる」といったフレーズが並んでいたにもかかわらず、期待した効果を得られなければ会員は離れていきます。
こうした会員は明確な結果を求めているため、見切りをつけるまでの期間が短いことも少なくありません。1、2回使っただけで「この商品は効果がない」と早々と見切りをつけてしまうことも多いのです。
確かに、商品に問題のある可能性もゼロとはいえません。ただ、すべてのサイトが本当に効果のない商品を販売しているわけではないでしょう。
たとえば、体質的に商品と合わず、本来の効果が表れないケースもありえます。また、会員が正しい使用方法を守っていなかった場合も商品の効果は発揮されません。
しかし、このように適切な使い方をしていない会員からも、「この商品は自分には合わない」と一括りにされてしまうのです。
余っている・使用頻度が少ない
継続回数が多くなるにつれ、発生しやすい事例です。
本当なら、定期購入型のサイトではしかるべきタイミングでしかるべき量を購入してもらえるのがメリットです。
しかし、健康食品や化粧品を定期購入していると、前の分が余ってしまうことも珍しくありません。こうした状況が続くと、十分な数があるのに新しい分を買わなければならなくなってしまいます。
なかなか商品を使いきれないまま、余分な量が蓄積されていくので面倒に感じる人もいるでしょう。ただこの場合、本人が使い忘れているケースもあるでしょう。
毎日使わなければならない商品をうっかり忘れていた期間があったり、そもそも使用量を守っていなかったりすると余りは出てしまいます。
一概に、サイト側の問題とも断定はできないのです。
やはり費用が高いと感じた
料金が高いと思われることも引き留めることが難しい理由のひとつです。
実際に使ってみたうえで「料金に見合う価値がない」と判断されてしまえば、契約者はどんどん離脱していきます。
また、契約者の金銭状況が変わることもありえます。仕事を辞めたり、子どもが大学に入ったりして節約をしなければならない事情ができれば、通販サイトを解約しようと考えるのは自然な流れです。
もちろん、「高い」と感じる基準は人それぞれなので、サイト側に非があるとは限りません。ただ、あまりにも解約が続出するようなら価格を見直すなどの対策は必須です。
費用対効果を考え、適切な価格帯を設定し直すなどしましょう。
「効果がない」の解約対策・施策
契約者が「効果を得られない」と感じていたとしても、アフターフォローのあり方次第で、その印象を大きく変えることは可能です。
多くの解約理由の中でも、「効果が実感できない」は最も多い要因のひとつですが、その多くは商品の質ではなく“使い方”や“期待値のズレ”に起因する誤解によるものです。
そのため重要なのは、購入後のフォローを通じて商品理解を深めてもらうことです。
具体的には、使用開始から1週間前後に「正しい使い方」や「効果を感じやすくするコツ」をメール・LINEなどで丁寧に案内するのが効果的です。
以下、「効果がない」と思っている契約者の解約対策を紹介していきます。
逆に効果的なマーケティング戦略や集客方法について以下の資料で解説しております。
特に集客について悩んでいる方必見の資料となっているので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
顧客が適切に使えるようサポートする
考えられるのは、商品に問題はなくても顧客が使い方を間違えているというパターンです。
例えば、使用するタイミングを間違えていると本来の効果は出ません。
「食前に使う」ことを想定して作られた健康食品が食後に使用されているなど、顧客の間違いで効果が表れていない可能性があります。
また、サプリメントやダイエット食品などは使用量も重要です。つい目分量で使用を続けている人などは、なかなか良さを実感しにくいといえるでしょう。
ただ、じっくりと使用方法を調べて注意深く商品と付き合ってくれる契約者は決して多くありません。
自然と使用方法を理解できるような仕組み作りが重要です。
そのために、まずは使用方法の記載されたパンフレットを充実させましょう。
イラストや写真を多くして、視覚的に情報を把握できるように工夫します。
テキストは簡潔にして、見出しなどを設けながらポイントを押さえられるようにします。
そのうえで、使用上の注意点なども盛り込むことが肝心です。
使い続けることで効果が出ることを実感してもらう
健康や美容関連の商品は継続的に使用してようやく効果を表します。
そのため、1カ月程度では目立った実感を覚えにくく、「効果がないのではないか」と勘違いされることも少なくありません。
契約者が早とちりで見切りをつけないよう、予防線を張っておきましょう。
たとえば、効果が出るまでの期間をあらかじめ伝えておくとトラブルを予防できます。
「3カ月ほどで肌に潤いが生まれます」など、目安があれば契約者も根気強く効果に期待してくれます。
また、リアルな口コミを紹介するのもひとつの方法です。
過去に寄せられた口コミから的確なものを選び、サイト内で紹介するようにします。
「お客さまの声」と題し、「はじめはなかなか効果が分かりませんでした。でも、2カ月くらいで違いが出てきました」といったコメントを掲載すると、説得力につながります。
そして、契約者に「もう少し続けるべきかも」と思ってもらいやすくなるのです。
「余っている」の解約対策・施策
商品が余ってしまうのは、契約者本人のミスだともいえます。ただ、サイト側からの誘導で予防することも不可能ではありません。
以下、商品が余って解約するパターンへの対策です。
失敗事例は下記にてご紹介します。
休止の制度をつくる
もしも契約者が商品を余らせてしまった場合、一時的にサービスを停止できるシステムです。
余剰分を使い切るまで新たに商品を購入しなくてよくなるので、わざわざ解約する必然性はなくなります。
また、「スキップ」といって、何回か分の定期購入を省略してしまう方法もあります。
もちろん、その間の料金は発生しません。
契約者からすれば「無駄なお金を払っている」という感覚がなくなるため、離脱をしにくくなります。
ただし、これらの制度を設けても顧客に伝わらなければ意味がありません。
サイト内や契約書に記載するのはもちろん、顧客に目につきやすい書き方をするよう努めましょう。
また、顧客は少しでも制度を複雑だと感じたら、そもそも契約をしてくれなくなります。
何をどのような手順で行えばいいのか、明確に記すことが大事です。
使用し忘れを防ぐ
正しい使い方を顧客に伝えれば、自ずと商品は余らなくなります。
その結果、顧客が解約を希望することも減っていくでしょう。
特に、適切な量を伝える努力は必須です。
感覚的に商品を使用していると、本来の規定よりも少ない量になってしまうことが珍しくありません。
明確に「1回あたり何個」と記載しておくことが肝心です。
そのほか、「使用し忘れ」もよくある問題です。
社内で顧客にリマインドを促す方法を提案し合い、確実に共有していきましょう。
「高い」の解約対策・施策
顧客が商品を「高い」と感じるのは、「コストパフォーマンスを認められない」という意味だといえます。
すなわち、価格に見合うだけの効果がともなっていないから、お金を払う意義がないと思っているのです。
逆をいえば、高額であっても十分な効果が得られる商品なら多くの顧客は「コストパフォーマンスが優れている」と感じるので、不満を覚えにくくなります。
コストパフォーマンスを顧客に理解してもらうことが、解約を減らす鍵なのです。
たとえば、他の方法との比較を同梱するパンフレットやメルマガなどで示しましょう。
自社商品以外を批判するのではなく、「なぜこの方法がおすすめなのか」を理論的に説明していきます。
信頼できる根拠があれば、顧客の心をつかむことは可能です。
さらに、ダウンセルという手段も広まってきました。現在よりもグレードが落ちるかわりに、安価の商品を提案することを指します。ダウンセルではサイト側の収益が減ってしまいます。
ただ、解約という最悪の事態を逃れられる上、顧客と接点を持ち続けられるのもメリットです。
定期購入の「初回体験」を改善するポイント
開封体験をデザインする:届いた瞬間の「感動」をつくる
定期購入の初回で最も重要なのは、顧客が商品を開封する瞬間の体験です。初回の印象はその後の継続率に大きく影響します。開封体験を「ただの受け取り」ではなく「特別な体験」に変えることが大切です。
たとえば、ブランドの世界観を感じさせるパッケージデザインや、開けた瞬間に笑顔になれるメッセージカードの同梱が効果的です。
さらに、初回限定の小冊子や「ご購入ありがとうございます」の手書き風メッセージを添えることで、顧客に“自分のために用意された”というパーソナルな感覚を与えられます。
また、開封動線も工夫の余地があります。
箱を開けたときに「一番伝えたい情報(ブランドの想い・使用手順など)」が視覚的に目に入るよう設計すると、自然と理解促進につながります。
こうした細部の体験設計が「丁寧なブランド」という印象を形成し、初回解約を防ぐ第一歩となります。
同梱物・メッセージの工夫でブランド体験を強化する
定期購入は「商品を届けること」が目的ではなく、「ブランドとの関係を築くこと」が本質です。そのためには、同梱物の内容が重要な役割を果たします。
例えば、ブランドの開発ストーリーやこだわりを伝えるリーフレット、「商品を使うことで得られる理想の未来」を描く冊子を添えると、単なる商品以上の価値を感じてもらえます。
さらに、実際に愛用しているユーザーの声を紹介することで「継続すれば自分もこうなれる」という共感を生み出せます。
また、メッセージトーンにも工夫が必要です。
企業目線の説明文よりも、「お客様の生活を応援する」や「日々の変化を一緒に喜ぶ」といった共感的な語り口が効果的です。
到着後フォローで使用定着を支援する
商品が届いたあと、「どう使えばいいのか分からない」「効果が分からない」と感じる顧客は多く、ここで離脱が起きやすくなります。
そのため、到着後のフォロー設計が定期購入ビジネスでは非常に重要です。
商品到着から3日以内に、サンクスメールやLINEメッセージで「正しい使い方」「効果を感じやすくするコツ」「注意点」などを丁寧に案内しましょう。
さらに、動画を活用して使用手順を視覚的に説明すれば、初心者でも安心して利用できます。
また、到着1週間後には「使い心地はいかがですか?」という軽いフォローメールを送り、疑問点や不満を早期に拾い上げるのも有効です。
問い合わせ導線を明確にし、「気軽に相談できる」雰囲気を作ることが継続率向上につながります。フォローを“売り込み”ではなく“伴走”と捉えることで、信頼関係を築くことができます。
以下の記事ではLINEミニアプリ連携について詳しく解説しています。
ぜひ合わせてご覧ください。
2回目以降の“継続理由”をつくる仕掛け
初回の感動体験を得ても、2回目購入前の時期に「やめようかな」と迷う顧客は多いです。そこで重要になるのが、継続する理由を自然に感じてもらう仕掛けです。
たとえば、2回目配送の1週間前に「次回のお届け内容確認」とともに「継続特典」や「限定コンテンツ」を案内するメールを送ると、解約抑止につながります。
また、使用を続けることで実感できる変化を「ステップアップ体験」として可視化するのも効果的です。
さらに、SNSやレビューで継続利用者の声を発信することで、「続ける価値」が社会的に証明される仕組みをつくることもポイントです。
顧客が“ブランドと一緒に成長している”と感じられると、単なるリピートではなく共感による継続が生まれます。継続率を高めるには、モノではなく「体験価値」を届ける視点が欠かせません。
顧客の声を初回体験設計にフィードバックする
初回体験を最適化するうえで欠かせないのが、「顧客の声を聞く仕組み」です。
解約アンケートやレビュー分析を通じて、“なぜ離脱したのか”“どの部分に満足していないのか”を定量・定性の両面から把握しましょう。
例えば、「使い方が難しい」「香りが好みでない」「効果を感じにくい」といった声が多ければ、同梱物やフォロー内容を見直すサインです。
また、ポジティブな口コミも重要なヒントです。「丁寧な梱包が嬉しい」「動画が分かりやすかった」などの声を積極的に反映し、次の顧客により良い初回体験を届けましょう。
CRMを活用すれば、解約理由の傾向を自動で可視化し、施策ごとの改善効果を分析できます。顧客の声を一度きりの参考情報で終わらせず、継続的に活かすことで“顧客中心の定期通販運営”が実現します。
以下の記事では口コミの活用方法について詳しく解説しています。
ぜひ合わせてごらんください。
解約理由をできるだけ正確に知るには
もしも解約者が増えているのであれば、原因を突き止めなければ対処できません。そのまま解約者が増えていくとサイトの収益は下がる一方です。
理由を知るには、解約者本人に聞くのがもっとも効率的です。解約フォームに「理由」を記入する欄を設け、運営が確認できるようにしておきましょう。
電話で解約を受け付けているサイトであれば、オペレーターから理由を聞きだしてもらいます。オペレーターが顧客とコミュニケーションを取るメリットはさまざまにあるので、後述します。
ただ、入力フォームやオペレーター越しの質問では、正確な答えを得られるとは限りません。その場を早く切り上げたくて適当な回答をする顧客もいます。
そこで、顧客情報やサイトを解析するツールを使うのもひとつの方法です。
これらのツールを利用すれば、ネットユーザーの潜在意識をデータ化できます。
表層的な数字をさらに深く掘り下げ、すぐには分かりにくい理由を可視化できます。
次のマーケティング戦略を考えるうえでも有効な手段といえるでしょう。
コールセンターによるサポートの効果
なぜコールセンターのオペレーターが解約防止を担えるのかといえば、「適切な方法を提案する」ことが可能だからです。
たとえば、電話口で顧客から解約理由を聞き出せたとします。
そこで、オペレーターが詳しくヒアリングしたうえで、「それならば、このようなプランにに変更する方法もありますよ」と持ちかけられれば、翻意する顧客もいるでしょう。
思い込みや勘違いで解約してしまう顧客もいるので、オペレーターから正確な情報を提供できることは予防策になりえます。
特に、「商品が余る」「効果が出ない」といった、先述の解約理由には効果的です。
また、解約をしなくても休止で十分の場合、オペレーターからその手順を案内できます。特別な手続きが必要なときでも、丁寧に説明すれば顧客は手間に感じになくなります。
仮に顧客を引き留められなかったとしても、解約理由の細かいヒアリングができるのは魅力です。
収集できた情報は今後、サイトの改善点を探るために利用することができるでしょう。
解約のトラブルに気をつけよう
定期購入の通販サイトでは、解約にまつわるトラブル事例が相次いでいます。運営者としては、トラブル内容を知ったうえで対策を立てましょう。
この段落では、具体的なトラブルの概要を説明します。
急増する定期購入のトラブル
トライアルのつもりで契約した顧客が、回数縛りのある定期購入だったと知ってクレームを投げかけてくることは少なくありません。
本来、お試し期間であれば料金は格安か無料になります。
そのため、定期購入の費用を払わされるとなると顧客はだまされたように感じてしまいます。
また、自由に解約できると思っていたのに、一定期間は購入し続けなければならないと知った場合もトラブルにつながりかねません。
悪徳業者の中には、わざと解約の連絡をしにくくしているところもあります。
さらに、定期コースであることや解約条件をあえて小さく表記している業者もいます。
こうした業者は顧客から「不当だ」と批判されても「しっかりお伝えしていました」と言い逃れをするのです。
そのほか、「期日までもうすぐ」といったカウントダウン表示を常にしている業者もあります。
カウントダウンを見た顧客は焦って商品を購入してしまい、解約しづらいシステムに後から気づくのです。
以下ではECサイト構築チェックシートを配布しております。
是非合わせてご覧ください。
事業者側が気をつけるべきこと
顧客はあるサイトで不満を感じたとき、「ここは悪徳業者だ」と思い込んでしまうことがあります。
定期購入の運営者なら、顧客から悪徳業者だとみなされないよう意識して活動しましょう。中には、「法律に違反していないのだから、顧客から恨まれる筋合いなどない」という意識で運営している事業者もいます。
また、顧客側のミスや勘違いで悪徳業者と批判されるのも理不尽ではあります。
ただ、どのような流れであれ、一度悪徳業者という噂が広まれば世間からのイメージが失墜しかねません。口コミサイトにも不名誉な記述が残り、今後の経営に影響します。
顧客との不要なトラブルを避けるには、定期通販としての自社の運営方法や解約条件を分かりやすく伝えることが大切です。そうやって誤解を招かず、顧客と良好な関係を維持していきます。
なお、通信販売については「特定商取引法」によって経営の形態、ルールが法律で規定されています。
この法律を常に念頭に置いて運営することが重要であり、そうすることで、いざトラブルが起こったときにも冷静に対処できるでしょう。
解約原因の特定と対策にはシステム導入もおすすめ
定期購入の通販サイトは、契約者がいるからこそ経営を続けられます。そのため、解約率の上昇は深刻な問題です。
CRM(顧客管理)のデータ利用などで、解約理由を特定し対策を練りましょう。CRM機能を搭載した定期購入型通販用のカートシステムの導入も得策です。
弊社のシステムである分析機能やカスタマサポート機能も搭載している「W2Repeat」では様々な解約防止施策が打てることで多くの事業者様の導入実績があります。
実績や機能面など詳細も含めてお気軽にお問い合わせください。
なお、これからネットショップ構築を検討している方に向けて「ECサイト構築のしくじり事例100選」をまとめました。
そこで下記資料では、実際にEC事業者から聞いたネットショップ(ECサイト)構築における失敗事例を100個とECシステムの選定チェックポイントを解説/一覧化しました。
資料は無料でダウンロードできるので、ネットショップの構築/リニューアルを検討している方はぜひあわせてご一読ください。
まとめ:定期購入の解約理由を押さえて対策しよう
改めて、本記事の内容をまとめます。
- よくある定期購入の解約理由3つ
1. 効果がなかった・実感しない
2. 商品が余っている・使用頻度が少ない
3. やはり費用が高いと感じた - 効果がない場合、アフターフォローに注力する
- 商品が余ってる場合、休止制度や使い忘れ防止の仕組みを作る
- 高いと感じる場合、コスパが優れていると訴求する
本記事の内容を参考に、まずは自社の解約理由を正確に把握し、課題ごとの打ち手を体系的に整理してみてください。
定期購入ビジネスで長期的な売上を伸ばし続けるには、「解約率を下げる」だけでなく、顧客が自然と“続けたい”と思える仕組みを作ることが欠かせません。
商品やサポートを通じて「このブランドなら信頼できる」と感じてもらうことが、結果的に継続率向上とLTV最大化につながります。
小さな改善の積み重ねが、安定した定期収益モデルを育てる第一歩です。
そこで、定期購入の成功率をグンッと上げるリピート通販の成功ポイントを完全網羅する形で、「【完全版】 売れるD2Cリピート通販 成功ガイドライン」にまとめました。
また、定期通販では以下のECカートシステムがおすすめですのでこの機会にご覧ください。