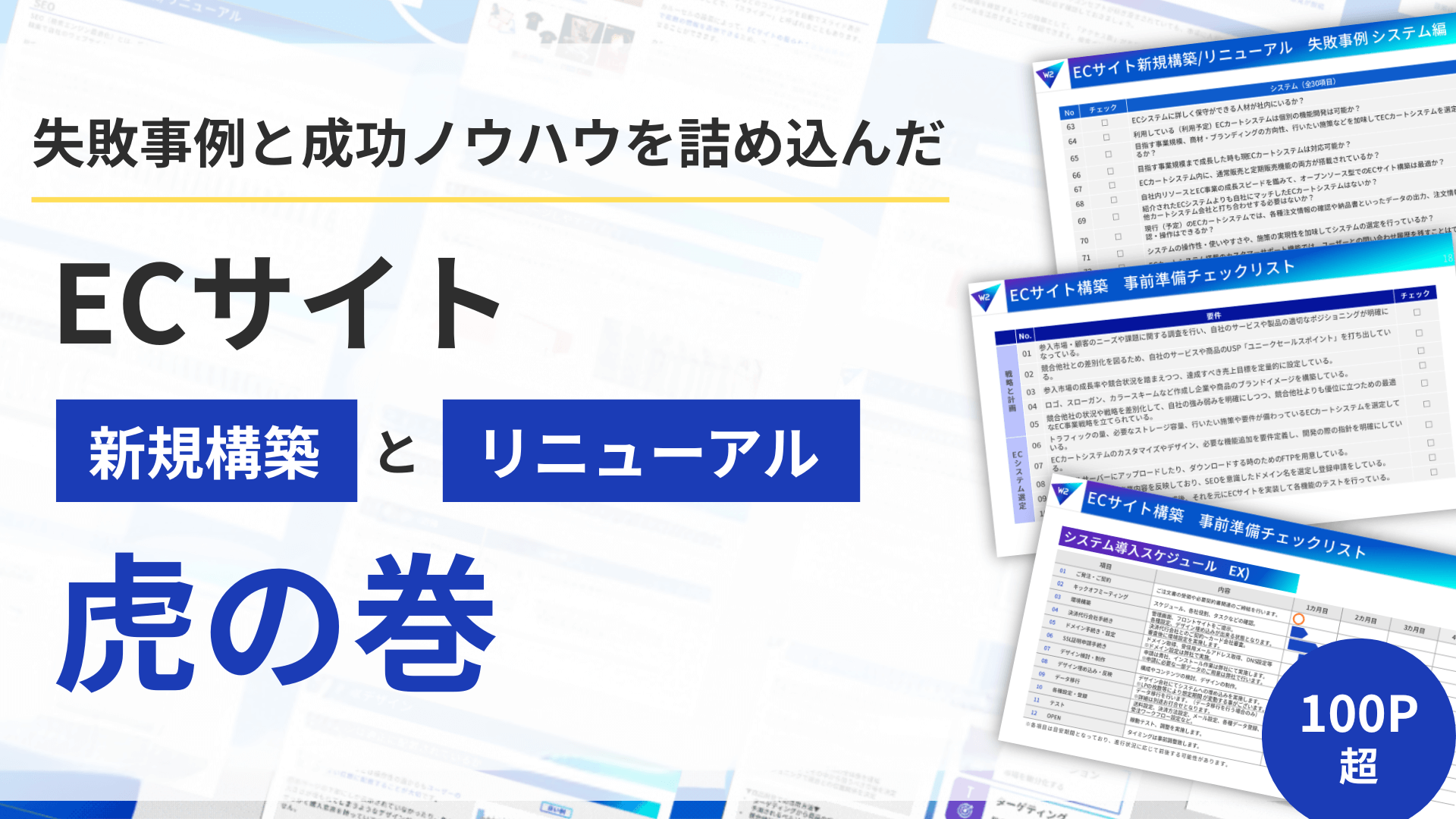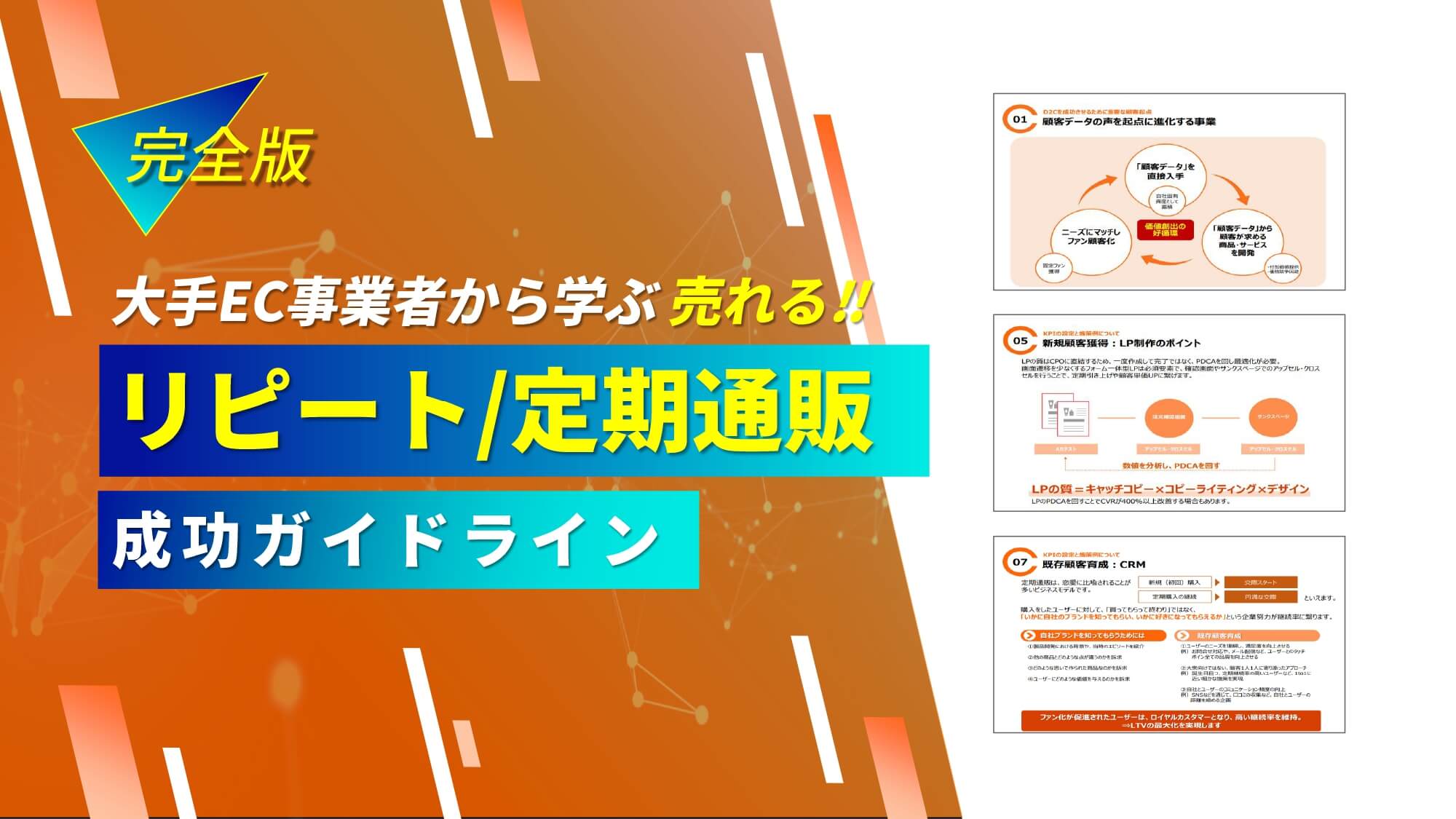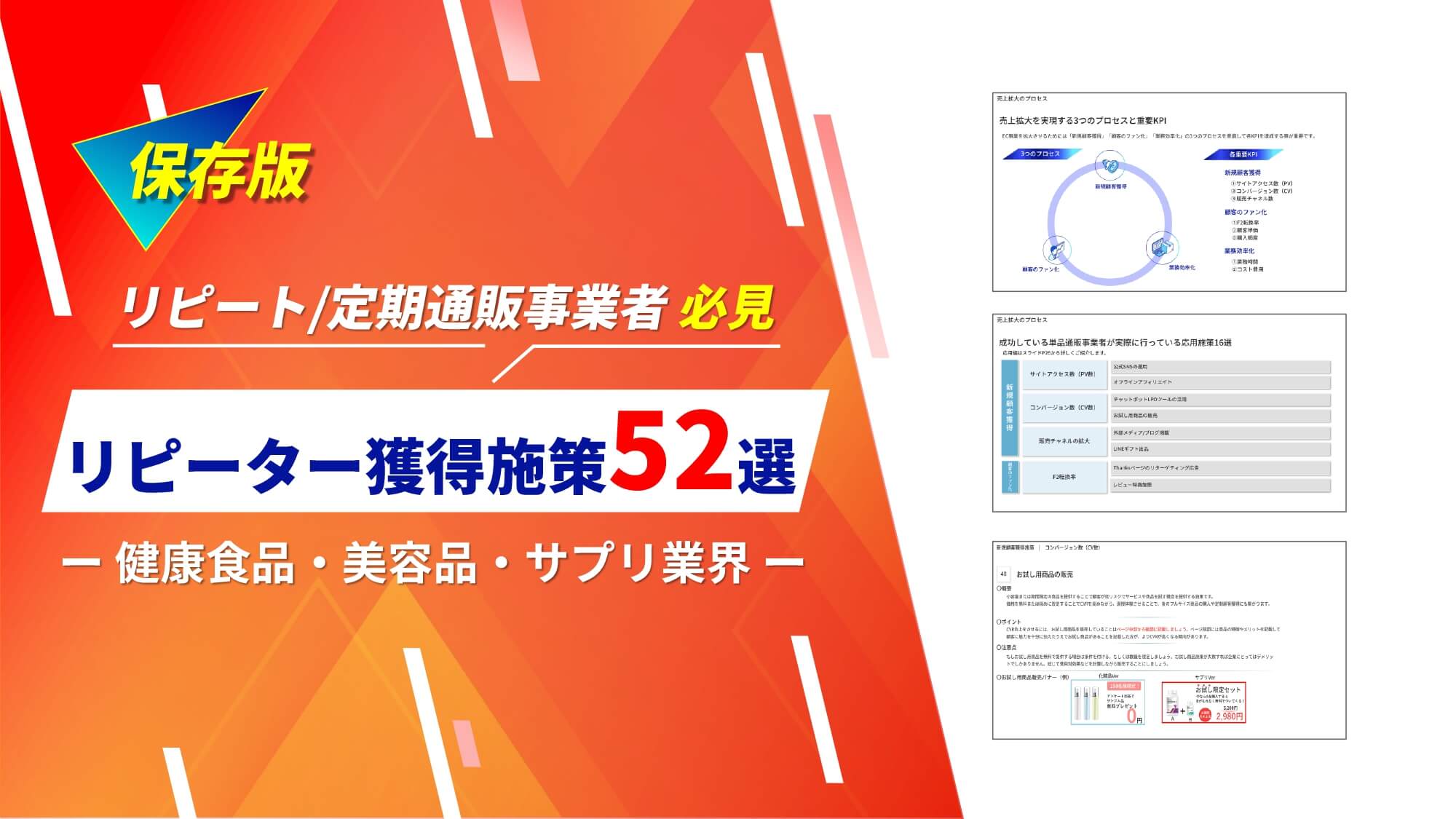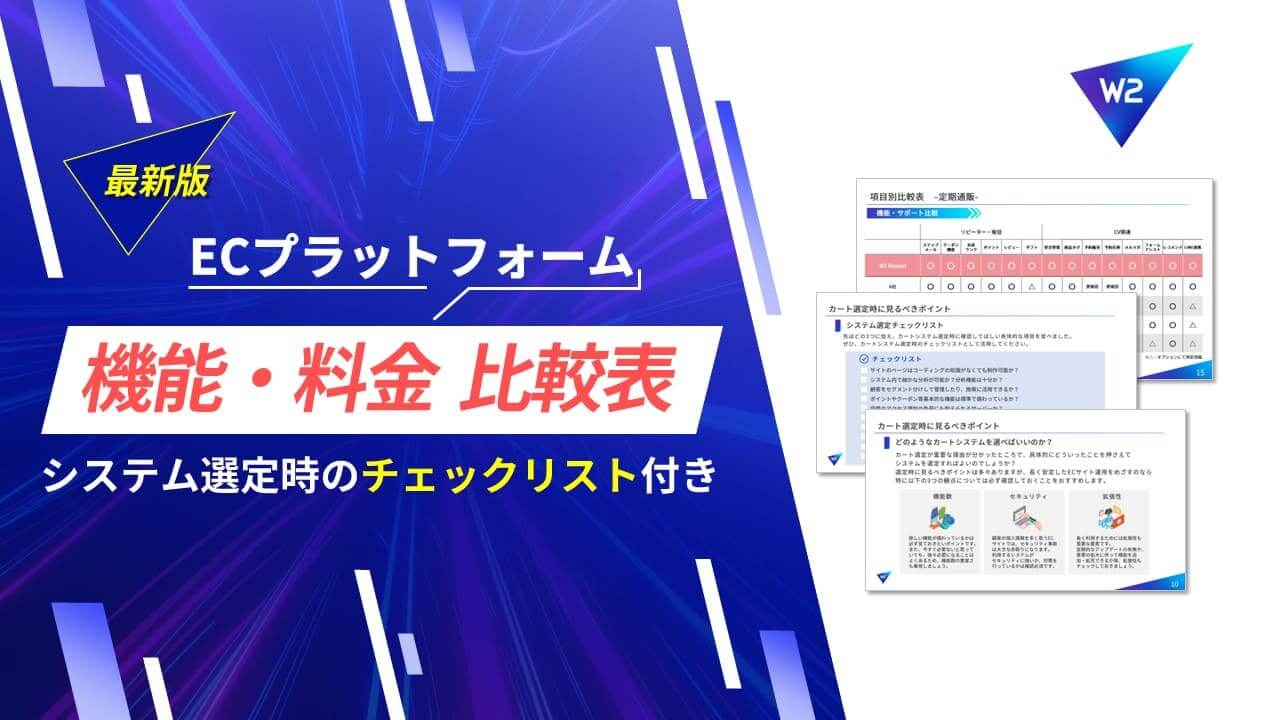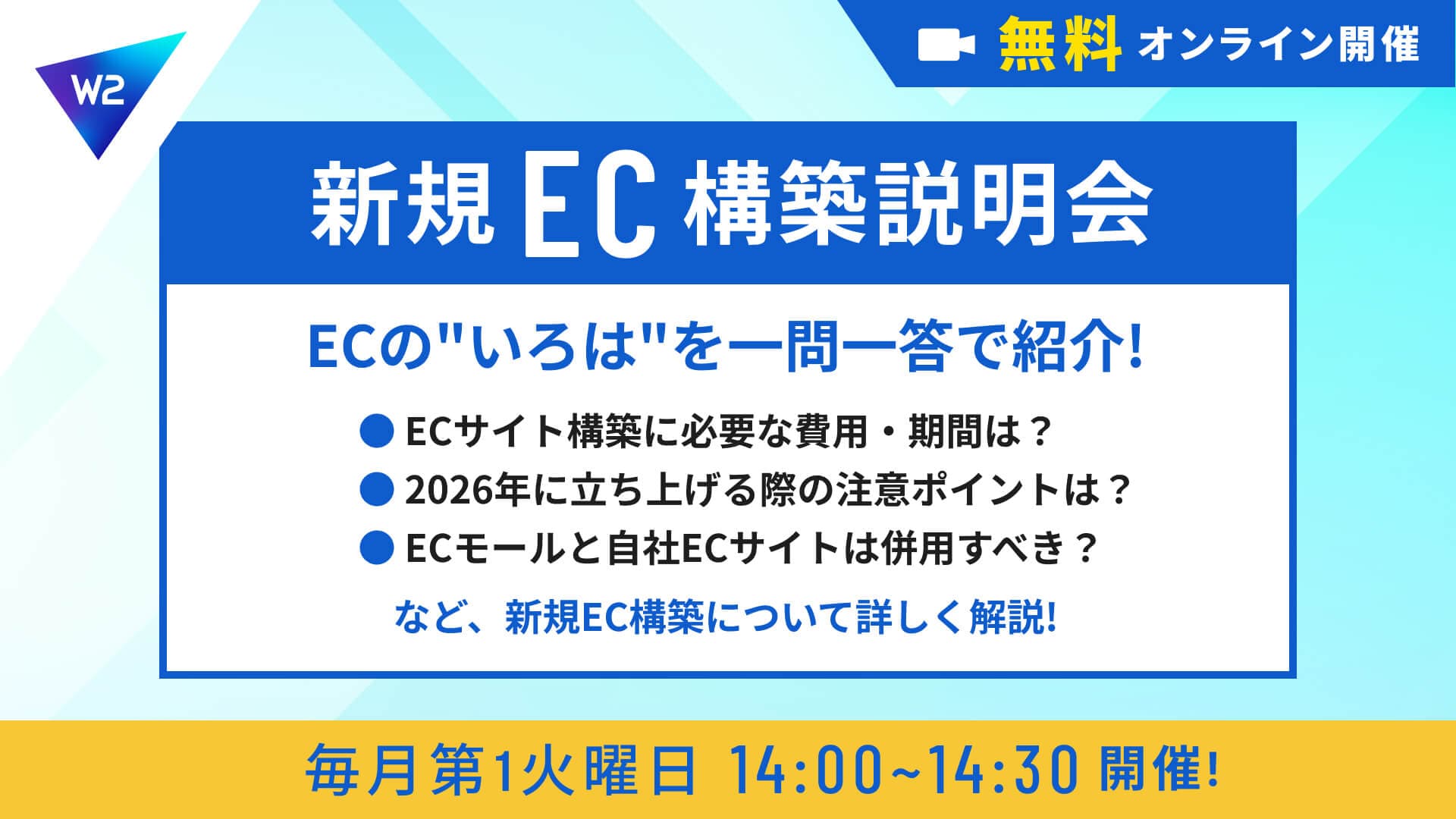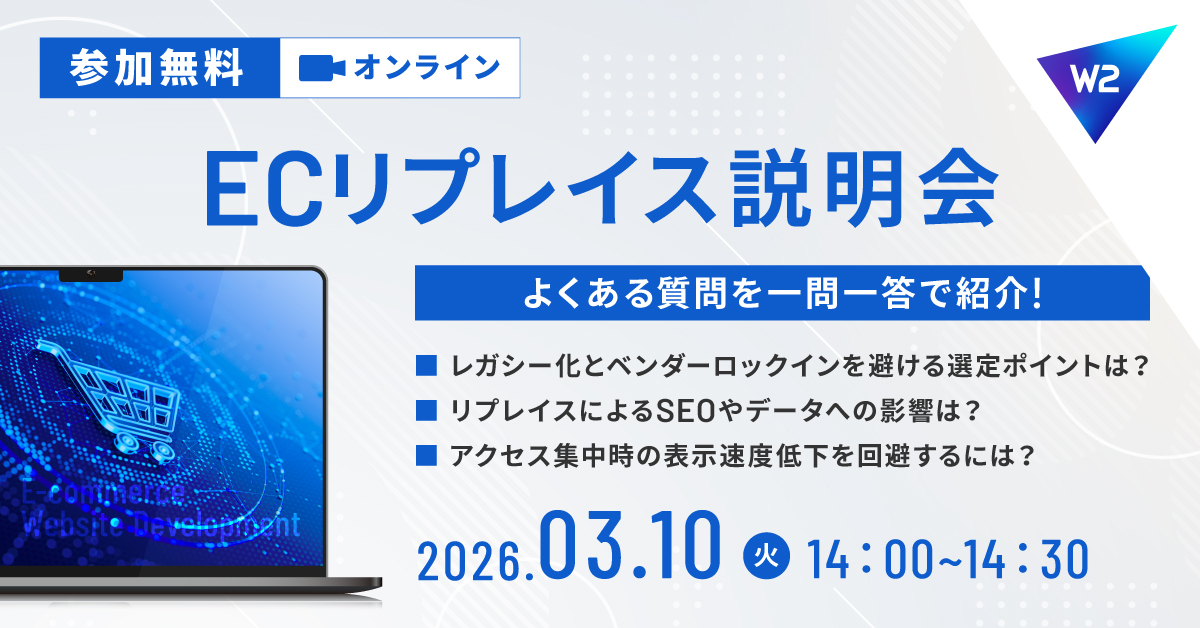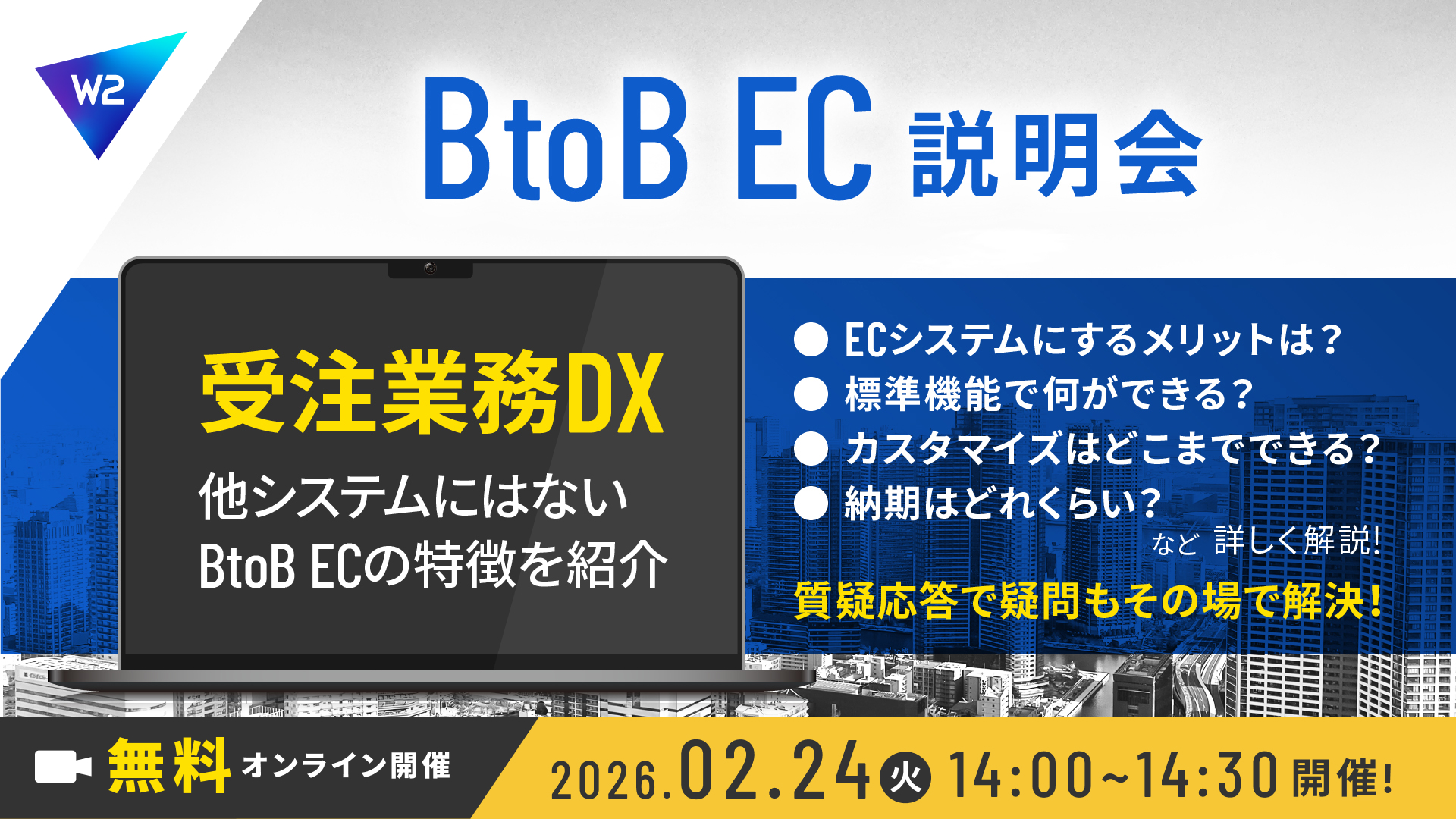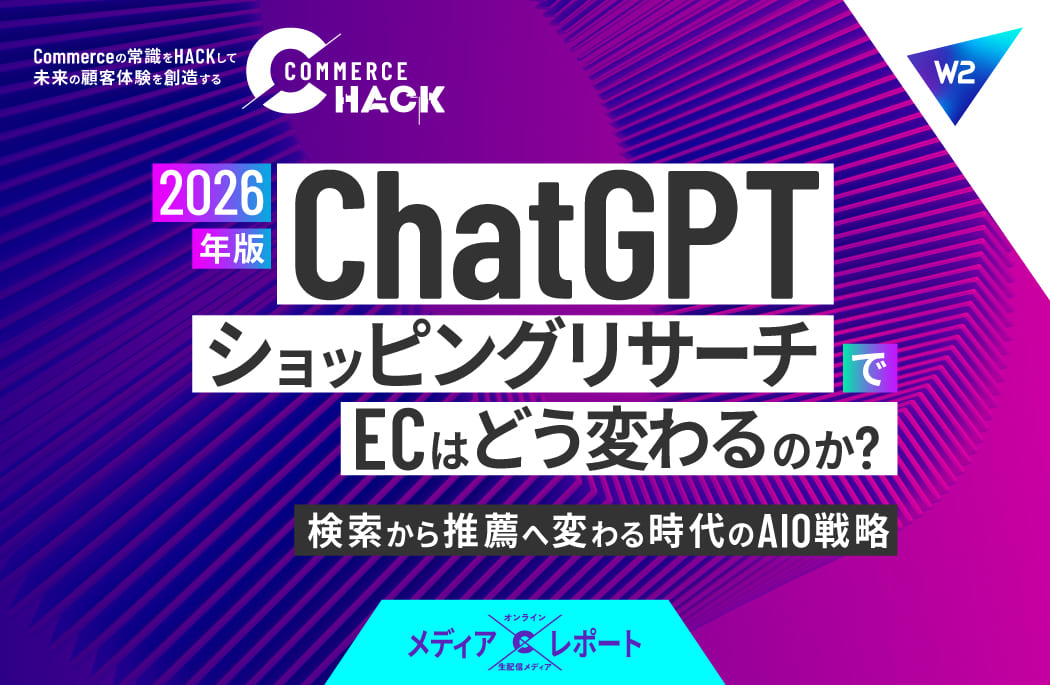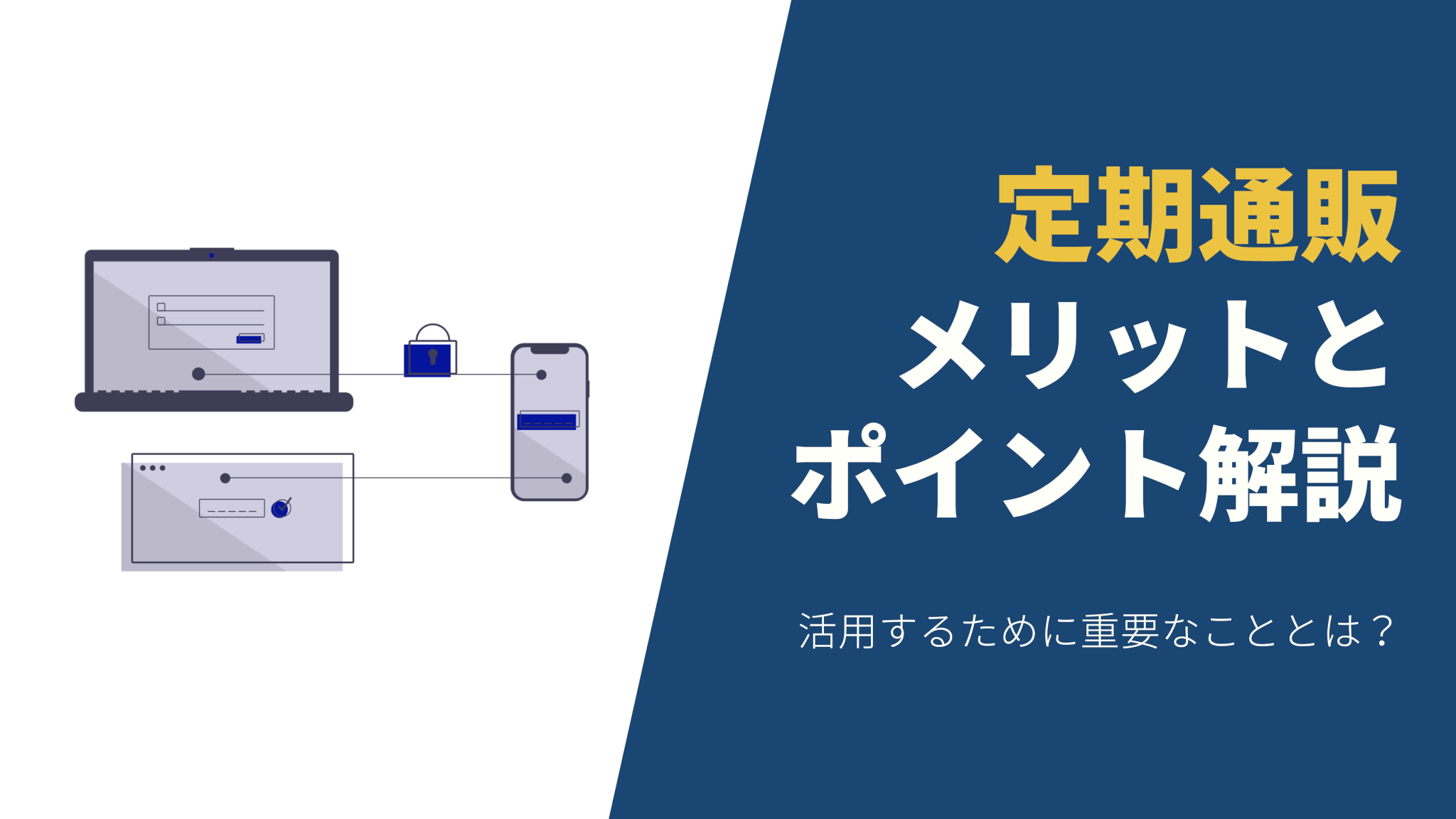
「定期通販ってどんなビジネスモデル?サブスクリプションとの違いは?」
「定期通販を成功させるためのポイントを知りたい」
このようにお考えではありませんか。
定期通販はインターネット技術が発展した現代で有効なビジネスモデルですが、特徴を把握しないまま始めると失敗する恐れがあります。
そこで本記事は、
- そもそも定期通販とは?サブスクリプションの違い
- 定期通販を導入するメリット4つとデメリット2つ
- 定期通販を成功させるためのポイント5選
- 定期通販におすすめなECカートシステム
- 定期通販の成功事例2選
- 定期通販を始める際によくある質問
を紹介します。定期通販のビジネスモデル開始を検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
定期通販とは

定期通販とは、定額の料金を支払うことで、同じ商品を一定のサイクルで届ける販売手法のことです。「定期便」や「定期購入」「定期販売」とも呼ばれ、顧客にとっては購入の手間が省ける利便性があり、企業にとっては安定した収益を見込めるメリットがあります。
代表的な商材としては、健康食品やサプリメント、化粧品、日用品などの消耗品が挙げられます。特に美容関連商品や健康食品は定期的な摂取や使用が効果を高めるという特性から、定期コースが主要な販売方法となっています。
その他にも、食材宅配サービス、ペットフードの定期配送、雑誌や書籍の定期購読、オフィスコーヒーの定期補充サービスなど、多様な商品カテゴリーに広がっています。
定期通販の歴史は、1980年代に化粧品や健康食品メーカーが電話やハガキ、雑誌や新聞による定期購入の仕組みを導入したことがきっかけです。インターネットの普及に伴い、2000年代に入ると電子商取引の発展とともに定期通販の形態も大きく変化し、オンライン上での申し込みや顧客管理が容易になったことで急速に普及しました。
2010年代以降はスマートフォンの普及により、いつでもどこでも配送サイクルの変更や一時休止などができる利便性が向上し、より柔軟なサービス提供が可能となりました。
定期通販は、顧客のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能であり、企業にとっても持続可能な収益源を確保するための効果的な方法です。顧客は一貫した価値を受け取ることができ、企業は長期的な顧客関係を築くことができます。
定期通販とサブスクリプションの違い
定期通販とサブスクリプションは、定額サービスで利用できる点は同じです。しかし、取り扱っている商材が異なります。定期通販は有形のモノを取り扱っていますが、サブスクリプションは無形のサービスも含まれます。
サブスクリプションの例を挙げると、下記のとおりです。
- Netflix:動画配信
- Kindle Unlimited:電子書籍
ただし、サブスクリプションは「定額サービス」の意味合いが強くなっているため、有形商材のことも指すようになりました。
下記の記事でサブスクリプションのメリットや事例を紹介しているので、サブスクリプションも把握したい方はぜひご一読ください。
関連記事:サブスクリプションとは?仕組みや市場規模、業界別事例や特色などを徹底解説
定期通販を導入するメリット4つ

定期通販を導入するメリットは、下記のとおりです。
- 長期的な契約のため利益が安定しやすい
- 小規模スタートが可能
- 在庫管理がしやすく、ムダを省ける
- 価格競争を回避できる
定期通販は一定サイクルで顧客と接触するため、顧客の意見を得やすいです。順番に見ていきましょう。
また、その他の注意点などを抑えて、定期通販で成功する全ての要件を以下の資料で解説しています。もし、定期通販のスタートを考えている方は、この機会にぜひお読みになってはいかがでしょうか。
【メリット1】長期的な契約のため利益が安定しやすい
定期通販は継続的な利用を前提としたサービスなので、顧客一人ひとりとの関係が長期にわたります。継続的な売上が発生するため、利益が安定しやすいのです。
通常の販売モデルでは、新規顧客を常に開拓したり既存顧客を維持したりする必要があり、労力と費用がかかります。一方で、定期通販は新規顧客がそのままリピーターになるため、顧客の維持にかかるコストは最小限です。
したがって、商品開発やサービス改善にリソースを使えます。
【メリット2】小規模スタートが可能
定期通販は、初期投資が比較的少なくても始められるビジネスモデルです。
一般的なEC事業では、多くの商品を用意して、その商品ごとでページを作成したりなど、管理コストが大きく発生するのですが、定期通販では少量の在庫や限られた顧客数でスタートし、徐々に規模を拡大していくことができます。
特に消耗品や日用品など、定期的に需要がある商品を扱うことで、安定した売上を見込むことができます
また、受注が安定しているため、生産計画や仕入れ計画が立てやすく、無駄なコストの発生を防ぐことができるため小規模スタートが可能です。
【メリット3】在庫管理がしやすく、ムダを省ける
在庫管理がしやすいことも、定期通販事業の特徴です。通常の販売モデルはいつ購入されるかわからないため、欠品を防ぐためには多めに在庫を持つ必要があります。
しかし、在庫過多は売れ残りのリスクや管理コストが必要です。一方で、定期通販は販売予測が立てやすく、適切な在庫数を維持できます。
たとえば、毎月1つ商品を届ける定期通販の場合、顧客が1人なら年間で12個用意しておけば大丈夫です。顧客が2人なら24個、10人なら120個と在庫の必要数が簡単に判断できます。したがって、在庫を持ちすぎるムダを省くことが可能です。
【メリット4】価格競争を回避できる
定期通販事業では、商品そのものだけでなく、便利さや継続的な価値提供、パーソナライズされた体験など、独自の付加価値を提供することで価格競争から脱却できます。
例えば、定期宅配サービスを実施する際、単に食材を届けるだけでなく、季節に応じたレシピの提案や生産者との繋がりを感じられるストーリー性を提供することで、スーパーマーケットとの単純な価格比較を避けることができます。
また、顧客の継続利用に応じた特典やキャンペーン配布など、長期的な関係構築を重視することで、顧客満足度を高め、価格よりも価値を重視する顧客層を獲得することができます。
これにより、価格競争を回避しながら持続可能な利益率の確保が可能になります。
定期通販のデメリット2つ

定期通販のデメリットは、下記のとおりです。
- 新規顧客獲得に時間がかかる
- 解約が増えると利益が大きく落ちる恐れがある
定期通販は顧客がつけば安定しますが、新規顧客獲得が大変なビジネスモデルでもあります。ひとつずつ見ていきましょう。
【デメリット1】新規顧客獲得に時間がかかる
定期通販は、新規顧客獲得に時間がかかる点が難点です。新規顧客を獲得するためには、そもそも認知してもらう必要があります。広告費が潤沢な場合は、Web広告や4マス広告をたくさん打ち出して認知拡大を図れます。
しかし、予算に限りがある場合は、オウンドメディアやSNSなどで地道に認知を拡大しなければなりません。また、定期通販は初期費用を投じてから顧客を集めるため、サービス開始当初は利益が出づらいのです。
そのため、長期的な視点でマーケティング戦略を実行し、少しずつ顧客を集めるのが重要です。
【デメリット2】解約が増えると利益が大きく落ちる恐れがある
定期通販は利用者がいる限り利益が発生し続けますが、解約が増えると利益が大きく落ちる恐れがあります。利用者が1人減るだけでも、長期的には大きな利益減につながります。
また、新規顧客を獲得しづらいビジネスモデルでもあるため、取り戻すのは簡単ではありません。継続的に利用してもらうためには、成功させるためのポイントを押さえておく必要があります。
定期通販を成功させるためのポイント5選

定期通販を成功させるためのポイントは、下記のとおりです。
- 新規顧客を獲得するための施策を決める
- リピートしてもらうための仕組みを構築する
- 休止できるルールを設ける
- 法律やルールを随時確認する
- 定期通販に必要な機能を搭載したシステムを選定する
定期通販は、リピートをしてもらうための、顧客に寄り添った施策や仕組みが重要です。ひとつずつ見ていきましょう。
【ポイント1】新規顧客を獲得するための施策を決める
定期通販は新規顧客の獲得が難しいのですが、施策自体は難しくありません。多くの企業が実施している施策なので、再現性があります。
たとえば、下記のような施策です。
- オウンドメディアの運営
- SNS運用
- 広告出稿
特に、SNS運用は、顧客との関係性を築くためにも重要な施策です。公式アカウントを作成して、お役立ち情報やキャンペーン情報を発信しつつ、顧客とコミュニケーションをとりましょう。
顧客のファン化を促すことができ、定期通販を利用してもらえる可能性が高まります。
定期通販における効果的なマーケティング戦略や集客方法について以下の資料で解説しております。
特に集客について悩んでいる方必見の資料となっているので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
【ポイント2】リピートしてもらうための仕組みを構築する
定期通販を成功させるためには、リピート購入をしてもらうための仕組み構築が重要です。施策や仕組みもなく、ただ商品を届けるだけでは顧客に飽きられてしまいます。
たとえば、下記の施策はよく見かけます。
- 定期縛りを設けて低価格で販売
- 新商品のサンプルやクーポンを配布
「2ヵ月は解約できない」といった縛りを設定して低価格で販売すると、顧客の心理ハードルが下がって、購入に至るケースがあります。商品そのものに魅力があれば、そのまま継続利用してもらえる可能性が高いです。
【ポイント3】休止できるルールを設ける
定期通販を成功させるためには、休止できるルールを設けることも重要です。定期的に欲しいものであっても、一時的に不要になる場合も考えられます。
その際に、解約ではなく休止できるルールを設けることで「解約したくないけど今は不要」という顧客の取りこぼしを防げます。また、下記の記事で解約理由と対策を解説しているので、ぜひご一読ください。
関連記事:【通販サイト運営】定期購入の解約理由って?解約されないポイント
【ポイント4】法律やルールを随時確認する
定期通販を運営する際には、関連する法律や規制を常に確認し、遵守することが重要です。特に、消費者保護を目的とした法律が頻繁に改正されるため、最新の情報を把握する必要があります。
例えば、改正特定商取引法では、消費者が誤認しやすい表示を禁止し、契約内容を明確に表示することが義務付けられています。これには、商品の数量、販売価格、支払い方法、引渡し時期、解約条件などが含まれているため定期通販事業者は確認する必要があります。
また、消費者契約法も改正され、消費者が不利な条件で契約を結ばないようにするための規定が強化されています。
これらの法律を遵守することで、消費者との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐことができます。
【ポイント5】定期通販に必要な機能を搭載したシステム選定をする
定期通販の成功には、適切なシステム基盤の選定が不可欠です。
定期通販に必要な機能の代表例は以下になります。
- 会員ランク管理機能:購入頻度や金額に応じて顧客をランク分けし、特典やサービスを提供する機能です。顧客のロイヤリティを高めることができます
- 定期購入の履歴管理機能:顧客が過去の定期購入履歴を確認できる機能です。透明性を高め、信頼関係を築くことができます
- アップセル・クロスセル機能:定期購入中の顧客に対して、関連商品や上位商品を提案する機能です。これにより、顧客単価を向上させることができます
- サンプル提供機能:新商品や関連商品のサンプルを定期購入と一緒に提供する機能です。顧客に新しい商品を試してもらうことで、追加購入を促進します
- 定期サイクルの変更機能:顧客が自身のペースに合わせて配送サイクルを変更できる機能です。例えば、毎月から隔月に変更するなど、柔軟に対応できます
- キャンペーン・クーポン機能:定期購入者向けの特別キャンペーンやクーポンを発行する機能です。リピート率を高めることができます
特に重要なのは柔軟な周期設定機能で、顧客ごとに異なる配送間隔や商品の組み合わせをカスタマイズできることが求められます。
また、休止・スキップ・解約処理を顧客自身が簡単に行えるセルフサービス機能も不可欠です。
システム選定時には、将来の事業拡大に対応できる拡張性や、他の業務システムとの連携のしやすさも考慮すべきポイントです。コスト面だけでなく、サポート体制や定期的なアップデートの提供状況も確認し、長期的な運用視点で選択することが重要です。
下記の資料では、10のECカートシステムを費用面・機能面・サポート面から比較しています。
この比較表を活用することで、短時間で検討が可能となり、最適なECカートを選択いただけます。ぜひ資料をご覧になってはいかがでしょうか。
定期通販におすすめなECカートシステム「W2 Repeat」
もし定期通販事業の立案を考えている方は、W2 Repeatを利用してスタートさせるのがおすすめです。

公式URL:https://www.w2solution.co.jp/w2_repeat/
導入企業:ロゼット株式会社 / 天藤製薬株式会社 / 株式会社サザコーヒー
W2 Repeatは、サブスク/定期通販特化型のECカートシステムで、健康食品・化粧品・美容品・サプリメント・食品関連といった定期商材の販売に適しています。
特徴としては以下の4つです。
- 定期通販に特化した1,000以上の豊富な標準機能を搭載
- 煩雑化しやすい受発注業務を自動で行うことが可能なシステム基盤
- ノーコード対応のためサイトやLP制作が自由自在に可能
- SaaS型のため低コストで運用開始が可能
また、新規顧客向けのフォーム一体型ランディングページ作成やLINEでの集客、既存顧客向けにステップメールやクロスセル・アップセル訴求も可能です。
料金は事業規模に応じて3つのプランが用意されており、スタートアップから年商100億円を超える大規模事業まで幅広く対応しています。
W2 Repeatのより詳しい内容は、下記よりご確認ください。
また、比較検討材料として、より詳しく定期通販特化型のECカートシステムをお探しの方は、以下の記事で解説しているので、この機会にぜひご覧になってはいかがでしょうか。
定期通販の成功事例
定期通販事業を始める際は、他社の成功事例を学んでおくとよいでしょう。
以下から、定期通販事業で成功した事例を2選ご紹介します。
ゆめじん有限会社
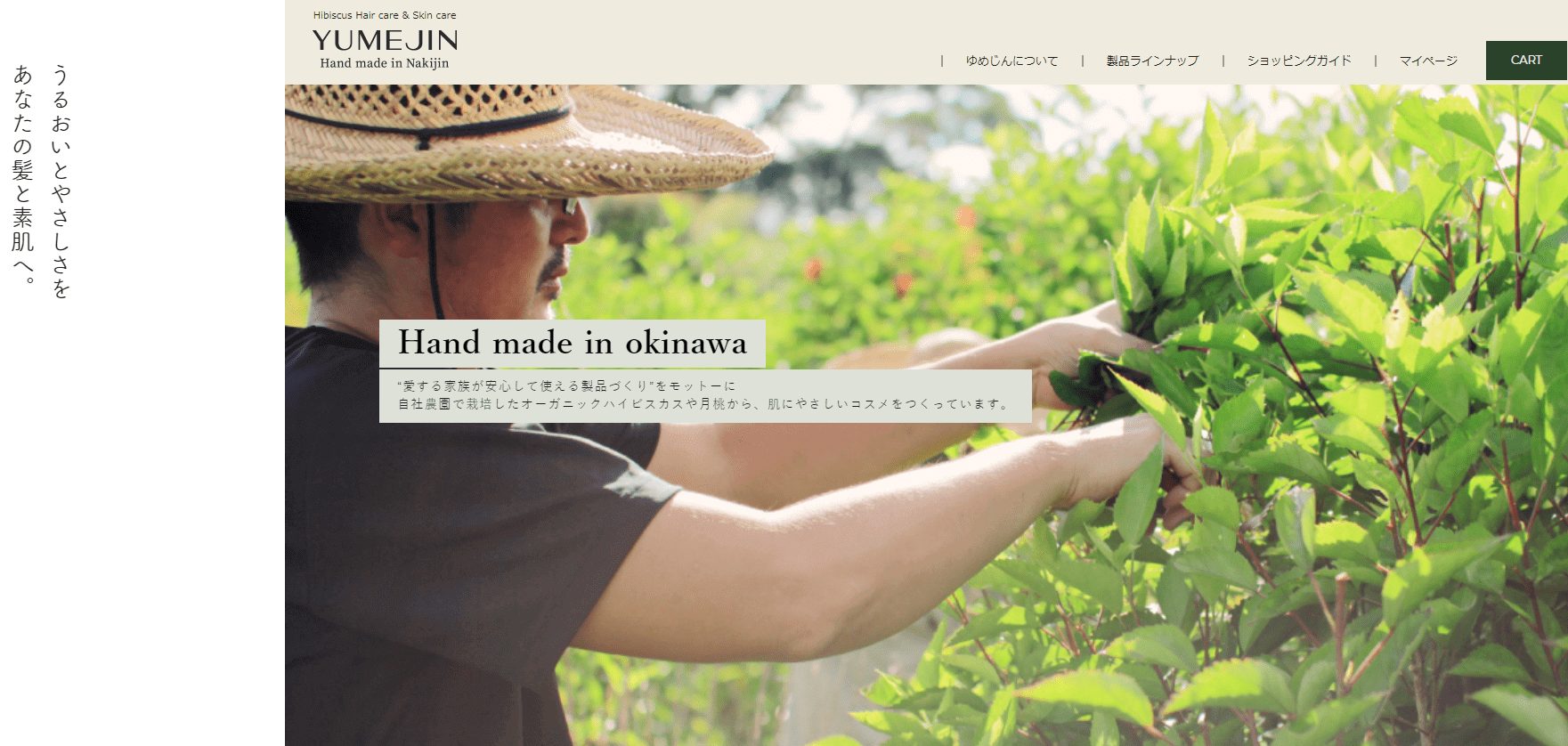
画像元URL:https://www.yumejin.jp/
ハイビスカスの葉や花から抽出した「ハイビスカス葉エキス」をヘアケア・スキンケア商品として提供している「ゆめじん」は、定期ECサイト「YUMEJIN」で売上140%以上向上させた実績があります。
売上向上した要因として、スマートフォン専用ページの入力フォームの設置した結果、スマートフォンからの離脱率が改善したことが挙げられます。
また、購入回数や店舗に来店した方、誕生日月などでさまざまな条件を掛け合わせてお客様を細かくセグメントしてクーポン施策を行った結果、購入者数の約500名以上の方が10回以上購入しているという実績もございます。
さらに、メインの商品とサブの商品をセットにしたキャンペーンを実施し、LTVやF2転換率も伸ばして売上向上を実現しています。
梅乃宿酒造株式会社
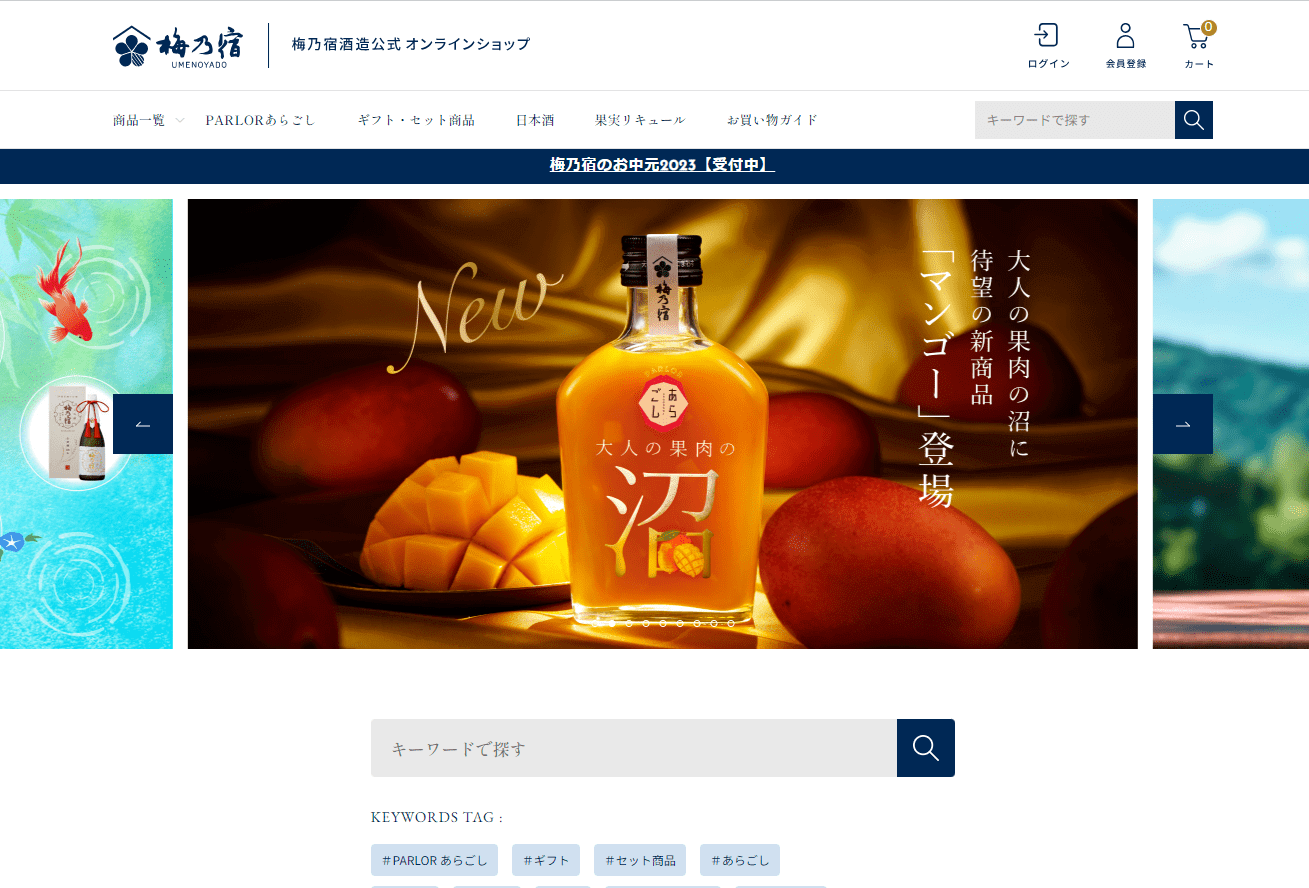
画像元URL:https://shop.umenoyado.com/
お酒の開発から製造、販売を行っている梅乃宿酒造株式会社は高精度なセグメント機能を活用したCRM施策を行った結果、半年で売上が10倍になっています。
具体的には、顧客の行動や購買データをもとに、顧客情報を活用したプロモーションを実施や商品購入後のフォローメルマガを数回に分けて配信した結果、リピート率が急激に伸びています。
また、商品レビューを記載して頂いたお客様の中から、抽選で30名様にクーポンを配布する施策を行った結果、商品レビュー数を短期間に100件以上集めることに成功しています。
この経験をもとに、レビュー数の少ない商品はクーポンを配布することでレビュー数を増やし購入率を高めています。
現在では、人気商品の再販をした際は、開始1時間以内で完売となることもあり、定期通販事業で成功しているといえるでしょう。

W2 Repeatは、定期購入やサブスクリプションコマースに特化したECプラットフォームです。20年以上にわたり培ってきた大規模EC基盤をパッケージ化しており、スクラッチ開発に匹敵する多機能性・拡張性を備えています。商材数が少ない事業者でも運用しやすく、CRM施策を通じてF2転換率やLTVの最大化します。
また、定期通販に必要な業務を自動化し、継続課金やサブスクリプション型ビジネスの基盤としても柔軟に活用できます。
定期通販を始める際によくある4つの質問

定期通販を始める際に、よくある質問を紹介します。
- 定期通販の仕組みはどうやって構築すべき?
- 定期通販の発送代行は可能?
- 定期通販の解約率を下げるにはどうすべき?
- 定期通販以外にLTVを上げる施策や考え方は?
定期通販を始める前に、疑問を解消しておきましょう。
【質問1】定期通販の仕組みはどうやって構築すべき?
定期通販の仕組みを構築する際は、定期通販型のECサイトの構築や運営に特化したカートシステムを活用しましょう。汎用型のカートシステムより、特化型のカートシステムを導入したほうが高い効果を見込めます。
【質問2】定期通販の発送代行は可能?
定期通販の発送代行は可能です。発送業務は売上に直結しないノンコア業務ですが、在庫管理や梱包、発送など多くの業務が存在します。
発送代行に依頼することで、自社の従業員はマーケティングやサービス改善にリソースを集中できます。
【質問3】定期通販の解約率を下げるにはどうすべき?
定期通販の解約率を下げるためには、下記のポイントが重要です。
- 商品のメリットをあらためて説明する
- リピート購入してもらうための仕組みを作る
- 休止できるルールを設ける
重要なのが、商品のメリットをあらためて説明することです。購入当初は覚えている商品情報も、期間があけば使用していても忘れてしまいます。
あらためて説明することで、商品の良さを思い出してもらいましょう。
【質問4】定期通販以外にLTVを上げる施策や考え方は?
定期通販以外にLTVを上げるためには、クロスセル・アップセルが考えられます。つまり、購入してもらった商品の関連品や、より上位商品の購入を促します。
まとめ:定期通販ビジネスを展開して安定した利益を目指す

定期通販とは、定額で商品が届けられるサービスです。一定のサイクルで届けられるため、日用品などの生活必需品と相性が優れています。
利益が安定したり顧客満足度向上につながったりするため、有形の商材を取り扱っている場合はぜひ検討してみてください。
W2 Repeatは豊富な機能で、定期通販をサポートします。売上を上げる機能を網羅しているため、W2 Repeatの詳細を知りたい場合は下記よりご確認ください!

W2 Repeatは、定期購入やサブスクリプションコマースに特化したECプラットフォームです。20年以上にわたり培ってきた大規模EC基盤をパッケージ化しており、スクラッチ開発に匹敵する多機能性・拡張性を備えています。商材数が少ない事業者でも運用しやすく、CRM施策を通じてF2転換率やLTVの最大化します。
また、定期通販に必要な業務を自動化し、継続課金やサブスクリプション型ビジネスの基盤としても柔軟に活用できます。