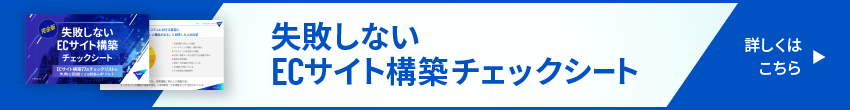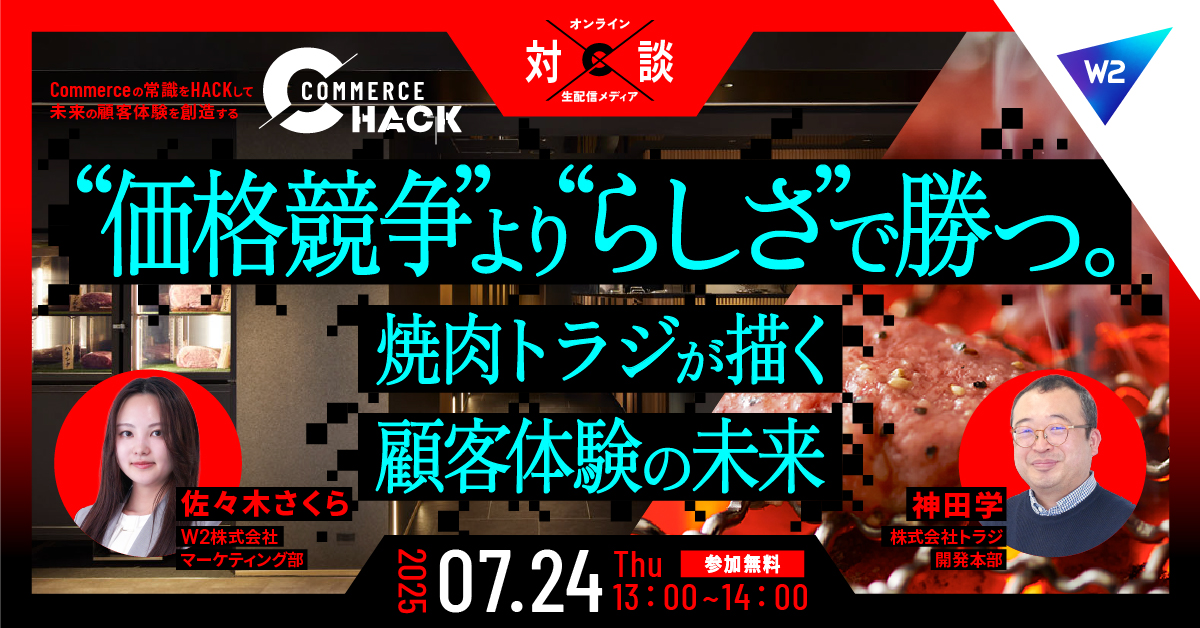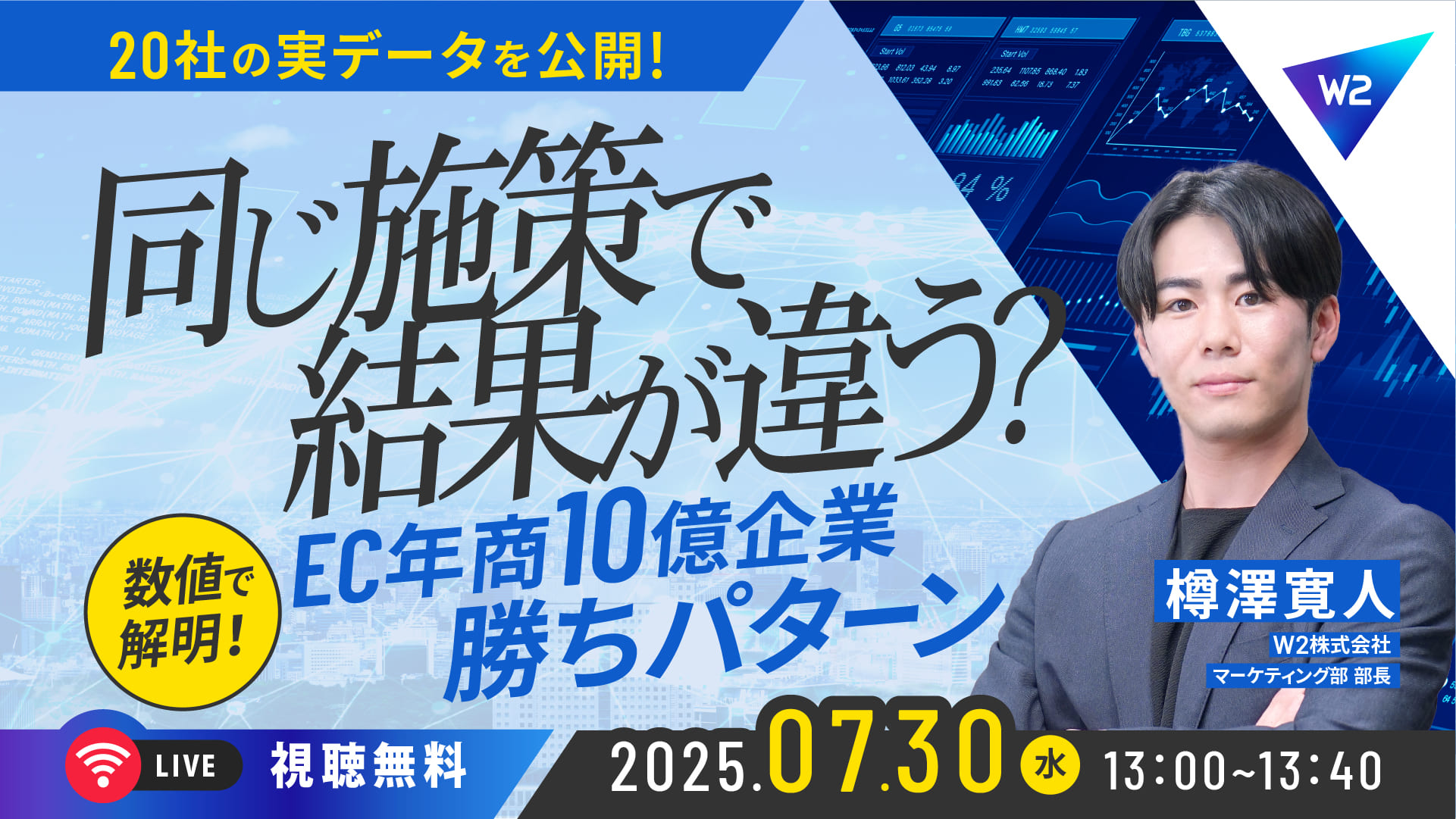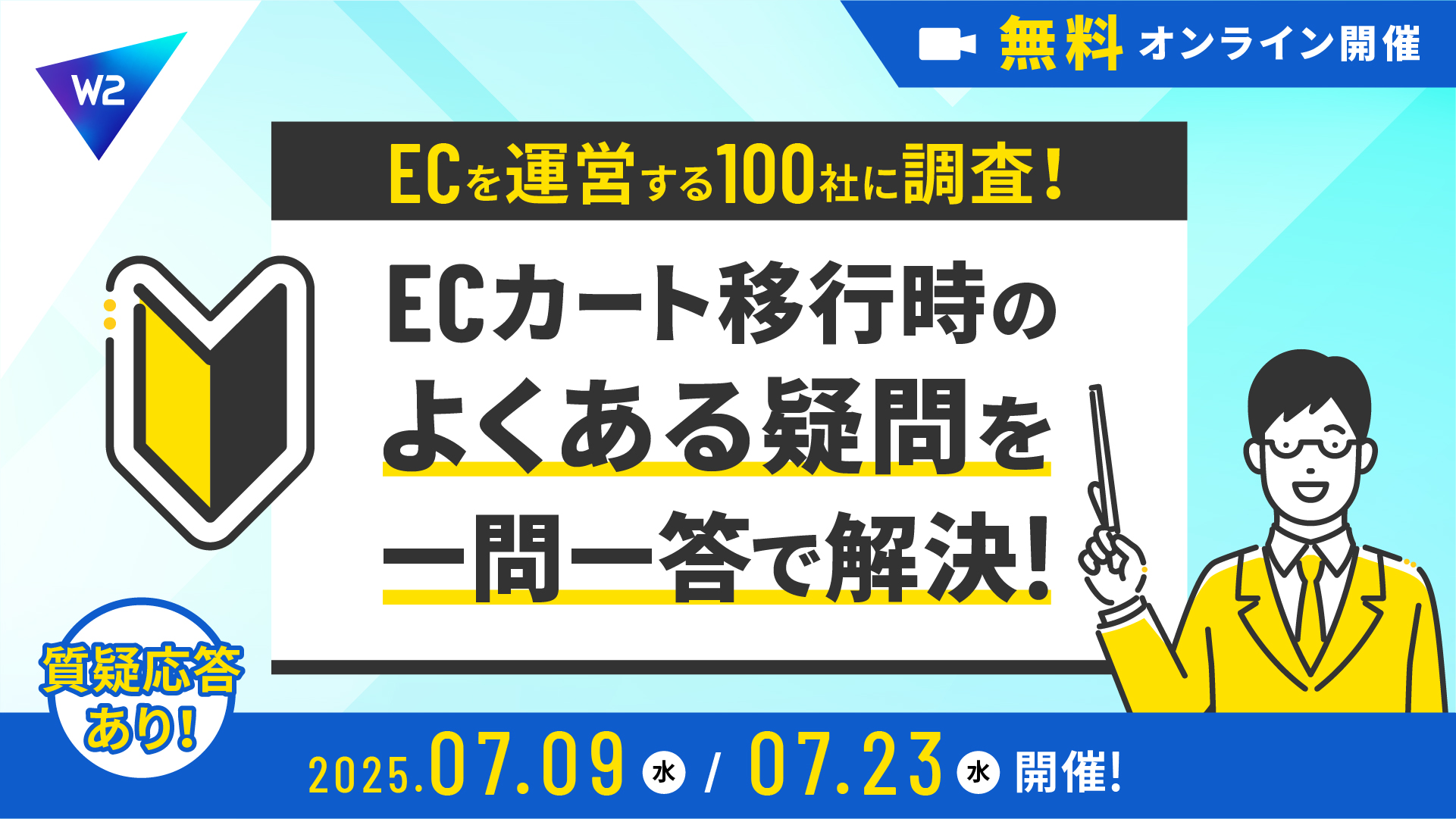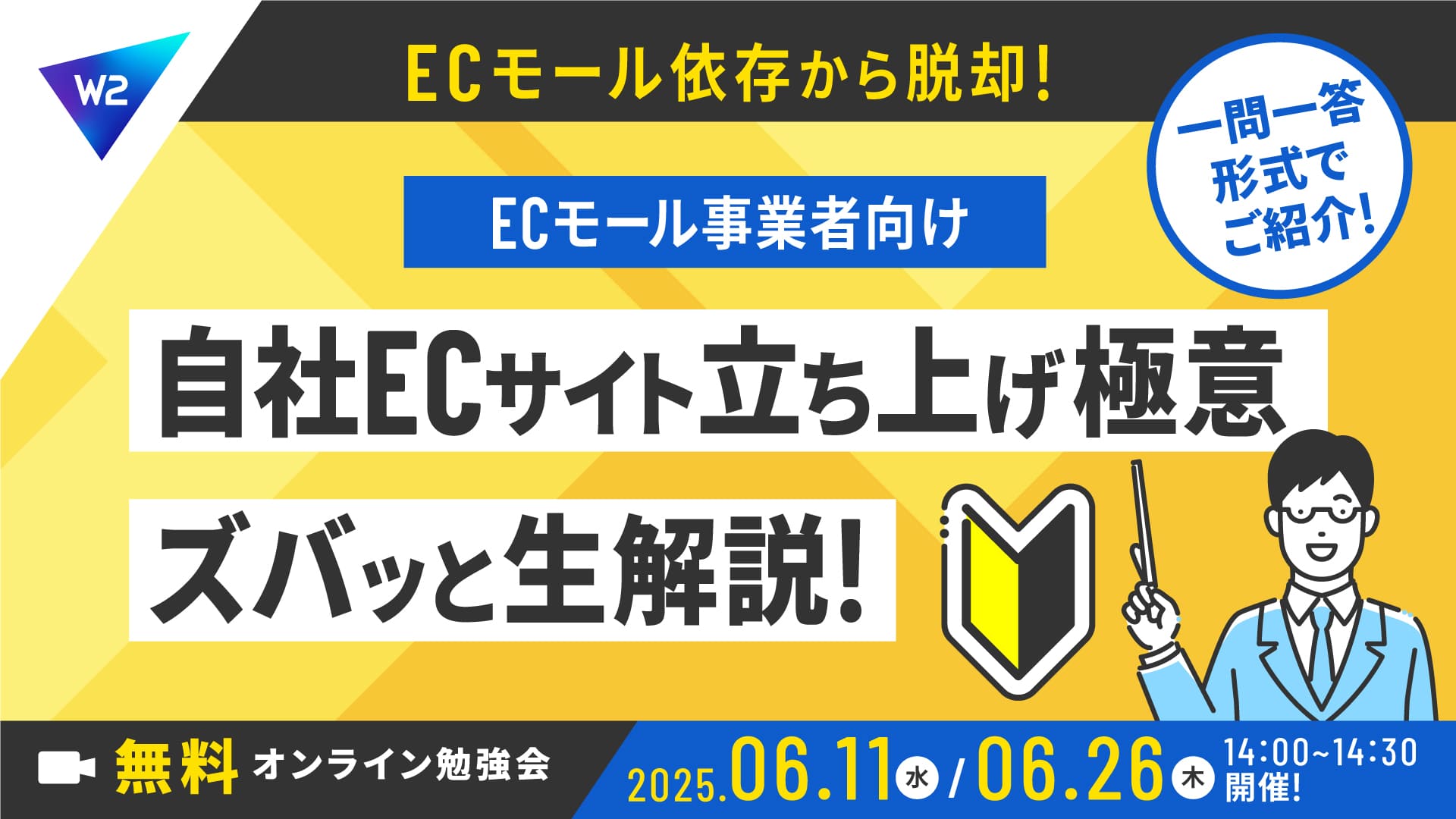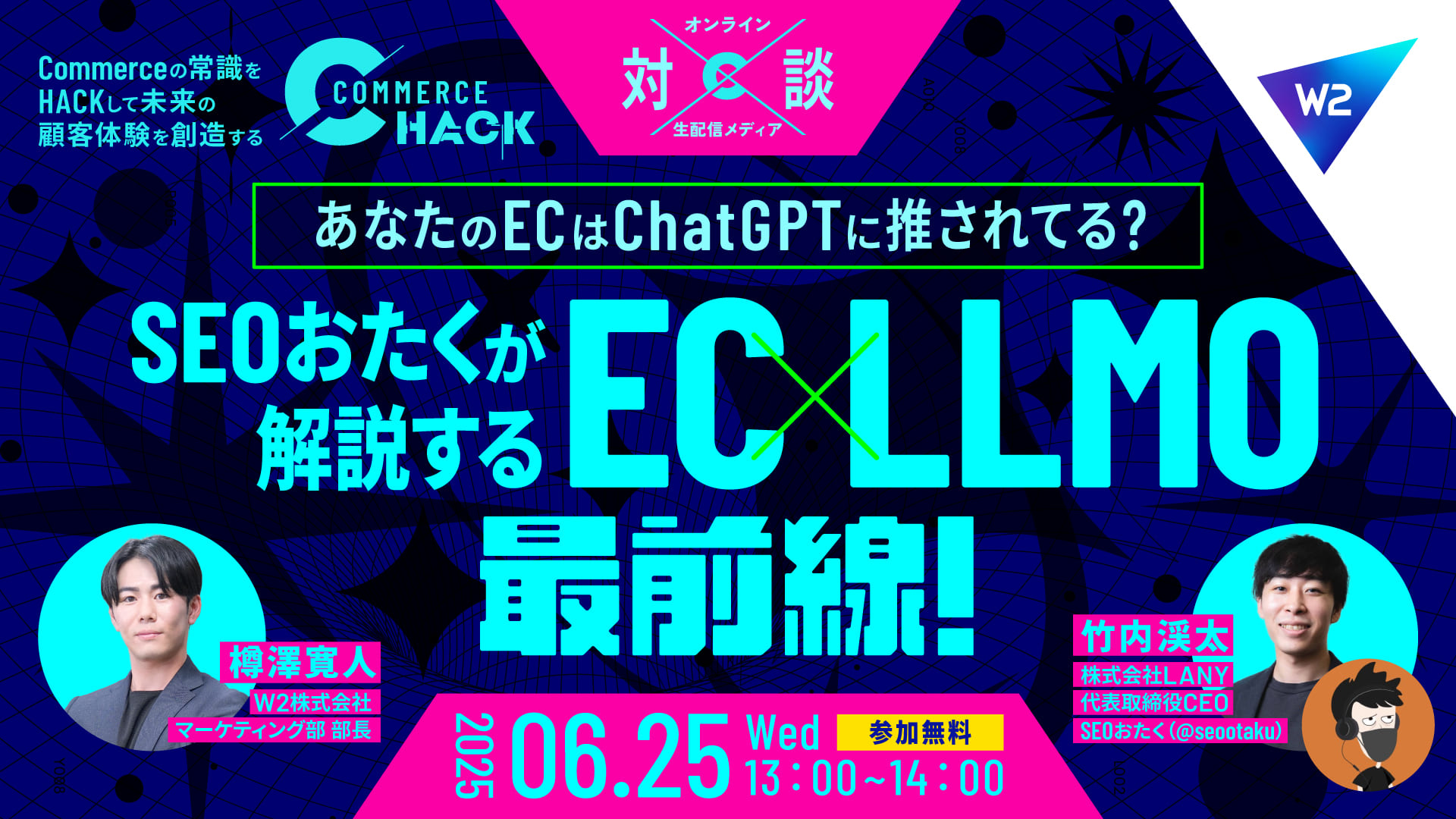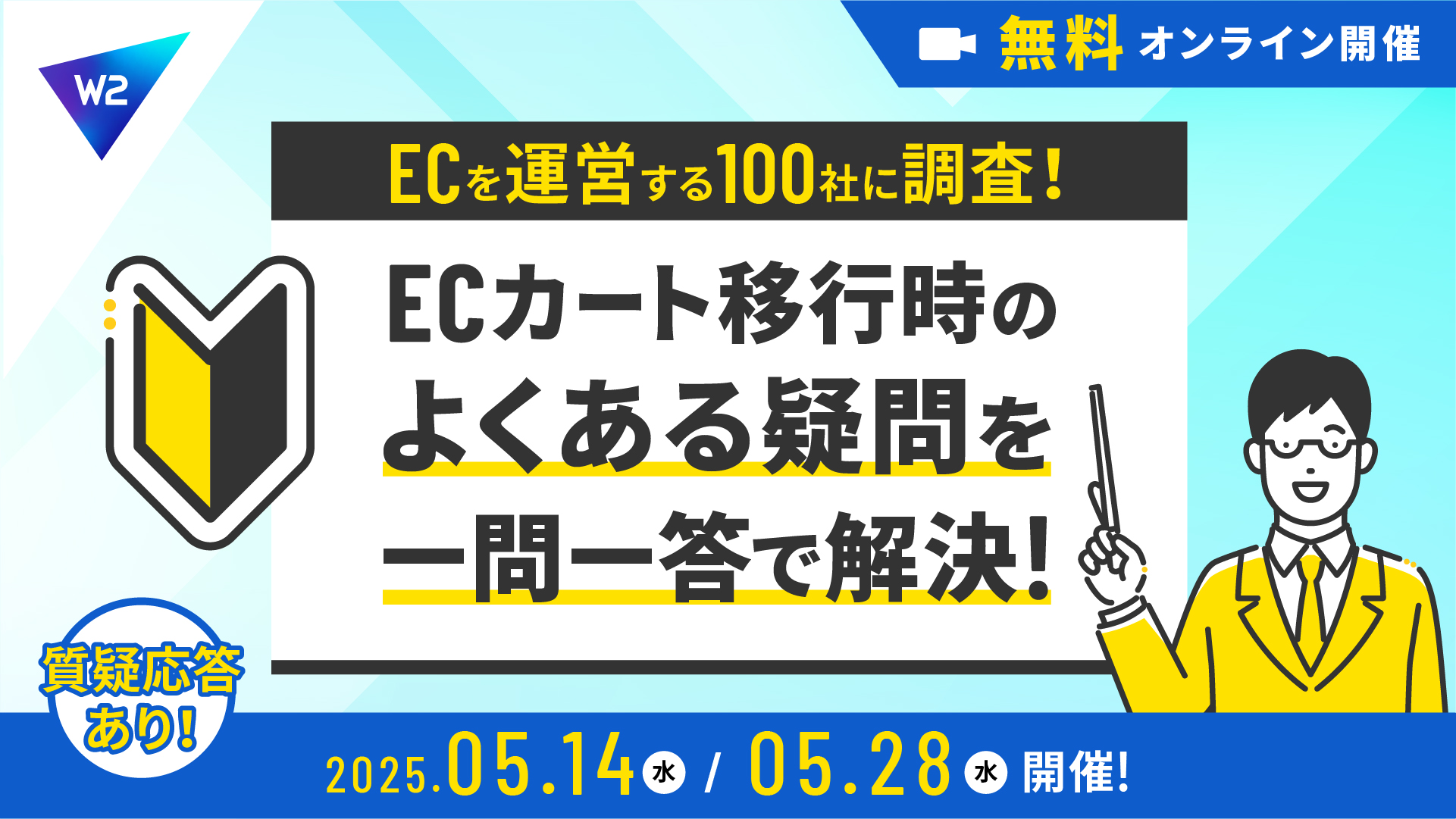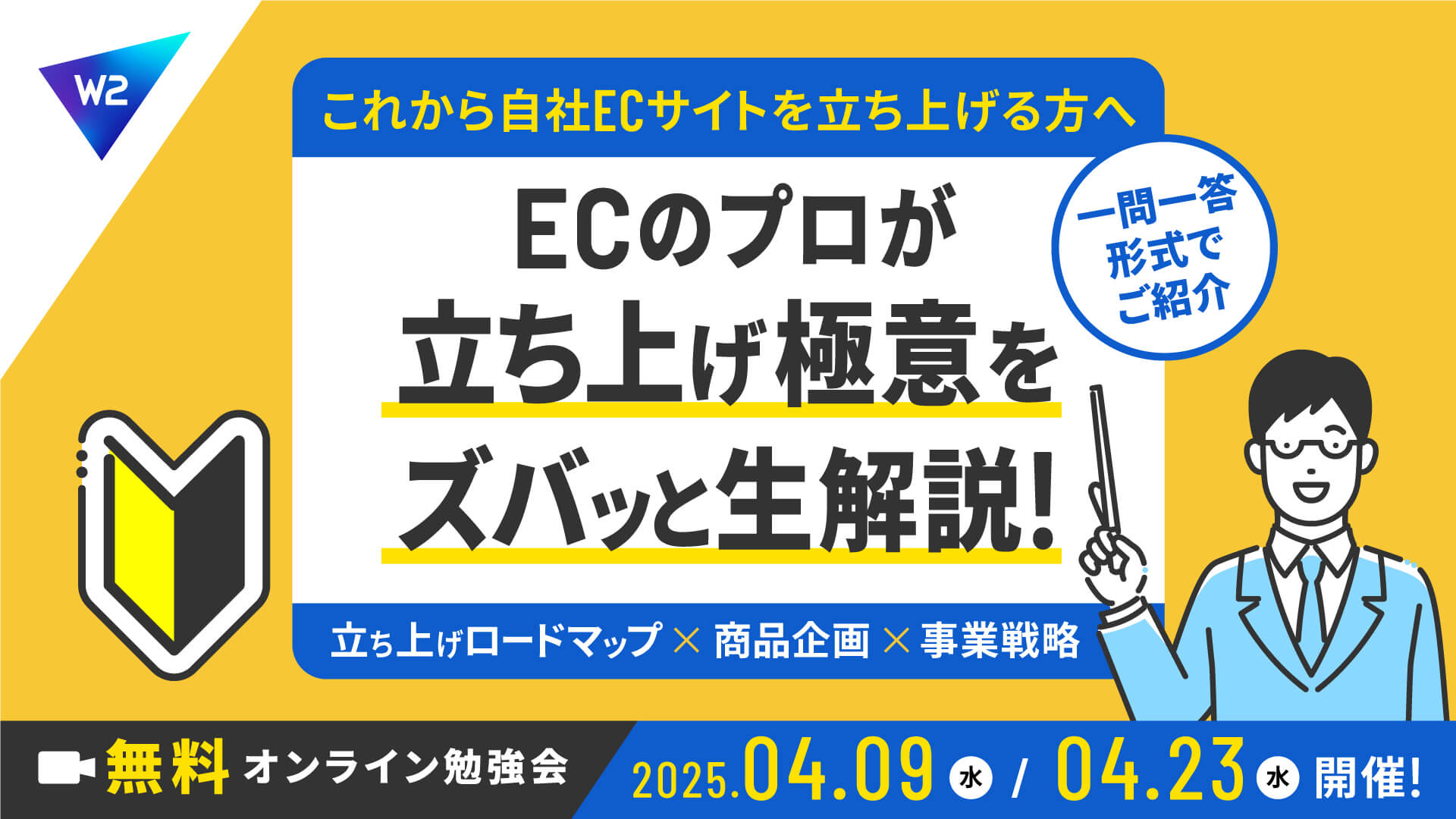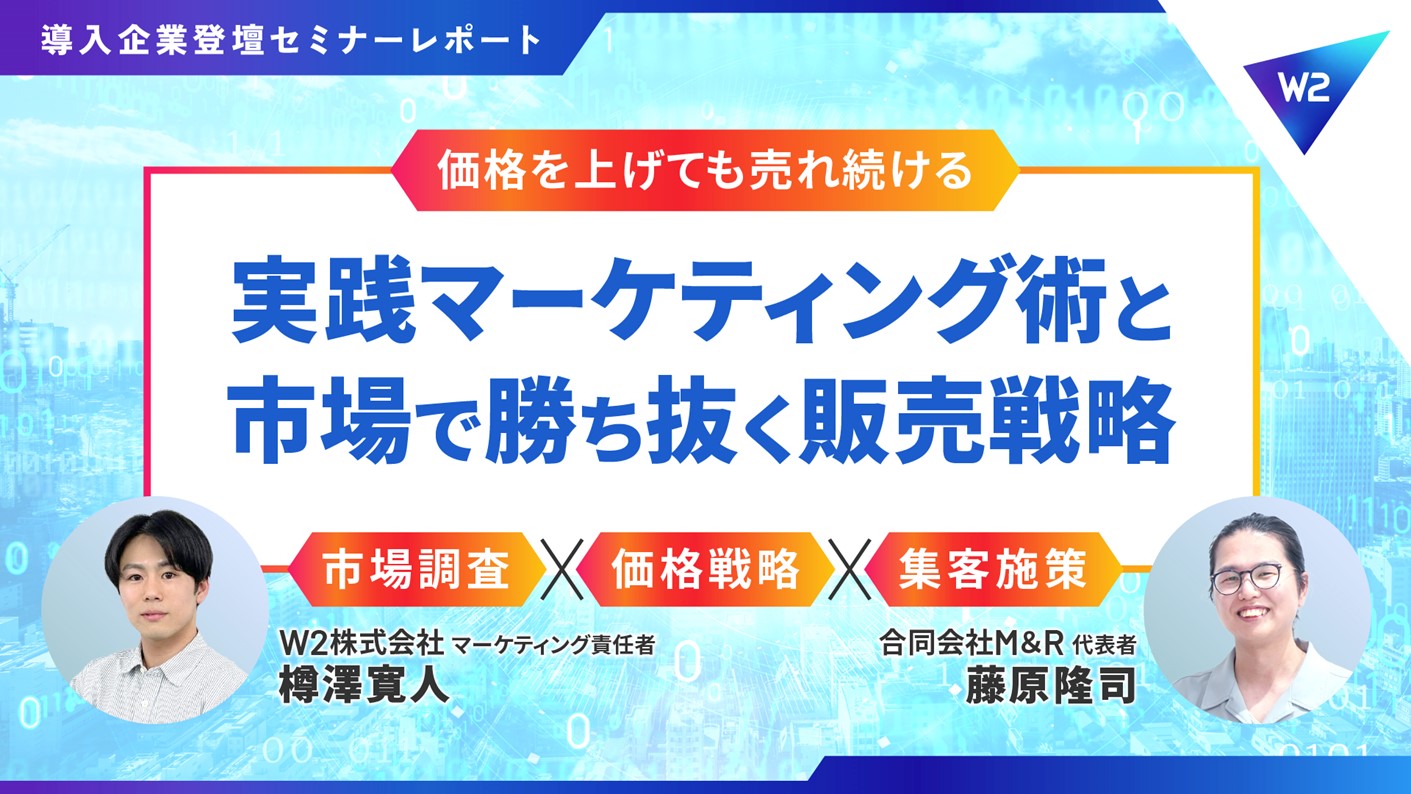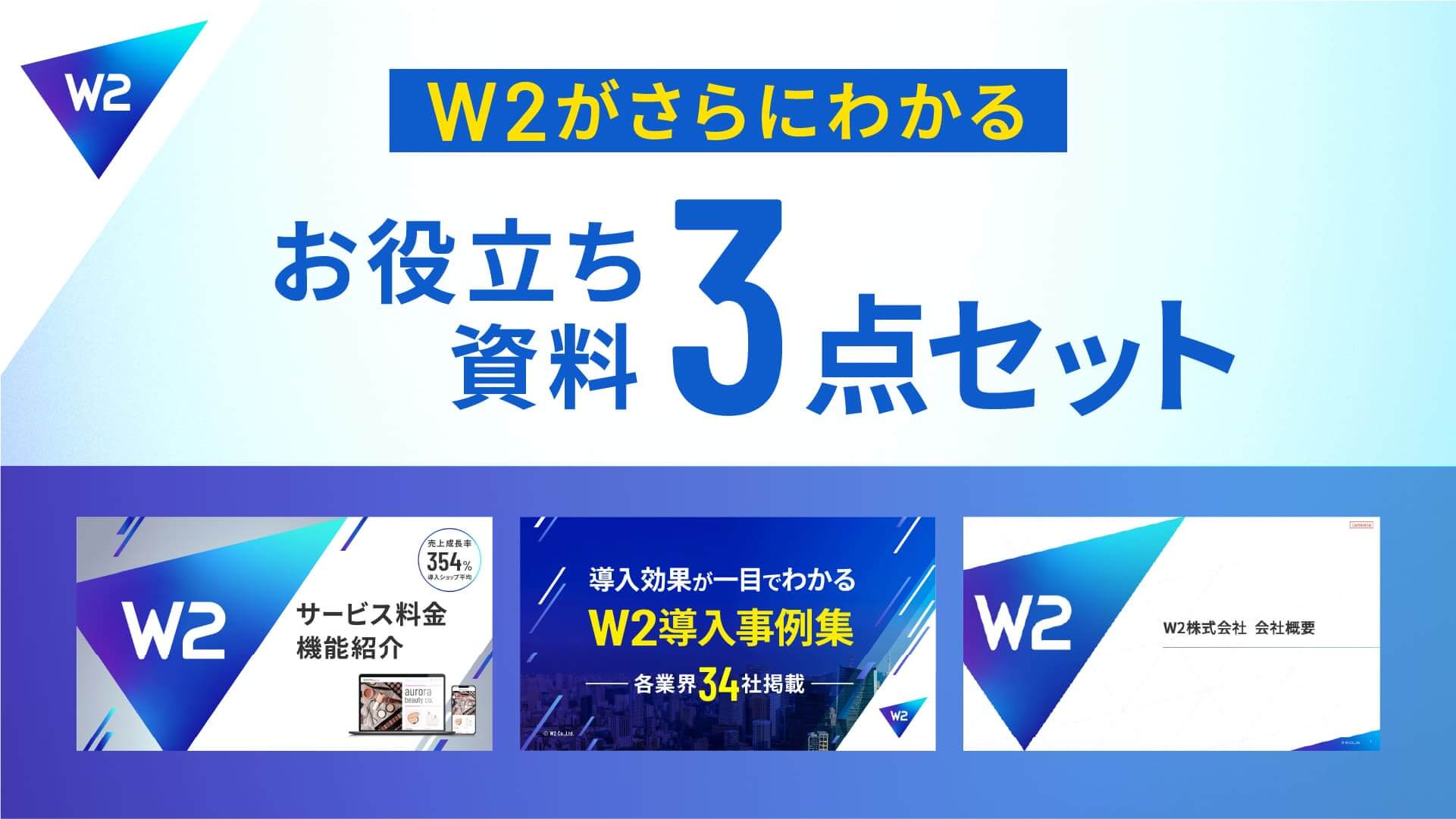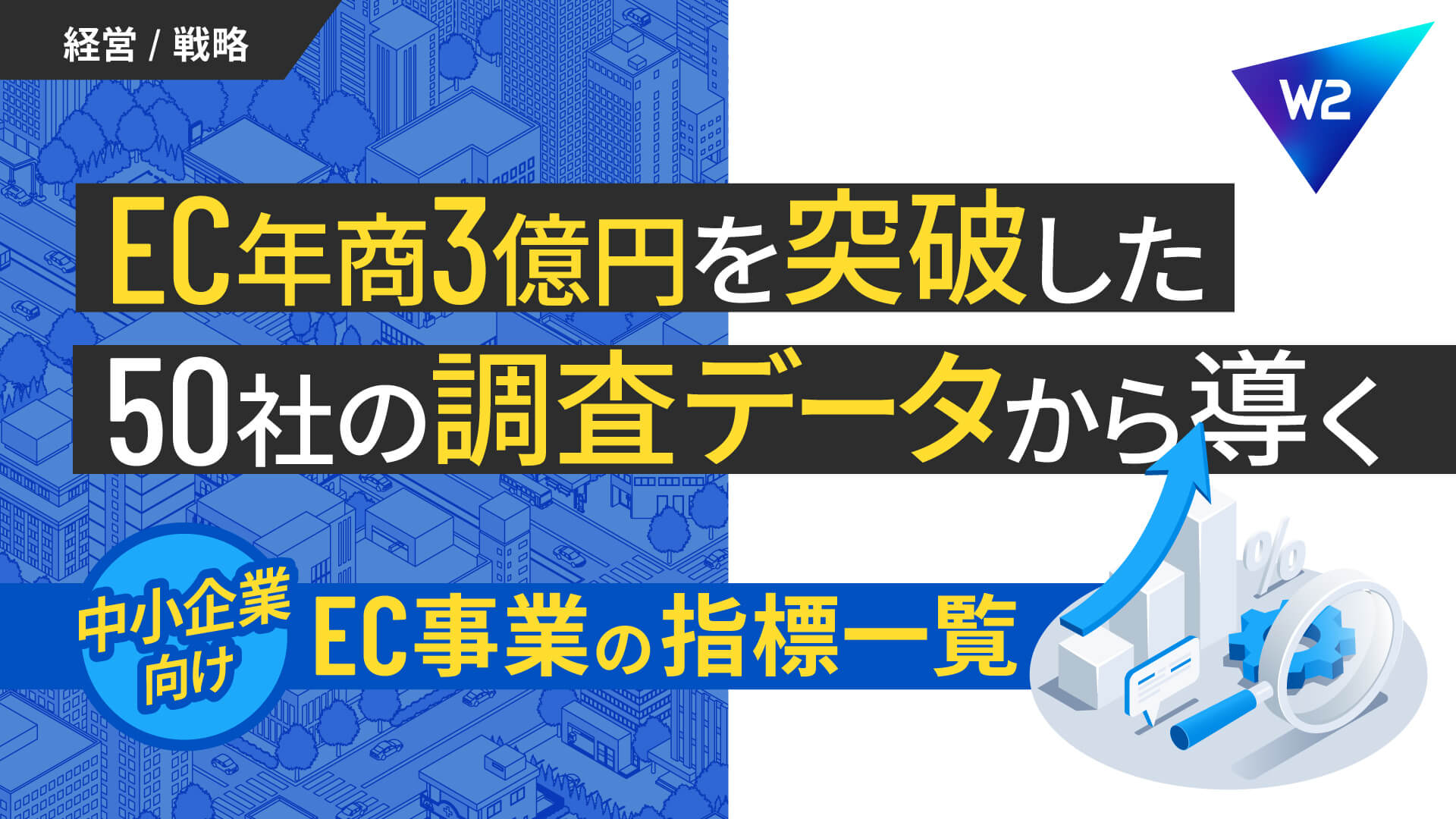【2025年最新版】ライブコマースとは?メリット・デメリットや相性がいい商材、成功事例などを徹底解説


【2025年最新版】ライブコマースとは?メリット・デメリットや相性がいい商材、成功事例などを徹底解説
ライブコマースとは、ライブ配信とオンライン販売(Eコマース)を組み合わせた新しい販売形態で、視聴者がライブ動画を見ながらリアルタイムで商品を購入できる新しい通販手法です。
イメージとしてはテレビショッピングに近いですが、大きな違いは、視聴者が配信中に質問を投げかけることができる点にあります。このインタラクティブな要素により、多くの企業がライブコマースを積極的に取り入れています。
このライブコマースをいち早く取り入れたのは、KOL(Key Opinion Leader:影響力のあるインフルエンサー)を活用したマーケティングが盛んな中国です。中国では、インフルエンサーマーケティングと動画配信が融合し、ライブコマースへと発展していきました。
ライブコマースが発展した背景には、文化的に偽物の流通が多く、「信頼できる人から購入したい」という消費者心理があります。また、コロナ禍をきっかけにオンライン販売市場が急成長し、今後もさらなる市場拡大が見込まれていることも理由の一つです。
本記事では、今後ますます注目される「ライブコマース」とはどのようなものかをわかりやすく解説します。また、導入を検討している方に役立つ事例もご紹介します。
ライブコマースの基礎知識について

新型コロナウイルスの流行に伴う「巣ごもり需要」の拡大を受け、ライブコマースを利用して買い物をする消費者は、ここ数年で飛躍的に増加しました。
日本のみならず、世界的にもライブコマースは主要なマーケティング手法の一つとして大きな注目を集めています。特に、中国ではライブコマースをいち早く取り入れた結果、たった1時間で数億円の売上を達成するインフルエンサー(KOL:Key Opinion Leader)が登場するなど、その勢いはとどまるところを知りません。
中国の市場規模について
中国の市場規模大手会計事務所である「KPMG」が2021年に発表したレポート(※)によると、2021年時点での中国におけるライブコマース市場は1兆9,950億元(約33兆9,150億円、1元=約17円)で、2020年に比べ、90%増の成長を記録しました。
※参照元:jetro
中国商務部の発表によると、2020年のライブコマースイベントの開催回数は計2,400万回、視聴回数は500億回、販売商品は2,000万アイテムを超えたとしています。
また、中国でのライブコマース利用者の数は「第47回中国インターネット発展状況統計報告」で発表されており、2020年末時点で3億8,800万人となっています。
日本国内の市場規模
MMD研究所が全国の18~59歳の男女5000人を対象におこなった調査(※)によると、2021年時点で「ライブコマース」という言葉自体の認知度は、視聴経験があると回答した人から「言葉は聞いたことがあるが、利用方法や内容はよく知らない」と回答した人まで、合計で43.2%の結果となりました。
また、ライブコマースの配信コンテンツを見たことがある人の数もまだ少なく12.7%。さらにその中で商品の購入に至った人は5.8%でした。
※参照元:MMD研究所
ライブコマースは中国で人気がある販売方法
中国国内でいち早くライブコマースを成功させたのは、主要ECサイトの一つである「タオバオ」でした。タオバオは2018年にライブコマースで1.5兆円もの流通を生み出すことに成功、その翌年2019年には前年度の2倍である約3兆円の売り上げを記録しました。
それから多くのECサイトや動画プラットフォームがこぞってライブコマースを導入、中国全体でのライブコマースの市場規模は急激に拡大し、2020年に約17兆円(前年より111%上昇)、2021年には33.9兆円の予測と報告されています。
ライブコマースと相性がいい業界

この章ではライブコマースと相性がいい業界をご紹介していきます。
ライブコマースと相性がいい業界は、以下の3つです。
- アパレル業界
- 食品業界
- 化粧品業界
それぞれ詳しく説明していきます。
アパレル業界
アパレル業界は、言うまでもなくライブコマースと非常に相性の良い分野です。実際、他業界と比較しても、ライブコマースの実施件数が最も多い業界の一つとなっています。
ECサイトではサイズ表が記載されているものの、実際に試着してみないと着心地やサイズ感がわからず、商品が届いてから「思っていたのと違った」と感じた経験を持つ人も少なくありません。
そこで、ライブコマースでは、さまざまな身長や体型のモデルを用意し、実際に試着してもらうことで、視聴者に着心地やサイズ感を具体的に伝えることができます。これにより、購入後の失敗への不安を軽減し、購買意欲を高める効果が期待できます。
このような理由から、アパレル業界はライブコマースとの親和性が非常に高いといえるのです。
食品業界
食品業界は鮮度が重要なため、これまでECサイトでの販売はあまり普及していませんでした。しかし、現在、EC市場はさらに拡大しており、今後は食品もオンラインで購入する機会が増えていくと予想されています。
ライブ配信では、実際に食べながらのレビュー(食レポ)や、レシピ・食べ合わせの提案などを通じて、文字や画像だけでは伝えきれない情報を補足することができます。
テレビショッピングのようなスタイルに加え、視聴者との双方向コミュニケーションを取り入れることで、さまざまなトレンドや商品の魅力をリアルタイムに伝えることができます。
その結果、ECサイト以上の臨場感が生まれ、視聴者の満足度も高まりやすくなるため、食品業界とライブコマースの相性は非常に良いといえるでしょう。
化粧品業界
美容系のライブコマースでは、多くの企業が現役の化粧品販売員を配信者として起用しています。
実際に商品を手に取り、自分の肌で試す様子を見せることで、まるで店頭で接客を受けているかのような感覚を視聴者に与えられるのが、ライブコマースならではの特長です。
化粧品や美容アイテムは肌に直接使用するもののため、実際の使用感がわからないと購入に踏み切れないという人も少なくありません。
その点、ライブ配信では配信者がリアルタイムで使い心地や効果をレポートするため、「自分の肌にも合いそう」と具体的にイメージしやすく、購入の後押しになります。
さらに、視聴者からの悩みや質問にその場で答えられる点も大きなメリットです。店頭で相談する機会が少ない人や、対面での会話が苦手な人にとっても、気軽に情報を得られる手段となります。
オンラインショッピングの需要が高まっている今、ライブコマースは美容業界と非常に高い親和性を持つ販売手法だといえるでしょう。
ライブコマースのメリット5選

この章ではライブコマースのメリットをご紹介します。
ライブコマースのメリットは以下の5つです。
- 写真や文章だけでは伝えにくい商品の魅力を訴求できる
- ライブならではの双方向性
- ライブ動画閲覧から購入までのスムーズな導線ができる
- ライブならではの商品理解ができる
- ライブを見逃してもアーカイブで動画を残せる
それでは詳しく解説していきます。
写真や文章だけでは伝えにくい商品の魅力を訴求できる
実際に商品を使ったときの感覚や感動を、リアルに伝えることができます。
さらに、商品の使い方やサイズ感に加え、アパレル商品であれば素材感や着心地、シルエットなど、写真や文章では伝わりにくい魅力も、まるで利用者のような視点で動画を通じて訴求しやすい点が、大きなメリットです。
ライブならではの双方向性
商品をよく知るスタッフだからこそ伝えられる、現場ならではの情報を顧客に届けることができます。
特に、顧客との距離が近い店頭スタッフの言葉は、企業の公式SNSやWebサイトから発信される情報よりも、よりリアルで信頼性の高いものとして受け取られやすいでしょう。
ライブ動画閲覧から購入までのスムーズな導線ができる
ライブコマースに対応しているアプリやサービスの多くは、視聴中に商品ページへ移動し、そのまま購入画面に進める仕組みを導入しています。
そのため、事前に商品ページのURLを共有しておき、ライブ配信中に「ご購入はこちらのURLからどうぞ」と案内することで、視聴者をスムーズに購入へ誘導することができます。
ライブならではの商品理解ができる
視聴者は、商品の使い方や購入方法など、疑問に思ったことをその場で運営者に質問することができます。一方でECサイトの運営者は、視聴者がどの商品に興味を持ち、どのような点に関心を寄せているのかといったリアルな声を直接知ることができます。
また、配信者が商品の詳細や返品ルールなどについて視聴者の質問に答えることで、買い物に対する不安や疑問をその場で解消できる点も、ライブコマースの大きなメリットです。
ライブを見逃してもアーカイブで動画を残せる
ライブコマースに対応したアプリやサービスの多くには、視聴者がリアルタイムで視聴できない場合でも、アーカイブ(過去の配信記録)として動画を保存・公開できる機能があります。
「ライブを見たいけれど、その時間には参加できない…」といった視聴者の悩みに応えることができるため、購入意欲を損なわずに済むのも大きな利点です。
さらに、アーカイブを残しておくことで、「後でゆっくり見てから購入したい」という視聴者にも対応でき、配信後の購入機会を広げることができます。
ライブコマースのデメリット4選

この章では、ライブコマースのデメリットについて説明していきます。
ライブコマースのデメリットは以下の4つです。
- 集客が難しい
- 配信内容によっては企業のイメージが損なわれる可能性がある
- ライブ配信特有のトラブルが発生する可能性がある
- ある程度配信スキルが求められる
それぞれ詳しく解説していきましょう。
集客が難しい
ライブコマースは、いつでもどこでも視聴できる点が大きなメリットですが、最大の課題は「集客」です。サービスによっては、フォローしているユーザーにしか配信が表示されない場合もあり、フォロワー数によって視聴者数が大きく左右されることも少なくありません。
そのため、ライブ配信の前には、他のSNSや公式サイトなどを活用して事前に告知を行い、集客につなげることが重要です。
さらに、ライブ配信だけに頼るのではなく、アーカイブ動画として保存・活用することで、配信後も継続的に視聴・購入を促すことができます。
配信内容によっては企業のイメージが損なわれる可能性がある
ライブ配信においても、企業ブランディングを反映した内容やセット、世界観を構築することが求められます。
企業のブランドイメージと異なる雰囲気のライブ配信を行ってしまうと、顧客の期待を裏切り、ブランドへの信頼を損なう可能性があります。
例えば、ルイ・ヴィトンがライブコマースに挑戦した際には、その試みに対して肯定的な意見も多く寄せられましたが、一方で、同社のラグジュアリーブランドとしてのイメージとかけ離れた演出に戸惑うユーザーも少なくなかったといいます。
このような事例を踏まえると、ライブコマースを実施する前には、自社のブランドイメージを改めて確認し、その世界観を反映した企画・演出を意識して取り組むことが重要です。
ライブ配信特有のトラブルが発生する可能性がある
ライブコマースはインターネットを利用して行うため、回線状況の悪化によって配信が予定通りに進まなくなったり、コメント欄が荒らされるといった予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
そのため、あらかじめトラブル時の対応マニュアルを用意しておくことや、万が一の事態にも冷静に対応できる配信者を選定しておくことが重要です。事前の準備をしっかり整えることで、配信中のトラブルを最小限に抑えることができます。
ある程度配信スキルが求められる
ライブコマースは一見、ただ配信するだけのように見えますが、視聴者の疑問にその場で対応する必要があるため、高いスキルや専門的な知識が配信者に求められます。
そのため、配信者を選定する際には以下の点を十分に確認することが重要です。
- コミュニケーション能力があるか
- 商品に関する十分な知識を持っているか
- 動画を通じたプレゼンテーションスキルがあるか
- 配信に関する基本的な知識があるか
これらのスキルが備わっていることで、視聴者との信頼関係を築き、スムーズな配信運営と購入促進につながります。
ライブコマースを成功させるポイント

この章ではライブコマースを成功させるポイントをご紹介していきます。
ライブコマースを成功させるポイントは、以下の4つです。
- 視聴者との円滑なコミュニケーションを図る
- 配信者や出演者へのこだわり
- 配信時間や頻度のタイミング
- 商品購入の導線を作る
詳しく見ていきましょう。
視聴者との円滑なコミュニケーションを図る
ライブコマースにおいては、視聴者とのコミュニケーションが重要な要素となります。
ECサイトでは、店舗に行かなくても自宅で簡単に商品を購入できるという大きなメリットがありますが、情報の提供はどうしても事業者からの一方通行になりがちです。
その点、ライブコマースでは視聴者からのコメントにリアルタイムで反応し、疑問や不安をその場で解消できるため、視聴者の購入意欲を高めやすく、売上にもつながりやすくなります。
視聴者の質問に的確に答えるためには、商品知識が豊富な人物を配信者として起用することも、ライブコマース成功の大きなポイントです。
配信者へのこだわり
商品に関する知識が豊富な配信者を起用するだけでなく、企業ブランドに合ったキャラクター性を持つ配信者を選ぶことも重要なポイントです。
配信者の選定においては、単に「時間がある人」や「ライブ配信が好きな人」を選ぶのではなく、視聴者の質問に適切に答えられるスキルや、企業イメージに合致したキャラクターを持っているかどうかを慎重に考慮する必要があります。そうでないと、企業ブランドのイメージダウンにつながる可能性が高まります。
そのため、台本や配信構成に加えて、配信者選びには特に意図を持って行うことが重要です。「商品に対する知識が豊富で、その魅力を上手に伝えられる人」や、「企業のブランドイメージに合ったキャラクターを持つ人」を配信者として選ぶと良いでしょう。
配信時間や頻度のタイミング
配信時間や頻度のタイミングは、視聴者数に大きく影響を与えるため、非常に重要です。
例えば、学生をターゲットにした商品では、朝から夕方にかけて授業や部活動があるため、ライブ配信を視聴するのは難しいことが多いです。
そのため、帰宅時間である17時以降やお昼休みの12時頃など、学生が視聴しやすい時間帯に配信を行うことで、より多くの学生に気軽に視聴してもらえる可能性が高まります。
また、配信時間や曜日、頻度を固定することで、視聴者に習慣的に視聴してもらいやすくなります。「この時間帯にライブ配信がある」と顧客に認識させることができ、一定の視聴者数を確保することが可能になります。
商品購入の導線を作る
ライブコマースの最終的な目的は、「視聴者に商品を購入してもらうこと」です。そのためには、ライブ配信から購入までの流れ(導線)をわかりやすく整えておくことが非常に重要です。
ライブコマースは、商品の魅力を伝えながら、購買意欲が高い顕在層や、購入を検討している層にアプローチできる施策です。だからこそ、視聴者が「欲しい」と感じたタイミングでスムーズに購入できないと、せっかくの購買意欲が下がってしまう可能性があります。
例えば、商品購入ページのURLを画面上の見やすい位置やコメント欄にあらかじめ表示しておくことで、視聴者は迷わず購入に進むことができます。
さらに、配信者が購入方法を丁寧に説明することで、視聴者の不安が解消され、安心して購入してもらえるようになります。
日本でのライブコマースの成功事例
【食品】漬物専門店「四十萬谷本舗」

(参照元:石川県産業創出支援機構ISICO)
かぶら寿しに代表される発酵食品の老舗である四十萬谷本舗では、昨年1月から首都圏の大企業で働く副業人材が参加するプロジェクトを立ち上げ、新商品の開発や販路の開拓に挑戦しています。
ライブコマースは土曜の夜に6回、1時間から1時間半ほどかけて配信しており、双方向のコミュニケーションができる強みを生かして、おすすめの食べ方やお酒との相性などのweb上の視聴者から寄せられる質問やコメントに答えながら、商品を紹介しています。
常時約20人が視聴し、多いときには約8万円を売り上げるなど、予想を上回る反響で、今後もしばらく継続する予定とのことです。
【百貨店】三越伊勢丹

(参照元:PR TIMES)
百貨店の老舗である株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、2019年11月15日に初めてのライブコマースを実施しています。年末年始の主力商品であるお歳暮を特集し、「パッケージの華やかさ」や「ものづくりのストーリー」から紹介したライブ配信では、過去最高のECでの売上を記録しました。
以来、お中元・お歳暮などの従来の催事にあわせて「三越伊勢丹ライブショッピング」と銘打ったライブコマースを展開し、バイヤーや販売スタッフ、また多彩なゲストも交えて商品の魅力を配信しています。
【アパレル】ユニクロ

(参照元:UNIQLO LIVE STATION)
ファーストリテイリング傘下の「ユニクロ」が、「UNIQLO LIVE STATION」でライブコマースを始めたのは2020年12月のことでした。
著名人がコーディネートのポイントなどをライブで解説し、視聴者の質問などに答えながらユニクロの商品を紹介。消費者はライブ配信動画を見ながら、気になった商品をそのままECサイトやアプリ内で直接購入できるようにしました。
現在では多くの販売番組が存在し、よりユーザーニーズに合わせた番組の配信を行っています。
【化粧・美容品】資生堂

(参照元:資生堂 ニュースリリース)
「SHISEIDO」は、中国市場においてBC(ビューティーコンサルタントやビューティーカウンセラーの略:美容部員)が出演するライブコマースを推進しており、好調な売り上げを記録しました。
これを受けて、資生堂は日本国内でのライブコマースの本格的な展開を開始し、その第一弾として、化粧品や美容法を紹介するライブ映像を配信し、消費者がリアルタイムでBCとコミュニケーションしながら商品を購入できるライブコマースを開始しました。
第1弾として、株式会社三越伊勢丹ホールディングス(以下、三越伊勢丹)の化粧品オンラインストア「meeco」で2020年7月に実施、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ「非接触型」購買ニーズが増している中での「オフライン」と「オンライン」の強みを融合させたオムニチャネルモデルを構築しました。
【インテリア】LOWYA
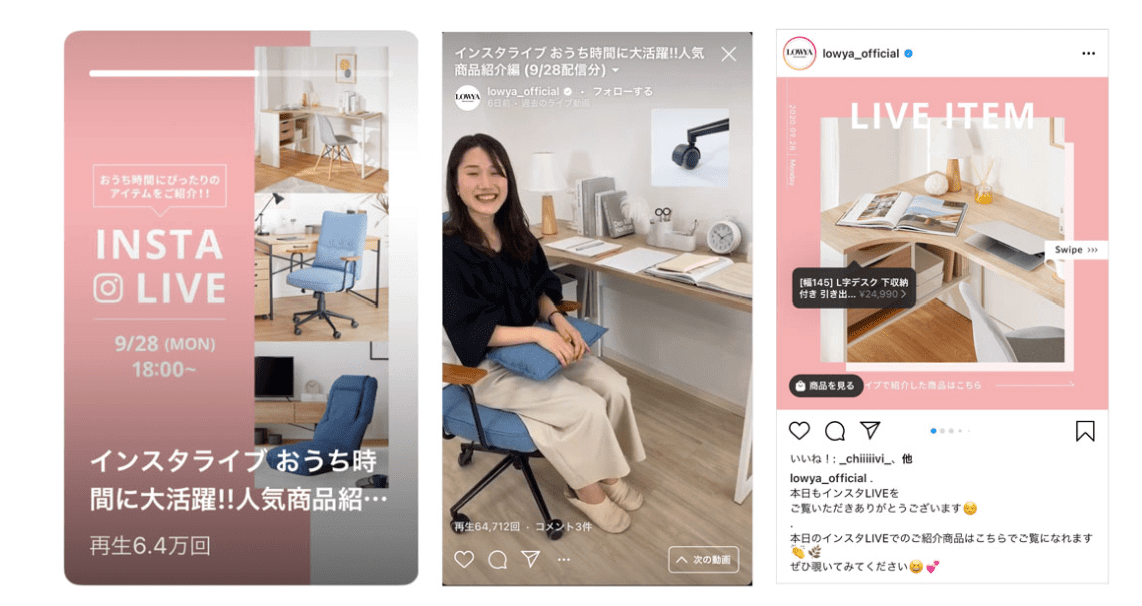
「LOWYA」は、家具やインテリアをECサイトで販売しており、インスタライブを活用してライブコマースに取り組んでいます。
家具やインテリアは実店舗で買うお客様も多く、ECサイトではサイズ感や雰囲気などがいまいち伝わりにくくなってしまいます。
ライブコマースだと家具の隣に立って説明をするので大きさもわかりやすく、雰囲気や使いごごちなども発信できるため相性がいい業界になってきます。
「LOWYA」は特にライブコマースの評判がいいです。
理由としては、ライブ中にコメントをピックアップして質問に回答したり、事前にInstagramストーリーズで質問を集めたりと視聴者の疑問に丁寧に答えていることで、視聴者の満足度が高くなっているからです。
【雑貨】カインズ

(参照元:PRTIMES)
「カインズ」は、主に雑貨やライフスタイル用品などを販売しています。
期間限定でメーカー27社の商品を集め、「カインズデザイン展」として実店舗とオンラインのイベントを開催しています。
「毎日のシーンをたのしく」をテーマに、日用品やペット用品など39点以上の商品が展開されました。
基本的にはカインズの店舗で行われており、バス・ランドリー、リビング用品、キッチン用品がライブ配信で紹介されました。
実店舗とオンラインのコラボで、欲しいと思った商品はネットで買えるのはもちろん、近くのカインズの実店舗に行って買うこともできるため、顧客の購買意欲を搔き立てることができます。
ライブコマースのおすすめサービス

この章ではライブコマースを導入する際の、おすすめサービスをご紹介していきます。
おすすめのサービスは、以下の4つです。
- YouTube
- ライブTV
- SHOPROOM
詳しく見ていきましょう。
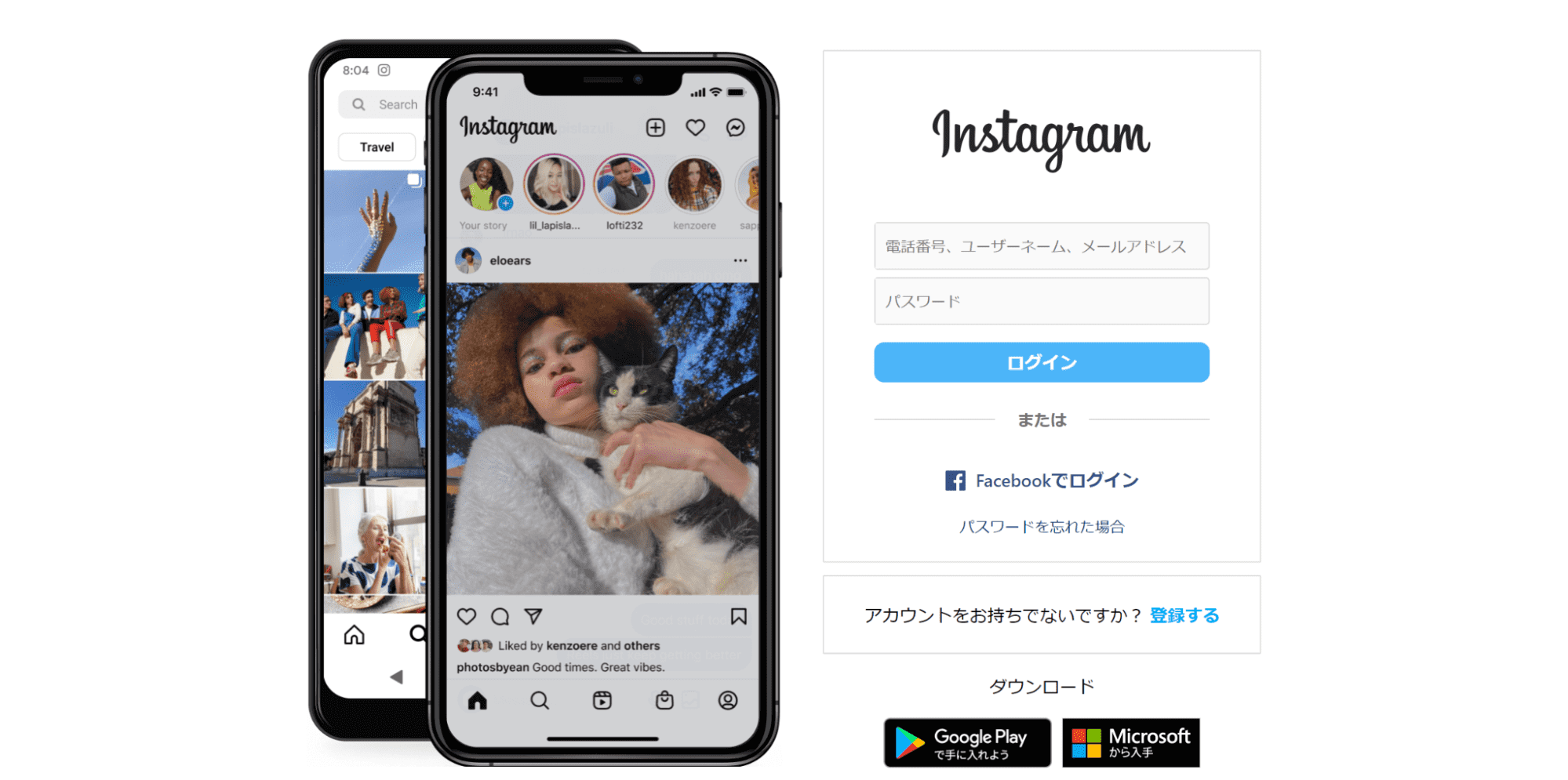
(参照元:Instagram)
Instagramは、ライブ配信機能を備えたSNSです。アカウントを作成すれば、誰でも手軽にライブ配信を行うことができます。
配信は主にフォロワーに向けて行われるため、フォロワー数が多いアカウントであれば、ライブコマースとして高い効果が期待できます。
さらに、InstagramはECサイトとの連携も可能で、ライブ配信中に紹介した商品のURLを掲載することができます。
視聴者がそのまま商品ページへアクセスできるため、購入までの導線もしっかり整えられます。
YouTube

(参照元:YouTube)
YouTubeは、世界最大級の動画配信プラットフォームであり、ユーザー数が非常に多いため、視聴者を集めやすいという特徴があります。Instagramと同様に、アカウントを作成すれば誰でもライブ配信を行うことができ、配信時間に制限がない点も大きな魅力です。
ただし注意点として、「ブラジル、インド、イギリス、アメリカ」のいずれかを拠点にしていない場合、ライブ配信画面に商品のURLを直接貼り付けることができません。
そのため、日本を拠点とする事業者は、ライブ中に口頭で商品名やURLを案内したり、動画の説明欄やコメント欄を活用したりして、ECサイトへ誘導する工夫が必要です。
ライブTV

(参照元:ライブTV)
ライブTVは、KDDI株式会社とauコマース&ライフ株式会社が運営する「au PAY マーケット」アプリのライブコマースサービスになります。
配信中に、視聴者からコメントや質問をもらえることはもちろん、ライブ配信はアーカイブとして残され商品の購入もそこから行えます。
SHOPROOM
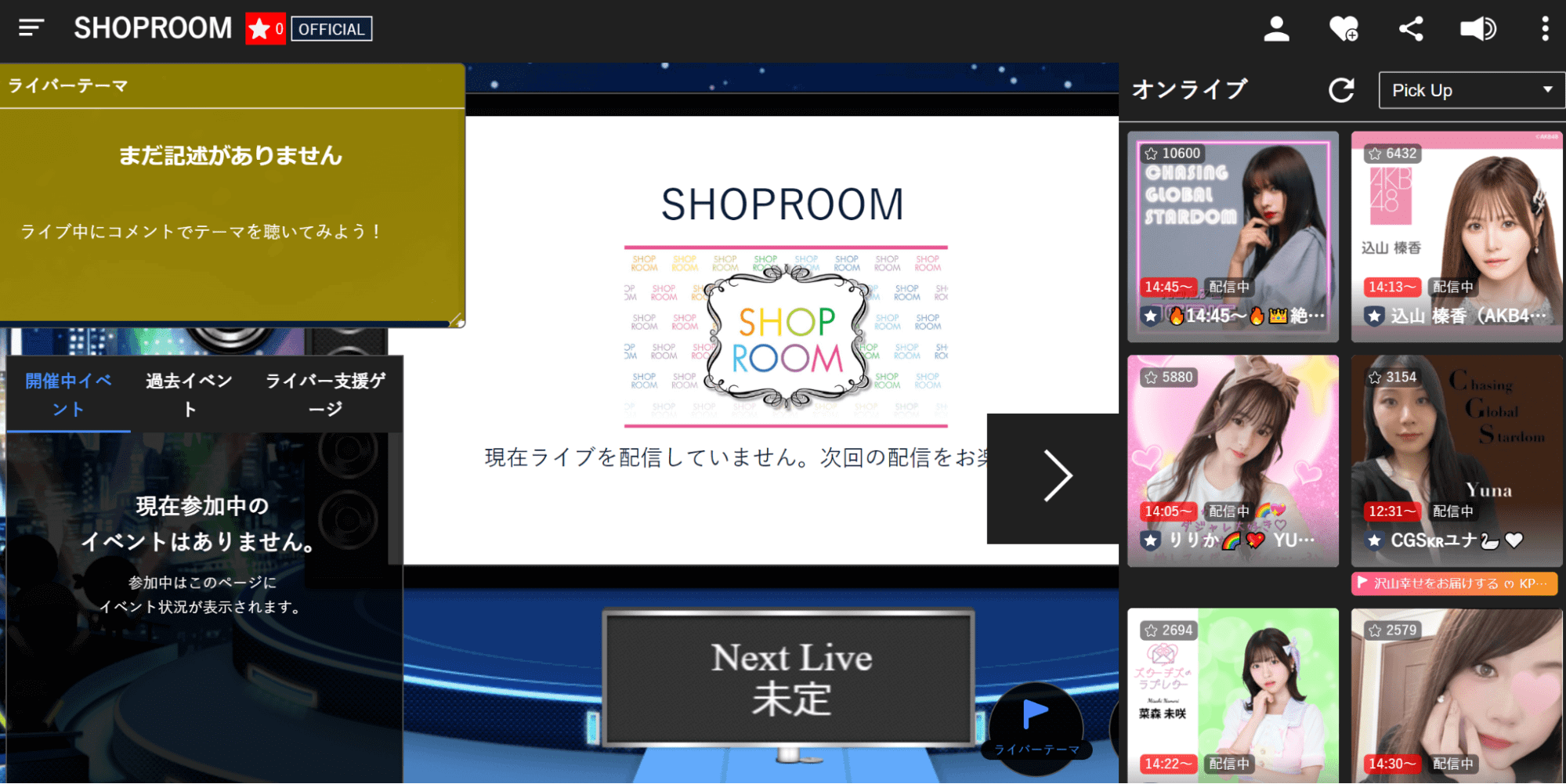
(参照元:SHOPROOM)
SHOPROOMは、SHOPROOM株式会社が運営するライブコマースのアプリです。ライブショッピング機能を使うことで、視聴者はライブ配信中に紹介されている商品を購入することができます。
お笑い芸人やアイドル、モデルなど多くの芸能人が配信をしており、視聴者は無料でコメントできるため、利用者は多くいます。
ライブコマース×自社ECの活用ならW2へ

ライブコマースを成功させるには、自社ECサイトへのスムーズな購入導線を整えることが重要です。視聴者が「買いたい」と思っても、ECサイトに以下のような課題があると、購買までつながらない可能性があります。
- 入力項目が多く、購入手続きが面倒
- ライブ配信で紹介された商品が見つけにくい
- 利用できる決済方法が限られていて購入できない
このような課題に対応するためにも、ライブコマースを含む最新のトレンドに合わせて、自社ECのカートシステムを見直すことが必要です。
W2株式会社が提供するECカートシステムは、ライブコマースとの連携に適した設計がされています。
例えば、美容品や健康食品などのサブスク/定期通販に特化した「W2 Repeat」、オムニチャネル/OMOに対応した「W2 Unified」など、目的に応じた選択が可能です。
実際に、ライブ配信を視聴しながら紹介された商品を自社ECサイトでそのまま購入できるようなカスタマイズにも対応しています。
まとめ
今回はライブコマースの基礎知識やライブコマースを実施するメリット、ライブコマースのやり方や相性がいい商品や業界を解説しました。以下、本記事のまとめになります。
- ライブコマースの市場規模は年々拡大しており、参入企業も増えている
- ライブコマースはお客様との双方向でコミュニケーションを取ることができ、商品に対して疑問が解消されるため購買意欲を向上させられる
- ライブ配信をするための前準備をしっかりと行わないと企業イメージを下げる可能性がある
- アパレル業界や化粧業界・食品業界などがライブコマースとの相性がいい
- ライブコマースを成功させるポイントは、特に視聴者との円滑なコミュニケーションを取ることが重要であり、視聴者の満足度で商品の売上げが変わってくる
ライブコマースは中国で盛んに行われている販売手法で、特にコロナ禍を受けてさらなる市場規模拡大が見込まれます。ライブコマースは事業者と視聴者それぞれにメリットがあり、相性がいい商品や業界も多いのです。
日本でも食品やアパレルなど、ライブコマースを取り入れる企業や業種が増えてきました。