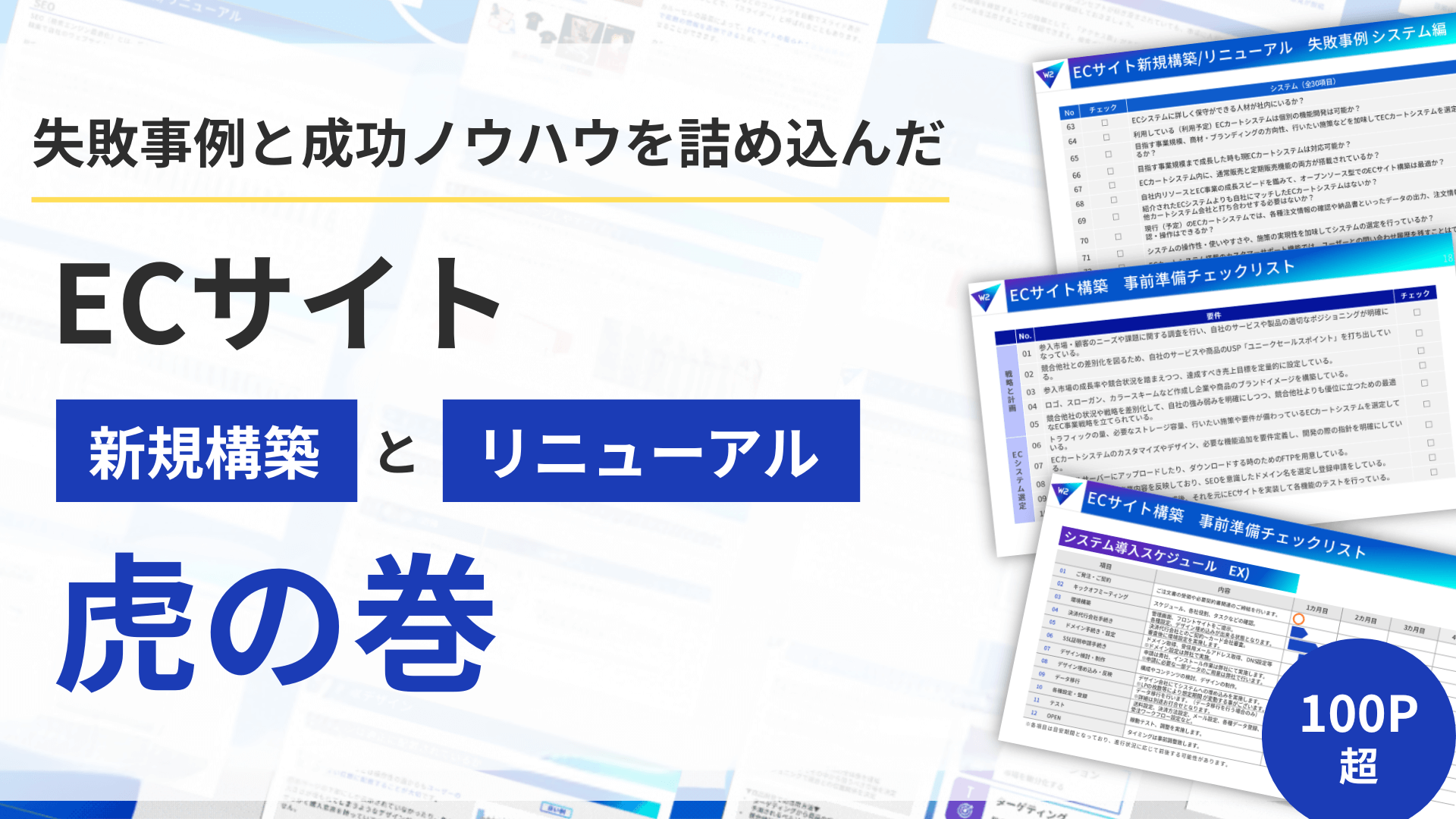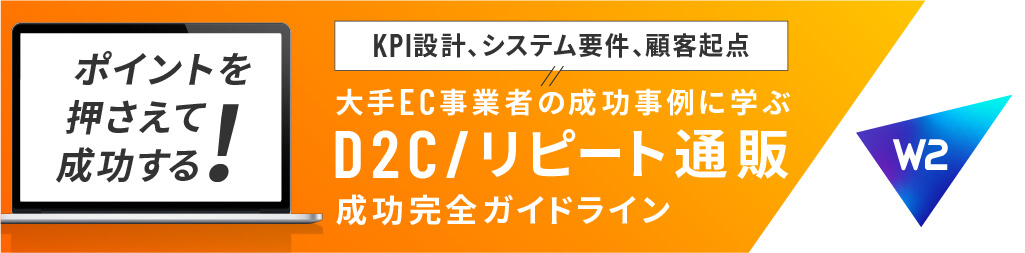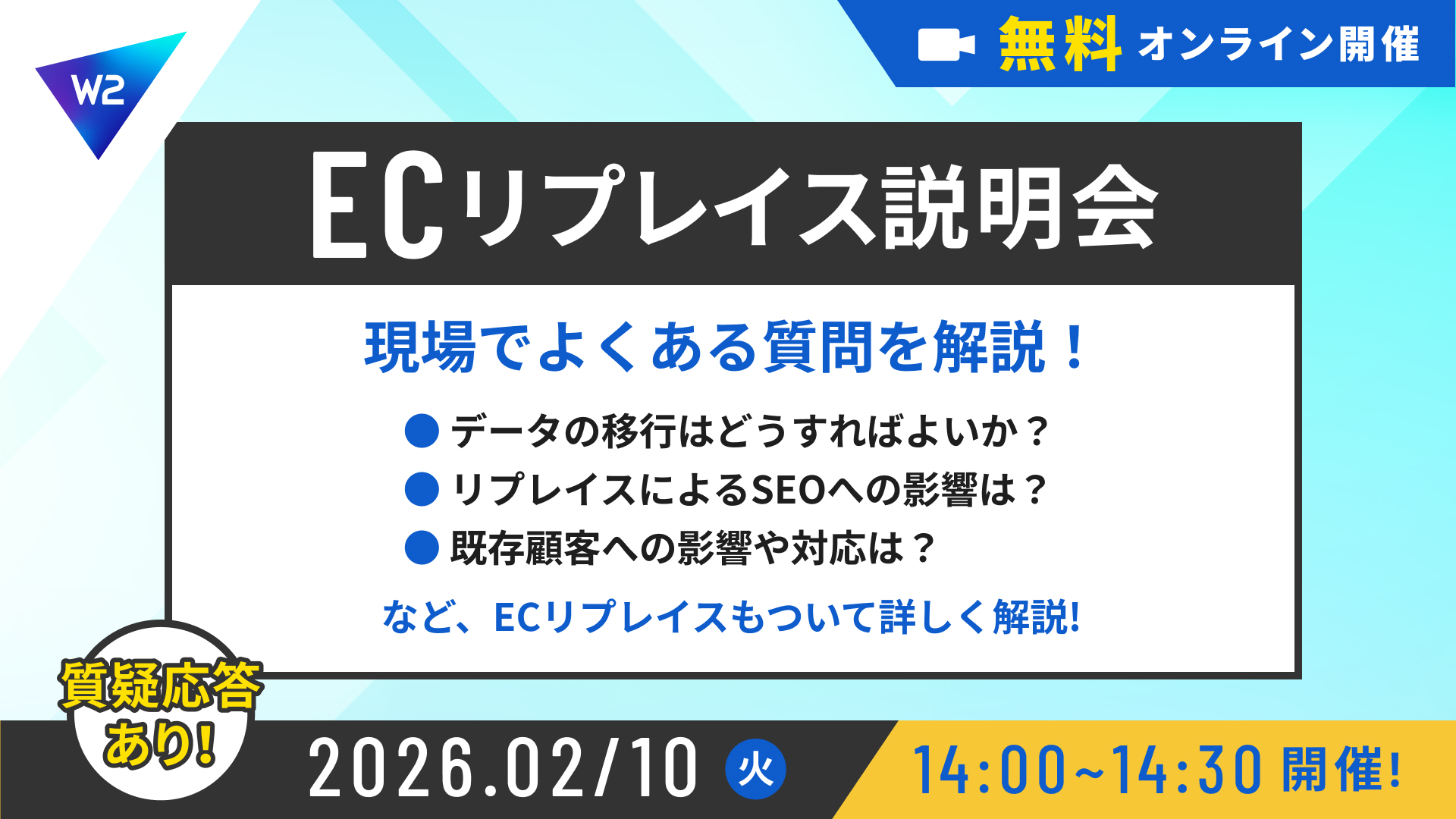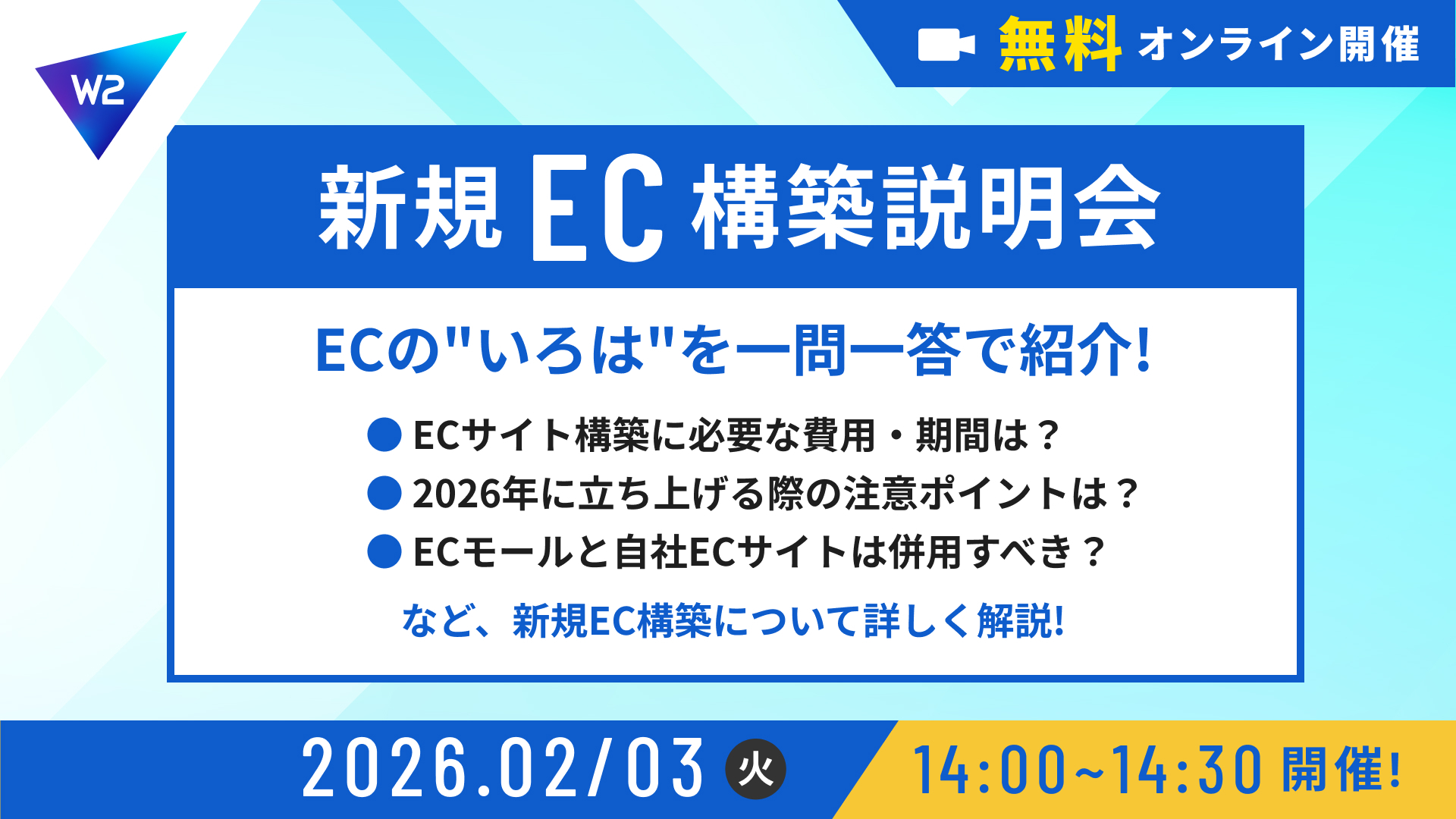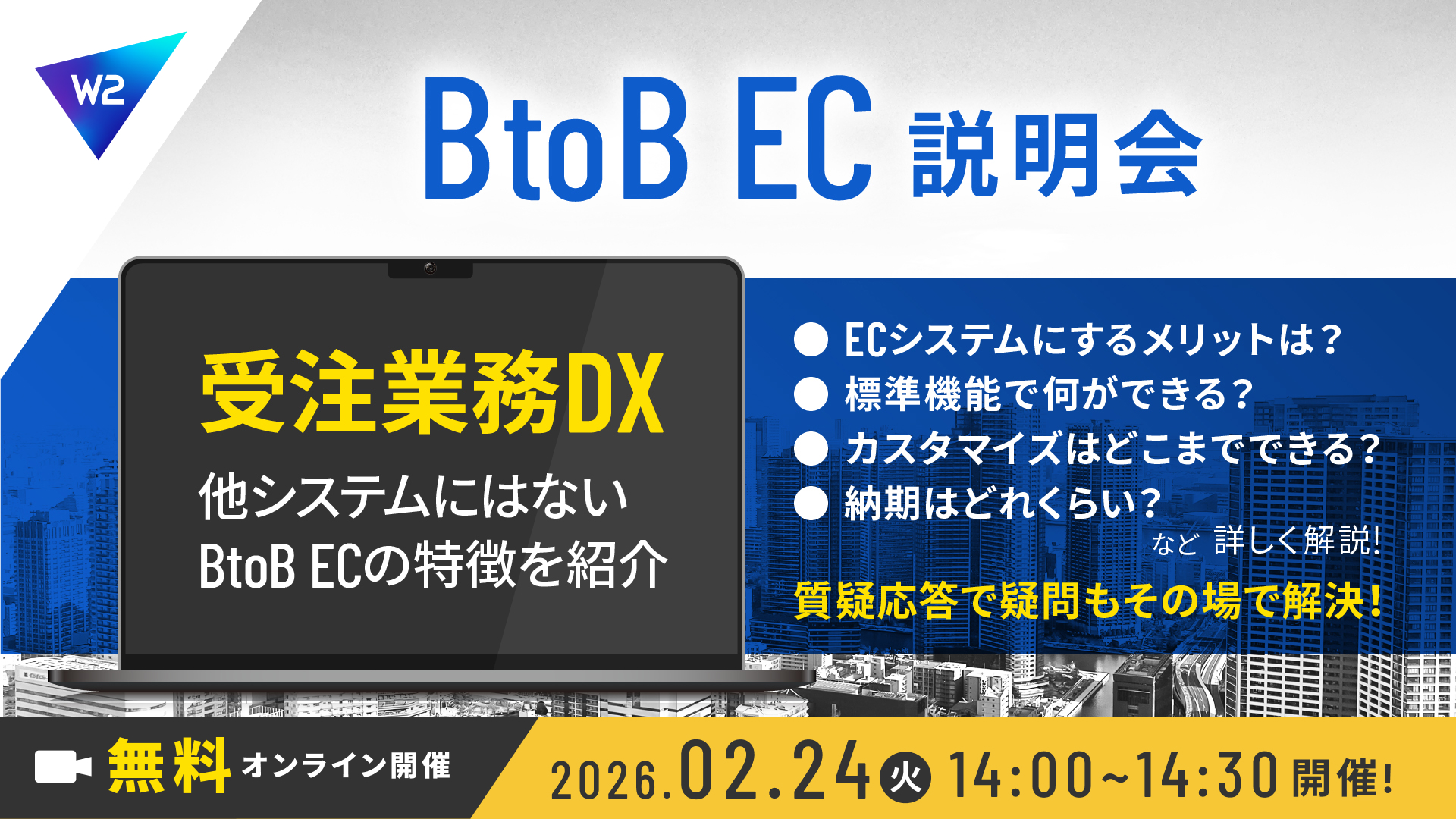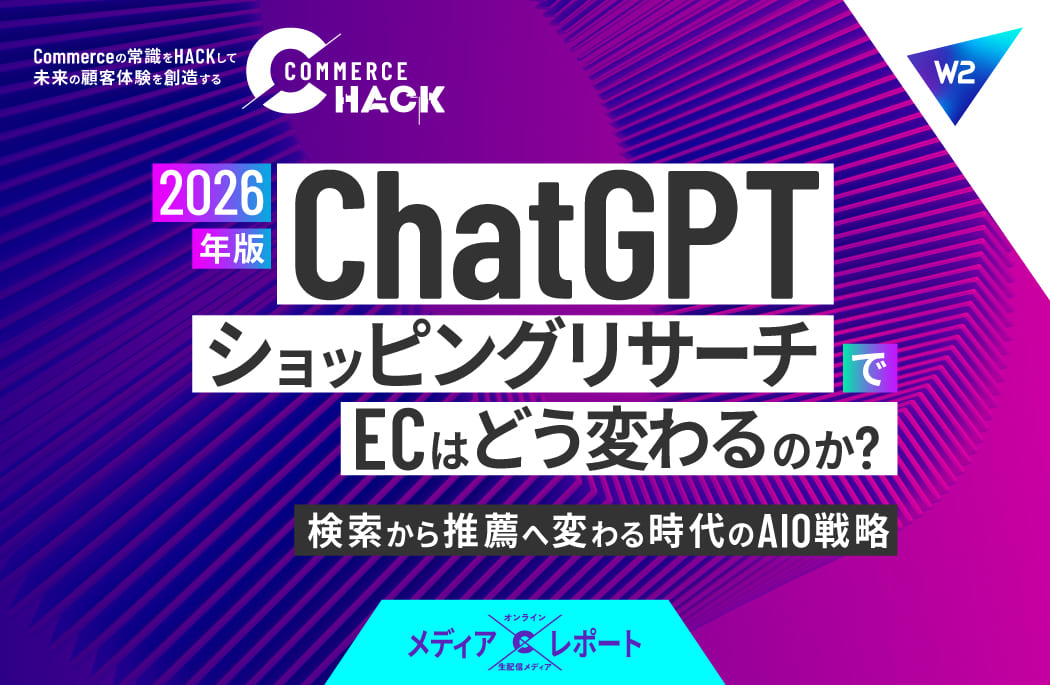・D2Cサイトで集客するにはどうすればいいの?
・効果的なマーケティング施策を知りたい
こんなお悩みはありませんか?
新たにD2Cサイトを立ち上げたものの、なかなか集客がうまくいかず苦戦している企業は少なくありません。
そこで本記事では、D2Cで結果を出すために必要な「マーケティングの方法や考え方」について解説します。
なお、D2Cに関する詳細は下記で詳しく解説しているのでぜひ合わせて一読ください。
関連記事:D2Cはなぜ求められる?ビジネスモデルを事例をもとに徹底解説!
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
D2Cマーケティングのオーソドックスな集客方法はメルマガ
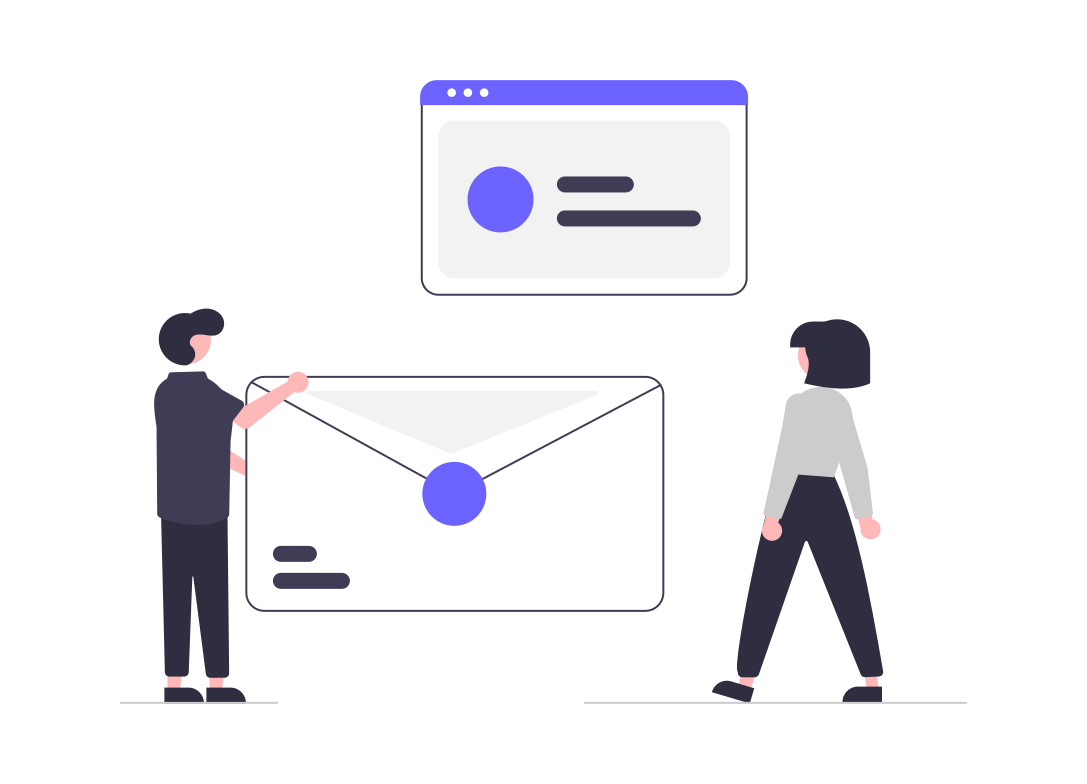
メールマガジンは、以前から多くの企業がマーケティングに利用してきたツールです。なかには、「メールは古い手法だ」と感じている人もいるかもしれません。
たしかに、メールマガジンが普及しはじめたのは2000年ごろのことですから、オンラインの手法としては古くから使われているものだともいえます。
しかし、その活用方法は今でも進化を続けており、メールマガジンが強力なマーケティングツールである点に変わりはありません。
多くの企業がマーケティングの手法としてメールマガジンを採用しています。
登録したユーザーにメールを送るには、印刷代や送料がかかることはありません。
また、最近ではLINE@を利用した顧客への情報提供と チャットボット機能などによる顧客獲得なども施策の一つとして取り入れられています。
メールに記載するコンテンツの制作費(ライターへの依頼)や顧客管理などの費用は別途必要ですが、マーケティングのためのツールとしては格安といえます。
新製品のお知らせやキャンペーンの告知など、大勢に届けたいニュースレターに最適です。
ECサイトでの販売を中心とするD2Cの事業者にとっては、メールマガジンには特別な意味があります。
実店舗で商品を手に取って確認してもらえる既存事業に比べて、オンラインでの体験を提供するツールは重要性が高いのです。
メールマガジンの内容を気に入ってもらえれば、商品が売れる機会は増えるでしょう。
反対に、不快な思いをさせてしまえば講読解除のリスクがあります。
D2Cでは、メールマガジンの講読解除はユーザーとのつながりを失うことを意味します。
D2Cのマーケティングにメールマガジンを活用する際は、ユーザーに「つながっていたい」と感じてもらえるような運営を心がけることが大切です。
まず気を配りたいのは、メールを送る頻度でしょう。
高い販売目標を達成するためや、ライバルとの競争に勝ちたいがために、メールマガジンの発行回数を増やしすぎると「うっとうしい」と感じるユーザーが増えてしまいます。
どれくらいが妥当な頻度なのかはブランドイメージや商品によっても変わってくるので一概にはいえないところですが、多くの企業が週に2回以内を目安にしているようです。
季節性のある商品を扱うD2Cでは、シーズン中だけ発行回数を増やして勝負をかけるという考え方もあります。
どのようなコンテンツにするかも、メールマガジンを活用する際のポイントです。
宣伝のためだけの内容を定期的に送りつけるようでは、講読を続ける価値がないと思われてしまいます。
そのため、多くの企業が商品の魅力を高めるような活用例や、商品に直接関係しなくても関連性のある話題など、ユーザーにとって価値のあるコンテンツの制作に力を入れています。
写真を大きく使って視覚に訴えたり、ときにはティザーで気を引いたりするのも効果的です。
メールのコンテンツ自体はシンプルにして、自社サイトに誘導したうえで続きを読んでもらうという構成も少なくありません。
近年では、メールマガジンのコンテンツをパーソナライズする手法も使われるようになってきました。
自社ECサイトでの購入実績などの履歴情報にもとづいて、記載内容や送信頻度をユーザーごとに変えるのです。
これにより、購入意欲が高まる最適なタイミングでユーザーとコミュニケーションをとれる可能性が高まります。
ユーザーにとっても、欲しい情報がタイミングよく手に入るメールマガジンになります。
2.D2Cを成功に導くマーケティング方法にSNSの運用を
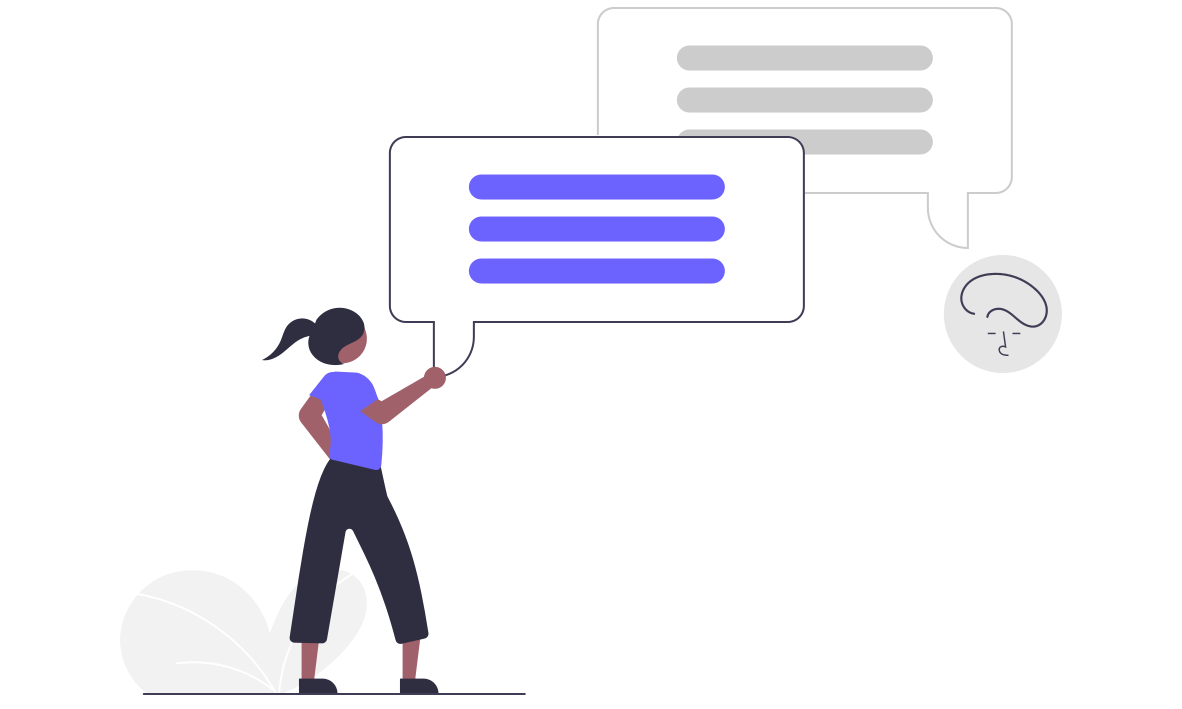
メールマガジンはうまく使えば効果を発揮するマーケティングツールですが、単独では不十分な場合もあります。
読み応えのあるコンテンツも盛り込めるのでユーザーに情報を伝えやすい一方、読者層としてはパソコン利用者が多い傾向があるためです。
D2Cのマーケティングでは、スマートフォン利用者に訴求したい部分も多いでしょう。
そのためには、SNSを活用するのがおすすめです。
これまでメールマガジンは活用してきたものの成果が今ひとつという場合には、ターゲットの違いによってSNSとの使い分けを意識してみるとよいでしょう。
ここからは、SNSをD2Cのマーケティングに活用する方法について、具体例を挙げながら説明していきます。
2-1.D2CマーケティングにおけるSNSチャネルの使い分け
企業にとってのSNSは、消費者と直接つながって近い距離でのコミュニケーションを可能にしてくれるサービスです。
メーカーとしてオンラインでの直販を行うD2Cとは、親和性が高いツールだといえるでしょう。
ただし、SNSにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。メールマガジンとSNSを使い分けるのと同様に、SNSも自社のブランドや商品、ターゲットユーザーなどから最適なものを選ぶことが大切です。
主要なSNSをアクティブユーザー数だけで比較すれば、もっとも規模が大きいのはLINEです。
しかし、これからSNSを導入するなら、Facebook、Twitter、Instagramの3つについて検討してみるのがよいでしょう。
いずれも利用者が多く、マーケティングのための新たなチャネルとしても活用しやすい特徴を備えています。
Facebookは、企業や団体が実名で活動するのに向いているSNSです。
ビジネス目的で利用登録しているユーザーの割合が比較的高いため、ビジネス色の強い商品を扱うD2Cのマーケティングに効果が期待できます。
また、近しいユーザーに情報を「シェア」する機能があるため、企業として魅力的な情報を発信できれば、ユーザー自身の手によって広まっていく可能性があります。
Twitterも、情報の拡散力が高いことで知られるSNSです。
Facebookの「シェア」に相当する「リツイート」という機能によって、利用者が情報を広めてくれる可能性があります。
さらに、「フォロー」機能では互いの承認を必要とせずにユーザーがつながれるようになっているため、利用者同士のネットワーク構築が進みやすいのが特徴です。
口コミによってさまざまなセグメントにリーチできると考えれば、特徴を理解しやすいでしょう。
Instagramは、写真の投稿を主体としたSNSです。
「インスタ映え」という言葉からもわかるように、ビジュアルが重要な商品を中心に紹介したい企業に向いています。
Twitterと同様「フォロー」もできるので、口コミによるリーチも広範囲です。
D2CのマーケティングにSNSの導入を検討する際は、どれかひとつに絞らなければならないというわけではありません。
とはいえ、SNSの運用はそれなりにコストがかかるものです。
全部に対応するよりも、SNSごとの特徴から自社にとって必要なものを見極めて、マーケティングの新たなチャネルに加えるとよいでしょう。
2-2.D2CマーケティングでのSNS活用 ①企業公式アカウントの開設
企業がSNSを活用したマーケティングを行う際には、自社の公式アカウントを作るのが一般的です。
公式アカウントは、企業がファンと交流するための場所だと考えればイメージしやすいでしょう。
既存顧客には、新商品などの新着情報を知らせることができます。自社の魅力を広く伝えられれば、潜在顧客を惹きつけてファンになってもらうことも可能です。
SNSはメールマガジンよりもユーザーからの気軽な反応を得やすいので、ファンの心理やニーズを探るためのツールとしても役立ちます。
公式アカウントを開設したら、その存在を少しでも多くのユーザーに知ってもらう必要があります。
このときに大切なのは、公式アカウントを好きになってもらうことです。
ユーザーを第一に考えた情報発信や、メリットを提供する姿勢を心がけて、つながりを増やしていきましょう。
また、SNSにはフランクな交流を望むユーザーが少なくないという点も意識するとよいでしょう。
形式ばった情報や、自社に都合のよい宣伝ばかりでは、ユーザーは離れてしまいます。
情報発信の頻度があまり高いと嫌われるかもしれない点は、メールマガジンと同様です。
ユーザーとのつながりがある程度できてきたら、情報の拡散によってブランドの認知をさらに広げていけるようになります。
ユーザーは「感動した」、「誰かに自慢したい」、あるいは「人の役に立ちたい」といったさまざまな動機で情報を広めるための行動をとるものです。
この点をふまえて、多くの人が広めたいと感じるような情報を発信するのは、ある意味では効果的だといえます。
しかし、ブランディングを考えるなら、広く拡散されることを第一の目的とすべきではありません。
もっとも大切なのは、ブランドのコンセプトや商品の魅力といった、「らしさ」を伝えることだといえます。
2-3.D2CマーケティングでのSNS活用 ②Instagram,Facebook、SNS広告の運用
SNSには広告を出稿する機能を備えているものも多く、D2Cブランドの宣伝に活用できます。
広告もSNSごとに特徴があるので、プロモーションチャネルとして使い分けるとよいでしょう。
Facebookでは、同社がもつ広範囲なネットワークを対象にした出稿が可能です。
Facebook本家のタイムラインのほか、インスタントメッセージや通話のための「Messenger」や、Instagramにも広告を出すことができます。
フォーマットは、画像や動画にテキストを添えたシンプルな表示が基本です。
そのほかには、スライドショーのような見せ方ができる「カルーセル」や、複数商品をカタログのように見せる「コレクション」といった、複数の画像を用いた形式も利用可能です。
Facebookはビジネスでの利用を目的としたユーザーが比較的多いのに対し、Twitterではカジュアル用途のユーザーが多くを占めます。
紹介したい商品によっては、Twitterに広告を出すほうが高い効果を期待できるでしょう。
Twitterでもっとも基本となる広告フォーマットは、タイムラインに表示される「プロモツイート」です。
これには、最初の投稿のみが課金対象で、リツイートなどの2次的な投稿には費用がかからないという特徴があります。
そのため、ユーザーの手によって拡散されるような広告を出すことができれば、費用対効果の高いプロモーションを実現できます。
また、公式アカウントのフォローを増やしたいときに利用できる「プロモアカウント」も利用可能です。
これは、Twitterの利用者に「おすすめユーザー」などとして自社をアピールするための広告です。
Instagramには、女性ユーザーがやや多いという特徴があります。
洋服やアクセサリーなど、女性向けの商品を写真付きで紹介したい場合に向いているといえます。
また、ショッピング機能を連動させることが可能な点も、Instagramの特徴です。
これにより、広告の閲覧から商品の購入までの一連の体験を、スムーズな流れで提供できます。
どのSNSに広告を出す場合も、出稿までの流れに大きな違いはありません。
まず、出稿用のアカウントを作成して、画像や動画などのクリエイティブとテキストを用意します。
準備ができたら、予算やターゲット、課金方法を選択して出稿するだけです。
ターゲットは、紹介したい商品などをもとに決めます。
課金方法には、一般的なインターネット広告と同様、インプレッション課金やクリック課金などのタイプがあります。
2-4.D2CマーケティングにSNSを活用する際の注意点
D2CのマーケティングにSNSを活用する際には、気をつけたほうがよい部分もあります。
多くの場合、D2CではECサイトをビジネスの中心に据えることになるでしょう。
このとき、SNSの運用をECサイトの「おまけ」のように扱ってしまうと、SNSを利用しているユーザーの体験を損なう恐れがあります。
例えば、SNSでの投稿や広告は、常にECサイトに誘導すればよいというわけではありません。
コンテンツに触れたり購入したりといった体験が、SNSのみで完結したほうがよい場合もあるのです。
SNSの利用者は、手軽さや気軽さを求めていることが多いという点を念頭に置くとよいでしょう。
オンラインのみで展開しているD2Cブランドでは、商品の実物を店舗で手にとって確認することができません。
ECサイトでの商品紹介はこの点を意識したものになっていることと思いますが、SNSではより注意を払う必要があるでしょう。
拡散力の高さによって情報が速やかに広がる可能性のあるSNSだからこそ、実物をイメージしやすい投稿が重要だといえます。
SNSは情報の伝達スピードはもとより、メディアとしての変化の早さにも目をみはるものがあります。
SNS運用のために社内に専任者を置いている企業も少なくありませんが、それでも適切なキャッチアップは簡単ではありません。
変化の激しいデジタルコンテンツのスピード感に追従できないリスクを避けるためには、SNSによるマーケティングを専門とする企業に相談することも一度は検討してみましょう。
外部の専門家を味方につければ、インフルエンサーの起用などのような積極的な施策で高い効果を得ることも可能になるかもしれません。
3.D2Cマーケティングの動画広告:YouTubeの運用
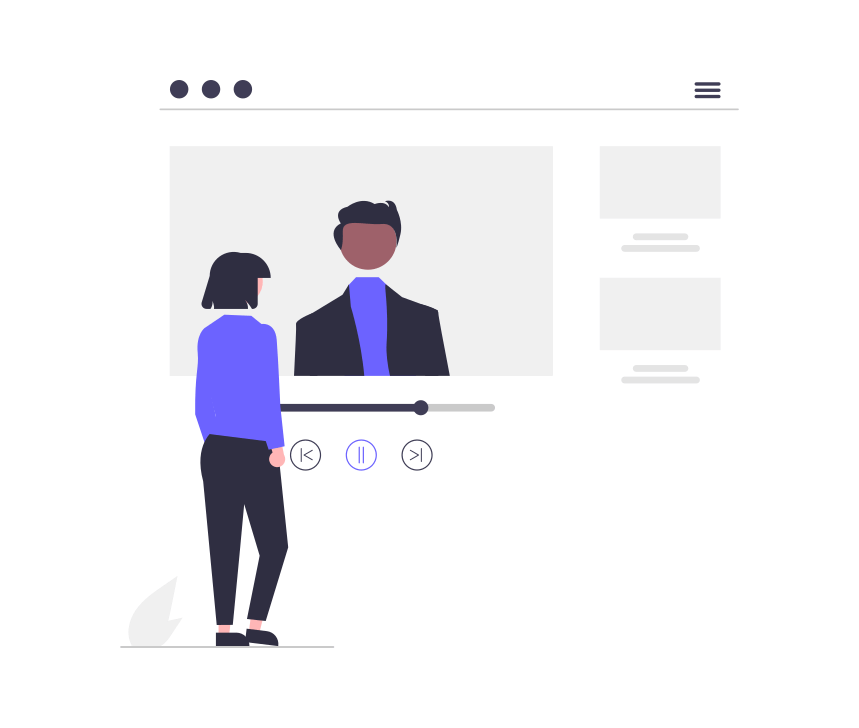
動画広告は、自社商品の魅力など多くの情報を短い時間に圧縮して伝達するのに適した手法です。
広告のCVRを向上させたい場合にも、動画が最適な場合があります。
動画を用いた広告はSNSでも出稿できますが、動画そのものがコンテンツであるYouTubeに広告を出すという方法についても検討してみるとよいでしょう。
3-1.D2Cマーケティングの動画広告:動画広告の戦略の設計
動画広告のコンテンツは、戦略的に決定することが大切です。
YouTubeを運営するGoogleによると、動画広告には「3H」という考え方があります。
これは、「Hero」、「Hub」、「Help」という3タイプの広告の頭文字をとった用語です。
「Hero」は、人としての普遍的な欲求を刺激するような広告です。
できる限り多くのユーザーに見てもらい、まず興味をもってもらいたいというときにこのタイプの動画を制作します。
「Hub」は、より細かくセグメント分けされたターゲットが身近に感じられるような広告です。
自社ブランドの世界観や価値を伝えたいときは、このタイプの動画が適しています。
「Help」は、ユーザーの顕在化したニーズに応えるような動画です。
自社商品の使い方や既存ユーザーからの評判など、具体的で説明的なメッセージを伝えたいときはこのタイプの動画を選びます。
動画広告を制作するときは、訴求したい事柄が3Hのどれにあたるのかを踏まえてコンテンツを決めていくのが効果的だといえます。
例えば、できる限り広範囲にイメージを伝えたいのか、それともユーザーごとの個別の課題を解決するような内容にしたいのかというようなことです。
あるいは、今はまだブランドを知って欲しいだけなのか、すぐにでも購入につなげたいのかによっても作るべき動画は変わってきます。
3-2.D2Cのための動画広告の制作と運用指標
動画広告を制作する具体的な方法は、内製するか外注するかによって変わってきます。
自社内で制作できるのなら、制作意図を汲んだ動画を素早く仕上げることも可能でしょう。
しかし、制作技術に不安がある場合は、外部の専門企業やフリーランスに外注することになります。
これは手離れがよく、コストを抑えられる可能性もある方法ですが、期待通りの仕上がりにするには制作意図を正確に伝えるための綿密な打ち合わせが求められます。
動画広告の成果を測定するには、あらかじめ指標値(KPI)を定めておくことが重要です。その際、もっとも基本となるのはCVRでしょう。
動画広告におけるCVRとは、動画を視聴したユーザーに対する購買ユーザーの割合です。
より詳細に分析したい場合は、「視聴完了率」、「LP遷移率」、「LP遷移後の購入率」というように段階に分けて計測する手法も効果的です。
計測した結果、指標値が思ったよりも低いという場合には、原因を考えて対策を講じる必要があります。
例えば、「視聴完了率」が低い場合は、動画コンテンツの問題が考えられます。
退屈なシーンがないかや、テンポが悪くないかなどを確認しましょう。
一方、「LP遷移率」が低くなるのは、動画は最後まで試聴されているものの、商品を欲しいと感じてもらえていない場合です。
視聴者が商品のターゲットからずれていないかや、視聴するだけで満足してしまえるような内容になっていないかチェックしてみるとよいでしょう。
「LP遷移後の購入率」が低い場合は、動画による集客そのものはできています。
しかし、ランディングページのクオリティが、動画から期待されるイメージからずれている可能性があります。
または、ランディングページからの購入方法がわからないなど、ユーザビリティに問題があるのかもしれません。
4.D2Cマーケティングにおけるカートシステムの重要性
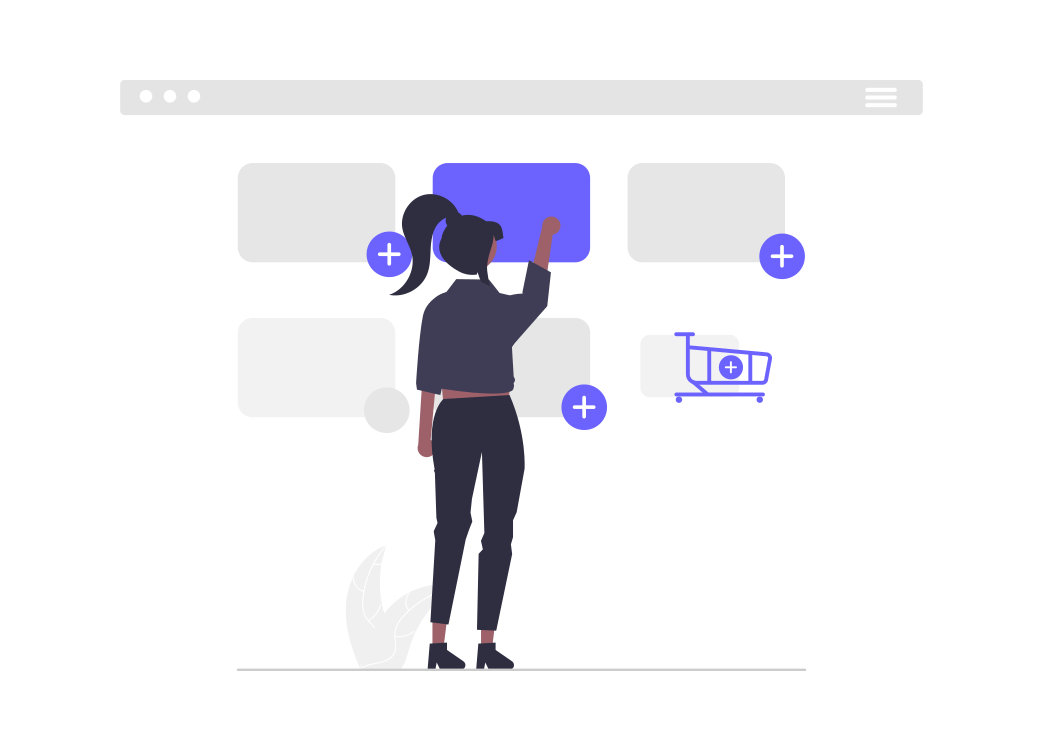
メールマガジンやSNS、YouTubeをプロモーションに活用するとき、メインの集客先となるECサイトのクオリティは重要です。いくら集客に成功しても、最後のステップで購入に至らなければ収益につながらないためです。
特に、CVRの高いランディングページを作成できるかどうかは、重要なポイントだといえるでしょう。
そのためには、ECサイトのベースになるシステムの選定が肝心です。
W2のECカートシステム「W2 Repeat(旧:リピートPLUS)」なら「フォーム一体型LP」作成機能でスムーズな購入体験をユーザーに提供することが可能です。
定期通販にも最適なさまざまな機能と効率性を備えているので、サブスクリプション型のビジネスモデルを採用するD2Cブランドにもおすすめできます。
あらゆる規模のD2C事業にマッチするプランが用意されていますので、ぜひ一度検討してみてください。
まとめ:最適なマーケティング施策でD2Cサイトの集客を伸ばそう
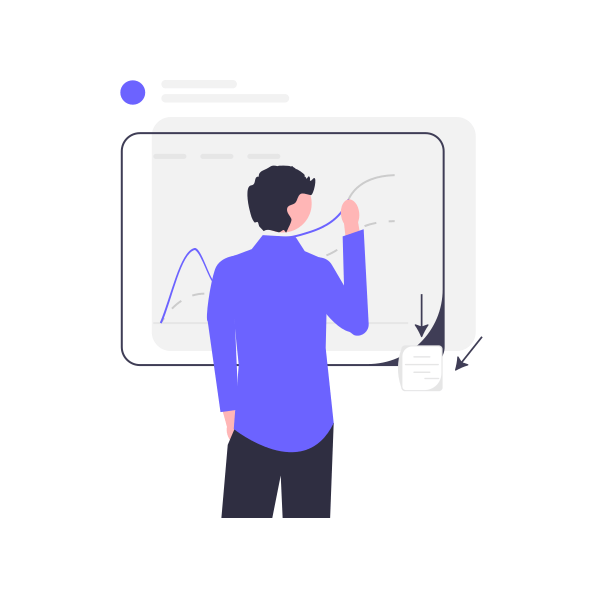
改めて、D2Cサイトにおすすめのマーケティング施策をまとめます。
・メルマガ:今もなお効果的なオーソドックスな手法
・SNS:公式アカウント運用やSNS広告で認知を拡大
・動画:YouTubeなどでターゲットに刺さる動画を制作
ぜひ本記事の内容を参考に、D2Cサイトの集客方法について検討してみてください。
なお、「D2Cの成功完全ガイドライン」の資料では「D2Cを成功させるToDo」を全80P超で解説しているため下記から無料ダウンロードください。