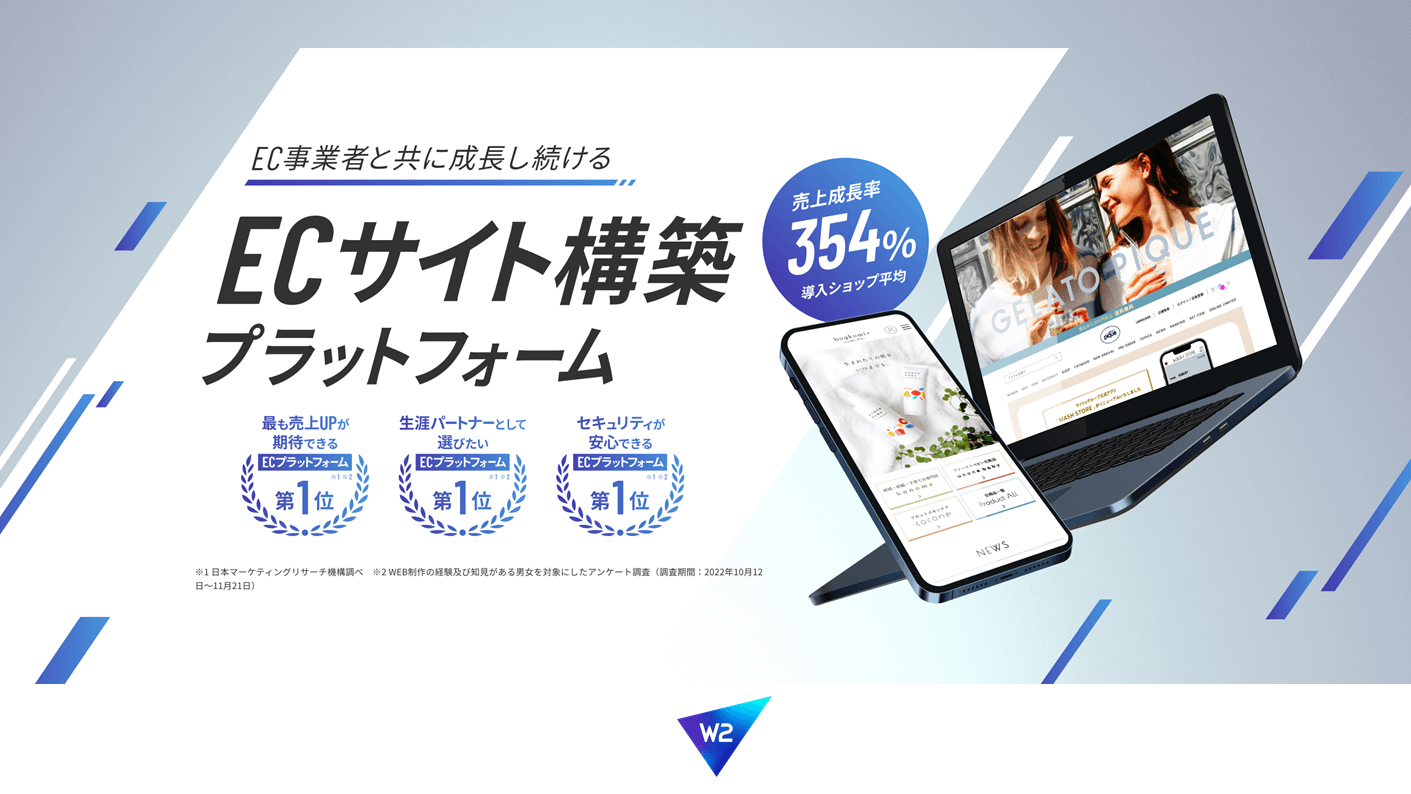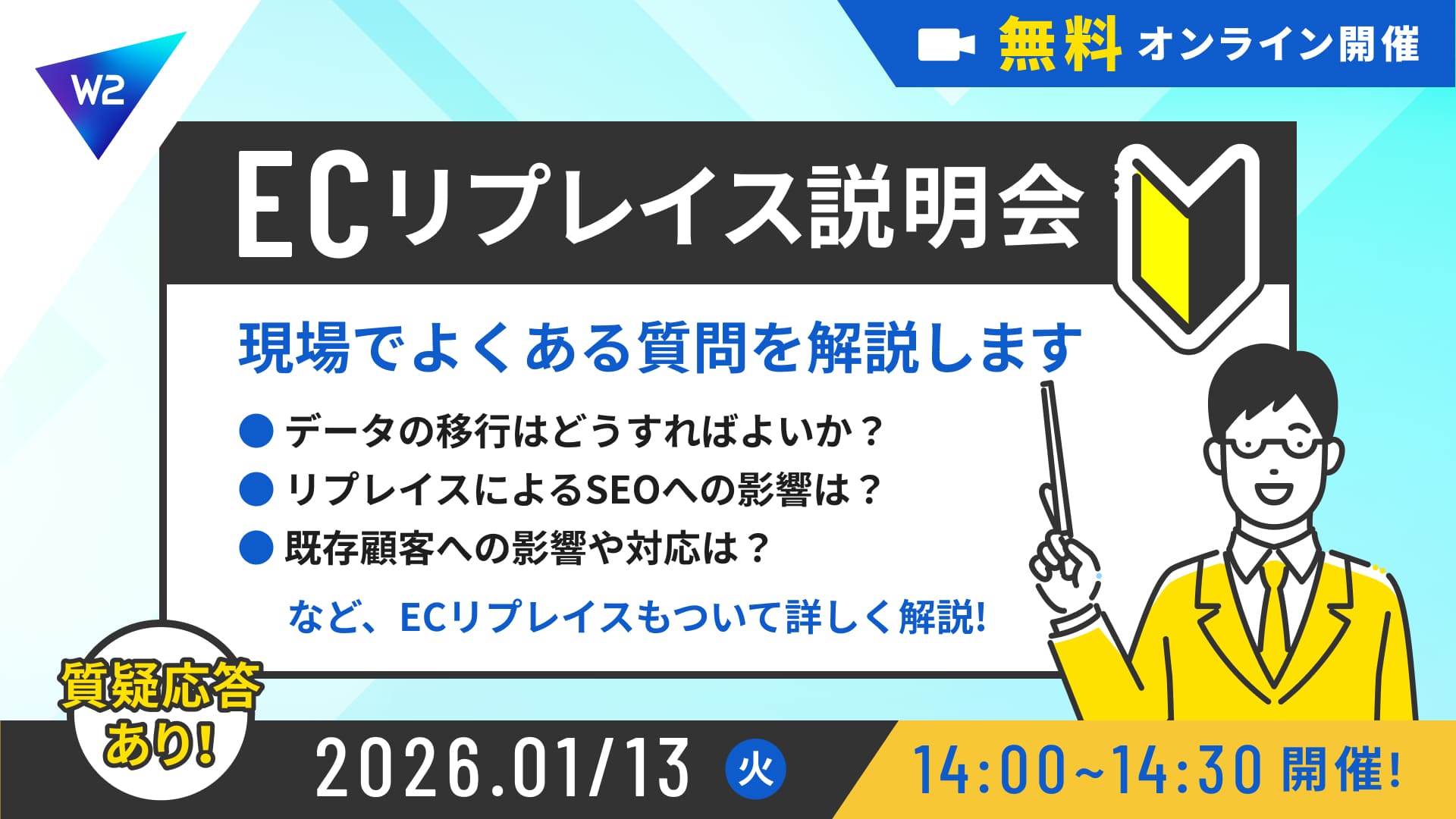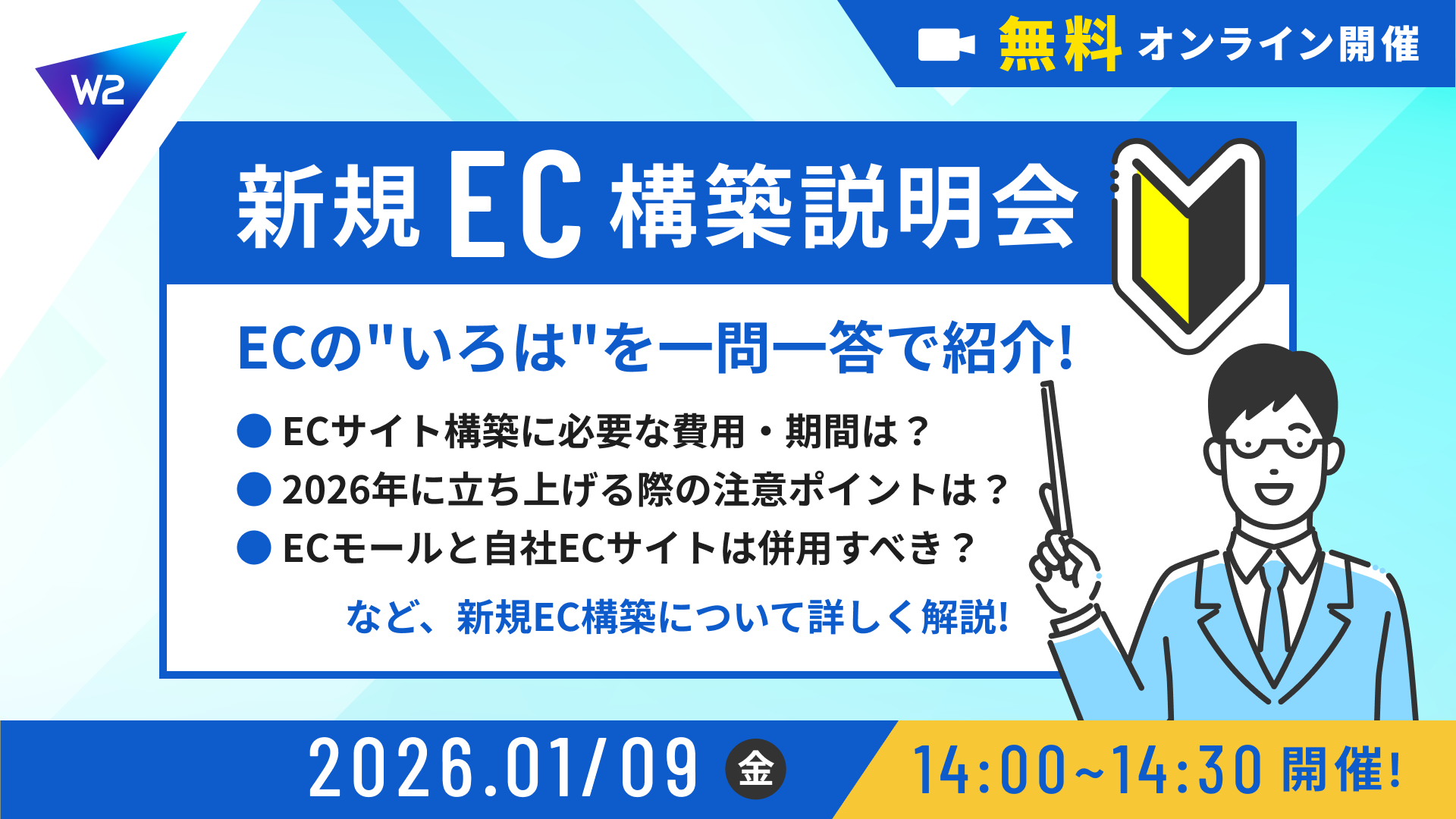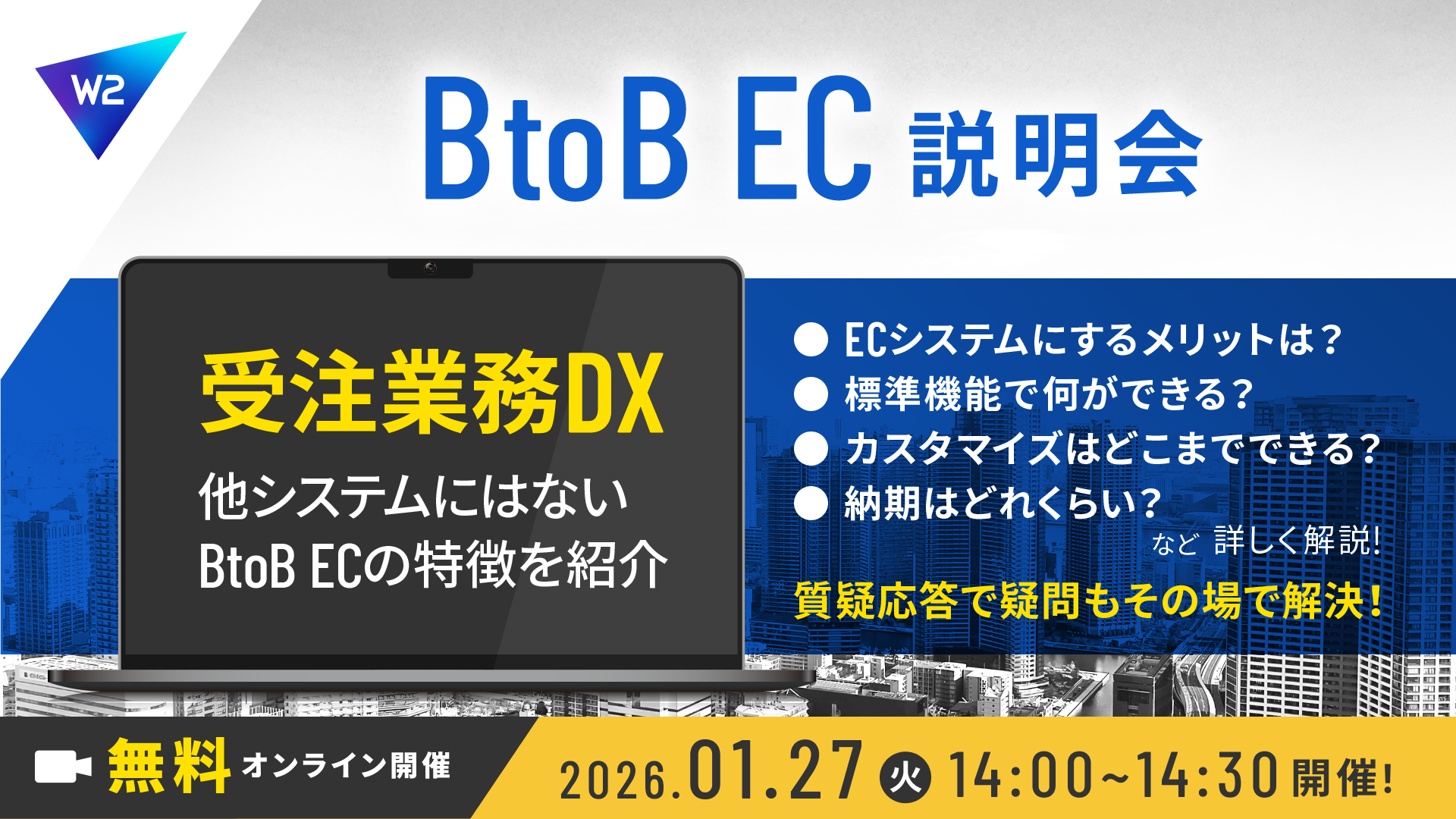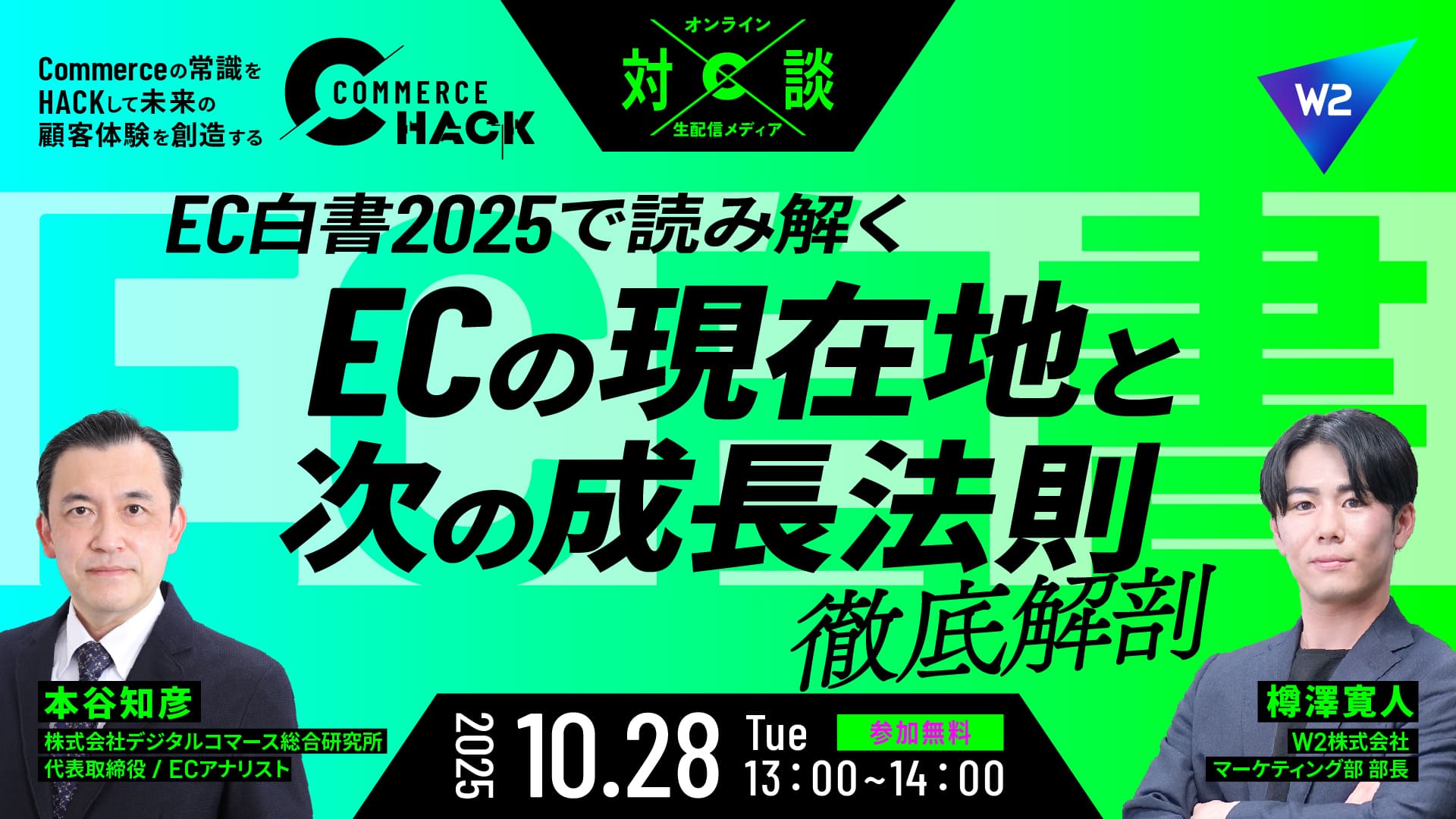「ECサイトの売上が頭打ちになっている」「実店舗への来店客数が減少している」 多くの事業者が抱えるこれらの課題は、ECサイトと実店舗を連携させる「OMO(Online Merges with Offline)」戦略によって解決できる可能性があります。
ECと店舗は、もはや競合ではありません。それぞれの強みを活かして顧客データを統合し、顧客一人ひとりにとって最適な購買体験を提供することで、売上を最大化する「オムニチャネル」の実現が、現代の小売業における成功の鍵です。
本記事では、ECプラットフォームを提供する専門家の視点から、ECと店舗連携を成功に導くための具体的な7つのポイント、そして導入で失敗しないための注意点までを網羅的に解説します。
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
ECと実店舗の連携を考える前に知るべき「違い」とは?
ECサイトと実店舗の連携を成功させるには、まず両者の根本的な違いと、それぞれが持つ独自の強みを理解することが不可欠です。これらを把握することで、なぜ連携が必要なのか、より深く見えてくるので、順に解説します。
1. 時間と場所の制約
ECサイト最大の強みは、時間と場所の制約がないことです。お客様は24時間365日、スマートフォンやPCさえあれば、日本全国どこからでも商品を探し、購入することができます。
一方で、実店舗は商圏が物理的な距離に縛られており、営業時間や定休日があり、お客様が来店できる距離にも限界があります。しかし、その地域に根ざした存在として、独自のコミュニティを形成できる強みもあります。
2. 購買体験とコミュニケーション
実店舗ならではの価値は、スタッフによる直接的な接客です。商品の詳細な説明やコーディネートの提案はもちろん、お客様との何気ない会話の中からニーズを汲み取り、信頼関係を築くことができます。この人的なコミュニケーションが、ブランドのファンを育てる土壌となります。
一方、ECサイトでは基本的に顧客自身が情報を集めて購入を決定するため、スタッフとの直接的な対話はありませんが、その分、豊富な商品レビューや詳細なスペック情報、動画コンテンツなどで購買をサポートします。
3. 商品の確認方法
商品を実際に手に取り、素材感や重さを確かめたり、洋服であれば「試着」したりできるのは、実店舗だけの特権です。購入後の「イメージと違った」というミスマッチを最小限に抑えることができます。
一方、ECサイトではこの「試着」ができません。サイズが合うか、色がイメージ通りかといった不安が、購入のハードルになることがあります。そのため、詳細なサイズガイドや様々な角度からの写真、着用動画などで、その不安をいかに払拭するかが重要になります。
このように、ECサイトの「利便性」と、実店舗の「体験価値」は、互いに補完し合える関係にあります。
後ほど、これらの違いを乗り越え、両者の強みを掛け合わせることで生まれる具体的な成功ポイントも解説します。
ECと実店舗の連携で実現できる7つの施策
ECと実店舗を連携させることで、具体的にどのような施策が可能になるのでしょうか。顧客体験を向上させ、売上を拡大させる7つの代表的なポイントをご紹介します。
- 【店舗受取】ECの利便性と店舗の安心感を両立する(クリック&コレクト)
- 【店舗でのEC活用】店舗を「無限の棚」に変える
- 顧客情報・ポイントを一元化する
- オンラインとオフラインを回遊させる
- 全チャネルの在庫を可視化し、機会損失を防ぐ
- 販売員をブランドの「インフルエンサー」にする
- 「オンライン接客」で商品の魅力を最大化する
順に解説します。
1. 【店舗受取】ECの利便性と店舗の安心感を両立する(クリック&コレクト)
ECサイトで購入した商品を、お客様の都合の良い時間に最寄りの店舗で受け取れるサービスです。これは、ECの「いつでもどこでも買える」利便性と、実店舗の「実際に商品を確認できる」安心感を融合させた、OMOの基本的な施策です。
送料が無料になるという直接的なメリットだけでなく、「日中不在がちで宅配便を受け取れない」「宅配ボックスがない」といった現代のライフスタイルにおける不便を解消する価値を提供します。
店舗側にとっては、単に商品を渡す場所ではありません。お客様が来店することで、ECサイト上では伝えきれなかった商品の使い方をアドバイスしたり、関連商品を提案したりといった新たな接客機会が生まれます。このリアルなコミュニケーションが顧客満足度を高め、「ついで買い」によるアップセルだけでなく、ブランドへの信頼と愛着を育むのです。
2. 【店舗でのEC活用】店舗を「無限の棚」に変える
店舗に在庫がない商品や、店舗では扱いきれないEC限定商品を、その場で店舗スタッフがタブレット端末などを用いてECサイト経由で注文・決済する接客です。これは、在庫切れによる販売機会損失を防ぐだけでなく、店舗の役割そのものを変革する重要な施策です。
お客様にとっては、「せっかく店舗に来たのに目当ての商品の在庫がなかった」という最悪の購買体験を回避できます。さらに、手ぶらで帰宅して後日商品を受け取れるため、大型商品やかさばる商品でも気軽に購入を検討できます。
店舗側は、物理的なスペースの制約を超えて、ECサイト上のすべての商品を提案できます。これにより、店舗は商品を「売る」場所から、商品を「体験し、発見する」場所へと進化し、より付加価値の高い接客に集中できるようになります。
3. 顧客情報・ポイントを一元化する
ECと店舗の顧客IDを統合し、ポイントシステムや購買履歴、閲覧履歴といったあらゆるデータを一元管理します。データが分断されたままでは、真のオムニチャネルは実現できません。
お客様にとっては、ECでも店舗でも同じようにポイントが貯まり、使えるという利便性はもちろん、「ECで見て気になっていた商品を、来店時にスタッフがおすすめしてくれた」といった、自分のことを理解してくれている、と感じられる特別な接客体験が可能になります。
店舗側は、統合されたデータを分析することで、顧客一人ひとりの解像度が劇的に向上します。
「ECで特定の商品をよく閲覧しているAさんは、次回来店時にその商品を試着する可能性が高い」といった予測が可能になり、データに基づいた質の高い接客が実現します。これは、LTV(顧客生涯価値)の高い優良顧客を育成する上で最も強力な武器となります。
4. オンラインとオフラインを回遊させる
EC会員向けのアプリで「実店舗で使える限定クーポン」を配信したり、店舗のPOPに記載されたQRコードからECサイトの「限定コンテンツ」へ誘導したりと、オンラインとオフラインの垣根を越えてお客様を行き来させる施策です。
この施策の真の目的は、単に送客することだけではありません。お客様の行動データを取得し、チャネルを横断した顧客行動を可視化することにあります。「ECでクーポンを取得し、A店の来店に繋がった」「B店で商品を見た後、ECサイトで購入した」といったデータを分析することで、各チャネルの役割を評価し、マーケティング施策全体のROI(投資対効果)を最大化することができます。
5. 全チャネルの在庫を可視化し、機会損失を防ぐ
EC、実店舗、倉庫など、社内に分散しているすべての在庫情報をシステムで一元管理し、リアルタイムで同期させます。
在庫が一元化されることで、ECサイト上で「〇〇店の在庫状況」を表示させることが可能になり、お客様は無駄足を踏むことなく来店できます。また、ある店舗で欠品していても、他店舗の在庫や倉庫在庫を引き当てて販売機会を逃さない「在庫融通」も実現できます。
経営的には、全チャネルの在庫を正確に把握することで、過剰在庫や欠品を減らし、在庫の最適化を図ることができます。これにより、キャッシュフローの改善や廃棄ロスの削減といった、直接的な利益改善に貢献します。
6. 販売員をブランドの「インフルエンサー」にする
店舗スタッフが自らInstagramなどのSNSアカウントで情報発信したり、個人のコーディネート投稿(スタッフDX)を行ったりすることで、お客様との新たな接点をオンライン上に創出する取り組みです。
これにより、店舗スタッフは単なる「販売員」から、ブランドの価値や商品の魅力を自らの言葉で伝える「インフルエンサー」や「コンテンツクリエイター」へと進化します。
画一的な企業アカウントの発信とは異なり、スタッフ個人の個性やキャラクターが加わることで、お客様は親近感を抱きやすくなります。
結果として、「この人のコーディネートが好きだから」「この人のおすすめなら信頼できる」といった、スタッフ個人に対するファンが生まれ、EC・店舗を問わず「〇〇さんから買いたい」という指名買いに繋がります。これはAIには決して代替できない、人間ならではの新しい価値創出です。
7. 「オンライン接客」で商品の魅力を最大化する
店舗の商品をスタッフがライブ配信で紹介し、視聴者はリアルタイムで質問しながらECサイトで購入できる仕組みです。これは、動画による一方的な商品紹介ではなく、双方向のコミュニケーションを伴う「オンライン上の接客」と言えます。
写真やテキストだけでは伝わりにくい商品の素材感やサイズ感、使用感を、動画を通じてリアルに伝えることができます。視聴者はチャットで「丈はどれくらいですか?」「他の色も見せてください」といった質問をその場で投げかけ、不安を即座に解消できるため、非常に高いコンバージョン率が期待できます。
さらに、配信のアーカイブ映像をECサイトの商品ページに掲載すれば、ライブ配信後も継続的に売上に貢献し続けるコンテンツとなります。
ECサイトとリアル店舗の連携を成功させるポイント3選
ECサイトとリアル店舗の連携を成功させるポイントは3つあります。
ECサイトとリアル店舗をばらばらに運営するのではなく、リアル店舗のためにECサイトを活用し、ECサイトの欠点をリアル店舗で補う視点が必要です。
まずは顧客情報とポイントシステムの連携から始め、ECサイト・リアル店舗の両方で決済・商品受け取りができる状態を目指しましょう。
1. ECサイトとリアル店舗のシナジーを意識する
ECサイトとリアル店舗にはそれぞれメリットがあります。
ECサイトには、スマホやタブレットを通じ、さまざまな商品を「いつでも・どこでも」閲覧・購入できるというメリットがあります。
一方、リアル店舗には商品の実物を店頭で触り、購入後はその場で持ち帰ることができるというメリットがあります。
それぞれのメリットを活かし、シナジーを得られるような仕組み作りを意識しましょう。
たとえば、消費者が商品を探すためのインフラとしてECサイトを積極的に活用し、商品の販売や顧客へのアプローチは、顧客との1対1でのコミュニケーションが可能なリアル店舗に注力するという考え方があります。
このモデルケースでは、ECサイトという間口を通じて潜在的顧客を集めつつ、リアル店舗の接客力と情報発信力で商品購入につなげることができます。
ECサイトとリアル店舗の壁をなくし、それぞれの強みを活かす方法を考えるのが大前提です。
2. 顧客情報とポイントシステムの連携が最初の1歩
最初に着手したいのが、ポイントシステムを連携し、ECサイト・リアル店舗のどちらでもポイントが溜まるような仕組みを整えることです。
せっかく商品を購入してもポイントが貯まらないのでは、消費者の購買意欲が削がれてしまいます。
また、ECサイトとリアル店舗の顧客情報を連携し、それぞれで購入履歴を閲覧できるようにしましょう。
顧客側はリアル店舗の購入履歴をスマホやタブレットなどで確認できるため、より利便性が増します。
店舗側はECサイトの購入履歴をチェックすることで、よりパーソナライズされた接客が可能です。
ポイントシステムについては下記記事で詳しく解説しているので、併せてご活用ください。
3. 「WEBで注文し、店舗で受け取る」という選択肢を作る
最近注目を集めているのが、商品の決済はECサイト側で行い、受け取りそのものは店舗側で行う仕組みです。
自宅での受け取りしかできないと、不在時は商品を受け取れず、再配達になってしまいます。
せっかく当日発送・翌日配送を実現しても、カスタマー側が商品を受け取れず、顧客満足度の上昇につながりにくくなるケースがあります。
とくに20代の購買層はECサイトの利用者が多い一方で、平日の日中は仕事で在宅していないことも少なくありません。
「WEBで注文して、店舗で受け取る」という仕組みを作ることで、ユーザーの商品受け取りの選択肢が増え、結果として顧客満足度の上昇につながります。
消費期限が短い食品などを購入した場合でも、リアル店舗があれば早めの受け取りが可能です。
ECと店舗の連携で失敗しないための4つの注意点
多くのメリットがある一方、計画なしに連携を進めると失敗に繋がるリスクもあります。事前に押さえておくべき4つの重要な注意点を解説します。
1. システム連携は最初から完璧を目指さない
顧客情報、ポイント、在庫、注文データなど、連携すべき項目は多岐にわたります。これらを一度に連携させようとすると、プロジェクトが複雑化し、莫大なコストと時間、そして失敗のリスクを伴います。まずは「顧客情報とポイントの連携」から始めるなど、フェーズを分けて段階的に進めることが成功の鍵です。
2. 店舗スタッフの評価制度を見直す
「店舗の売上が自分の評価に繋がる」という従来の評価制度のままでは、店舗スタッフがECサイトへの送客に協力的にならない可能性があります。
例えば、「店舗経由のEC売上」をスタッフの評価に加えるなど、ECと店舗の連携が、店舗スタッフ自身のメリットにも繋がるような新しい評価制度の設計が不可欠です。
3. 価格やプロモーション戦略の整合性をとる
「ECサイトのセール価格が店舗より安い」「店舗限定のノベルティがECではもらえない」など、チャネル間で価格やプロモーションに一貫性がないと、顧客に不信感を与えてしまいます。
ブランド全体として一貫した顧客体験を提供できるよう、全社的な戦略のすり合わせが重要です。
4. ECサイトの利用率を高める工夫を怠らない
店舗と連携しても、肝心のECサイトが使いにくければ意味がありません。スマートフォンでの見やすさ、決済のスムーズさ、魅力的なコンテンツなど、ECサイト自体の利便性と魅力を継続的に高めていく努力が必要です。
ECサイトと店舗連携を成功させるなら、拡張性の高いECシステムが必須
ここまで解説してきた高度な店舗連携を実現するには、ECシステムの選定が最も重要です。特に、以下のような要件を満たす必要があります。
- 顧客IDの統合やポイント連携が柔軟にできる
- 外部のPOSシステムや基幹システムと連携するためのAPIが豊富である
- 店舗在庫の表示など、独自の機能を追加できるカスタマイズ性がある
安価なASPカートではこれらの要件を満たすことは難しく、かといってフルスクラッチ開発は高額なコストがかかります。
そこでおすすめなのが、拡張性の高いパッケージ型のECプラットフォームです。豊富な標準機能と柔軟なカスタマイズ性を両立しており、コストを抑えながら自社のOMO戦略に合わせた最適なシステムを構築できます。
なかでも、弊社W2株式会社が提供するECプラットフォーム「W2 Unified」は、OMO/オムニチャネル戦略を実現するための機能を標準で数多く搭載しており、これまで数々のお客様の店舗連携プロジェクトを成功に導いてきました。
- 顧客情報/ポイント/購買履歴の統合管理機能
- 店舗在庫表示機能
- 店舗受取/クリック&コレクト機能
- POSシステムや外部基幹システムとの豊富なAPI連携実績
特に、実店舗で商品を体験したお客様を、ECサイトの定期購入(サブスクリプション)へと繋げるといった、リピート通販ならではのOMO戦略にも強みを持っています。
「ECと店舗の連携で、LTVの高い顧客を育成したい」 「自社の複雑な要件に、既存のカートシステムでは対応できない」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度W2にご相談ください。
まとめ:ネットショップと実店舗の連携で売上拡大を目指そう
改めて、「ECサイトとリアル店舗の連携を成功させる3つのポイント」をまとめます。
- ECサイトとリアル店舗のシナジーを意識する
- 顧客情報とポイントシステムを連携させる
- 「Webで注文し、店舗で受け取る」という選択肢を作る
ぜひ本記事の内容を参考に、オムニチャネル化を進めてみてください。
本資料では、オムニチャネルの成功事例や戦略などを紹介しています。資料は無料でダウンロードできるので、ぜひご一読ください。
ECサイトと実店舗の連携に関するよくある質問
Q: ECサイトと実店舗の連携を始めたいのですが、何から手をつけるべきですか?
A: まずは「顧客情報とポイントシステムの一元化」から始めるのがおすすめです。これにより、ECと店舗の双方で顧客データを蓄積・分析できるようになり、その後の在庫連携や相互送客といった施策の効果を最大化するための重要な基盤となります。
Q.: 店舗スタッフの評価は店舗の売上が基準ですが、ECサイトへの送客に協力してもらうにはどうすれば良いですか?
A: 店舗スタッフの評価制度を見直すことが重要です。「店舗経由のEC売上」を個人の評価に加えるなど、ECへの貢献がスタッフ自身のメリットにも繋がる仕組みを作ることで、モチベーションを高め、全社一丸となって連携に取り組むことができます。
Q: ECサイトと店舗で価格が違う場合、連携する上で問題はありますか?
A: はい、問題になる可能性があります。チャネル間で価格やプロモーションに一貫性がないと、お客様に不信感を与えてしまう恐れがあります。ブランド全体として一貫した顧客体験を提供するため、ECと店舗の担当者が連携し、戦略の整合性をとることが重要です。