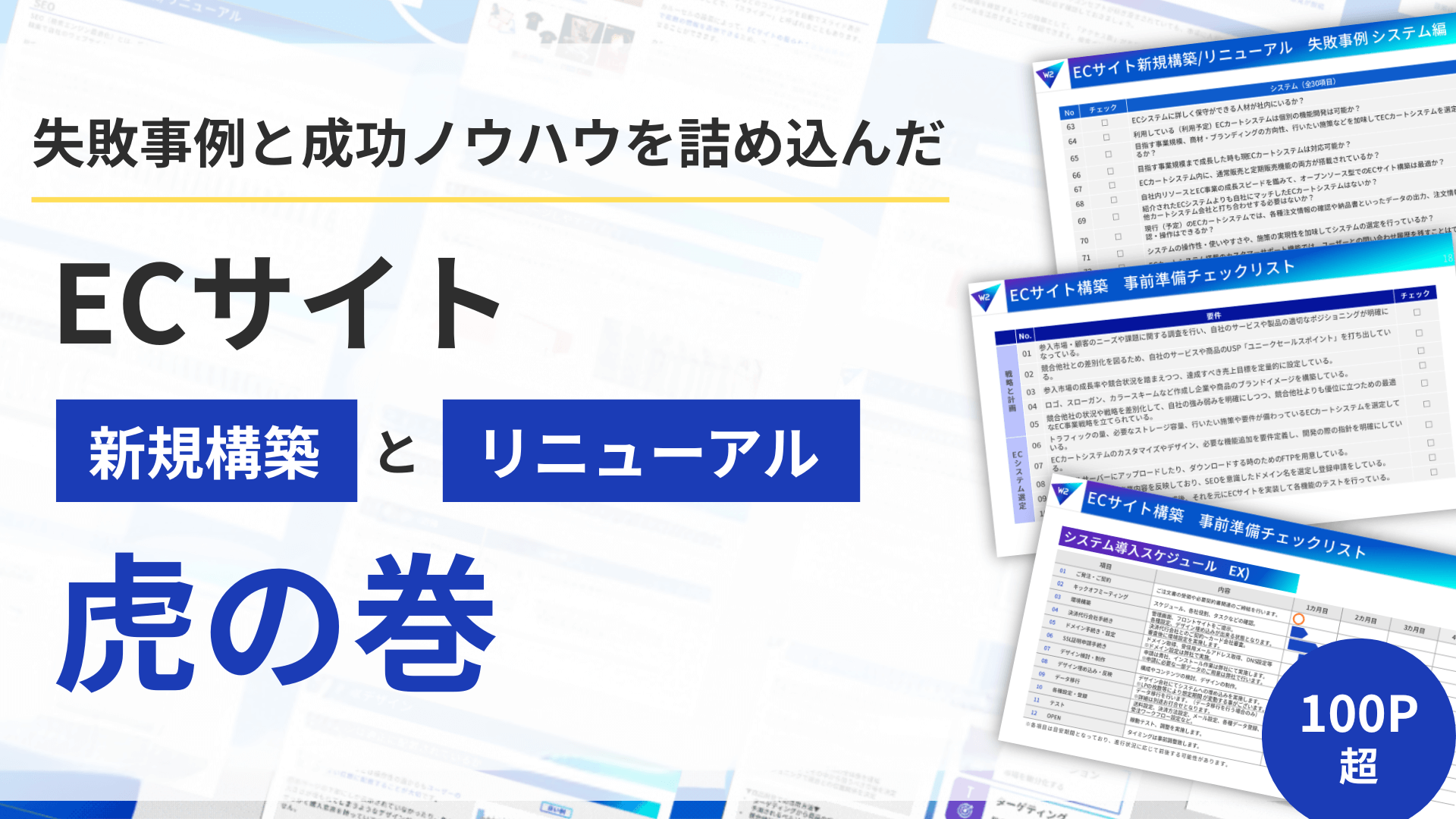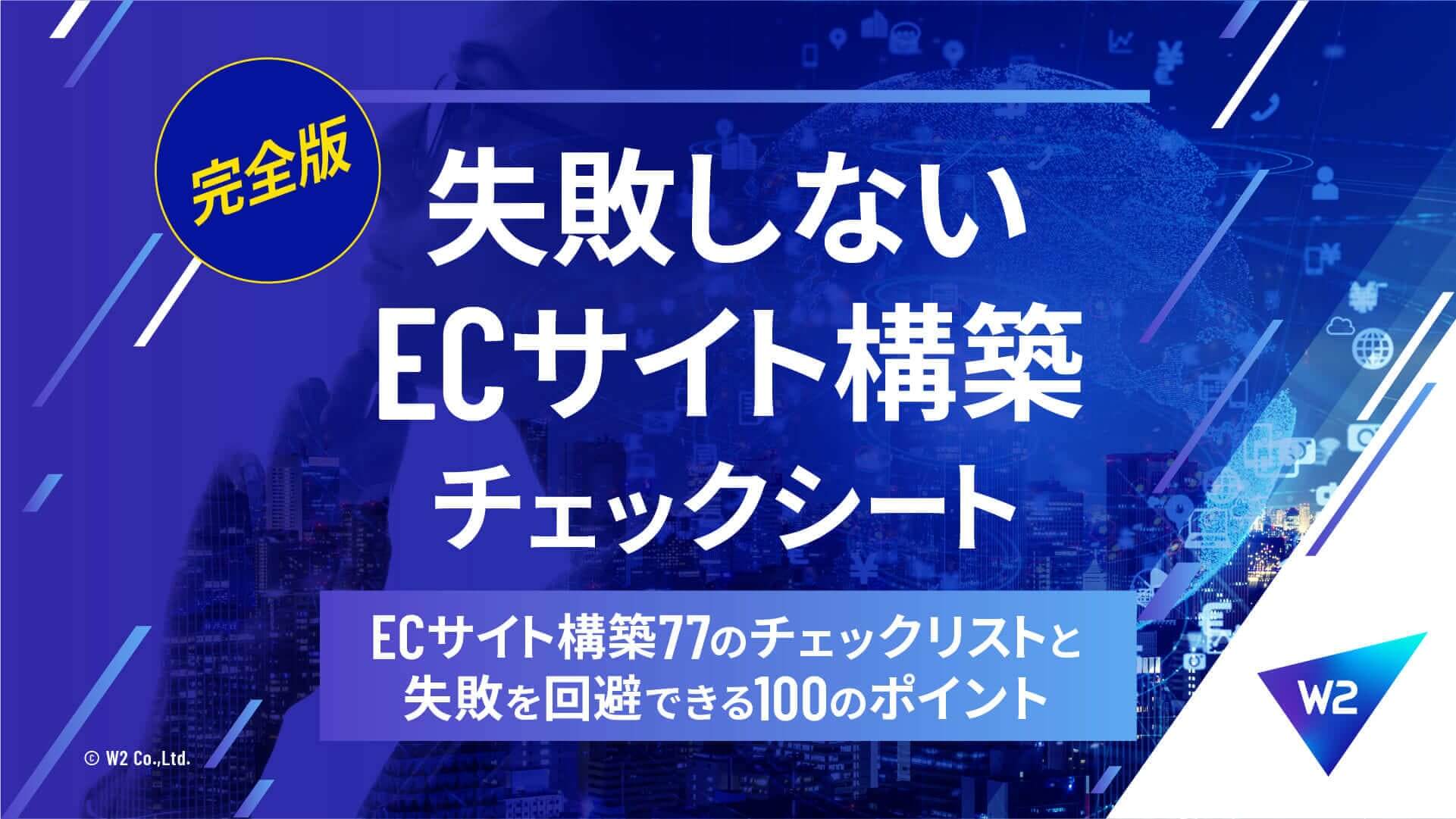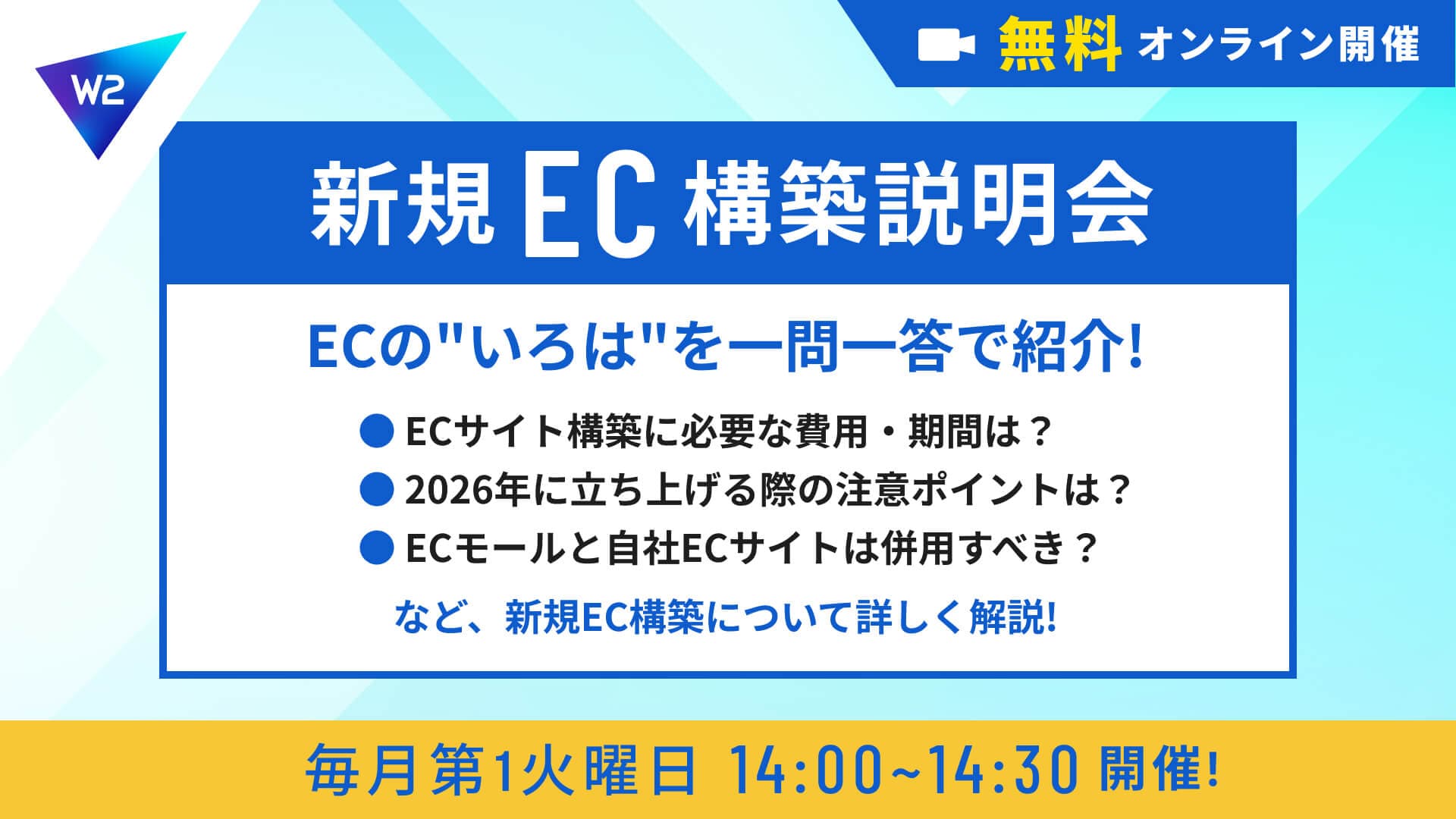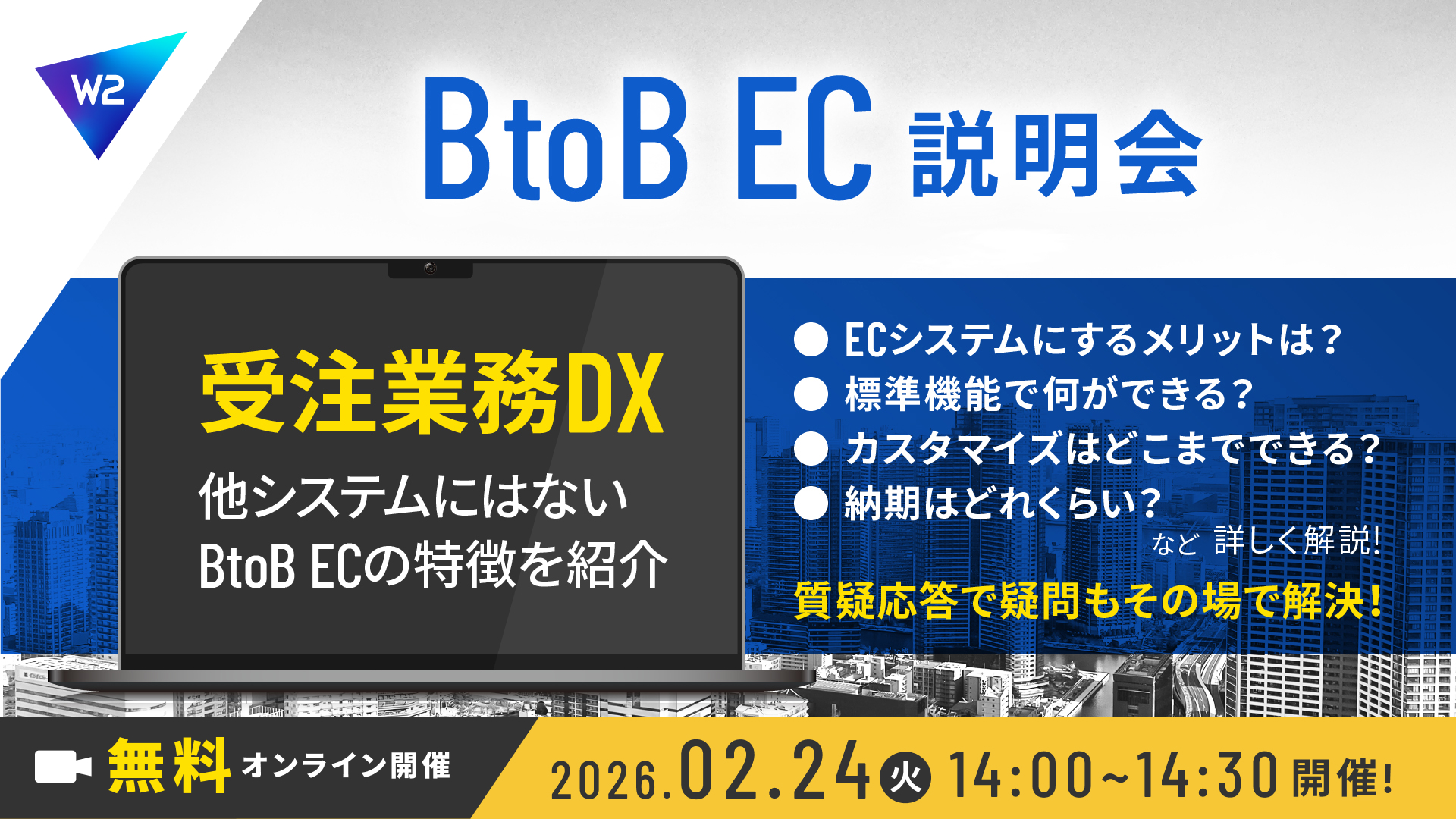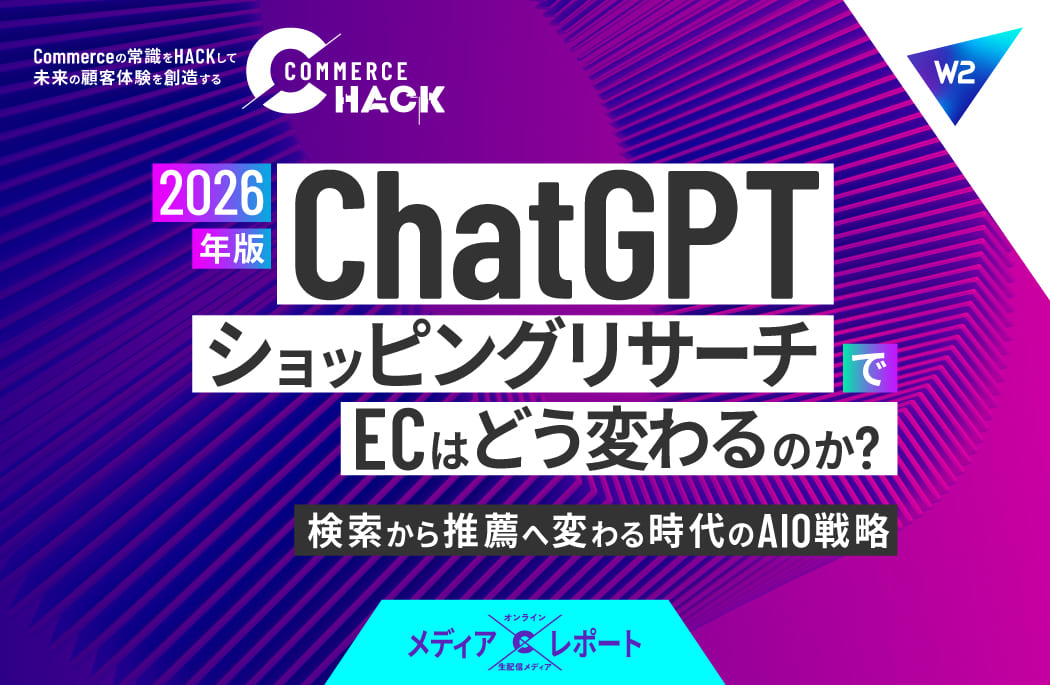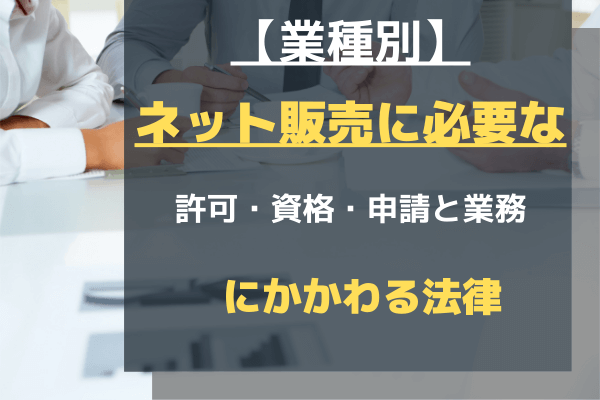
・ネット販売にはどんな許可や資格が必要なの?
・ネットショップ運営に必要な手続きを知りたい
このようなお悩みはありませんか?
運営に必要な許可申請や資格取得を怠ると、トラブルや法律違反になるおそれがあります。
そこで本記事では、ネットショップ運営に必要な許可・資格などを業種別に解説します。
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
ネット販売の業種によっては許可・申請・資格が必要
実店舗で商品を売る場合と同じように、ネットショップで商品を売る場合でも、業種によってはさまざまな許可や申請、資格が必要となることがあります。
これらの手続きを後回しにしてしまうとトラブルに発展してしまったり、ショップの運営ができなくなるおそれもあります。
特に食品や酒類、医薬品、輸入品などを販売する場合は、事前の許可や申請が必要です。
ここでは業種別にネット販売に必要な許可や資格などを業種別に紹介します。
以下のお役立ち資料ではネットショップ開設について詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。
①食品のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
食品のネット販売をする場合、食品衛生法にもとづいた営業許可と食品衛生責任者の資格が必要となります。ただし、品目によっては許認可が必要ない場合や、自治体の条例などで届出が必要となる場合があります。
以下のお役立ち資料では食品のネット販売について詳しく解説しています。是非合わせてご覧ください。
食品衛生責任者は、食品に関する事業運営には必要な資格で、食品衛生法に定められた営業許可施設ごとの配置が義務付けられています。
許認可の要不要は、製造や加工をするかどうかで決まります。
製造や加工を施してネット販売する場合は許認可が必要となります。
主に飲食店や喫茶店、菓子製造業、アイスクリーム製造業、食肉販売業、魚介類販売業が対象となります。
また、つけもの製造業や製菓材料等製造業なども、自治体によっては許認可が必要となります。
それ以外の業種でも、ケーキやジュースやジャム、魚介類や乳製品など製造されたものを小分けしてパッケージし直す場合に、営業許可が必要な場合もあるので気をつけましょう。
許認可が不要なのは、農作物を直接配送する場合や、スナック菓子や缶詰などパッケージされた商品を開封することなく販売する場合です。
弁当や惣菜パンなどの完成品を仕入れて販売するだけの場合も許認可は必要ありません。
営業許可や食品衛生責任者の届け出は、食品衛生法に基づく場合であれば営業所を管轄する保健所へ、食品衛生責任者の資格が必要な場合は各都道府県の食品衛生協会や特定市における食品衛生協会へそれぞれ申請します。
②古物商のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
中古品を仕入れて販売するためには、古物営業法にもとづいた許認可が必要で、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
「古物」とは、一度使用されたものや使用のため取引されたものをさします。美術品や商品券なども「古物」に含まれます。
ただし、自分で使用するために購入したものを販売する場合は、「古物」に含まれないため許認可の必要はありません。
また、無償で譲り受けたものや手数料を受け取ったうえで回収したものを販売する場合も許認可は不要です。
ただし、転売目的で購入した場合は「古物」にあたるため許可が必要です。
物を買い取って修理して販売する場合や、使える部分を販売する場合、レンタルする場合も許認可が必要となります。
以下の13種類の「古物」を取り扱う場合は、営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を届け出なければなりません。
- 衣類
- 機械工具類
- 金券類
- 事務機器類
- 時計・宝飾品類
- 自転車
- 自動車
- 自動二輪車・原動機つき自転車
- 写真機類
- 書籍
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 美術品類
③健康食品のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
健康食品の場合は、特別な許認可は必要ありませんが、一般的な食品を取り扱う際に適用される条例や法令に従って販売します。
しかし、医薬品なのか健康食品なのかを明確にして販売する必要があります。
医薬品の場合は、「医薬品医療機器法(薬機法)」に従い販売しなければなりません健康食品にもかかわらず医薬品と誤解されるような効果や効能の表示は許されません。
また、健康食品の中には「保健機能食品」というものがあります。
「保健機能食品」は一般の健康食品とは違い、身体の生理機能に調整する働きについて効果がある食品のことです。
その種類の中には「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があります。
特に「特定保健用食品(トクホ)」は、製造事業者が消費者庁長官の許可をもらったものでないと表示することができません。
健康食品を取り扱うのであれば、その表示方法については十分注意しましょう。
④酒類のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
酒類のネット販売では、アルコール度数が1%以上の酒類やみりんを販売する場合は酒税法にもとづいた販売免許が必要です。アルコール度数が1%未満であれば許認可の必要はありません。
許認可のいらない主な商品としては「ノンアルコールビール」「ブランデーケーキ」「ウイスキーボンボン」などがあります。
お酒の販売免許は「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類になります。
もし卸売りをする場合は、「洋酒卸売業免許」と「輸入卸売業免許」、「輸出卸売業免許」、「全酒類卸売業免許」、「自己商標卸売業免許」、「ビール卸売業免許」など品目や業務内容により免許の内容が異なるので注意が必要です。
個人を対象としたネットショップでは「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」で販売することが可能な場合が多いです。
「一般酒類小売業免許」は販売できる酒類の制限がなく、同一都道府県であればこの免許を持っているだけで通信販売が可能となります。
しかし、酒類をネット販売する場合でもお酒を実際に販売している店舗が必要でなうえ、酒類販売管理者や責任者の選任・届出が必要となります。
「通信販売酒類小売業免許」の場合は販売できるお酒に制限が加えられます。
また、販売する場所にも注意が必要です。
酒類の製造や販売免許を受けている販売場や酒場、料理店と同一の場所であってはなりません。
こちらも、酒類販売管理者や責任者の選任・届出が必要となります。
このようにお酒を販売する際の許可申請の条件は非常に複雑で多岐にわたります。
そのため、自分で申請しようと思っている場合でも、一度税務署や許認可申請の専門家である行政書士に相談したほうがよいでしょう。
⑤医薬品のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
医薬品の販売は薬機法や薬剤師法により規制されており、医薬品の種類によりネットショップで販売することができるかどうかが異なります。
医薬品の中には「医療用医薬品」、「要指導医薬品」、「一般用医薬品」があります。
ネットショップで扱うことのできる医薬品は「一般用医薬品」です。
「一般医薬品」の中でも「第一類医薬品」と「第二類医薬品」と「第三類医薬品」でわけられます。
「第一類医薬品」をネット販売できるのは薬剤師のみで、「第二類医薬品」は薬剤師免許を持ったスタッフの在籍が販売条件です。
また、ネットショップで販売するための主体は薬局に限られているため、医薬品をネットショップで販売するには薬局を開設しなければなりません。
その他にも「医薬品販売許可」、「特定販売(インターネット販売許可)」が必要となります。
申請先は所轄の保健所や各都道府県の薬事課となるので、分からないことがあれば一度相談してみましょう。
⑥化粧品のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
化粧品も薬機法により規制を受ける品目で、化粧品もその種類により許認可が必要な場合とそうでない場合に分けられます。
化粧品は化粧品と薬用化粧品に分かれており、薬用化粧品は「医薬部外品」とされています。
化粧品の製造には全く関係せず、製造した化粧品を仕入れて改変することなくそのまま販売するような場合は許認可が必要ありません。
しかし、化粧品の製造を自社で行う場合は許認可が必要となります。
この場合、化粧品は「化粧品製造業許可」、薬用化粧品は「医薬部外品製造業許可」を取らなければなりません。
また、化粧品の製造は自社で行い他社で販売する場合や、他社に販売を委託する場合なども許可が必要です。
この場合も、化粧品であれば「化粧品製造業許可」、薬用化粧品であれば「医薬部外品製造業許可」を取らなければなりません。
化粧品や薬用化粧品の申請先は、所轄の保健所や各都道府県の薬事課となります。
化粧品の販売をネットショップで行おうと考えているのであれば、一度相談してみた方がよいでしょう。
⑦ペットのネット販売類に必要な許可・申請・資格・法律
ペットをネット販売する際に場合、特定の愛護動物の取り扱いは、動物愛護法の規制を受けることがあります。
魚類や昆虫類、もしくはペット用品やペットの餌をネットショップで販売する場合は、許認可を受ける必要はありません。
しかし、哺乳類や鳥類爬虫類などの動物を扱う場合は、畜産や実験などを行う場合を除いて許認可が必要となる場合があります。
営利を目的としてペットを取り扱うときは「第一種動物取扱業」、非営利の活動によりでペットを取り扱うときは「第二種動物取扱業」の許可を受けなければなりません。
また、事業所ごとに常勤職員の中から1名以上「動物取扱責任者」を配置する必要があります。
申請先は、ネットショップの所在地とする都道府県知事、又は政令指定都市市長となります。
しかし、東京都の場合は「動物愛護相談センター」、大阪府の場合は「動物愛護管理センター」となるためなど地域によって名称が異なるのでその点においては注意しましょう。
⑧輸入品のネット販売に必要な許可・申請・資格・法律
輸入品をネット販売する場合は、通常ならば許認可のいらない品目でも許可や申請が必要となることがあります。
食品や添加物、乳幼児を対象としたおもちゃ、酒類を取り扱う場合は、食品衛生法に基づき検疫を受けなければなりません。
また、精肉や食肉加工品を取り扱う場合は、輸出国政府機関にある検査証明書が必要な場合があります。
野菜や果物、ドライフラワーなどの植物も輸出国の政府機関による栽培地検査証明書が必要です。
また、動物の毛皮や革製品類を輸入する場合は際にも注意が必要です。
ワシントン条約により輸入が可能な動物が指定されているため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
上記以外にも、販売する際の商品表示方法などにおいて規制を受けるケースがあります。
W2はあらゆる業種のネット販売を支援!
「ネット販売をはじめたい」と思っても業種や販売品目によって、さまざまな法律や許可、申請、そして資格が必要となるため、多くの知識や手続きの手間がかかります。
これらをサイトの構築や商品の準備と並行しておこなうのは一苦労です。そんなときにネット販売の経験豊富な人に相談できれば安心ですよね。
W2はあらゆる業種のネットショップ運営をゼロから支援してきた実績が豊富なので、「ネット販売の立ち上げ方がわからない」「何を売るか決めていない」という状態からでもネットショップの立ち上げをサポートできます。
もちろん、法律や許可、申請、資格といった専門知識もカバーしているので、ネット販売を開始したあとに「実は許可が必要だった」といったトラブルも防げます。
また、業種にあわせたサイトデザインや機能を提供しているため、売りたい商品に最適な環境でネット販売をおこなえます。
まとめ:ネット販売の許可や資格の手続きを事前に進めておこう
改めて、本記事のポイントをまとめます。
- 業種によって、必要な許可や資格などが異なる
- 例えば食品の場合、営業許可と食品衛生責任者の資格が必要
- スムーズに運営するために事前に手続きを済ませることが重要
ぜひ本記事の内容を参考に、ネットショップ立ち上げの準備を進めてみてください。
なお、ネット販売には数多くのやるべきことがあり、手順を間違えるとその後の運営や成果に大きなダメージを与えるおそれがあります。
そこで下記資料では、実際にネット販売を行っている担当者から聞いたECサイト構築における失敗事例を100個とECシステムの選定チェックポイントを解説/一覧化しました。
資料は無料でダウンロードできるので、ECサイトの構築/リニューアルを検討している方はぜひあわせてご一読ください。