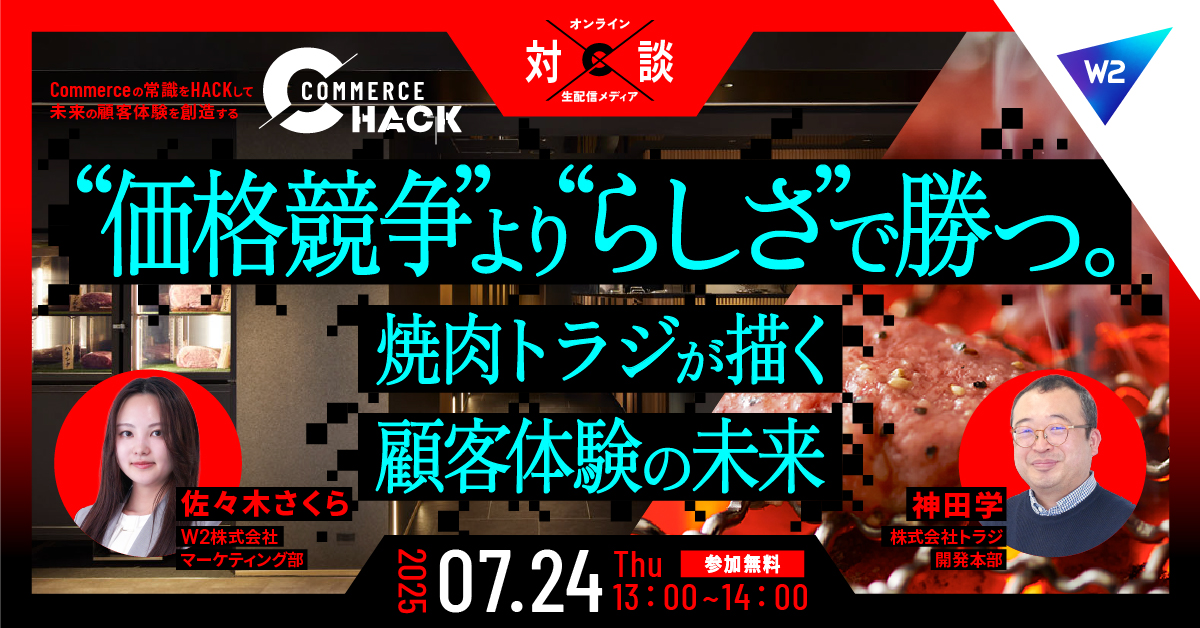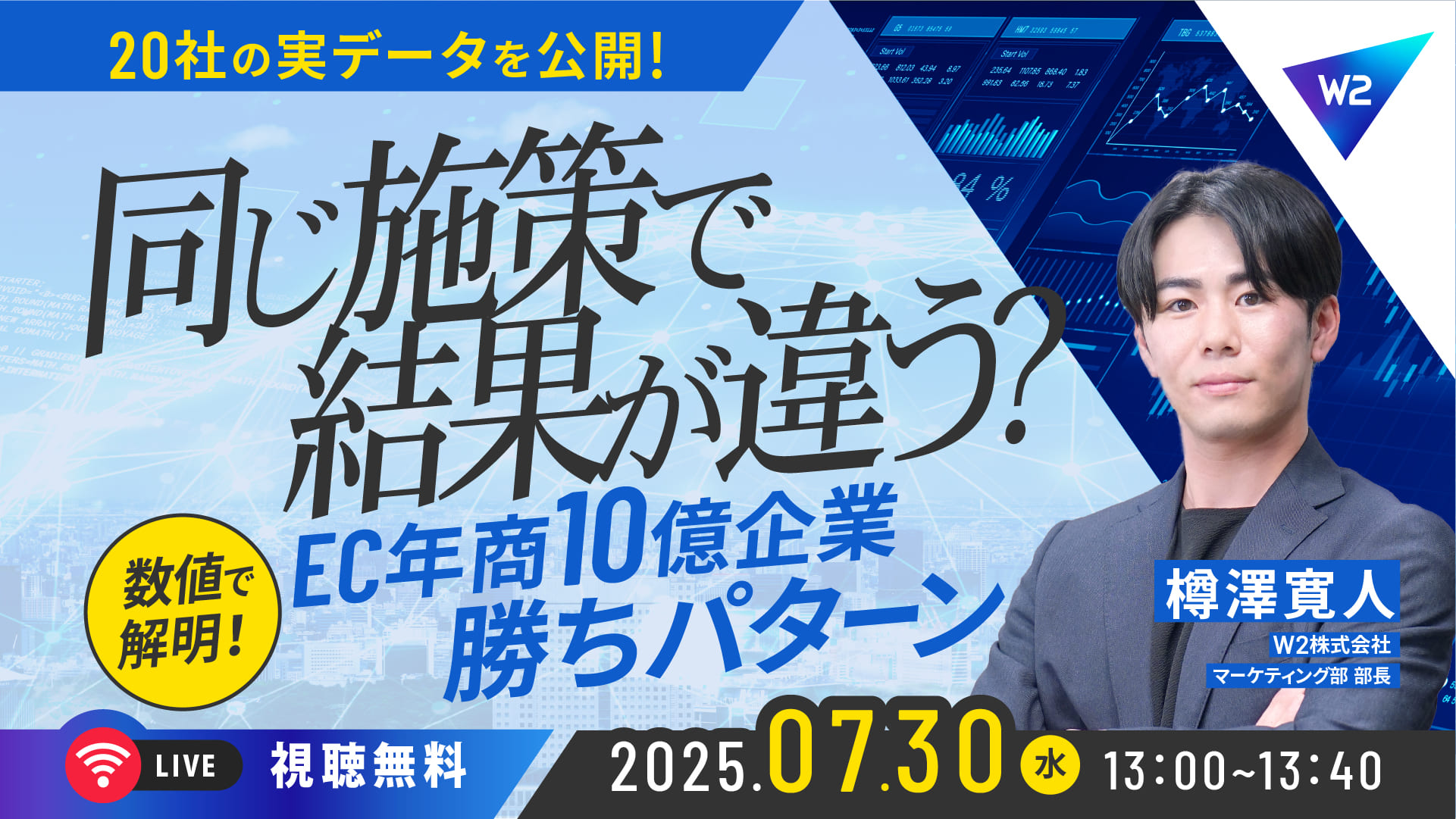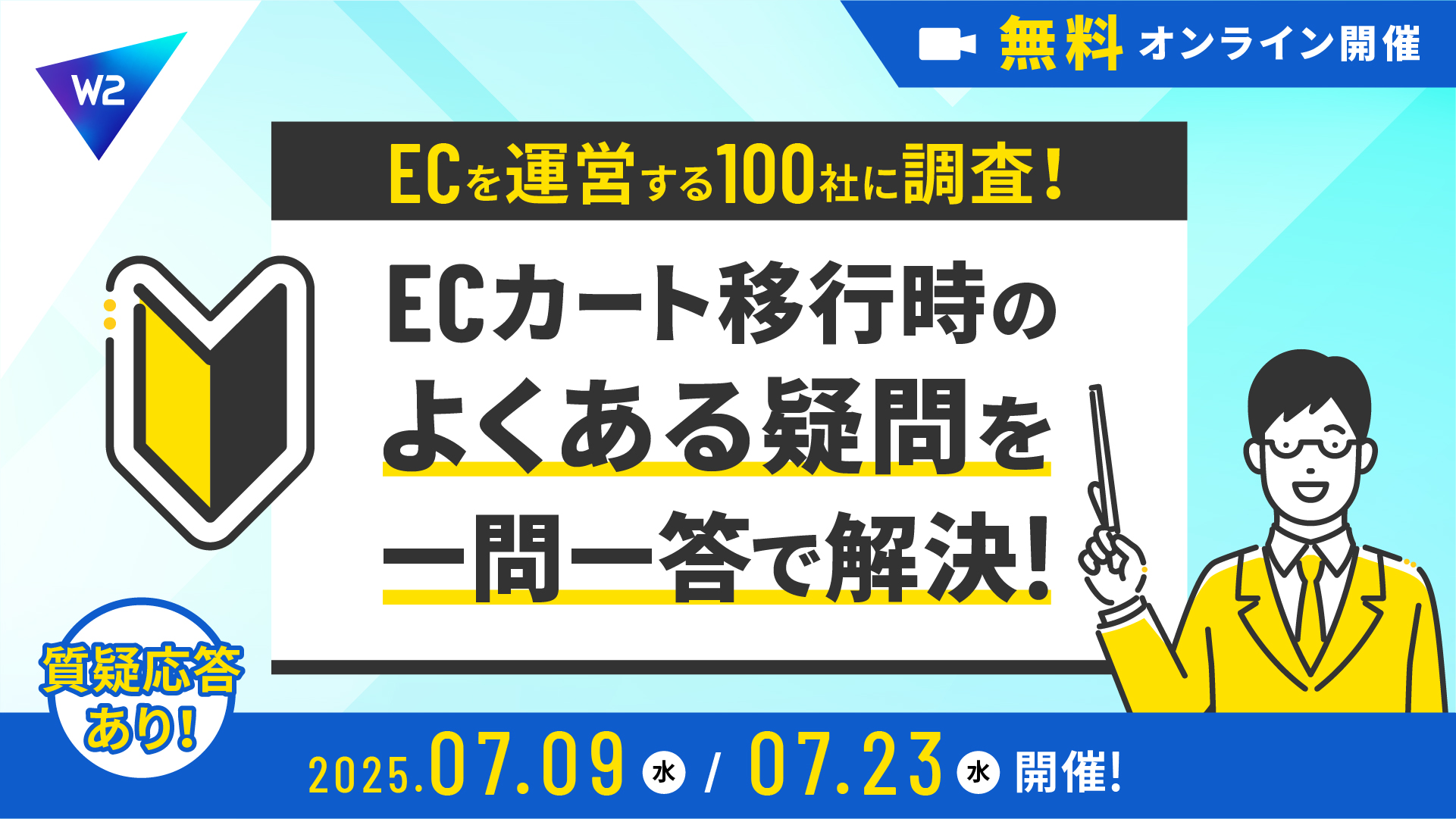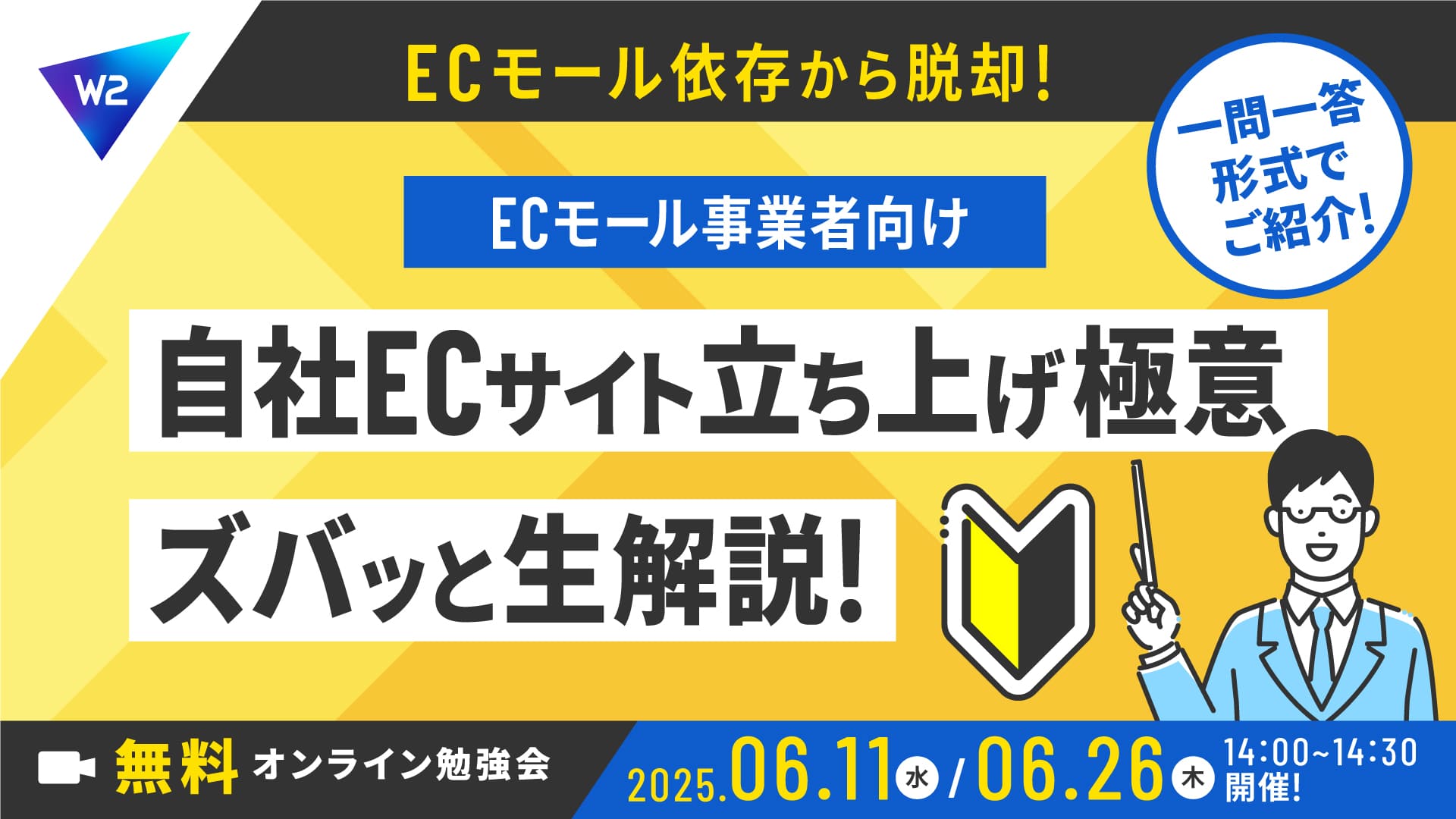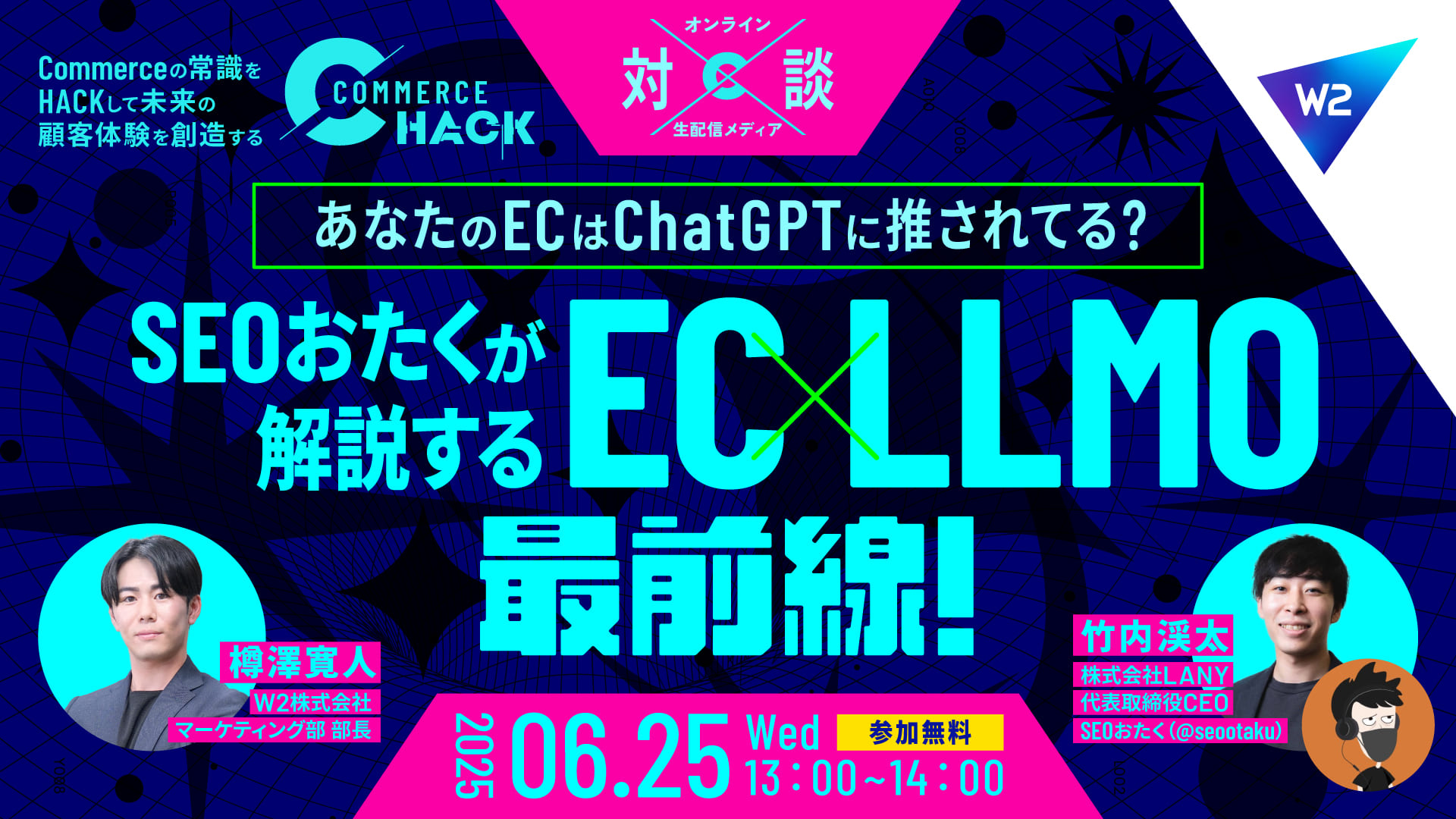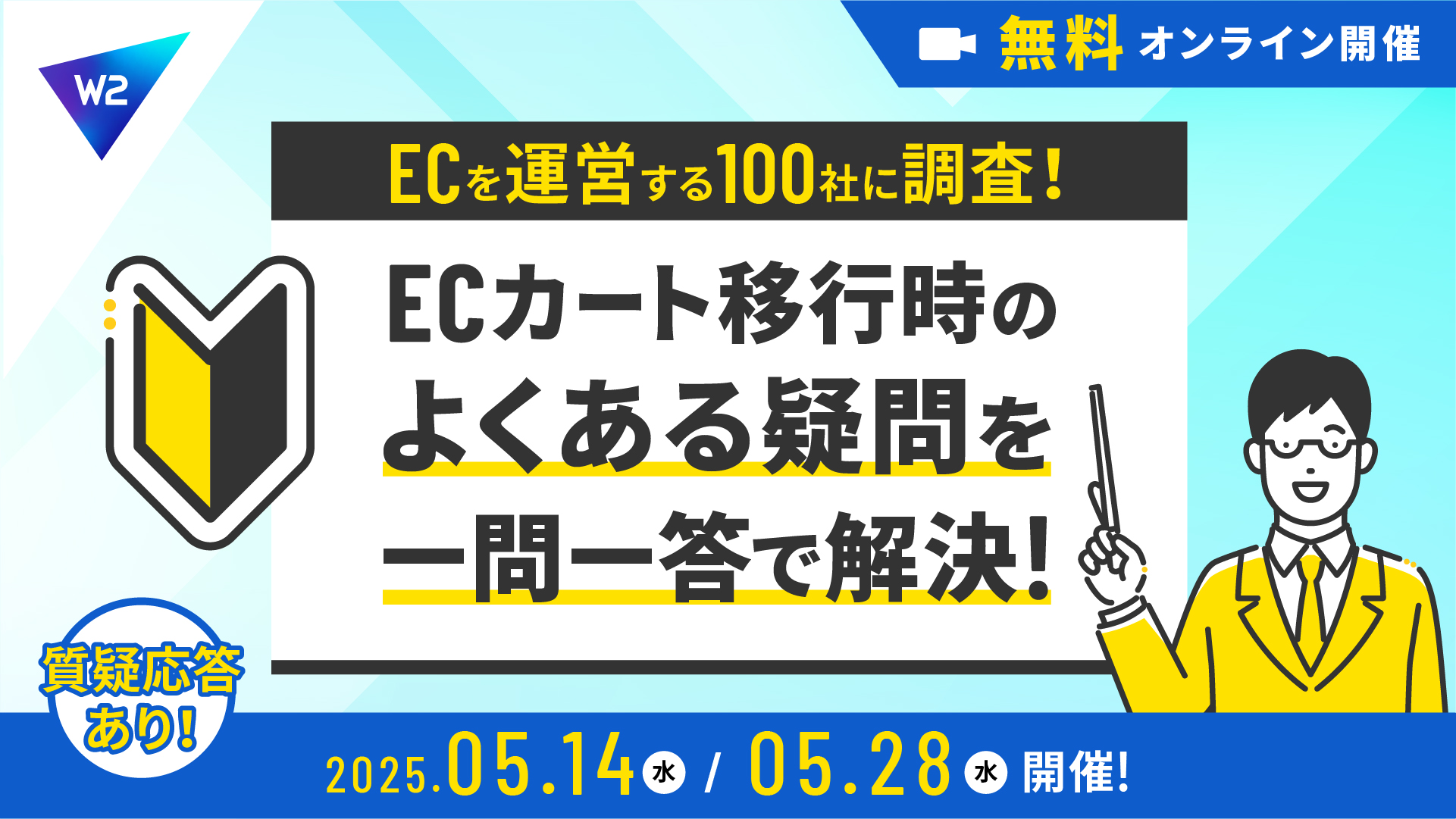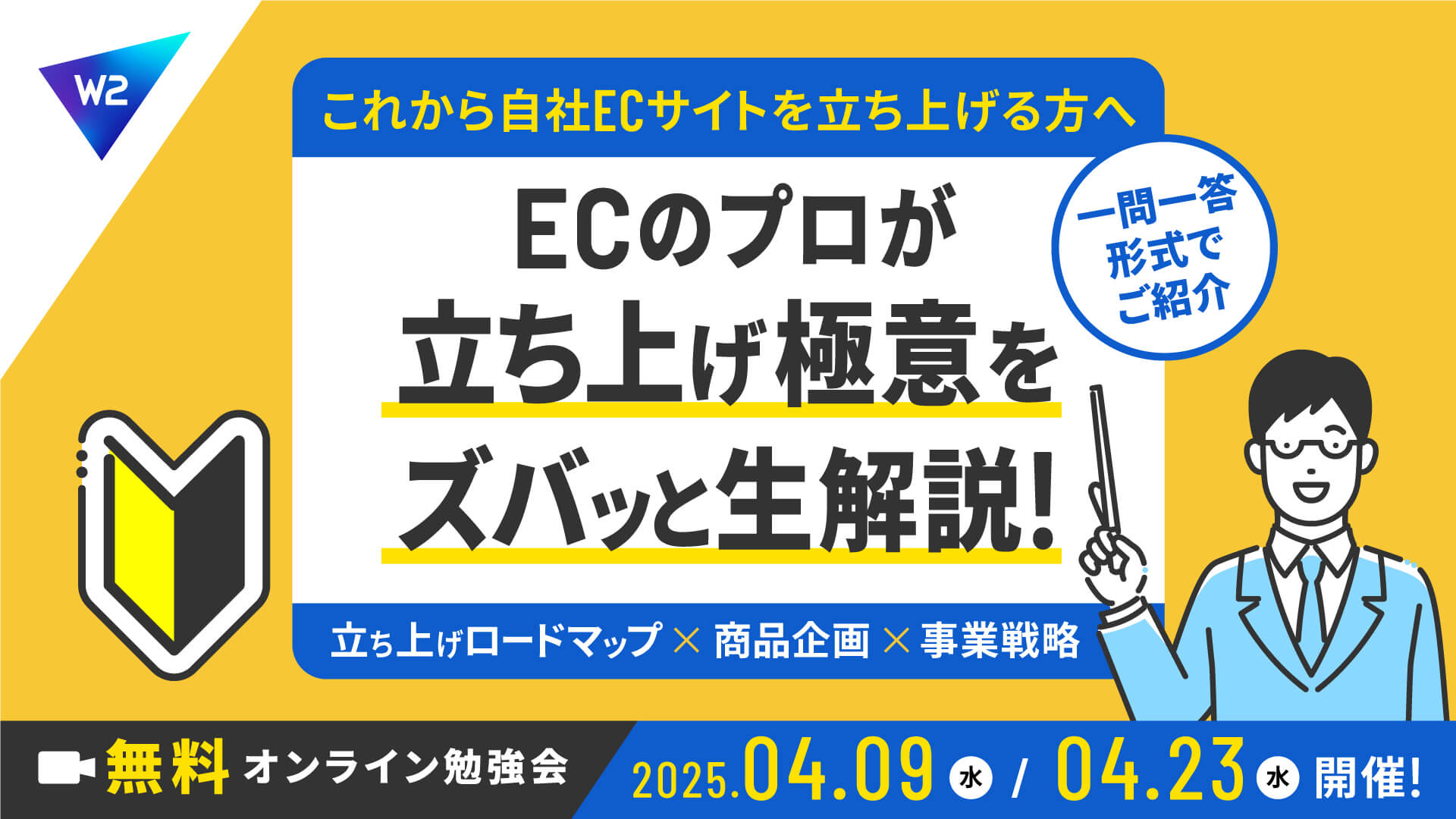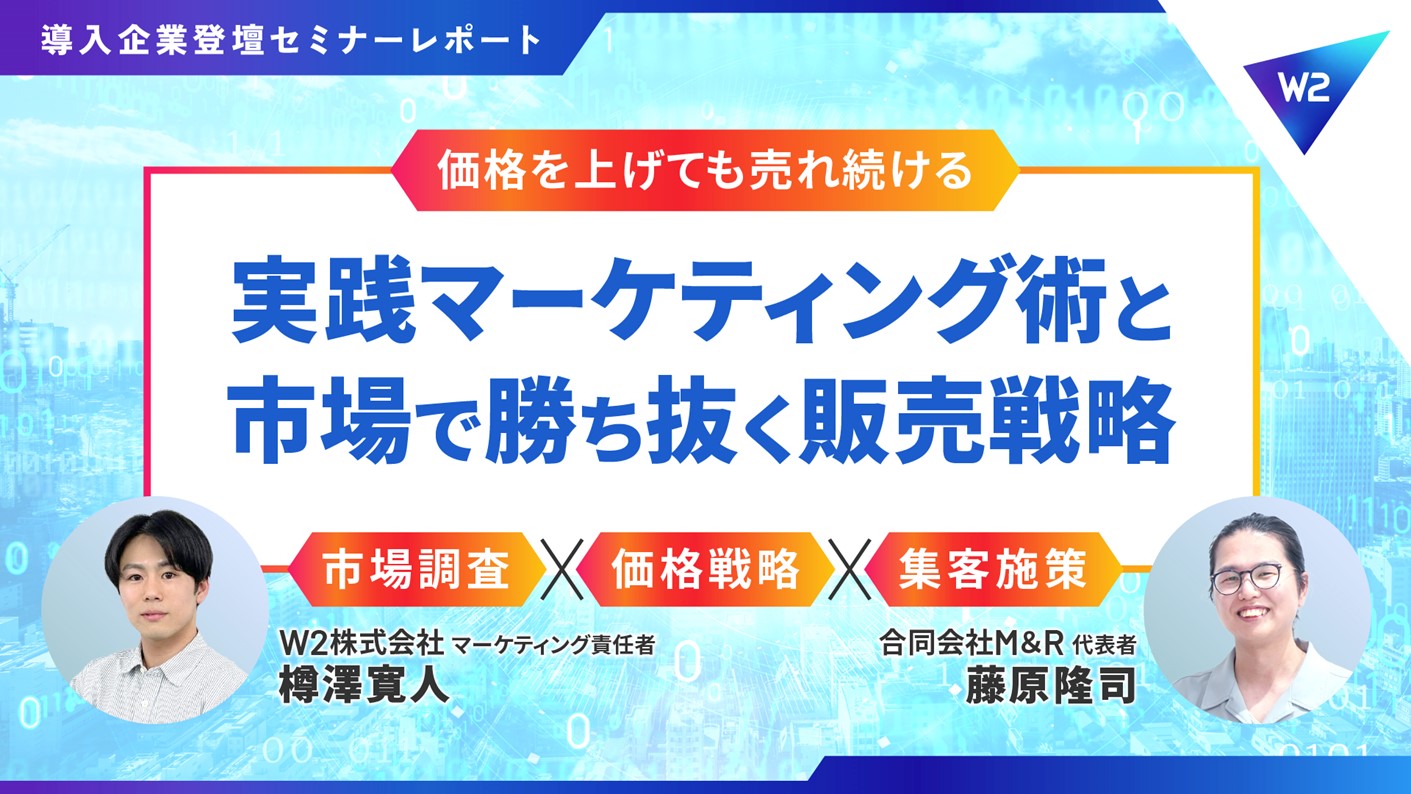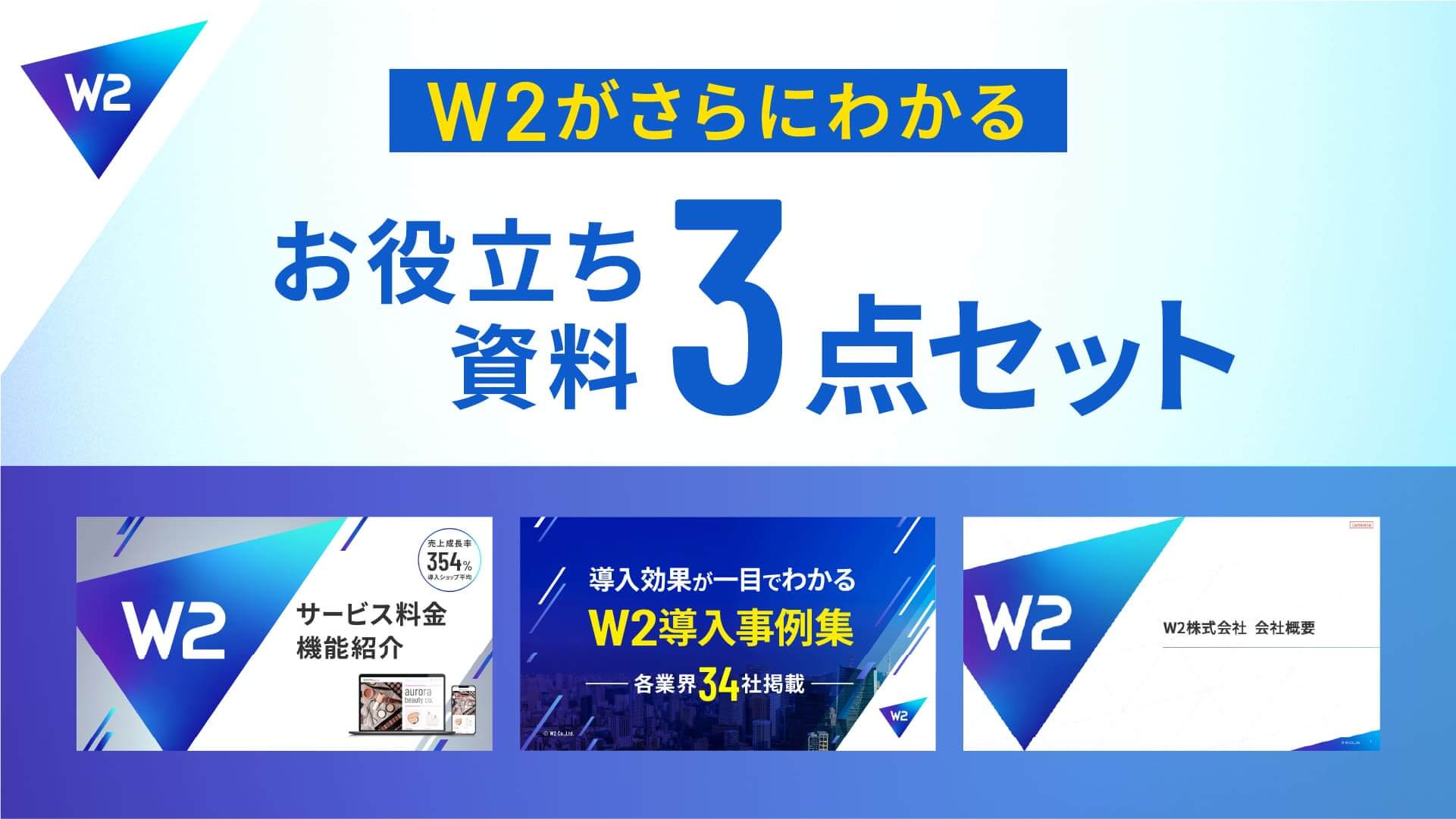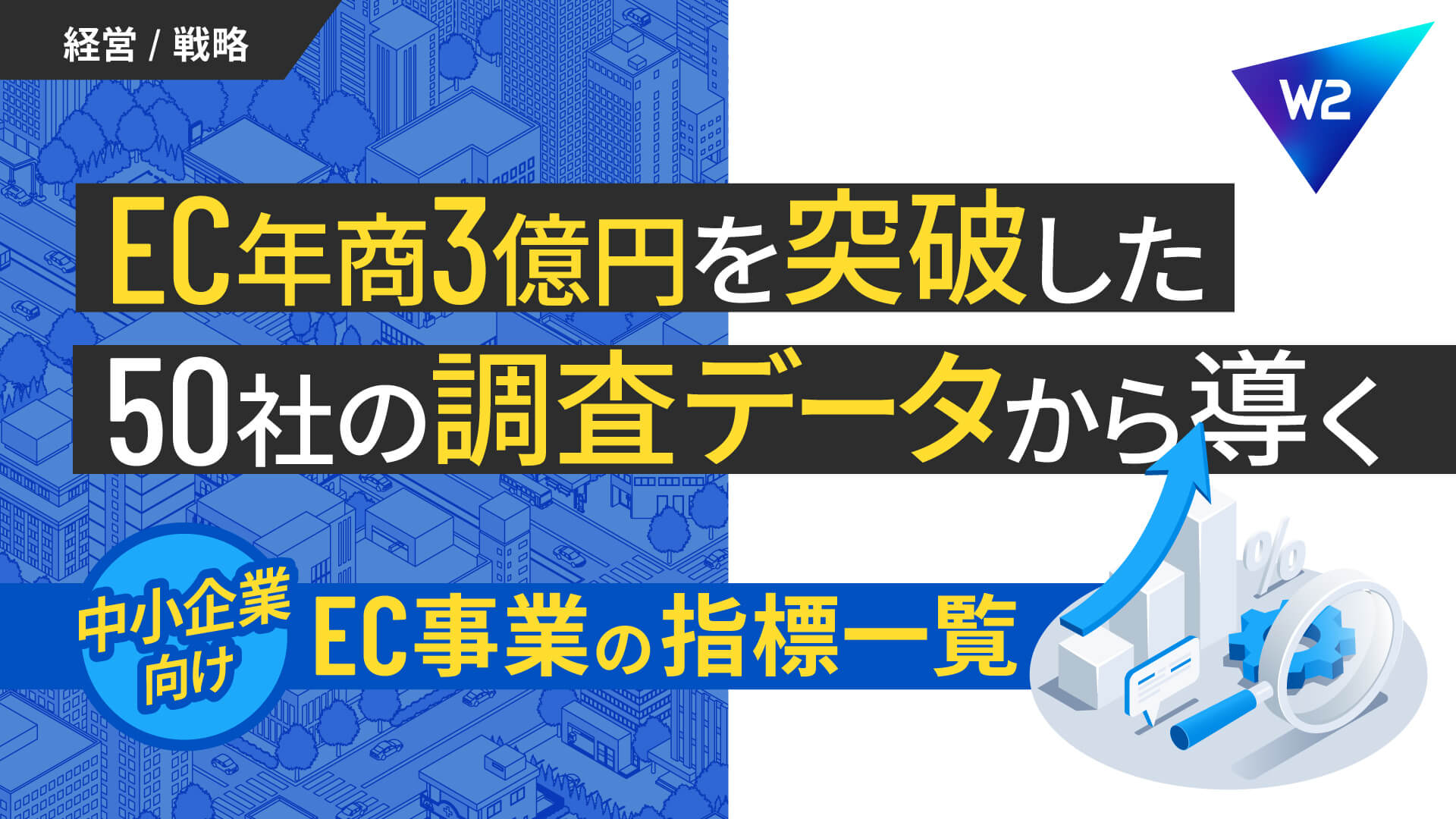ECサイト・ネットショップの倉庫はどう選ぶ?選び方・比較のポイント
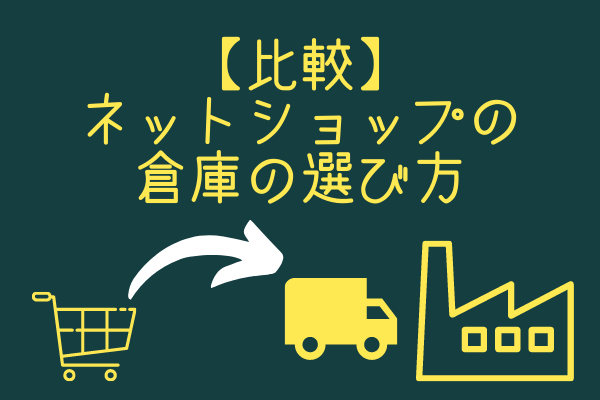
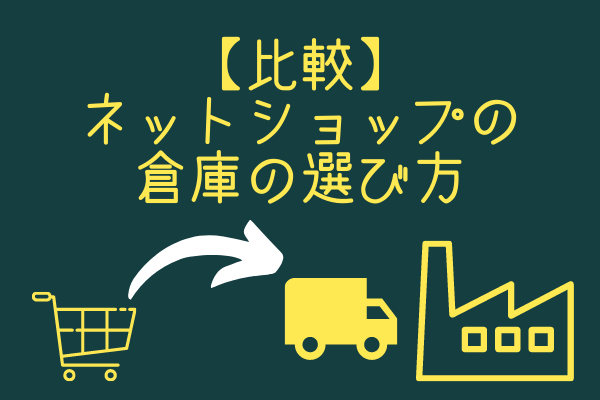
ECサイト・ネットショップの倉庫はどう選ぶ?選び方・比較のポイント
ネットショップやECサイトを運営するのであれば、商品の保管場所が必要です。
また、梱包から発送までを担える物流倉庫も不可欠だといえるでしょう。
ECサイトの物流にはさまざまな特徴があるので、倉庫を選ぶときの参考にしたいものです。
この記事では、ネットショップやECサイトの物流倉庫を選ぶポイントについて解説していきます。
W2は、「ECサイト/ネットショップ/通販」を始めるために必要な機能が搭載されているシステムを提供しています。
数百ショップの導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください!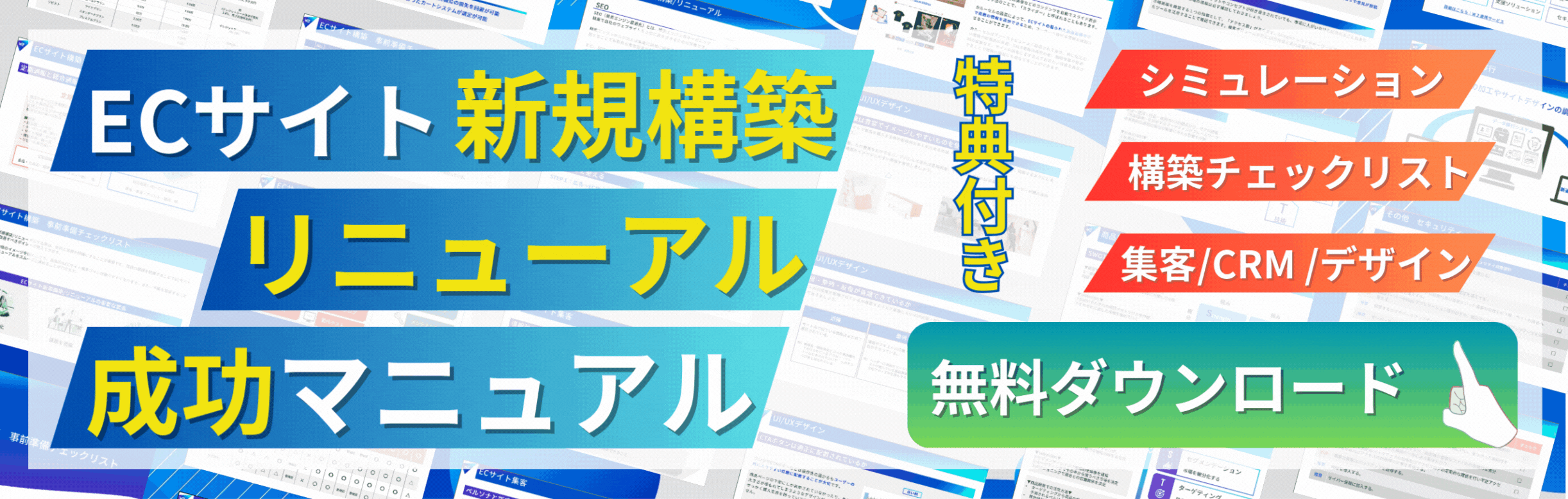
※本資料は上記バナーからのみダウンロードできます。
EC物流の特徴
一般的に「EC物流」を用いる場合、「電子商取引に関連する物流」を指しています。
そしてEC物流の主流は「BtoC型」のビジネスモデルです。
ECサイトを運営する企業から消費者に、商品を安全に送り届ける仕組みが重要視されています。
ちなみにECサイトは「自社サイト」と「モール型サイト」の2種類に分けられます。
自社サイトとは、企業がサイトを立ち上げて運営していく形です。
自由度は高いものの、開発費やランニングコストが高くなるなどのデメリットがあります。
一方、モール型はAmazonや楽天市場など、大きなサイトの中で複数の出店が行われている形式です。
出店までに手間がかからないうえ、サイトの知名度を利用できるのもメリットです。
EC倉庫・物流のよくある悩み
企業によっては倉庫を用意せず、自社のスペースだけで商品を保管しているケースも珍しくありません。
ただしこのやり方だと、商品数が増えるにしたがってスペースが足りなくなってしまうというデメリットが生まれます。
また自社の従業員に、在庫管理や出荷作業を任せなくてはならないのも問題です。
物流に時間を割かれているうちに、コア業務がおろそかになりかねません。
そして忙しい中で作業をしていると、どうしてもミスが発生します。
在庫の数が合わなくなったり、受注情報を見逃したりすることもあるでしょう。
さらに定期通販であれば、購入回数で顧客ランクが変動するなどの煩雑なシステムが導入されていることもありえます。
顧客ランクに応じた処理まで専門外の従業員にさせると、業務効率はより下がっていきます。
物流の重要性
いかに手間であろうと、物流の作業はおざなりにできません。
たとえば梱包や発送は、顧客満足度に大きく影響する工程です。
これらを適当に済ませていると、配送状況が悪化して顧客からの評価を落としかねません。
またEC物流の効率性が下がると、競合他社との差が開いていきます。
顧客がライバルに奪われてしまい、収益も落ち込んでいくでしょう。
そのため成功しているECサイトは、物流システムを徹底して整えてきました。
たとえばAmazonは、バックヤードの自動化を行い、365日24時間体制で稼働させています。
システム化されている物流と、自社スタッフの主導に頼っている物流とでは、処理能力が格段に違うといえるでしょう。
似たような商品を販売していても、顧客の感じる満足度は大きく変わるのです。
1. 物流の流れ
商品が消費者に届くまでの流れを知っておくと、倉庫を選ぶ際のポイントを理解しやすくなります。
さらに、「どこに時間を取られてしまうのか」を考えるきっかけにもなるでしょう。
ここからは、EC物流の構造を解説していきます。
2. ECの受注処理など
原則としてECサイトでの受注は、ネット上で行います。
つまり物流の中には、受注や会計の処理をネット上でできる機能が組み込まれていなければなりません。
また受注だけでなく、在庫管理も情報システムで進めていきたいところです。
倉庫を用意した後でこれらのシステムを選定し、本格的に導入する作業を始めるべきです。
3. 検品・入庫
検品・入庫は、正確な在庫管理のために欠かせない工程です。
検品では倉庫に届いた商品の種類や中身、個数などを細かくチェックしていきます。
万が一、発注ミスや配送ミスがあればその時点で指摘しなければなりません。
また不良品に気がつくチャンスでもあります。
品質を均一に保つには、非常に重要な作業です。
一方、入庫とは商品を倉庫に置いていく作業です。
単純な作業でありながら、決められた場所に決められた個数を入庫するのは緻密な計算に基づいて行われます。
さらに入庫時に商品を傷めないよう、気をつかわなければなりません。
検品や入庫が正しく行われれば、出荷がかかったときにすぐ高品質の商品を配送ルーツに乗せられます。
これらの作業も、バーコードシステムによって一元管理できる場合があります。
4. ピッキング
受注された商品を、倉庫内から取り出す作業です。
商品数が少ない倉庫であれば、ピッキングは決して難しくはありません。
人力でも十分にまわしていけます。
商品数が多くなってくると、人が倉庫を走り回ってピッキングするのはたいへんな労力です。
そもそも何がどの棚に保管されているのか、把握するだけでも一苦労といえます。
そこでEC物流では、ピッキングもシステム化するケースが増えてきました。
注文された品のある棚をシステムの画面上で確認し、ピッキングを行います。
5. 梱包・出荷
ピッキングされた品は包装されたり、段ボールなどの梱包資材に詰められたりして出荷可能な状態に加工されていきます。
包装は時期や顧客レベルに合わせて用紙が変わることも多く、現場と経営陣との情報共有が不可欠です。
また梱包する品物は、商品だけと限りません。
パンフレットやチラシを入れることもあるでしょう。
注意したいのは、クーポンなどの特典を入れ忘れないことです。
消費者が「もらえる」と思っていた特典が入っていないと、クレームを招くケースもありえます。
梱包や包装は見た目も重要です。
たとえ中身に傷がついていなくても、包装紙や箱が汚れていては消費者に不愉快な思いをさせます。
それをきっかけに企業への信用を失ってしまう消費者もいるので、慎重かつ丁寧に梱包ができる環境を整えましょう。
6. 発送・配送
梱包が終わったら、車両に乗せて商品を発送します。
無事に配送されるまでが、物流に該当する仕事の範囲内だといえるでしょう。
このとき、送り先を間違わないことは当然です。
また「送り方」もよく確認しておきましょう。
「割れ物」「冷凍食品」など、商品の性質によって送り方を工夫しなければなりません。
仮に消費者から要望があったにもかかわらず、見逃したまま送ってしまうとクレームにつながります。
近年では、「スピード発送」を売りにするECサイトも増えてきました。
受注後、早ければ翌日に消費者のもとへと商品を届けるサービスのことです。
競合他社がスピード発送を実践しているのであれば、自社も同等の素早さを身につけなければなりません。
消費者がサイトに求めるスピード感は時代とともに速くなっているので、相応の体制を準備しておくことが大事です。
物流倉庫を業者に外注・委託するメリット
ここまで物流の仕組みについて解説してきました。どの物流にもあてはまるのは、「商品数が多くなるにつれて社員だけで対応するのは難しくなる」という点です。
ECサイトを立ち上げたばかりだと、品数も少ないので本社スタッフだけでも十分に注文を処理できるでしょう。
しかし、サイトが成長すれば業務が枝分かれしていくうえ、注文数が何倍にもなっていくので受注を処理するだけでもかなりの時間をとられます。
そこで多くのECサイトは、物流の業務を外部委託して問題を乗り越えてきました。
物流を全面的にアウトソーシングする以外にも、一部の業務だけを外注する方法もあります。
EC物流を外注すると受注情報を見逃す確率が下がるうえ、倉庫に常時人員を割かなくてもシステムに任せて無人にする時間帯を設けられるのもメリットでしょう。
その結果、24時間体制で物流を稼働でき、業務スピードの改善やコストの削減が実現します。
物流倉庫の費用は?
EC物流を設けるうえで、重要なポイントとなるのが「コスト」です。
多くの場合、専用の倉庫でスペースを借りて商品を保管していきます。しかし、レンタル料が高すぎては、サイト運営を圧迫しかねません。以下、物流倉庫をレンタルする料金相場について説明します。
1. EC物流倉庫の料金体系
EC物流の料金は、まず「基本料金」が含まれます。
これは在庫管理システムの利用料など、倉庫を使ううえで必ず発生するコストです。
次に、商品を特定のスペースに置き続けるための「保管料」です。
そのほか、入庫や梱包、発送にも費用が発生します。
これら5つの費用はどの倉庫を借りるにせよ、必ずかかってくると考えていいでしょう。
ただし料金の相場は、倉庫によってまったく違います。
交渉の余地があるかどうかなども、詳しい作業内容を聞かなければ見えてきません。
倉庫を契約する前にはまず見積書を出してもらい、料金の明細を確認しましょう。
2. EC物流倉庫の料金相場
東京都内の基準では、倉庫の基本費用は「3万円」前後です。
商品数などによってはもっと高くなる可能性もあります。
そして保管費用は「5,000~1万円」前後です。
冷蔵や冷凍だとコストが増えるため、より料金は高くなります。
入庫費用は1ケースあたり「30~100円」ほどです。
また梱包費用として、1件あたり「100円」前後を見ておきましょう。
ただし作業の手間が増えれば、費用も高くなります。
たとえばラッピングが必要な商品だと、料金は上がる仕組みです。
そして、発送費用が「400~600円」ほどです。
ちなみに地方の倉庫になれば、都市圏よりも料金は安くなる傾向が顕著です。
特に保管費用などは節約できるので、倉庫を選ぶときに意識してみましょう。
物流倉庫の選び方
料金以外の要素も比較すれば、自社にもっとも相応しい倉庫と巡り合えるでしょう。
たとえば立地条件やサービス内容などは、倉庫によって異なる要素です。
わずかな違いで企業の物流が大きく変わることも珍しくありません。
この段落では、物流倉庫を選ぶときに注意したいポイントを紹介していきます。
また、定期通販を始めるにあたってほとんどの方は必要になる発送代行会社の選定の仕方は以下の記事でご紹介しています。
ぜひ合わせてご覧になられてはいかがでしょうか。
1. 倉庫の立地
倉庫の立地は作業効率を左右します。
たとえば交通の便が悪い場所にあると、入庫までに時間がかかるだけでなく、発送も遅れてしまいます。
即日配送のように、スピード重視のサービスには対応しきれないことも少なくありません。
地方の倉庫になると料金を安く抑えやすいので、コストを重視しているとつい契約したくなるところです。
しかし物流の費用が抑えられても、肝心の売上が下がっては痛手なのでよく検討しましょう。
高速道路や主要道路に近い倉庫が理想的です。
なお関東で倉庫が多い一帯は、東京都だと大田区や江東区、江戸川区にかけての湾岸地域です。
都心部から外れているのでコストが安い一方、交通アクセスもそれほど悪くありません。
神奈川県だと川崎の工業地帯、埼玉だと和光周辺が倉庫の集中している地域として有名です。
そのほか、千葉県だと市川から浦安にかけてのエリアをチェックしてみましょう。
2. サービス内容
倉庫によって、請け負ってくれる作業内容には違いがあります。
自社サイトが求めるサービスを提供してくれる倉庫をしっかり選びましょう。
たとえばラッピングにこだわりがあるのなら、倉庫側に確認をしなければなりません。
「倉庫で選んだ用紙しか使えない」というのなら、自社サイトのやり方とは合いません。
またチラシやクーポンを同梱してもらえるかもチェックしましょう。
同梱物は大切な営業活動の一環なので、対応できない作業があると売上にも影響します。
さらに保管の品質も重要です。
虫よけや温度管理などは、長期間にわたって商品を保管していると大きく質に関わってきます。
過去にクレームなどのトラブルを起こしている倉庫は避けましょう。
実績や設備などを入念にリサーチして、安心して任せられる倉庫を絞り込んでいきます。
3. 物流倉庫とのアウトソーシング・マッチング
いざ発送業務をアウトソーシングしようと思っても、情報を収集できずに困ってしまうことは少なくありません。
実際に倉庫を見て判断しようにも、そこにかける時間や手間はかなり大きくなります。
複数の候補先をまわって担当者にヒアリングしていくだけでも、骨の折れる作業です。
そこで発送作業を委託したい企業と、物流倉庫のマッチングサービスを利用してみるのもひとつの方法です。
こうしたサービスでは、エリアや業種によって候補先を絞り込むことが可能です。
倉庫の実績もさかのぼっていけるので、問題のある倉庫とうっかり契約を結んでしまうような失態を回避できます。
サービス上から見積をとれる場合もあり、比較検討を希望している企業にもぴったりです。
倉庫は物流の中心を担うスペースなので、さまざまな条件を照らし合わせながら慎重に決めたいところです。
スムーズで正確な物流はECサイト成功のカギ!ECサイトを経営していると、「物流にお金をかけたくない」という発想になることもあるでしょう。
しかし、物流は消費者の満足度に影響し、口コミなどの評判に反映されていきます。
梱包や発送業務はECサイトの発展のため、決して軽視できません。
従業員の負担を軽くするためにも、物流の外部委託を真剣に検討してみましょう。
検討する中で、W2株式会社はECサイト全般を手掛けているので、発送代行や倉庫内作業についても的確なアイデアを提供可能です。
まずは相談してみて発送代行についての提案を聞き、客観的にアウトソーシングの方向性を決めていくのがおすすめです。
また、下記の資料では、EC事業において、業務リソースが不足する原因や、業務を効率化する4つの方法についてご紹介します。
無料ダウンロードできますので、是非ご活用ください。
その他、下記にD2C事業に悩んでいる場合に役立つ「D2Cの成功完全ガイドライン」の資料をご用意しました。
D2Cをどのように成功させるのか気になる方は下記から無料ダウンロードください。