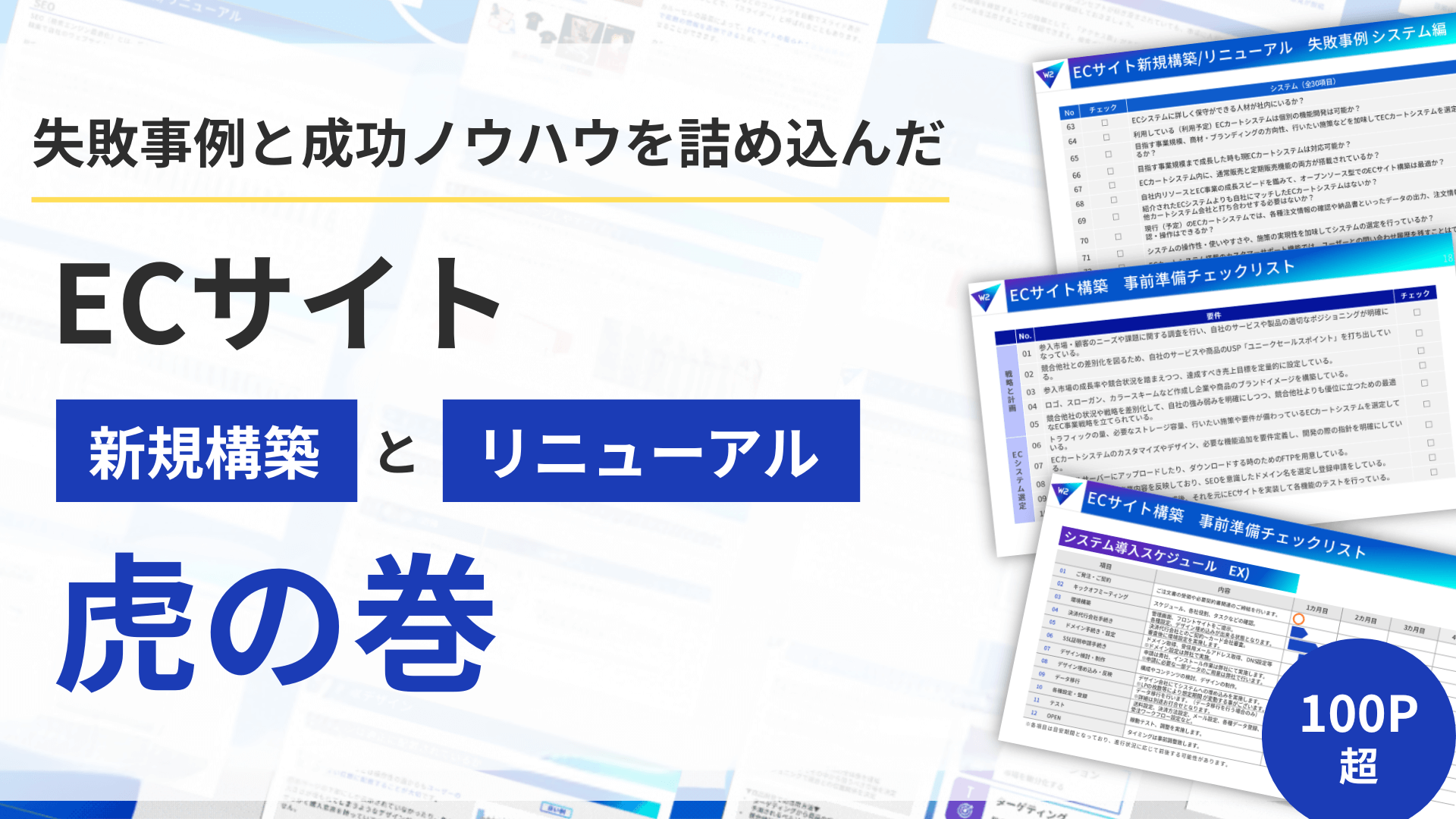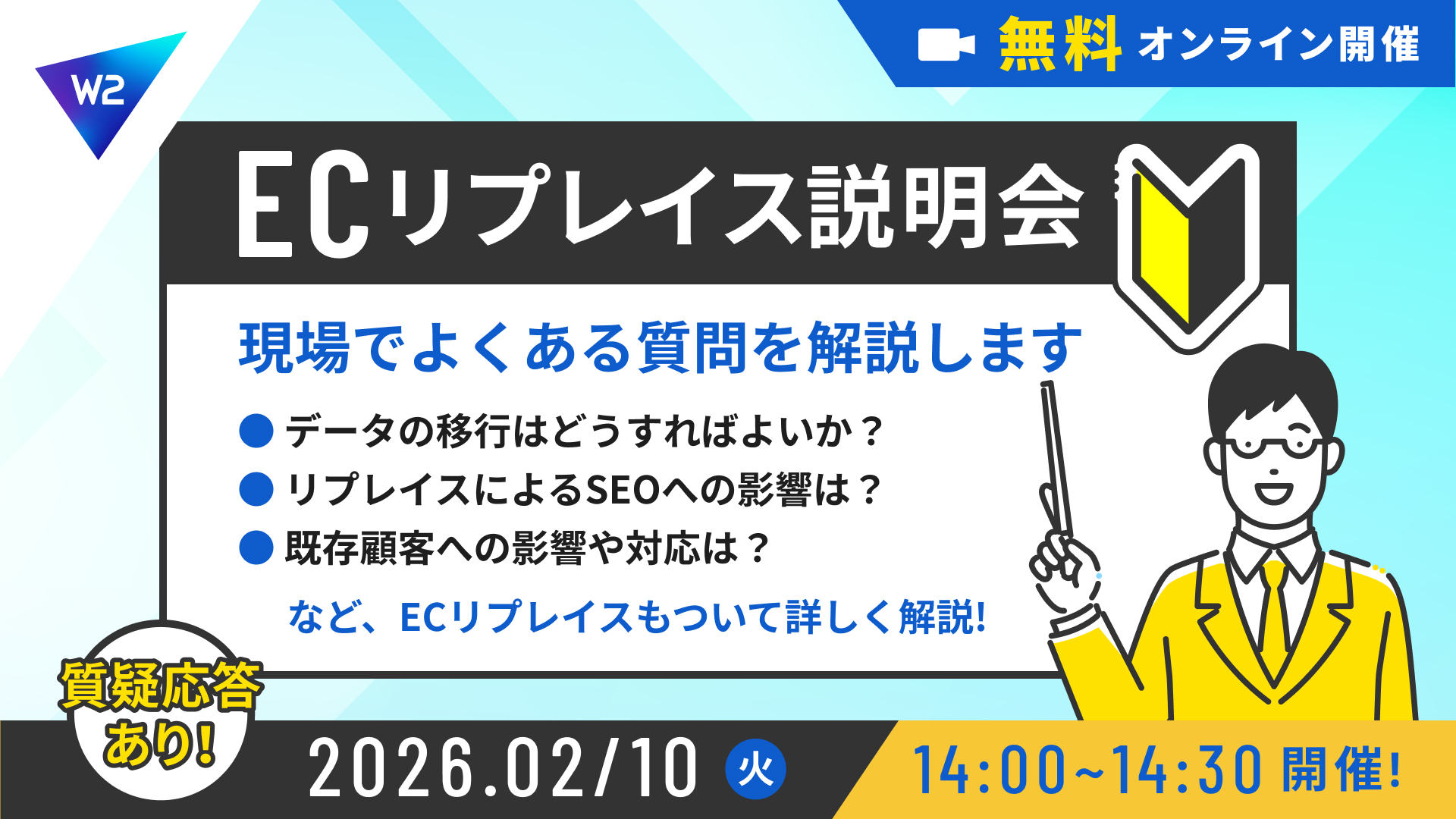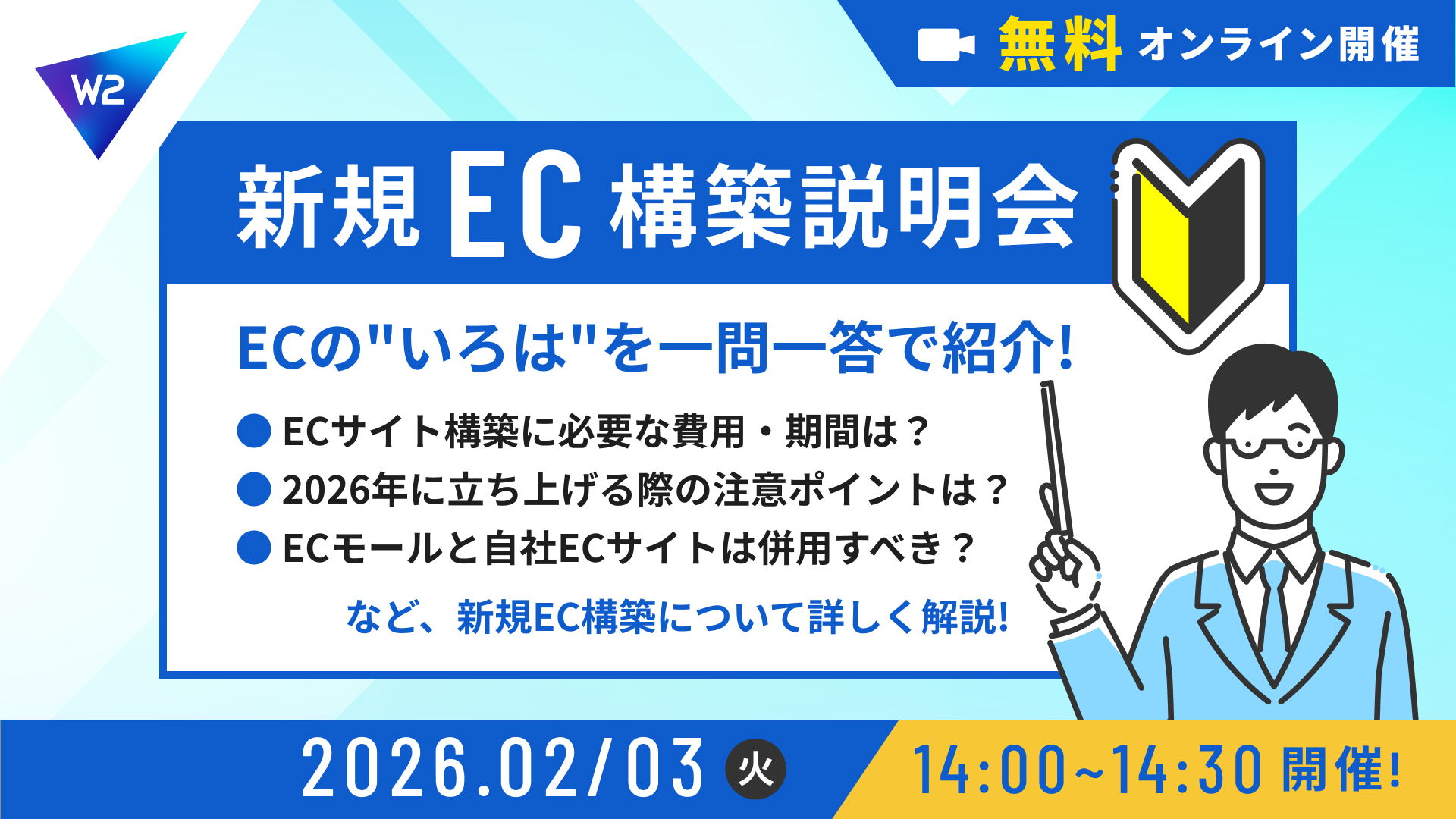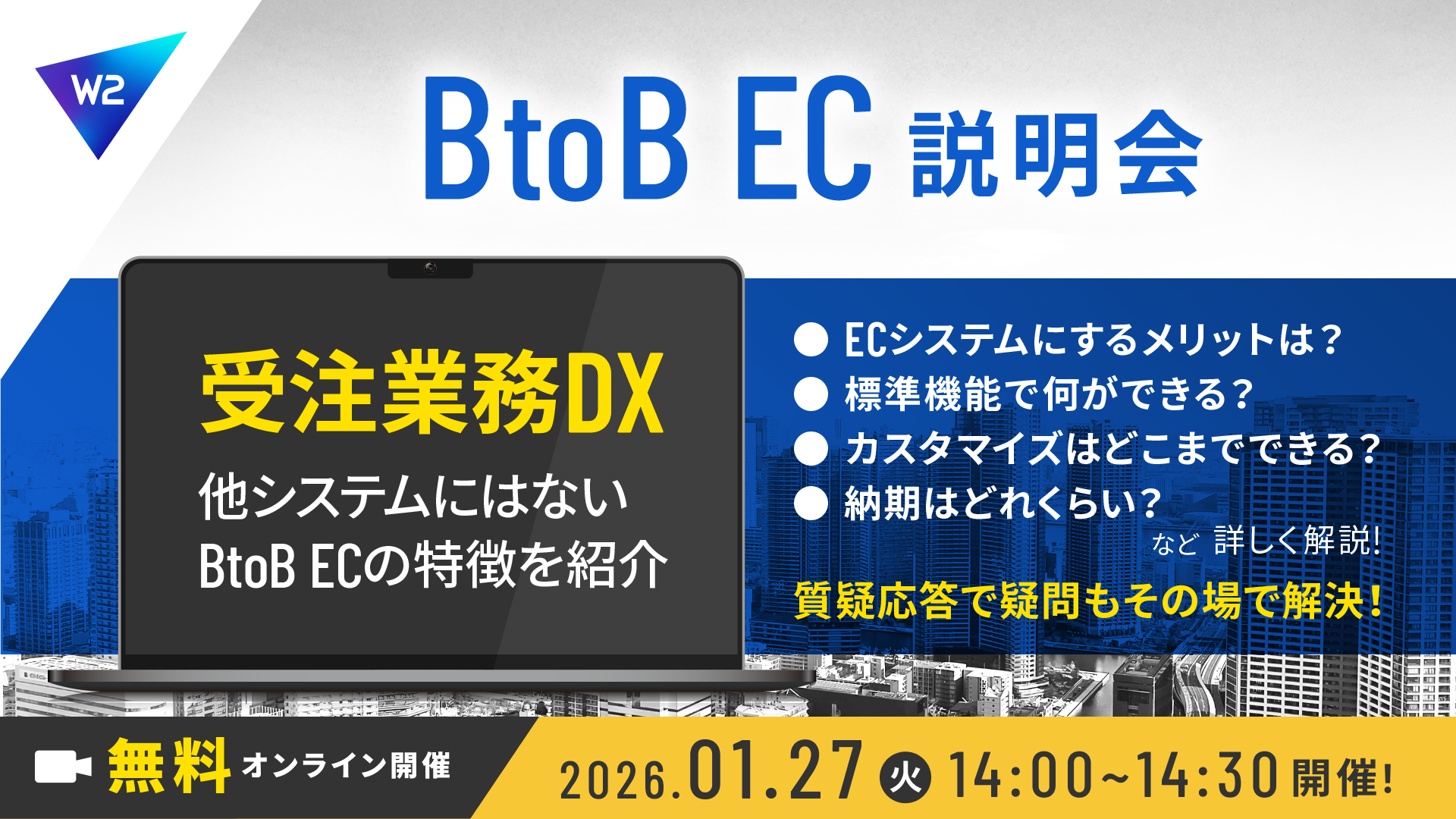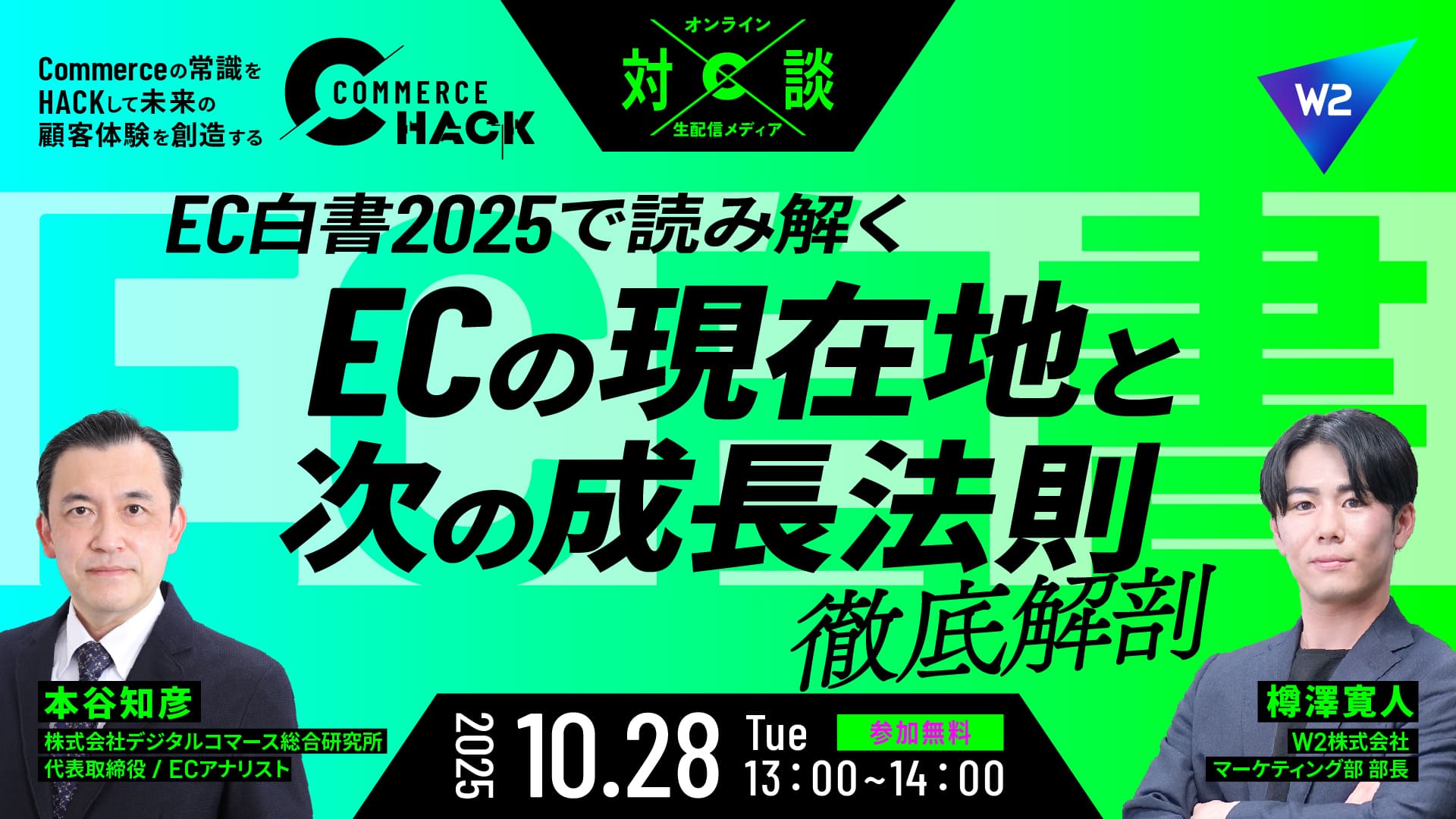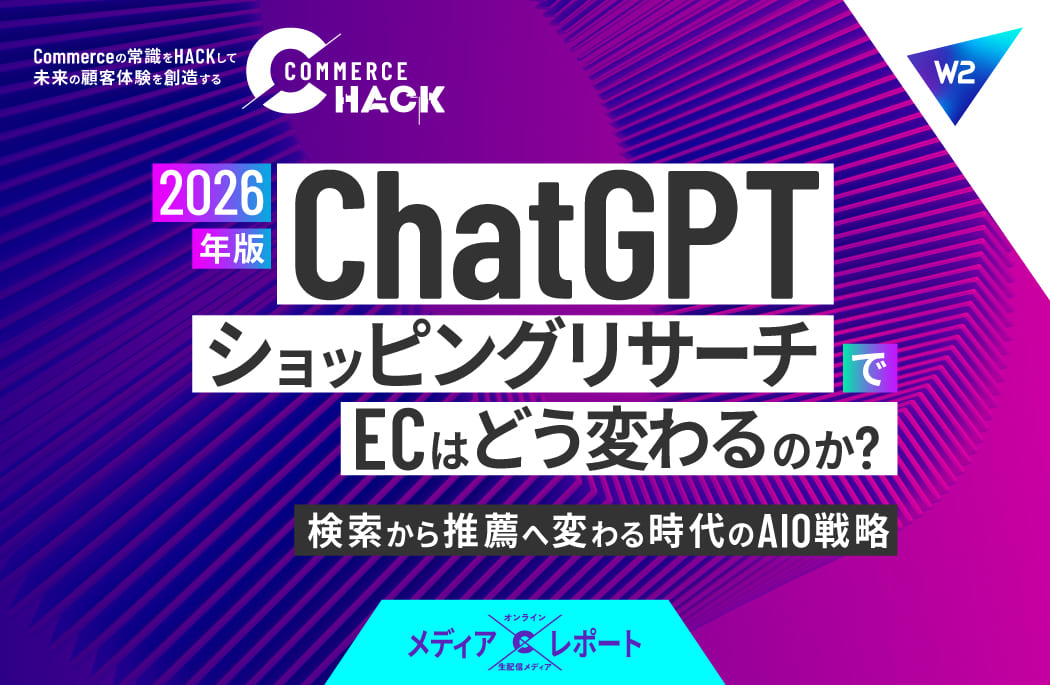SaaS EC(SaaS型ECサイト)は、現代のオンラインビジネスにおいて主流の構築方法となりつつあります。
しかし、「ASPやパッケージと何が違うのか」「ShopifyやBASEなど選択肢が多すぎて、自社に合うものが分からない」「導入後のコストやカスタマイズ性に不安がある」といった悩みを抱えるEC担当者の方は少なくありません。
現行システムからの乗り換えを検討しているものの、データ移行や業務への影響を懸念し、一歩を踏み出せないケースも多いでしょう。
この記事では、そのような課題を解決するため、SaaS型ECの基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、主要プラットフォームの徹底比較、そして失敗しないための選び方まで、専門家の視点で分かりやすく解説します。
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
SaaS型ECとは?意味と仕組み

SaaS(Software as a Service)とは、「サービスとしてのソフトウェア」を意味する言葉で、インターネットを通じてソフトウェアを利用できるサービス形態を指します。これをECサイト構築に応用したものが「SaaS型ECサイト」です。SaaS型ECサイトは、ECサイト構築専用のSaaSを利用して作られたオンラインショップを指します。
SaaS型ECの最大の特徴は、サーバーやドメインの準備、システム開発といった専門知識がなくても、比較的簡単にサイトを構築し、運用できる点にあります。
この手軽さから、短期間でオンラインビジネスを始めたい事業者にとって有力な選択肢となっています。
また、SaaSはクラウドサービスの一種であり、ASP(Application Service Provider)としばしば比較されます。ASPはサービス提供事業者やそのビジネスモデルを指す言葉ですが、SaaSは提供されるソフトウェアそのものを指すという違いがあります。
しかし、ECの文脈では、SaaS型ECはASPから発展したクラウドECとして、ほぼ同じ意味で使われることが一般的です。
SaaSとASP/オンプレ/オープンソースの違い
ECサイトの構築方法を選ぶ際には、それぞれの特徴を理解することが重要です。
SaaSは、初期構築費用が安く、数時間から1ヶ月程度の短期間で導入できる点が大きな魅力です. システム環境の保守運用やセキュリティ対策はサービス提供側が行うため、ユーザー側の運用負荷は非常に低くなります。カスタマイズ性には一定の制限があるものの、多くのサービスでは外部連携やオプション機能による機能拡張が可能です。
ASPサービスもSaaSと同様に低コストかつ短期間で導入できますが、一般的にSaaSの方がマルチテナント構造(一つのシステムを複数の企業で共有する仕組み)などを採用しており、より応用範囲が広く、拡張性が高い傾向にあります。
オンプレミス(パッケージやフルスクラッチ)は、自社でサーバーを管理し、システムを構築する方法です。高度なカスタマイズや独自のセキュリティ要件に対応できる反面、数百万から数千万円という高額な初期費用と、半年以上の長い開発期間が必要です。保守運用も自社で行うため、専門知識を持つ人材が不可欠です。
オープンソースは、無料で公開されているソースコードを基に自社でECサイトを構築する方法です。初期費用は抑えられますが、セキュリティの脆弱性を狙った攻撃のリスクがあり、その対策は全て自己責任となります。また、トラブル発生時のサポートがないため、高度な技術力が求められます。
他の型について、より詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:
【2025年最新版】ECサイトのフルスクラッチとは?費用からメリット・デメリット・失敗事例まで解説!
オープンソース型ECサイト構築|メリットや注意点、おすすめECシステムを解説
ECサイトをASPで構築するメリット・デメリットとは?ASPカートシステムの特徴や機能・料金を比較
SaaS・PaaS・IaaSの違いとECへの適用
SaaS、PaaS、IaaSは、いずれもクラウドサービスの一形態であり、ベンダーが提供するサービスの範囲によって分類されます。
- IaaS (Infrastructure as a Service):ネットワークやサーバーといったインフラ(基盤)部分のみを提供するサービスです。OSやミドルウェア、アプリケーションはユーザー側が自由に選んで導入します。最も自由度が高いですが、利用するには高度な専門知識が求められます。
- PaaS (Platform as a Service):IaaSの提供範囲に加えて、OSやミドルウェアなど、アプリケーション開発に必要なプラットフォームまでを提供します。ユーザーはアプリケーション開発に集中できるため、独自のシステムを効率的に構築したい場合に適しています。
- SaaS (Software as a Service):IaaS、PaaSの範囲に加え、ソフトウェア(アプリケーション)まで含めた全てをサービスとして提供します。ユーザーはアカウントを登録すればすぐに利用を開始できます。ECサイトにおいては、ECカートシステム全体をクラウド上で提供するサービスがこれにあたります。
ECサイト構築において、SaaSは専門知識がなくてもすぐに利用できるため、特に初心者やスモールスタートを目指す事業者に最適です。
一方、PaaSやIaaSは、フルスクラッチに近い大規模なECサイト構築や、独自のシステム連携を前提とするヘッドレスコマース、あるいは機能単位でシステムを組み合わせるComposable Commerceの土台として利用されることがあります。自由度が高い分、使いこなすための専門知識の難易度も上がると理解しておきましょう。
SaaS型ECのメリット

導入スピードと初期費用の低減
SaaS型ECは、自社でサーバーやネットワークなどのインフラを構築する必要がなく、ソフトウェアの開発も不要なため、導入コストを大幅に抑えることが可能です。多くのサービスでは初期費用が無料または低額に設定されており、月額のサブスクリプション料金を支払うことで、ECサイト運営に必要な機能とインフラを利用できます。
また、デザインテンプレートやテーマが豊富に用意されているため、専門的な知識がなくても、最短で即日、通常でも1週間程度の短期間でECサイトを開設できます。
この迅速性は、新しい事業をスピーディに立ち上げたい場合や、市場の反応を見るための仮説検証(MVP開発)を行いたい場合に大きな強みとなります。
運用負荷の軽減と自動アップデート
SaaS型ECサイトを利用する大きなメリットの一つが、運用負荷の軽減です。
システムのバージョンアップや新機能の追加、セキュリティパッチの適用といったシステム管理は、すべてベンダー側の専門チームが自動で実施します。ユーザーはサーバー管理やシステムの保守・メンテナンスにかかる手間やコストから解放されます。
この仕組みによって、EC事業者は常に最新の機能を利用できるだけでなく、Webブラウザの仕様変更や新たなセキュリティリスクへの対応もプロバイダー側に任せることが可能です。
結果として、運用担当者の負担は大幅に軽減され、集客や販売戦略の立案、顧客対応といった、売上拡大に直結するコア業務にリソースを集中させることができます。
高水準なセキュリティを簡単に実現できる
SaaS型ECでは、サービス提供会社が基本的なセキュリティ対策を行うため、自社で高度なセキュリティ体制を構築する手間が大幅に軽減されます。
多くのベンダーは、クレジットカード情報を安全に取り扱うための国際基準である「PCI DSS」に準拠しており、24時間365日の監視体制を敷くなど、高水準のセキュリティを提供しています。
また、可用性(システムの安定稼働)やスケーラビリティ(拡張性)に関しても、SaaSは大きな強みを持ちます。セールやメディア露出によってアクセスが急増(スパイク)した場合でも、クラウドの特性を活かしてサーバー容量を自動的に調整し、サイトがダウンすることなく安定した運営が可能です。
これにより、事業の成長に合わせてシームレスに規模を拡張でき、機会損失を防ぎます。これらの仕組みは、企業の監査対応や事業継続計画(BCP)の観点からも、自社で全てを管理する場合と比較して大きな安心材料となります。
SaaS型ECのデメリットと対策
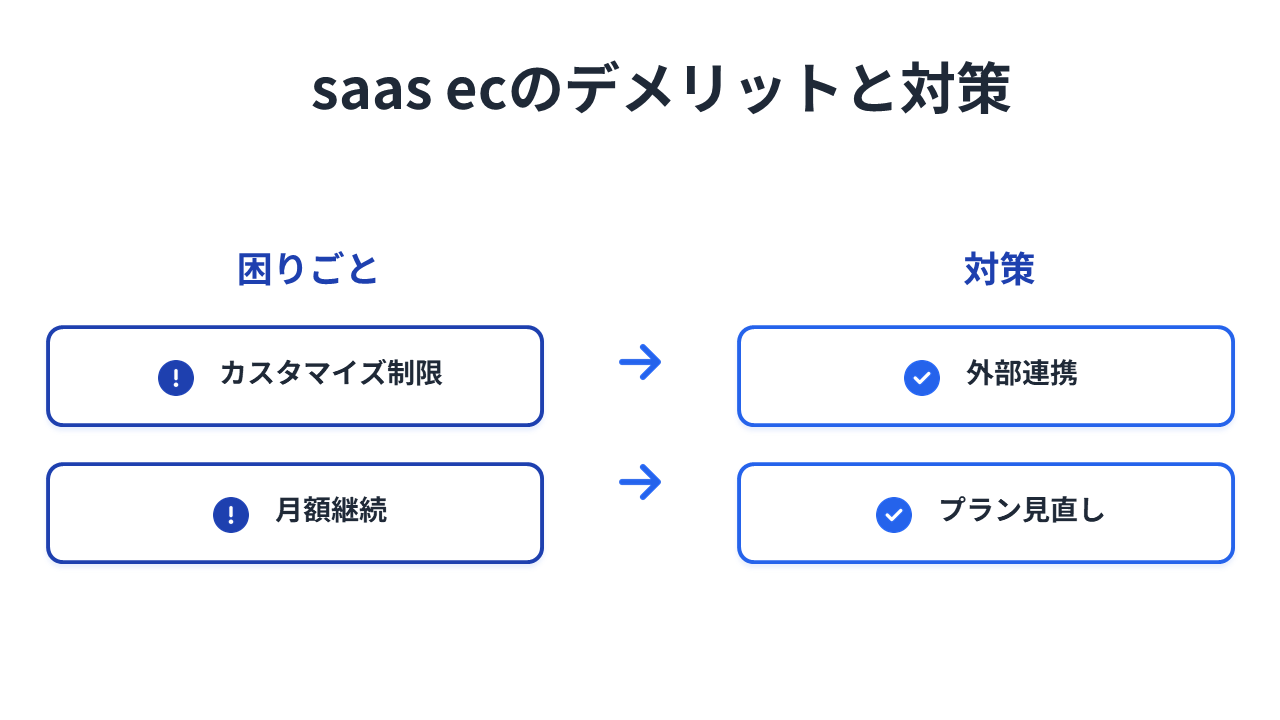
カスタマイズの制約
SaaS型ECは、基本的にベンダーが提供する標準機能の範囲内に限られます。そのため、独自の業務フローや複雑な要件を実現するためのカスタマイズ自由度が低い点が、最大の制約となることがあります。
しかし、この制約にはいくつかの回避策が存在します。
- アプリ/拡張機能の活用: 標準機能だけでは不足する場合、多くのSaaSプラットフォームでは「アプリストア」が用意されています。例えばShopifyのApp Storeのように、豊富なアプリや外部サービス連携機能を通じて、在庫管理、CRM、マーケティング機能などを柔軟に拡張できます。
- API連携の活用: BtoBサイトの構築や大規模ECのように、基幹システムとの連携や独自の画面設計が必要な場合は、API(Application Programming Interface)を通じた柔軟な連携に対応したSaaSを選定することが重要です。APIを利用することで、システム要件に合わせた自由度の高い運用が実現できます。
- ヘッドレスコマース: 究極の自由度と拡張性を求めるのであれば、ヘッドレスコマースという選択肢もあります。これは、バックエンド(カート機能など)をSaaSに任せつつ、フロントエンド(顧客が見る画面)を完全に分離して自由に構築する手法です。これを実現するには、API提供が充実したSaaSプラットフォームが土台となります。
外部システムとの連携が自由にできない場合がある
SaaS型ECはある程度完成されたパッケージとして提供されるため、外部システムとのデータ連携は、サービス提供者が公式に用意した連携の窓口である「API(Application Programming Interface)」を通じて行うのが基本です。
しかし、このAPIが提供されていなかったり、提供されていても機能が限定的だったりすると、自由なシステム連携ができないという制約が発生します。
例えば、自社で長年利用している独自の基幹システムや在庫管理システム(WMS)と、リアルタイムでの在庫・注文情報の同期ができないケースが考えられます。また、利用したい特定のMA(マーケティングオートメーション)ツールやCRMツールとの顧客データ連携に対応していない場合もあります。
この課題への対策としては、契約前に連携を希望するシステムとの接続に必要なAPIが提供されているか、その仕様を事前に確認することが不可欠です。
多くのSaaSでは、主要な外部ツールとの「公式連携ページ」が用意されているため、まずはその対応状況をチェックしましょう。もし公式な連携方法がない場合でも、CSVファイルの手動アップロード・ダウンロードによる定期的なデータ同期で代替できないかを検討するのも一つの手です。
SaaS型のECプラットフォームとは?

SaaS型ECプラットフォームとは、SaaS形式で提供される、オンラインビジネスを運営するための統合的な基盤(システム)を指します。
これは単に商品を販売するショッピングカート機能だけを指すのではありません。ECサイトの構築から日々の受注・在庫管理、さらには売上を伸ばすためのマーケティング活動に至るまで、事業運営に不可欠なあらゆる機能が一つにまとめられています。
具体的には、お客様が目にするサイトのデザインや商品ページといった「フロントエンド」、店舗運営者が利用する受注管理や顧客管理などの「バックエンド」、そしてそれらを24時間365日支えるサーバーやセキュリティといった「インフラ」まで、すべてが含まれています。
SaaS型ECプラットフォームに搭載されている主な機能
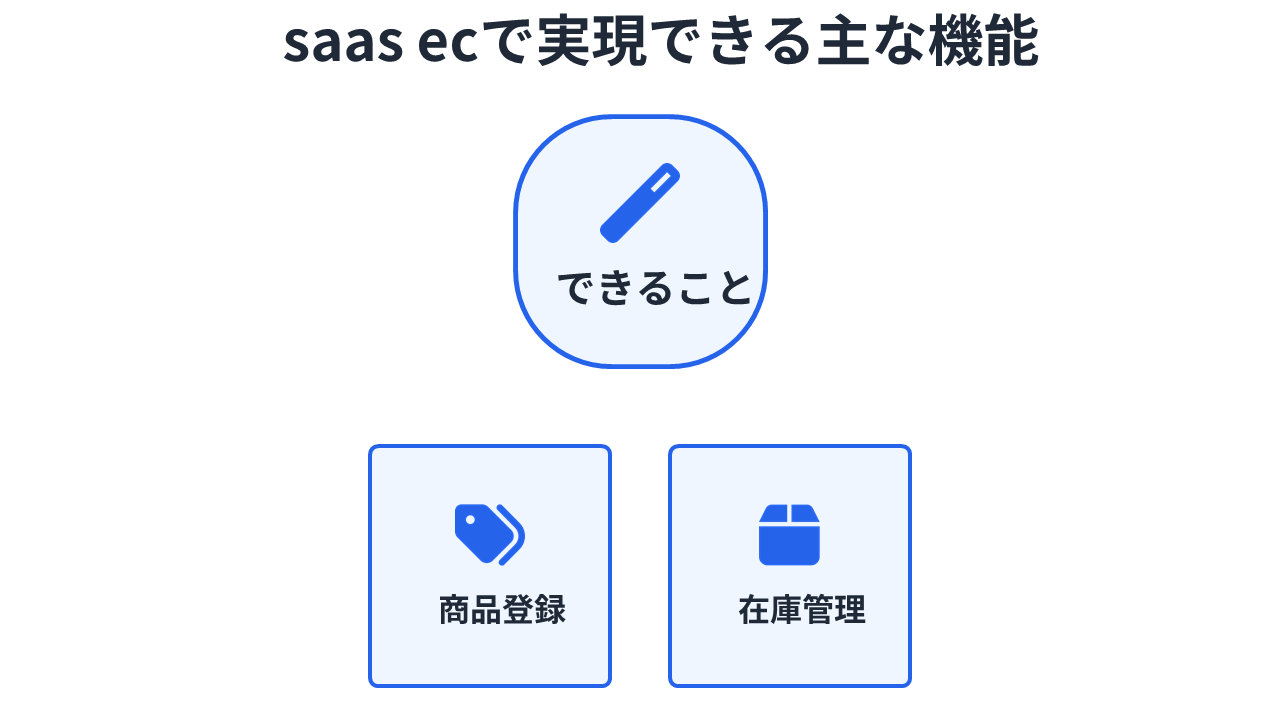
商品・在庫・受注・出荷管理(OMS/WMS連携)
SaaS型ECプラットフォームは、商品情報の登録、在庫数の管理、顧客からの注文受付、そして出荷指示といったECサイトの基本的な業務を管理する機能を標準で備えています。
在庫管理においては、複数倉庫の在庫を一元管理したり、実店舗の在庫と連携したりする機能を持つものもあります。
受注管理では、注文内容の確認、入金状況の管理、顧客への連絡などが管理画面上で行えます。
さらに、WMS(倉庫管理システム)やOMS(受注管理システム)といった外部システムとのAPI連携に対応しているプラットフォームも多く、より高度な在庫管理や受注処理の自動化を実現できます。
マーケティング(クーポン/ポイント/アップセル/CRM/MA/LINE)
売上を伸ばすためには、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客の育成(CRM)が不可欠です。SaaS型ECプラットフォームには、顧客の再購入を促し、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための多彩なマーケティング機能が搭載されています。
具体的には、特定の顧客層に限定したクーポンの発行、購入金額に応じたポイント付与、購入手続き中に別の商品を推奨するアップセル・クロスセル機能などがあります。
さらに、MA(マーケティングオートメーション)ツールやLINEとの連携機能を使えば、顧客の行動履歴に基づいたステップメールの配信や、LINEを通じた販促活動も可能です。
サブスク/定期購入
健康食品や化粧品、食品などの消耗品を扱うECサイトでは、サブスクリプション(定期購入)モデルが重要な収益源となります。
SaaS型ECプラットフォームの中には、このサブスクリプションビジネスに特化した機能を豊富に備えているものがあります。
基本的な定期購入の設定はもちろん、顧客がマイページから次回配送日の変更やスキップ、解約などを自由に行える機能は不可欠です。
さらに、定期購入の継続回数に応じて割引率を適用したり、別の商品を同梱してアップセルを狙ったりといった、解約率を下げてLTVを向上させるための高度な施策に対応できるプラットフォームもあります。
W2の提供するサービスは、こうした定期通販特有の要件にきめ細かく対応できる機能を数多く搭載しています。
詳しくは下記からご覧ください。
BtoB機能(見積/承認/掛け払い/価格表)
企業間取引(BtoB)のEC化も急速に進んでいますが、BtoB ECにはBtoCとは異なる特有の要件が求められます。
例えば、取引先ごとに異なる価格を設定できる「顧客グループ別価格設定」、オンラインでの見積書発行・承認フロー、そして企業間取引で一般的な「掛け払い(請求書払い)」への対応などが挙げられます。
また、特定の企業のみがアクセスできるクローズドなサイト構築も必要になる場合があります。
一部のSaaS型ECプラットフォームは、これらのBtoB特有の商習慣に標準機能やオプションで対応しており、従来は電話やFAXで行っていた受発注業務の効率化を実現します。
AI活用(レコメンド/需要予測/コンテンツ自動化)
近年、AI技術の活用はEC運営においても急速に広がっています。SaaS型ECプラットフォームでも、AIを活用した機能が続々と登場しています。
代表的なものに、顧客の閲覧履歴や購買履歴を分析し、一人ひとりに最適な商品を推奨する「AIレコメンド機能」があります。また、過去の販売データから将来の需要を予測し、適切な在庫管理を支援する機能や、商品説明文やブログ記事を自動生成する機能も実用化されています。
W2では、これらのAI機能をプラグインとして簡単に追加できる仕組みや、AIを活用したメディアコマースとの連携など、最先端の技術をECサイトに導入する支援を行っています。
SaaS型ECプラットフォームの料金や費用
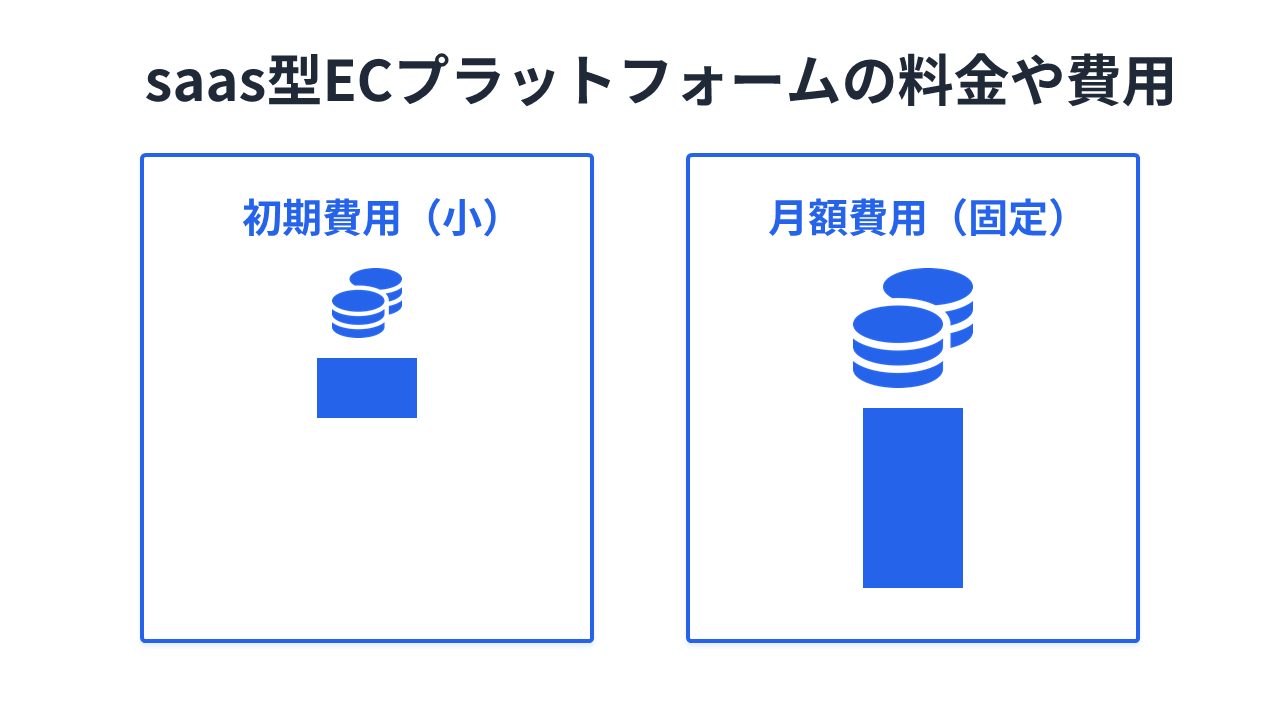
月額制や従量、トランザクションの構造
SaaS型ECの料金体系は、主に以下の3つの要素で構成されています。
- 月額/年額固定費: サービスを利用するための基本的な料金で、一般的にサブスクリプション形式で支払います。契約するプランによって、利用できる機能の範囲、商品登録数、サポートのレベルなどが異なります。
- 従量課金: ECサイトへのアクセス数(トラフィック)や登録ユーザー数、サーバーのデータ転送量など、利用した量に応じて料金が変動する方式です。
- トランザクション課金: 売上や取引件数に応じて発生する費用です。具体的には、クレジットカード決済などで発生する「決済手数料」や、一部のサービス(例:BASEのスタンダードプラン)で見られる「サービス利用料/販売手数料」がこれに該当します。
事業の初期段階や売上がまだ低いスモールスタートの時期は、月額固定費が無料または低額で、販売手数料がかかるプランが適している場合があります。
しかし、事業が成長し月商の目処が立つと、固定費は発生しても決済手数料率が低い有料プランへ移行した方が、結果的にトータルの支払いコストを抑えられるケースが多くなります。
自社の売上予測と照らし合わせて、どの料金体系が最も有利になるかシミュレーションすることが重要です。
月額・初期費用以外の隠れコスト
初期費用や月額固定費が安く見えても、ECサイトの成長や運用効率化を目指す過程で、見落としがちな「隠れコスト」が発生することがあります。
- アプリ/拡張費用: 標準機能だけでは不足する部分を補うために、外部サービス連携やオプション機能を追加すると、別途月額費用や従量課金が発生し、コストが積み上がっていく可能性があります。
- テーマ/開発費用: 多くのSaaSでは無料のデザインテンプレートが提供されていますが、ブランドイメージに合わせた独自のデザインを実現したい場合や、HTML/CSSをカスタマイズする場合には、外部のデザイナーや開発者への委託費用が発生します。
- 運用人件費: システムの保守はベンダーに任せられますが、商品登録、集客活動、マーケティング施策の実行、顧客対応といった日々のコア業務を行うための人件費は、TCOに含めて見積もる必要があります。
これらの隠れコストを抑制する一つの方法として、標準機能が豊富なプラットフォームを選ぶことが挙げられます。
例えば、W2のように業界トップクラスの1,000以上の機能をノンカスタマイズで利用できるSaaSカートの場合、多機能であるため、アプリや拡張機能の個別追加を最小限に抑えやすく、結果として隠れコストを抑制できる側面があります。
SaaS型ECプラットフォーム選定のための確認ポイント

標準機能
標準機能とは、プラットフォームを契約すれば追加料金なしで利用できる基本的な機能群を指します。商品管理、受注処理、顧客管理といったECサイトの根幹をなす機能から、クーポン発行やポイント制度といった基本的なマーケティング機能まで、その範囲はサービスによって様々です。
この標準機能の充実度は、日々の運用効率と将来的なコストに直結するため、選定において極めて重要です。自社の業務に必要な機能が標準で備わっていれば、高額な追加開発や有料アプリの導入を避けられ、総保有コスト(TCO)を抑制できます。
また、複数のツールを使い分ける必要がなくなるため、運用もシンプルになります。
具体的な確認ポイントとしては、まず自社の業務フローを洗い出し、それが標準機能だけで完結できるかをデモ画面などで確認しましょう。「定期購入」「BtoB向けの卸価格設定」「複数倉庫との在庫連携」など、自社のビジネスモデルに特有の要件が標準でカバーされているかは特に重要です。機能一覧の文言だけでなく、実際の操作感を確かめることをお勧めします。
カスタマイズ性やデザイン
カスタマイズ性やデザインとは、ブランドの世界観を表現するためのデザインの自由度や、企業独自の要件に対応するために機能を改修・追加できる柔軟性の度合いを指します。テンプレートの範囲内での軽微な修正から、HTML/CSSを直接編集して独自のレイアウトを組むことまで、その自由度はプラットフォームによって大きく異なります。
ECサイトにおいてデザインは、単なる見た目以上に、顧客の購買体験やブランドイメージを決定づける重要な要素です。他社との差別化を図り、顧客に一貫したブランド体験を提供するためには、一定レベル以上のデザイン自由度が不可欠となります。また、事業の成長に伴い、独自のサービスや業務フローに対応する必要が出てくるため、将来的なカスタマイズの余地も考慮すべきです。
選定時には、提供されるデザインテンプレートの質と量を確認すると同時に、HTML/CSS/JavaScriptをどの範囲まで自由に編集できるかを確認しましょう。また、特定のページに独自の機能を追加できるか、専門の開発パートナー企業が存在するかなども、将来の拡張性を見極める上で重要な判断材料となります。
拡張性や柔軟性
拡張性や柔軟性とは、他のシステムとデータを連携させる能力や、事業の成長に合わせてシステム規模を拡大できる能力を指します。具体的には、外部システムと接続するための「API」が豊富に提供されているか、また機能を追加するための「アプリ(プラグイン)」のマーケットプレイスが充実しているか、といった点が指標となります。
現代のEC事業は、カートシステム単体では完結しません。在庫管理システム(WMS)、顧客管理システム(CRM)、会計ソフト、MAツールといった様々な外部システムとのスムーズなデータ連携が、業務効率化と売上拡大の鍵を握ります。そのため、システムの「つなぎやすさ」である拡張性は、プラットフォーム選定における生命線とも言えます。
具体的な確認ポイントとしては、まず自社で利用中の、あるいは将来導入したいシステムと連携可能かを確認します。そのために必要なAPIが提供されているか、またその仕様書(ドキュメント)が開発者向けに公開・整備されているかは必ずチェックしましょう。アクセス数や商品数の増加に耐えうるインフラか、事業規模が拡大した際に上位プランへスムーズに移行できるか、といった点も将来を見据えた重要な視点です。
サポート体制
サポート体制とは、システム導入時の立ち上げ支援や、運用開始後に発生する問題の解決、さらには売上向上のためのコンサルティングなど、ベンダーが提供する人的な支援サービス全般を指します。単なる問い合わせ窓口だけでなく、EC事業者の成功を共に目指すパートナーとしての役割が期待されます。
ECサイト運営において、「決済ができない」「ページが表示されない」といったシステムトラブルは、売上の機会損失に直結します。そのため、万が一の際に迅速かつ的確なサポートを受けられるかは、安定した事業運営のための生命線です。また、社内にECの専門知識を持つ人材がいない場合、ベンダーの担当者から受けるアドバイスは、事業の成長を大きく加速させる要因となり得ます。
選定時には、サポートの窓口(電話、メール、チャット)、対応時間(平日日中のみか、24時間365日か)、返信速度などを確認しましょう。特に、緊急時に頼りになる電話サポートが無料か、回数制限がないかは重要なポイントです。さらに、システムの操作方法だけでなく、マーケティング施策など売上向上に関する相談にも乗ってくれるか、専任の担当者がつくかどうかも確認すべき項目です。
料金プラン
料金プランとは、プラットフォームの利用にかかる費用の体系のことです。一般的に、初期費用、毎月固定で支払う月額利用料、そして売上に応じて変動する販売手数料やトランザクション手数料、決済手数料などから構成されています。サービスによっては、初期費用や月額料金が無料のプランも存在します。
料金プランの比較は、EC事業の利益構造に直接影響するため、極めて慎重に行う必要があります。目先の月額料金の安さだけで判断してしまうと、高い販売手数料や決済手数料によって、売上が伸びるほど利益が圧迫されるという事態に陥りかねません。アプリの追加費用なども含めた総保有コスト(TCO)の視点で、長期的に評価することが不可欠です。
具体的な確認ポイントとして、初期費用と月額固定費はもちろん、売上に応じた手数料の料率を必ず確認しましょう。また、利用したい決済手段の手数料はいくらか、標準機能で不足しそうな有料アプリの費用はどのくらいかも見積もっておくべきです。自社の売上予測に基づき、複数のプラットフォームで数年間のTCOをシミュレーションし、最もコストパフォーマンスに優れた選択肢を見極めることが重要です。
セキュリティ
セキュリティとは、顧客から預かる個人情報やクレジットカード情報、そして自社の売上データなどを、不正アクセスや情報漏洩、データ改ざんといった脅威から守るための技術的・組織的な対策全般を指します。SaaS型ECでは、システムのセキュリティ対策の大部分をベンダーに依存することになります。
EC事業者にとって、情報漏洩は顧客からの信頼を完全に失墜させ、場合によっては事業の存続そのものを揺るがす最も重大なリスクです。顧客の大切な情報を預かる立場として、最高水準のセキュリティを確保することは企業の社会的責任でもあります。そのため、ベンダーがどのようなセキュリティ対策を講じているかを精査することは、プラットフォーム選定における最優先事項の一つと言えます。
選定時には、まずクレジットカード情報を安全に扱うための国際基準「PCI DSS」に準拠しているかを確認します。加えて、第三者機関による定期的な脆弱性診断の実施や、情報セキュリティに関する国際認証「ISMS(ISO27001)」などを取得しているかは、客観的な信頼性の指標となります。過去に重大なセキュリティ事故を起こしていないか、その実績も確認すべき重要なポイントです。
おすすめのSaaS型のプラットフォーム8選

W2 Unified

W2 Unifiedは、BtoCの総合通販からD2Cの定期通販、実店舗と連携するOMOまで、多様なビジネスモデルを一つのシステムで実現できる統合型ECプラットフォームです。
最大の特長は、業界最多クラスの1,000以上の機能を標準搭載している点にあります。これにより、多くの有料アプリや追加開発なしで高度な要件に対応でき、結果として総保有コスト(TCO)を抑制できます。
特にCRMやマーケティングオートメーション機能が充実しており、顧客のLTV(顧客生涯価値)向上を得意としています。100%内製開発による手厚いサポート体制も強みです。
年商数億円以上の中規模から大規模事業者で、特に定期通販やOMO戦略など、複雑なマーケティング施策やシステム連携を本格的に行いたい企業に最適です。既存のプラットフォームの機能や拡張性に限界を感じ、リプレイスを検討している企業にもおすすめの選択肢となります。
STORES
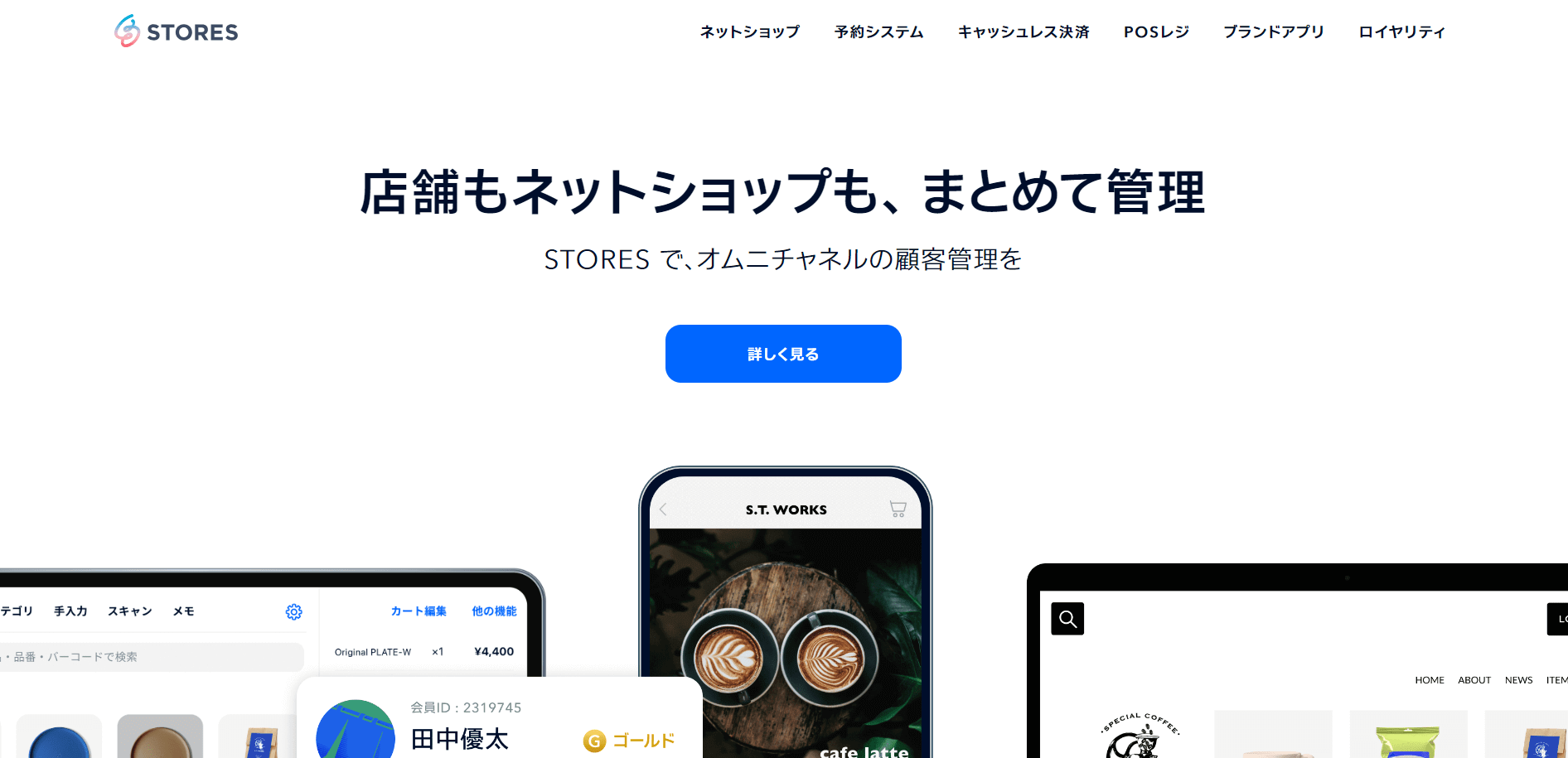
STORESは、ネットショップの開設、キャッシュレス決済、ネット予約システムなどを統合的に提供するサービスで、特に個人やスモールビジネス向けに設計されています。
初期費用・月額費用が無料のフリープランが用意されており、専門知識がなくても非常に低リスクでEC事業をスタートできるのが最大の魅力です。管理画面は直感的で分かりやすく、数ステップで簡単にショップを開設できます。
有料プランでも決済手数料が比較的安価に設定されており、コストを重視する事業者にとって魅力的です。POSレジ機能も提供しており、実店舗とオンラインの簡単な連携も可能です。
これから初めてネットショップを開設する個人事業主やハンドメイド作家、小規模な事業者で、まずはコストをかけずにECを始めたいという方に最適です。また、実店舗を運営しており、簡単な在庫連携や決済手段の統一からOMOを始めたいと考えている店舗オーナーにも適しています。
Shopify

Shopifyは、世界No.1のシェアを誇るカナダ発のSaaS型ECプラットフォームです。
その最大の特徴は、「App Store」と呼ばれるマーケットプレイスに存在する豊富な拡張アプリです。これにより、マーケティング、在庫管理、CRMといった多種多様な機能を自由自在に追加でき、圧倒的な拡張性を誇ります。
また、高品質で洗練されたデザインテンプレートが数多く用意されており、デザインの自由度も非常に高いです。特に越境ECに強く、多言語・多通貨への対応が簡単なため、グローバルな販売戦略をスムーズに実現できます。
デザイン性の高いブランドサイトを構築したいD2C事業者や、将来的に海外展開(越境EC)を視野に入れている企業に強く推奨されます。また、最新のマーケティングツールやアプリを積極的に活用し、EC事業をスピーディに成長させたいと考える、個人から大企業まであらゆる規模の事業者にフィットするプラットフォームです。
カラーミーショップ

カラーミーショップは、GMOペパボ株式会社が運営する、国内で長年の運用実績を持つECプラットフォームです。
事業規模に応じて選べる幅広い料金プランが特徴で、手軽に始められる無料のフリープランから、カスタマイズ性の高い有料プランまで用意されています。
特に有料プランではHTML/CSSの編集自由度が高く、テンプレートをベースにしながらもオリジナリティのあるデザインを実現しやすい点が強みです。長年の実績に裏打ちされた、日本の商習慣に合った機能や、国内ベンダーならではの手厚いサポート体制も安心材料です。
低コストでECを始めつつも、将来的にはデザインにこだわりたいと考えている個人事業主や小規模事業者に適しています。また、日本の商習慣に合った運営や、国内ベンダーによる日本語での手厚いサポートを重視する企業にもおすすめです。ある程度のITリテラシーがあり、HTML/CSSを編集して独自のショップデザインを構築したい方にもフィットします。
ecforce

ecforceは、D2C(Direct to Consumer)やサブスクリプション(定期通販)といったビジネスモデルに特化したECプラットフォームです。
その最大の特徴は、顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化することを目的としたマーケティング機能が標準で充実している点にあります。
カゴ落ち対策、アップセル・クロスセルの自動化、詳細な広告効果測定など、売上向上に直結する機能が豊富に搭載されており、顧客一人ひとりに合わせた販売シナリオを効率的に実行できます。これにより、広告費の回収効率を高め、持続的な事業成長を支援します。
化粧品や健康食品といった単品リピート通販をビジネスの主軸とするD2C事業者に最も適しています。サブスクリプションモデルを採用し、新規顧客獲得コストの回収とLTVの向上が最重要KPIとなっている企業にとって、強力な武器となるでしょう。広告運用と連携したデータ分析を重視し、データドリブンな事業運営を目指す企業にも最適な選択肢です。
futureshop

futureshopは、特にアパレル業界で高いシェアを持つECプラットフォームで、「顧客の創造」をコンセプトに掲げています。その強みは、CRM(顧客関係管理)機能が非常に充実している点にあります。
会員ランク機能、ポイント、クーポンなどを細かく設定・活用でき、顧客とのエンゲージメントを高めてファンを育成する施策を得意としています。また、デザインのカスタマイズ性も高く、ブランドの世界観を細部まで表現しやすい構造になっています。実店舗との会員・ポイント統合など、OMO戦略を支援する機能も豊富です。
アパレルやファッション雑貨、コスメなど、ブランドの世界観やファンとの長期的な関係構築を重視する事業者に最適です。年商1億円以上を目指す中規模から大規模の事業者で、特にリピート顧客の育成に力を入れていきたい企業におすすめです。実店舗とECサイトの連携を強化し、顧客に一貫したブランド体験を提供したいと考える小売事業者にもフィットします。
W2 BtoB
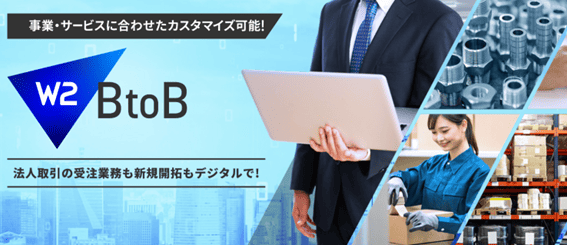
W2 BtoBは、BtoB(企業間取引)のEC化に特化して開発されたプラットフォームです。
その最大の特徴は、企業間取引特有の複雑な商習慣に標準機能で対応できる点にあります。
例えば、取引先ごとに異なる価格や掛け率を表示する「顧客別価格設定」、オンラインでの見積書発行と上長承認のワークフロー機能、そして与信管理と連携した請求書払い(掛け売り)決済などが可能です。特定の取引先のみがアクセスできるクローズドなECサイトの構築も容易で、既存の基幹システム(ERP)との柔軟な連携も強みとしています。
W2 Unified同様、100%内製開発による手厚いサポート体制も魅力です。
これまで電話やFAX、Excelでアナログな受発注業務を行ってきたメーカーや卸売業者に最適です。既存の業務プロセスを効率化し、BtoB取引を本格的にDX(デジタルトランスフォーメーション)したい企業にとって、強力なソリューションとなります。
ebisumart

ebisumartは、「SaaSのメリット」と「パッケージのメリット」の両立をコンセプトに掲げるクラウドECプラットフォームです。その最大の特徴は、SaaSでありながらシステムの根幹部分にまで手を入れることができるほどの圧倒的なカスタマイズ性にあります。
これにより、企業独自の複雑な業務フローや特殊な要件にも柔軟に対応可能です。また、週に一度のシステムアップデートで常に最新かつ安全な状態が保たれる点も強みです。APIも豊富に提供されており、外部システムとの複雑な連携も実現できます。まさに「カスタマイズできるSaaS」という独自のポジションを確立しています。
年商数十億円規模の大規模事業者や、独自のビジネスモデルを持っており、通常のSaaSでは要件を満たせない企業に最適です。将来的に大規模なシステム連携や特殊な機能開発を見据えている、技術力の高い企業にも適しています。フルスクラッチ開発に代わる、柔軟性と安全性を両立した選択肢として検討すべきプラットフォームです。
まとめ
SaaS型ECとは、ECサイトの構築から運営まで、必要な機能をインターネット経由でレンタルするサービスです。専門知識がなくても低コストかつ短期間でネットショップを開設できる手軽さが最大の特長で、システムの保守やセキュリティ対策もサービス提供者に任せられるため、事業者は販売活動に集中できます。
この手軽さの裏返しとして、デザインや機能のカスタマイズ、既存システムとの連携には一定の制約が生じやすい点がデメリットとして挙げられます。これは、完成されたシステムを多くのユーザーで共有利用するSaaSならではの特性です。
そのため、プラットフォーム選定では、自社の事業モデルに合ったものを見極めることが成功の鍵となります。標準機能の範囲、拡張性、サポート体制、そして月額料金や手数料を含めた総コストを総合的に比較検討することが不可欠です。ShopifyやSTORES、W2など多様なサービスが存在するため、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の将来像に合う最適な選択をしましょう。
SaaS型ECに関するよくある質問
-Q: SaaS型ECはASPやパッケージと何が違いますか?
-A: SaaS型ECはクラウド提供で保守やアップデートが自動化され、短納期かつ月額制で始めやすい点が特長です。ASPより拡張性が高く、パッケージより初期負担が小さいため、スピードと柔軟性のバランスに優れます。
-Q: 導入までの期間はどのくらいですか?
-A: 要件によりますが、標準機能中心なら短期間での立ち上げが可能です。デザイン調整や決済・外部連携の設定、テスト、データ移行を経て本番切替を行う流れが一般的です。
-Q: セキュリティやECのガイドラインには対応できますか?
-A: はい。TLSやWAF、脆弱性対策、監視・バックアップなどの運用を継続し、カード情報の非保持化やPCI DSS準拠の決済に対応可能です。ECサイト構築・運用セキュリティガイドラインへの準拠も支援します。