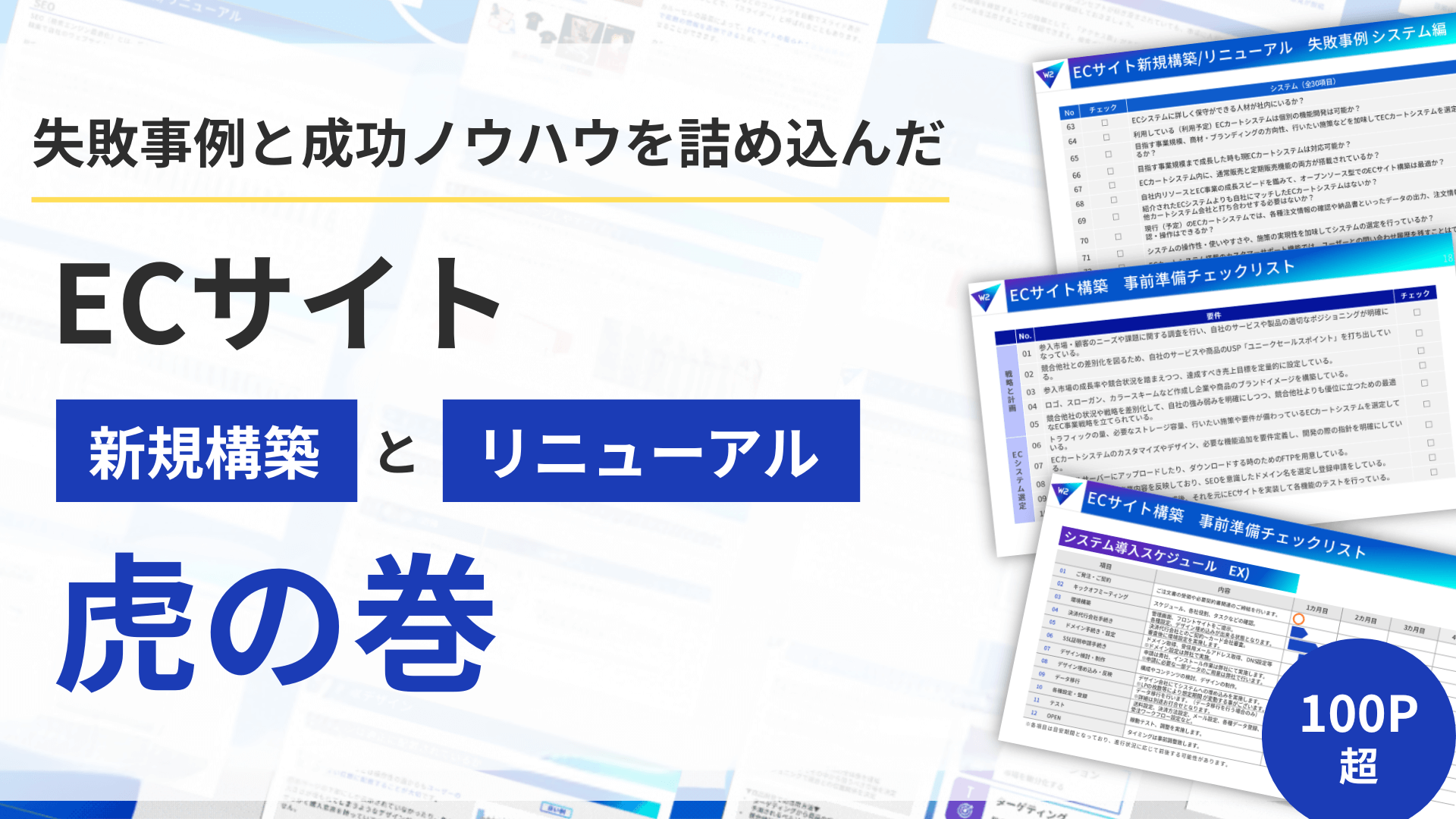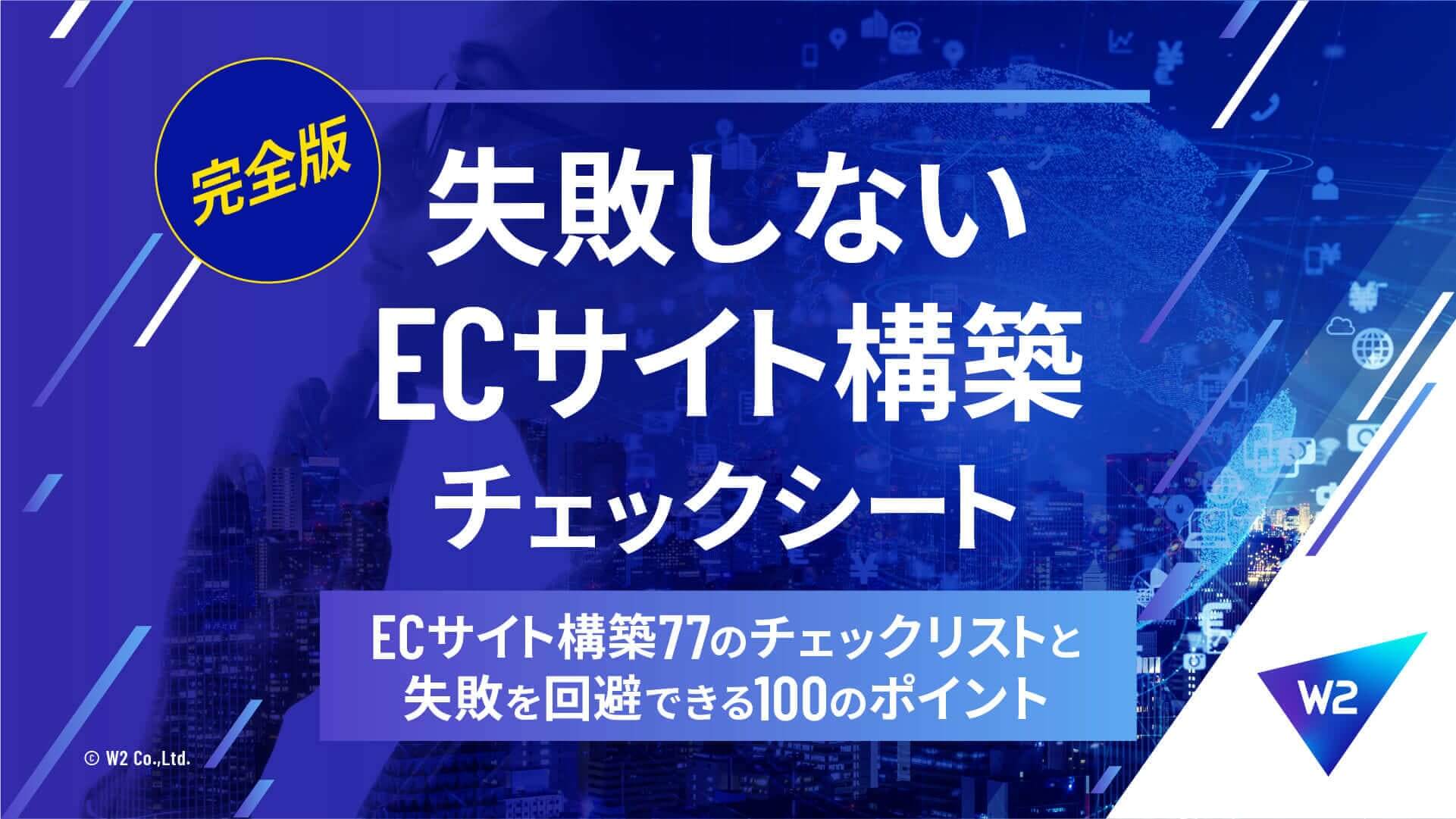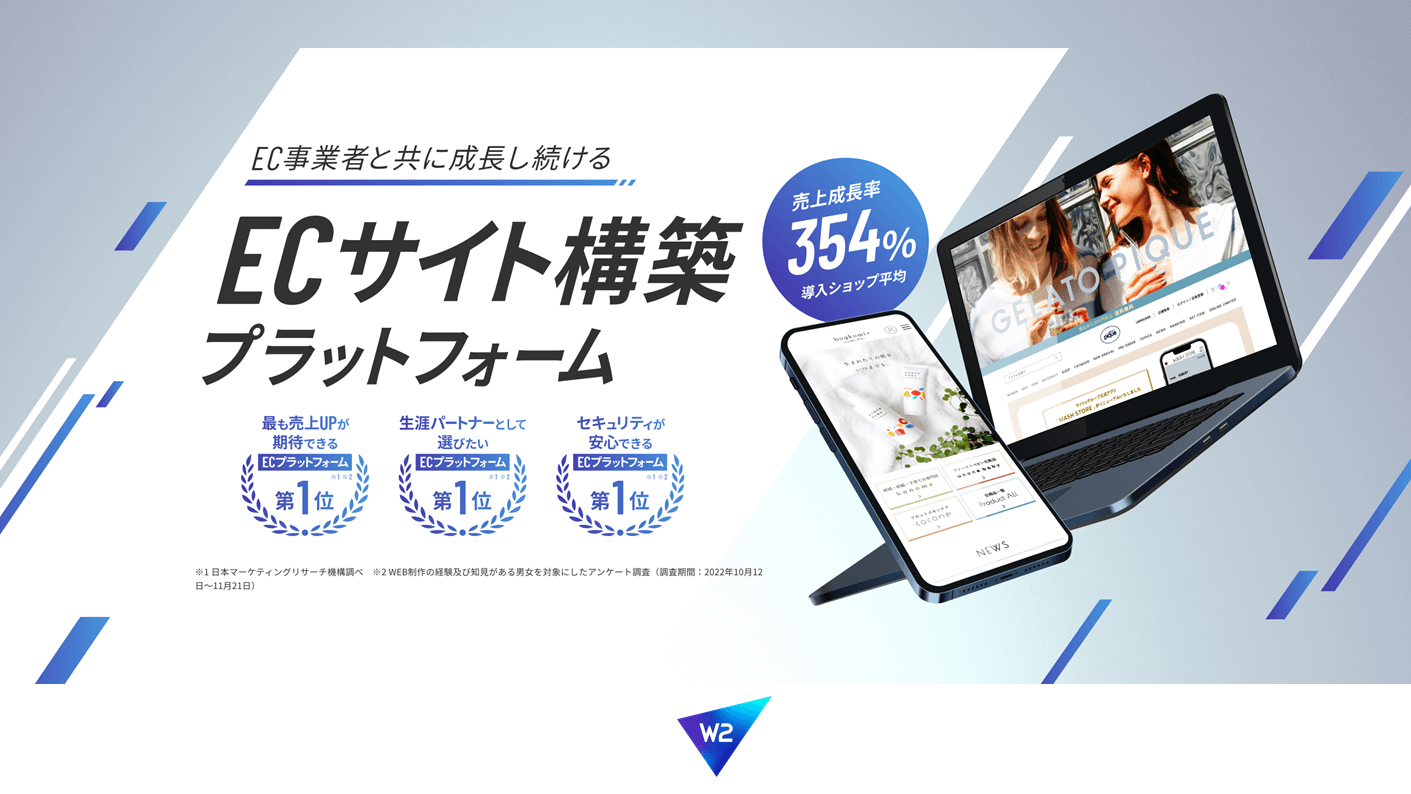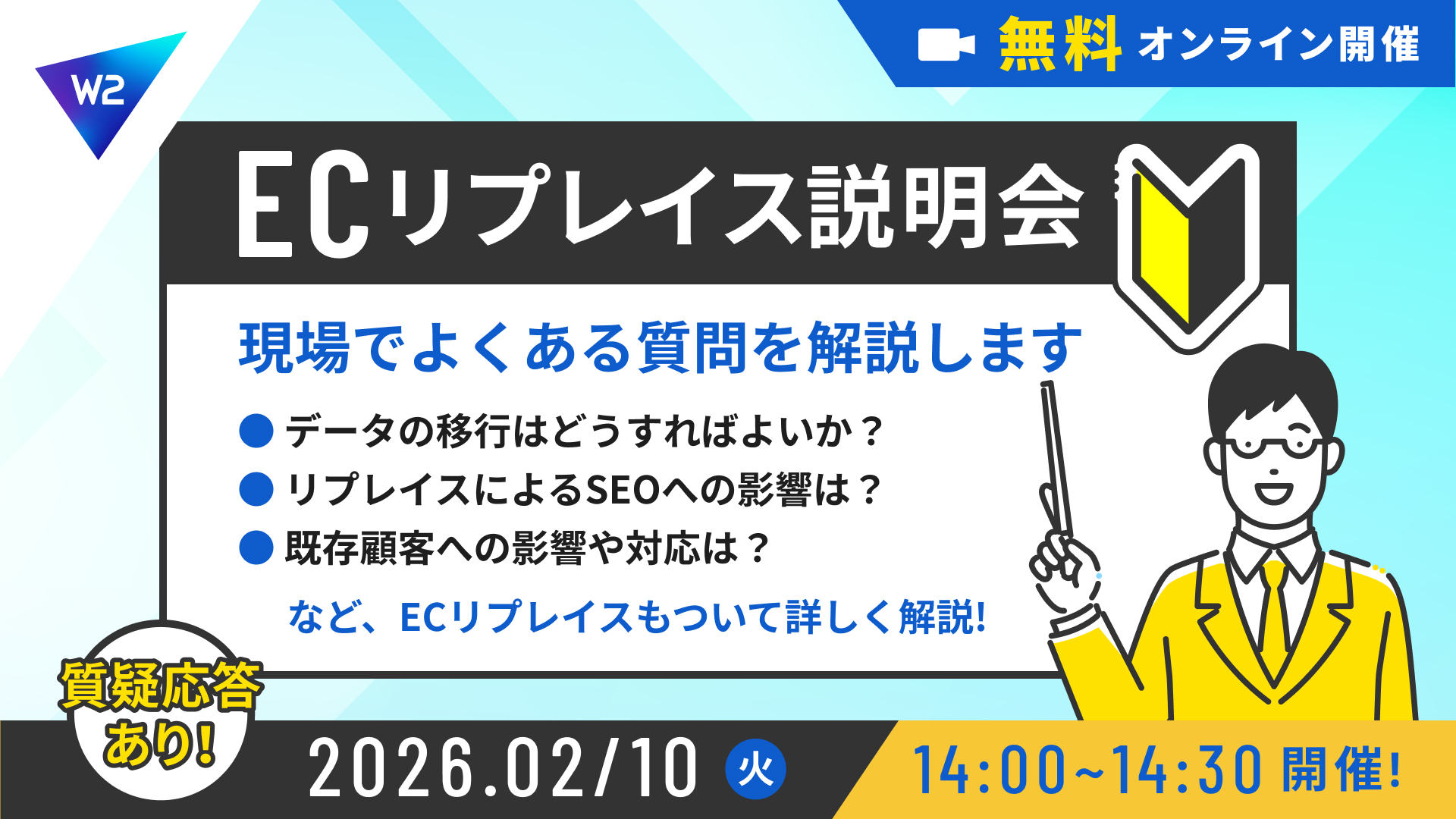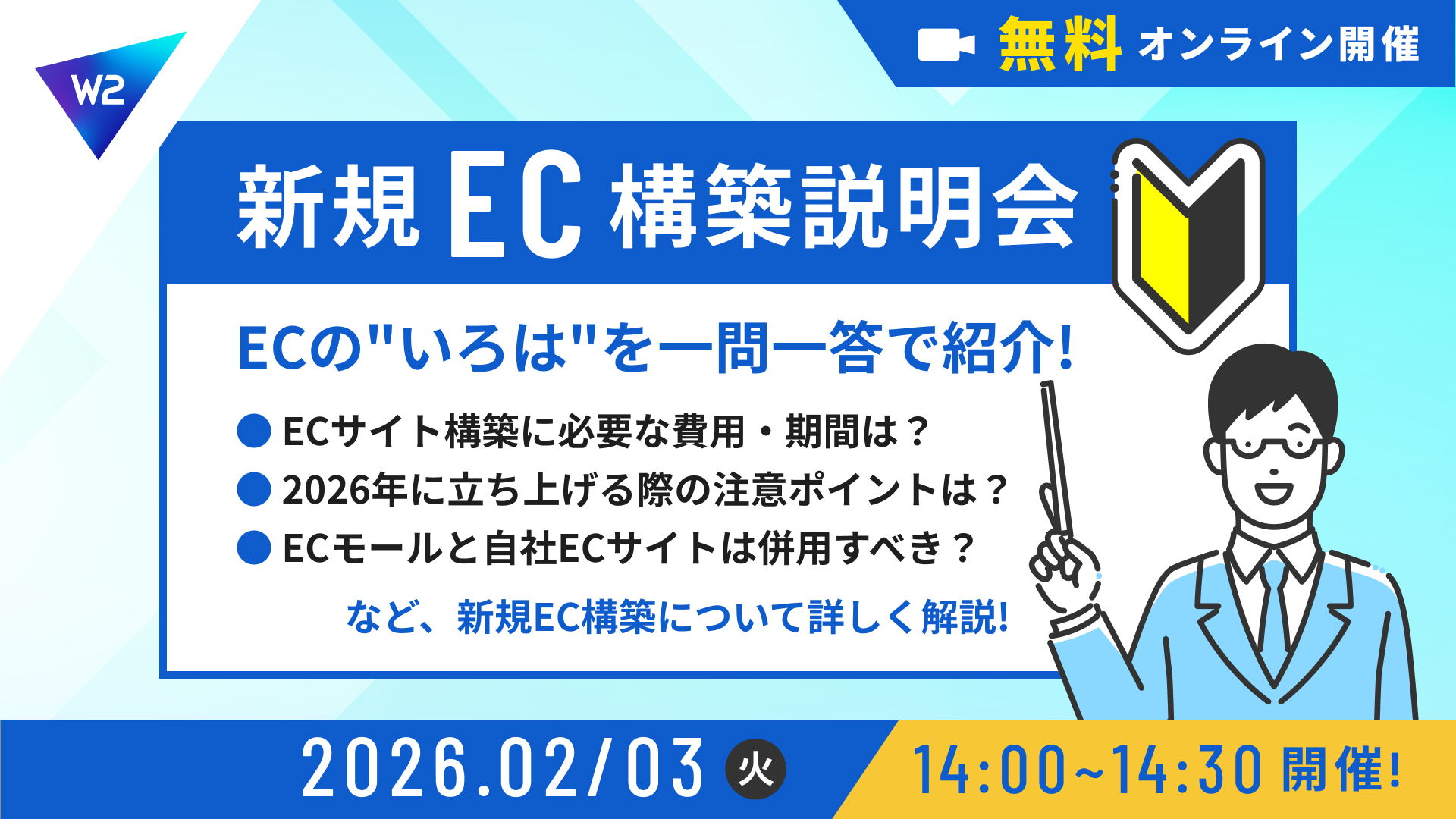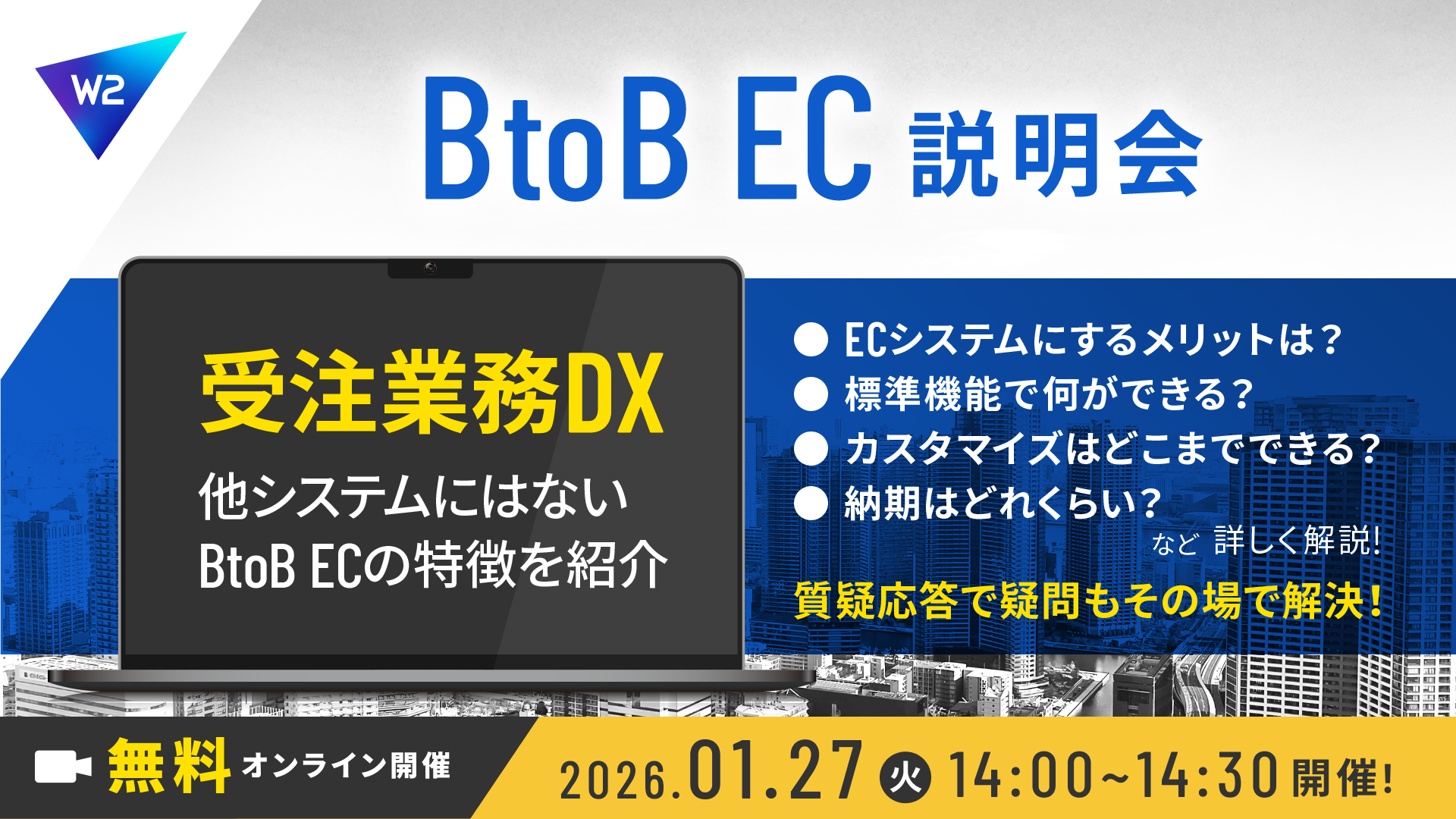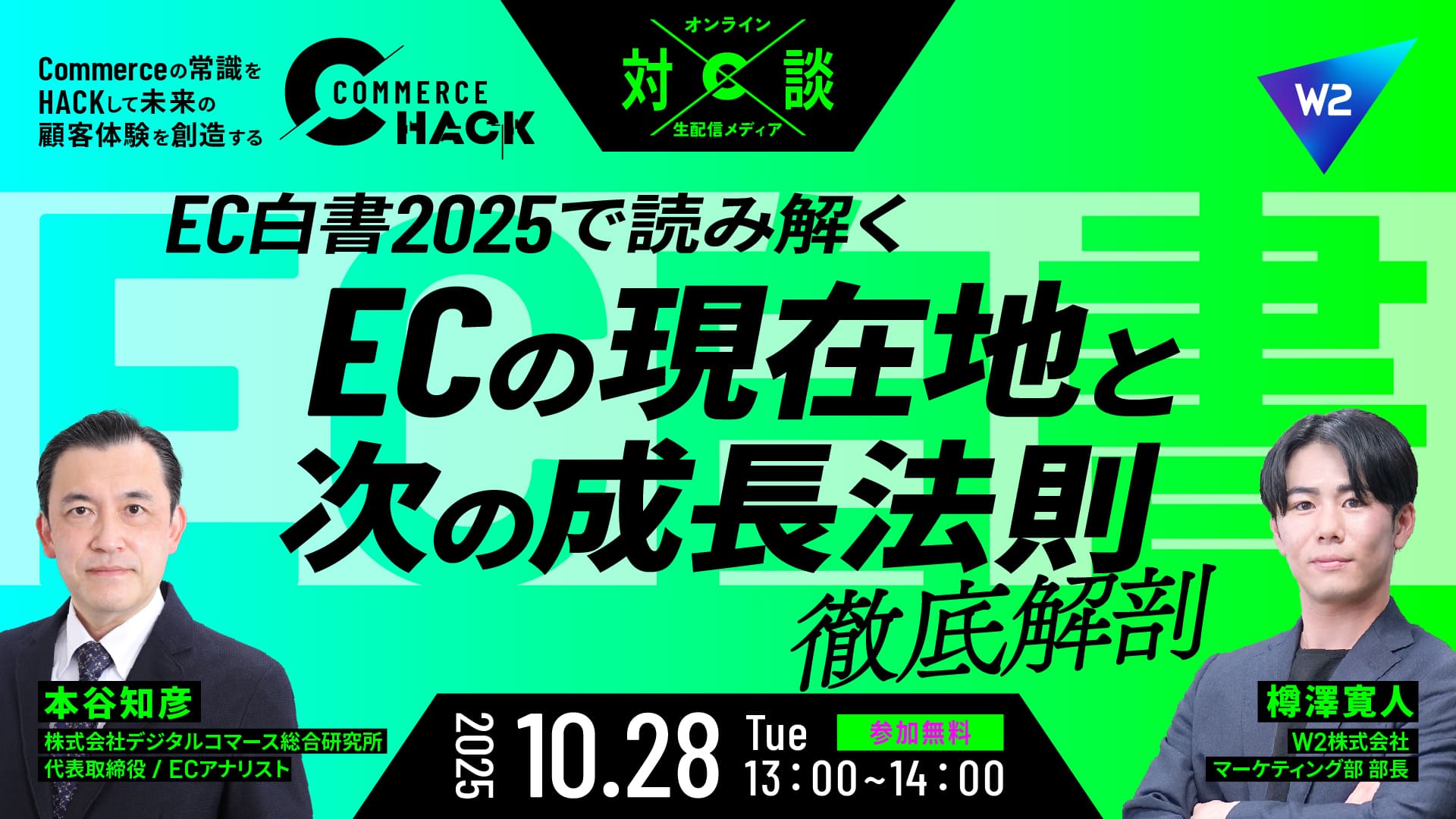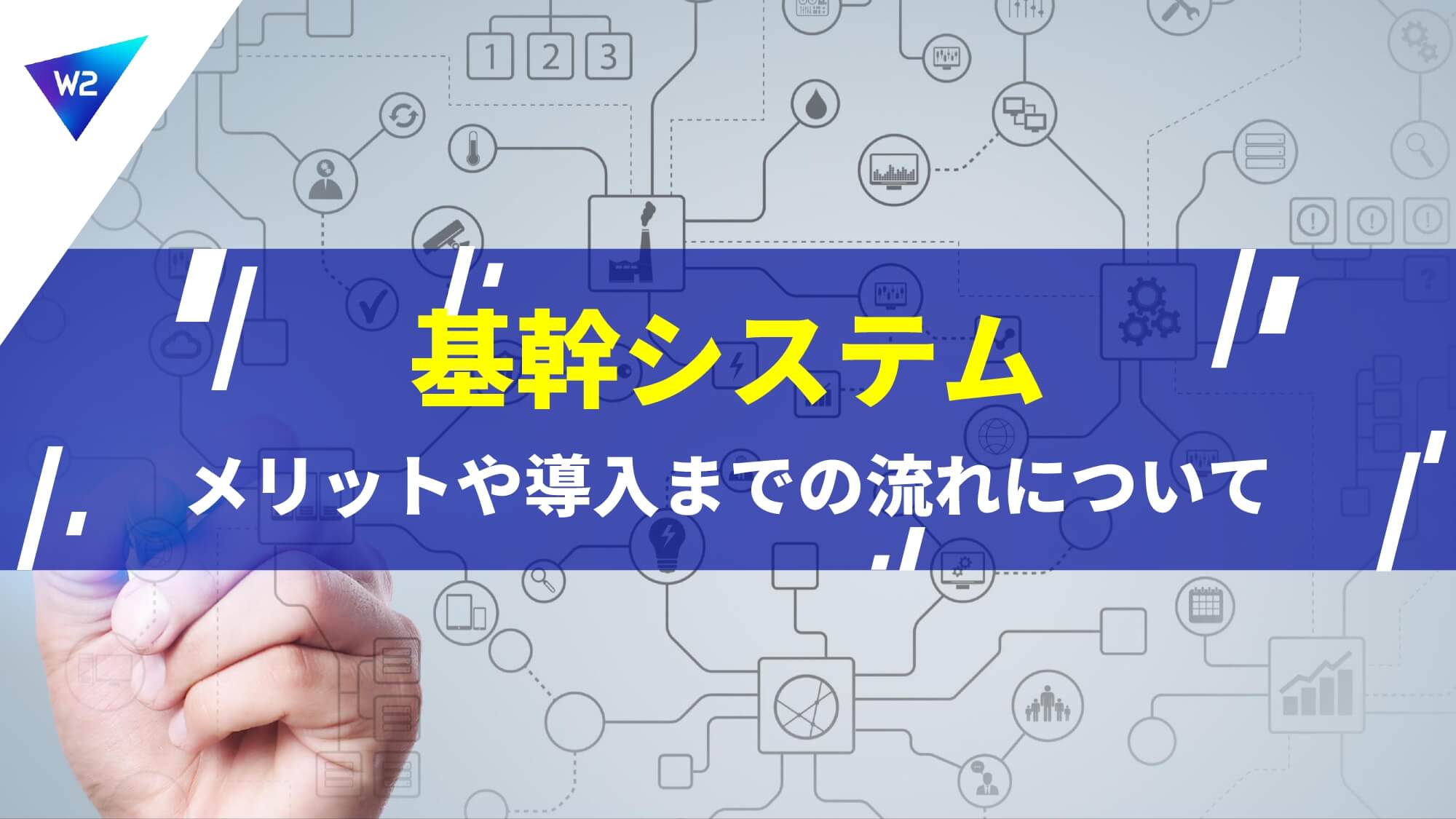
ECサイトの規模が拡大するにつれ、「在庫管理が煩雑で、実店舗とのズレが生じる」「受注処理や出荷作業に追われ、本来注力すべきマーケティング施策に時間を割けない」といったお悩みはありませんか?
このようなバックヤード業務の課題は、ECサイトと基幹システムを「連携」させることで解決できる可能性があります。
ただ、ECサイトと基幹システムの連携を考えている方のなかには、
・基幹システムとの連携は本当に必要?
・具体的にどのような連携方法がある?
などと疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ECプラットフォームを提供する専門家の視点から、ECサイトと基幹システムを連携させる必要性から、具体的なメリット、連携方法、そして失敗しないための重要なポイントまでを網羅的に解説します。
本記事を参考にECサイトと基幹システムを連携させることで業務効率化とWebサイトの品質向上を実現のために参考にして下さい。
1,000社以上の導入実績に基づき、ECサイト新規構築・リニューアルの際に事業者が必ず確認しているポイントや黒字転換期を算出できるシミュレーション、集客/CRM /デザインなどのノウハウ資料を作成しました。
無料でダウンロードできるので、ぜひ、ご活用ください
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
そもそも基幹システムとは?

基幹システムとは、企業の基幹業務を支えるシステムのことです。基幹業務とは、企業の存続や成長に不可欠な業務であり、具体的には、販売管理、在庫管理、生産管理、会計管理、人事給与管理、顧客管理などが挙げられます。
基幹システムは、これらの基幹業務を効率化・自動化することで企業の業務効率や生産性を向上させ、経営の意思決定を支援する役割を担っています。
基幹システムの種類には、以下のようなものがあります。
- 販売管理システム:商品の受注、出荷、在庫管理、売上管理などを行うシステム
- 在庫管理システム:商品の入荷、出荷、在庫状況の把握などを行うシステム
- 生産管理システム:製造工程の管理、原材料や部品の調達、生産計画の立案などを行うシステム
- 会計管理システム:売上、仕入、経費などの会計情報の管理、財務諸表の作成などを行うシステム
- 人事給与管理システム:人事情報の管理、給与計算、勤怠管理などを行うシステム
- 顧客管理システム:顧客情報の管理、営業活動の支援などを行うシステム
基幹システムは、企業の規模や業種によって、導入するシステムや機能は異なります。また、近年では、クラウド型の基幹システムも普及しており、オンプレミス型に比べて導入・運用コストを抑えることができます。
ECサイトに基幹システムの連携が必要になる3つの理由
なぜ、多くのEC事業者が基幹システムとの連携に踏み切るのでしょうか。それは、事業成長に伴って必ず直面する、以下の3つの課題を解決するためです。
- 在庫管理の複雑化と販売機会の損失
- 受注・出荷業務の逼迫と手作業ミスの発生
- データが分断され、正確な経営判断ができない
順に解説します。
1. 在庫管理の複雑化と販売機会の損失
ECサイトだけでなく実店舗や複数のECモールに出店するなど、販売チャネルが増えるほど在庫管理は複雑になります。手動での在庫調整では、下記のような問題が発生しがちです。
- ECサイトで注文が入ったのに在庫がなく、お客様に謝罪・キャンセル対応(欠品による機会損失)
- 実店舗で売れた商品の在庫がECサイト上で減らず、売り越しが発生
- 過剰在庫を抱えてしまい、キャッシュフローが悪化
システム連携により在庫情報を一元化することで、これらの問題を自動的に解決し、販売機会の損失を防ぎます。
2. 受注・出荷業務の逼迫と手作業ミスの発生
受注件数が増加すると、受注データの確認、出荷指示、送り状の作成、サンクスメールの送信といった一連の業務が担当者のキャパシティを超えてしまいます。
手作業に頼っていると、下記のようなヒューマンエラーも起こりやすくなります。
- 商品の送り間違いや住所の入力ミス
- 出荷遅延による顧客満足度の低下
- 業務過多による従業員の疲弊
システム連携によって受注から出荷までのフローを自動化することで、業務負担を大幅に軽減し、ミスなく迅速な顧客対応を実現できます。
3. データが分断され、正確な経営判断ができない
ECサイトの売上データ、実店舗の売上データ、顧客データ、在庫データなどが各システムに分散していると、「どの商品がどのチャネルで一番売れているのか」「どの顧客層が優良顧客なのか」といった分析が困難になります。
勘や経験に頼った経営判断は、現代のEC市場では通用しません。データを一元管理・分析することで、データに基づいた正確な経営戦略の立案が可能になります。
ECサイトと基幹システムを連携する4つのメリット
ECサイトと基幹システムを連携するメリットは、大きく分けて以下の4つが挙げられます。
- 業務効率化・自動化による時間とコストの削減
- データの統合・分析による経営の意思決定の改善
- セキュリティの向上
- 顧客体験(CX)の向上
順に解説します。
1. 業務効率化・自動化による時間とコストの削減
従来は手作業で行っていた業務をシステム化・自動化することができます。これにより、業務の処理速度が向上し、人的ミスの防止にもつながります。また、業務効率化・自動化によって、人件費や時間などのコストを削減することができます。
例えば、販売管理システムを導入することで、受注・出荷・在庫管理などの業務を自動化することができます。これにより、業務の処理速度が向上し、人的ミスの防止にもつながります。また、業務効率化・自動化によって、人件費や時間などのコストを削減することができます。
2. データの統合・分析による経営の意思決定の改善
これまで個別に管理されていたデータを一元的に管理することができます。これにより、経営に必要なデータをリアルタイムに把握・分析できるようになり、経営の意思決定の質を向上させることができます。
例えば、販売管理システムと会計管理システムを連携することで、売上データと原価データなどのデータを一元的に管理することができます。これにより、経営に必要なデータをリアルタイムに把握・分析できるようになり、経営の意思決定の質を向上させることができます。
3. セキュリティの向上
データの暗号化やアクセス制限などのセキュリティ対策を強化することができます。これにより、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクを低減することができます。
基幹システムの導入は、企業にとって大きな投資となりますが、上記のようなメリットを享受することで、企業の競争力を高め、事業の成長に貢献することができます。
4. 顧客体験(CX)の向上
迅速な出荷、正確な在庫表示、パーソナライズされた情報提供などは、顧客満足度を高める上で非常に重要です。
システム連携をすることで、バックヤードの安定稼働を実現し、結果として顧客にストレスのない購買体験(CX)を提供することができます。
これにより、リピート購入やブランドへの信頼感を醸成し、LTV(顧客生涯価値)の向上に大きく貢献します。
基幹システムの導入方法

基幹システムの導入方法は、大きく分けて以下の4つのステップに分けられます。
- 導入目的の明確化
- システム選定
- 要件定義
- 導入・運用
1. 導入目的の明確化
基幹システムを導入する目的を明確にすることで、システム選定や要件定義をスムーズに進めることができます。導入目的を明確にする際には、以下の点について検討しましょう。
- 現状の課題を解決するために、どのようなシステムを導入する必要があるのか
- システム導入によって、どのような成果を達成したいのか
- システム導入にかかるコストや期間はどの程度か
2. システム選定
自社のニーズに合ったシステムを複数のベンダーから比較検討して選定します。システム選定の際には、以下の点について検討しましょう。
- 機能:自社の業務に必要な機能が搭載されているか
- 価格:自社の予算に合っているか
- サポート体制:導入後のサポート体制が充実しているか
3. 要件定義
自社の業務要件を明確にして、システムに必要な機能を定義します。要件定義をしっかりと行うことで、システム導入後の不具合やトラブルを防止することができます。要件定義を行う際には、以下の点について検討しましょう。
- 業務フロー:現状の業務フローを洗い出し、システム化後の業務フローを検討する
- データ:システムに登録するデータの種類や量を検討する
- セキュリティ:データのセキュリティ対策を検討する
4. 導入・運用
選定したシステムを導入し、運用を開始します。導入・運用には、専門知識やスキルが必要となるため、ベンダーのサポートを活用することも検討しましょう。以下の点について認識しておくことをおすすめします。
- トレーニング:従業員にシステムの使い方を教育する
- テスト:システムを本番環境で稼働させて、不具合やトラブルを検証する
- 運用体制:システムの運用に必要な体制を整える
基幹システムの導入は、企業にとって大きな投資となります。導入を検討する際には、上記のステップを踏んで、慎重に進めることが重要です。
ECサイトと基幹システムを連携する3つの方法
連携方法はいくつかありますが、主に以下の3つの手法が用いられます。それぞれ特徴が異なるため、自社の状況や予算に合わせて選択する必要があります。
1. API連携
API(Application Programming Interface)とは、異なるシステム同士が情報をスムーズにやり取りするための公式な「窓口」や「通訳」のようなものです。API連携は、リアルタイムでのデータ同期が可能で、現在最も主流で推奨される方法です。
この方法の最大のメリットは、リアルタイム性の高さにあります。ECサイトで注文が入った瞬間に基幹システムの在庫が自動で引き落とされるため、売り越しや欠品といった販売機会の損失を限りなくゼロに近づけることができます。顧客にとっても常に正確な在庫状況が表示されるため、安心して買い物ができるという顧客体験の向上にも繋がります。
一方で、開発コストが発生する点は考慮すべきです。連携先のAPI仕様を理解し、それに合わせて接続プログラムを開発する必要があるため、専門知識を持つエンジニアのアサインや外注費用がかかります。また、連携したいシステム側が外部連携用のAPIを公開していなければ、この方法自体が選択できないという制約もあります。
2. ファイル連携(CSV連携)
一方のシステムから受注データや在庫データなどをCSV(Comma Separated Values)形式のファイルで出力し、もう一方のシステムに手動または定時バッチ処理で取り込む、古くからある連携方法です。
この方法のメリットは、比較的低コストで実現できる点です。多くのシステムが標準機能としてCSVファイルの入出力機能を持っているため、大規模な開発が不要なケースが多く、短期間かつ低予算で導入できる可能性があります。
しかし、リアルタイム性に欠けるという明確なデメリットが存在します。データの同期が1日に1回の夜間バッチなどに限定されるため、その間に発生した在庫の変動を即時反映できません。
これにより、日中に実店舗で売れた商品の在庫がECサイト上で減らず、売り越しが発生するといったリスクが残ります。また、担当者が手動でファイルをやり取りする場合は、アップロード忘れやファイルの取り違えといったヒューマンエラーが発生する可能性も常に付きまといます。
3. DB連携(データベース連携)
互いのシステムの心臓部であるデータベース(DB)同士を直接接続し、データを参照・更新する方法です。非常に高度な連携手法と言えます。
最大のメリットは、連携の自由度が極めて高いことです。データベースのテーブル構造を直接操作できるため、APIでは対応できないような非常に複雑で特殊な業務要件にも対応できる、高い柔軟性を持ちます。完全に自社の業務フローに合わせた独自の連携ロジックを組むことが可能です。
その反面、デメリットも非常に大きくなります。データベースの構造を深く理解した上で開発を行う必要があり、高度な技術力と高額な開発コストが求められます。
さらに、システムの根幹であるデータベースに直接アクセスするため、万が一の誤操作によるデータ破損や、外部からの不正アクセスによる情報漏洩など、セキュリティリスクが他の方法に比べて格段に高くなるという重大な懸念点も持ち合わせています。
【事業規模別】基幹システム連携の選び方

最適な連携方法は、企業の事業規模やビジネスモデルによって大きく異なります。ここではW2株式会社の豊富な実績から、事業規模別のポイントを解説します。
ケース1. 年商数億円規模のEC企業
このフェーズでは、コストを抑えつつ業務効率化を実現することが重要です。
まずはファイル連携(CSV連携)や、ECカートシステムが標準提供している簡易的なAPI連携から始めるのがおすすめです。すべての業務を最初から完全自動化するのではなく、「在庫連携」や「受注連携」など、最も課題となっている部分からスモールスタートしましょう。
ケース2. 年商数十億円以上の中〜大規模EC企業
多店舗展開や複雑な商品管理、独自の業務フローが存在する場合が多く、柔軟な連携が求められるため、API連携を主軸とした本格的なシステム構築が必須となります。
この規模になると、ECカートシステム側のカスタマイズ性や拡張性が極めて重要になります。将来的な事業拡大を見据え、柔軟に機能追加や改修が可能なECパッケージやクラウドECプラットフォームを選定しましょう。
ケース3. D2C/リピート通販事業者様
年商の大小に限らず、サブスクリプションモデルなど、独自の販売方法を採用している場合、定期購入のサイクル管理や顧客情報と紐づいた細やかな分析が求められます。基幹システムとの連携においても、定期購入の受注データを正確に連携できるかが重要な選定ポイントとなります。
基幹システム連携で失敗しないための5つの確認ポイント
基幹システムを選ぶ際のポイントは、大きく分けて以下の5つが挙げられます。
5つのポイント
- 導入目的を明確にする
- 自社のニーズに合ったシステムを選定する
- 複数のベンダーから見積もりを取る
- デモやトライアルを活用する
- ベンダーの信頼性を確認する
1. 導入目的を明確にする
基幹システムを導入する目的を明確にすることで、システム選定や要件定義をスムーズに進めることができます。導入目的を明確にする際には、以下の点について検討しましょう。
- 現状の課題を解決するために、どのようなシステムを導入する必要があるのか
- システム導入によって、どのような成果を達成したいのか
- システム導入にかかるコストや期間はどの程度か
2. 自社のニーズに合ったシステムを選定する
自社の業種や規模、業務内容に合ったシステムを選定する必要があります。また、システムの機能や価格、サポート体制なども比較検討しましょう。
基幹システムには、販売管理システム、在庫管理システム、生産管理システム、会計管理システム、人事給与管理システム、顧客管理システムなど、さまざまな種類があります。自社の業種や規模、業務内容に合ったシステムを選定することで、システム導入の効果を最大化することができます。
システムの機能は、自社の業務に必要な機能が搭載されているかどうかを検討しましょう。また、価格は、自社の予算に合っているかどうかを検討しましょう。サポート体制は、導入後のサポート体制が充実しているかを検討しましょう。
3. 複数のベンダーから見積もりを取る
複数のベンダーから見積もりを取ることで、価格や機能、サポート体制などを比較検討することができます。見積もりを取る際には、同じ条件で比較できるようにしましょう。
4. デモやトライアルを活用する
デモやトライアルを活用することで、実際にシステムを操作して、自社に合っているかどうかを判断することができます。デモやトライアルを実施する際には、自社の業務に即したシナリオで操作できるようにしましょう。
5. ベンダーの信頼性を確認する
ベンダーの信頼性を確認するために、実績やサポート体制などを調査しましょう。ベンダーの実績は、過去に導入した企業の評価や事例などを参考にしましょう。サポート体制は、導入後のサポートが充実しているかを検討しましょう。
基幹システムの導入は、企業にとって大きな投資となります。導入を検討する際には、上記のポイントを押さえて、慎重に進めることが重要です。
基幹システムを導入することで、企業の業務効率や生産性の向上、経営の意思決定の改善、セキュリティの向上など、さまざまなメリットが期待できます。上記のポイントを押さえて、基幹システムを導入することで、企業の競争力を高め、事業の成長に貢献することができます。
中〜大規模ECの複雑な基幹連携なら「W2 Unified」がおすすめ!
ここまで解説してきた通り、事業が成長すればするほど、基幹システムとの連携は複雑かつ高度になります。特に年商数十億円を超える中〜大規模EC事業者様が、ASPカートの制約やフルスクラッチ開発のコストに悩むケースは少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、弊社W2株式会社が提供するECプラットフォーム「W2 Unified」です。
「W2 Unified」は、1,000以上の豊富な標準機能に加え、フルスクラッチ並みの柔軟なカスタマイズ性を誇ります。1,000社以上の導入実績により、お客様が利用している様々な基幹システムとのシームレスな連携を数多く実現してきました。
- 複雑な在庫引き当てロジックにも対応
- 独自の受注フローや出荷指示にも柔軟に連携
- D2C/サブスクリプションモデルに特化した機能との連携実績も豊富
「既存のシステムでは要件が合わない」「将来の事業拡大に耐えうるECシステムを探している」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度W2にご相談ください。
まとめ
今回は、基幹システムの概要について紹介しました。
- 基幹システムの種類について
- 導入メリットについて
- 導入方法について
- 基幹システムの選び方について
ECサイト運営をスタートさせる時に重要なことは、中長期的な目線をもって運営に当たることが大事になります。
そのため、自社のEC運営において中長期的に売上向上を狙えるシステムを選定しましょう。
ECサイトの基幹システム連携に関するよくある質問
Q: ECサイトの規模がまだ小さいのですが、それでも基幹システムとの連携は必要ですか?
A: 現時点では必須ではありませんが、将来的に取扱商品数や販売チャネルの増加を見込んでいる場合、早い段階で連携を視野に入れたシステム選定が重要です。在庫管理や受注処理などの手作業に限界を感じ始めたら、連携を具体的に検討するタイミングと言えます。
Q: API連携、ファイル連携など、どの連携方法を選べば良いか分かりません。
A: 「リアルタイム性」と「コスト」のバランスが重要な基準です。在庫のズレによる販売機会の損失をなくしたい場合は、リアルタイム性が高いAPI連携が最適です。一方、まずはコストを抑えて業務負担を軽減したい場合は、ファイル連携からスモールスタートするのも有効な選択肢です。
Q: 基幹システムとの連携は専門知識が必要そうで、自社で対応できるか不安です。
A: 連携には専門知識が必要ですが、すべてを自社で対応する必要はありません。まずはECカートシステムのベンダーに相談することをおすすめします。実績豊富なベンダーであれば、お客様の課題や事業フェーズに合わせた最適な連携方法を提案してくれます。