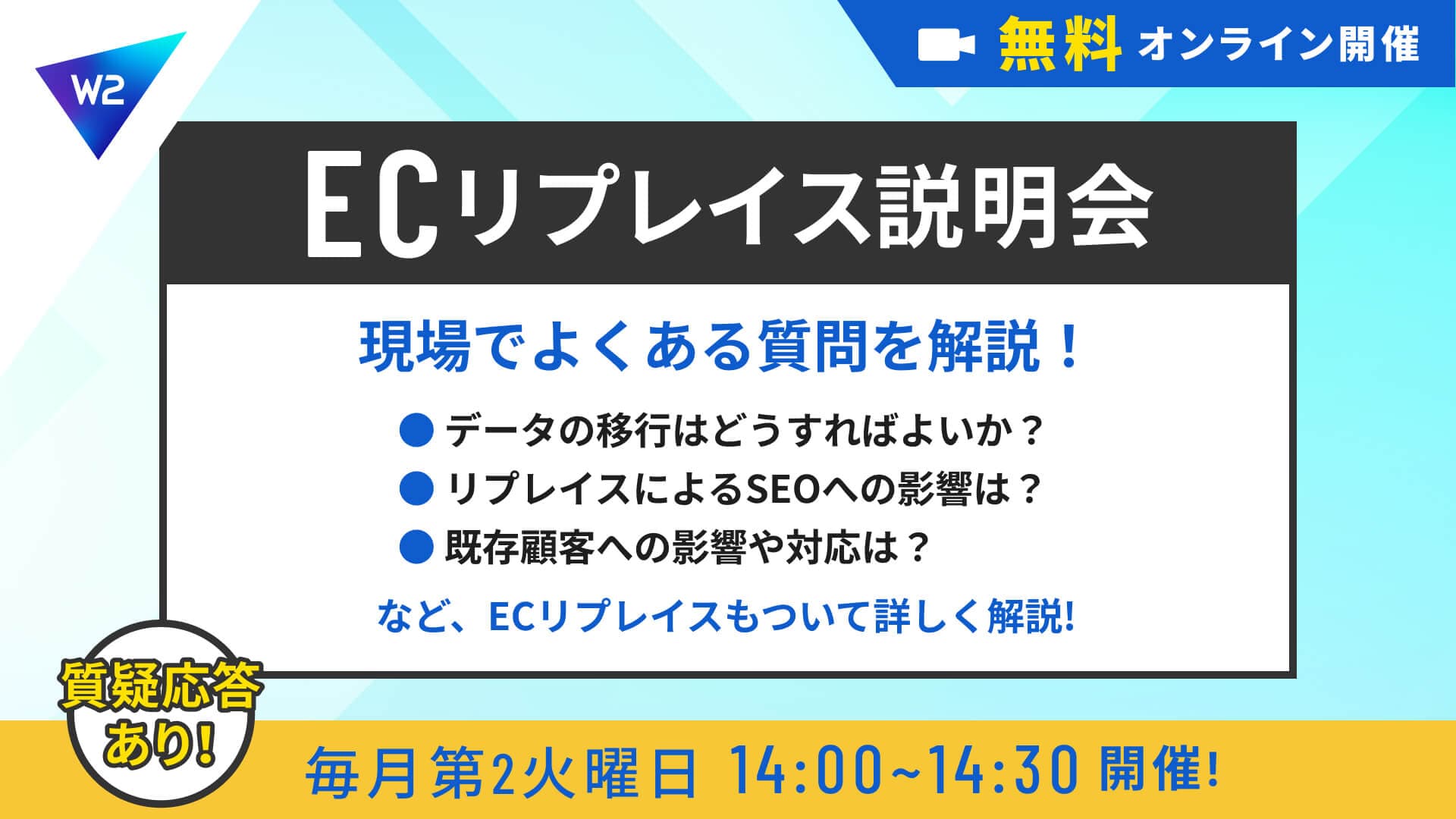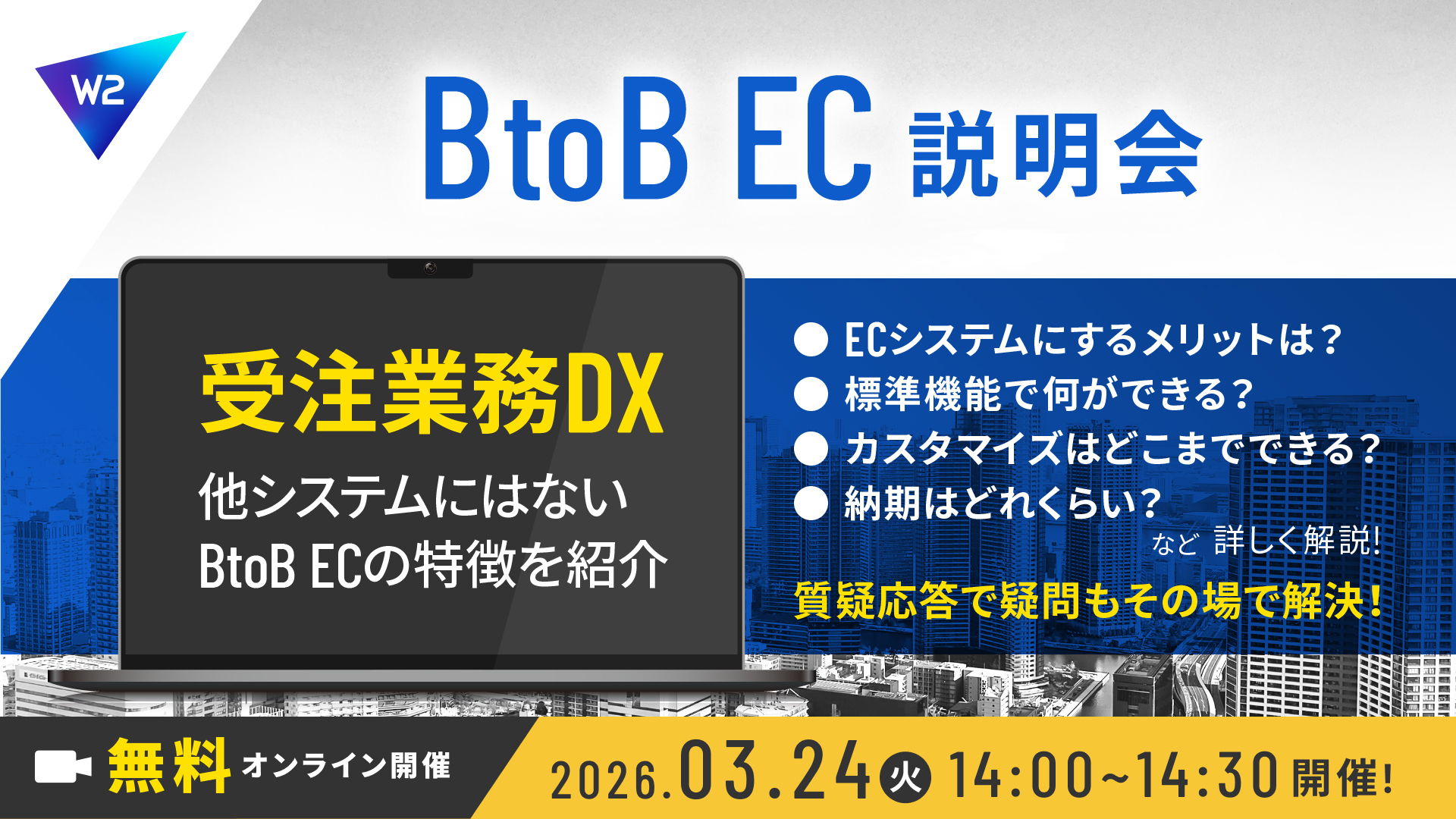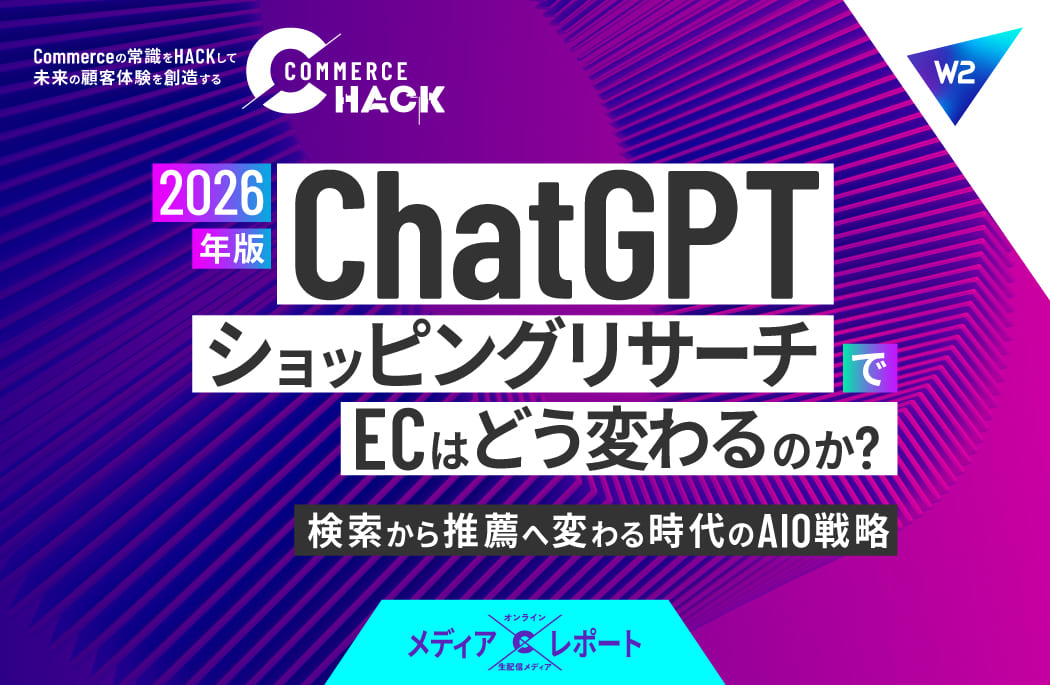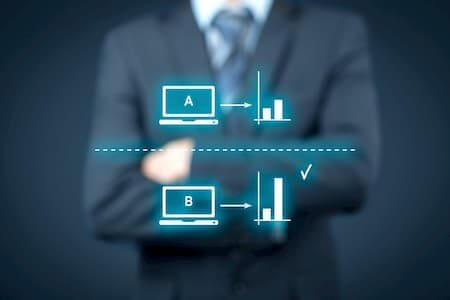
ECサイトを運営していくうえで重要なことは、サイト上でいかにたくさんの商品を売るかという点です。
より多くの商品が売れるECサイトを作るためには、広告費を増やしてサイトへの訪問数を増やす方法や、キャンペーンなどで購入を促す方法などが考えられます。 このような対策はもちろん重要ですが、短期的な売上アップになりがちですので、長期的に売上を確保できるような対策を取ることも大切です。
低コストで長期的に続けていける施策の1つがA/Bテストです。
A/Bテストとは、サイトの1つの要素に対してAとBの2パターンを用意し、それぞれのアクセス数やコンバージョン率を測定し、どちらが効果的だったのかを調査するテストです。 2パターン以上を比較する場合もあります。
今回は、A/Bテストを活用してECサイトを改善する際のポイントと注意点について紹介していきますので、参考にしてください。
ECサイトのLP制作ポイントについて詳しく知りたい方は以下の記事を活用してください。
この記事の監修者

神戸大学在学中にEC事業を立ち上げ、自社ECサイトの構築から販売戦略の立案・実行、広告運用、物流手配に至るまで、EC運営の全工程をハンズオンで経験。売上を大きく伸ばしたのち、事業譲渡を実現。
大学卒業後はW2株式会社に新卒入社し、現在は、ECプラットフォーム事業とインテグレーション事業のマーケティング戦略の統括・推進を担う。一貫してEC領域に携わり、スタートアップから大手企業まで、あらゆるフェーズのEC支援に精通している。
ECサイトでA/Bテストを活用する2つのコツ
A/Bテストにおいては、一定期間、AとBの2パターンを表示させ、それぞれのパターンにおける商品の購入件数やアクセス数などの数値を測定します。
どの数値で比較するかは、状況に応じて設定します。 また、数値はGoogleアナリティクスなどで測定するのが一般的でしょう。
A/Bテストは、広告のような新規顧客の流入を増やす施策というよりは、テスト結果に基づきサイトの改善を行うことで、よりコンバージョン率の高いサイトを作るための方法といえます。
以下のようなコツを把握して、適切なA/Bテストを実施しましょう。
1.ECサイトのA/Bテストはページごとのゴールの把握がポイント
A/Bテストにおいては、一定期間、AとBの2パターンを表示させ、それぞれのパターンにおける商品の購入件数やアクセス数などの数値を測定します。
どの数値で比較するかは、状況に応じて設定します。 また、数値はGoogleアナリティクスなどで測定するのが一般的でしょう。
A/Bテストは、広告のような新規顧客の流入を増やす施策というよりは、テスト結果に基づきサイトの改善を行うことで、よりコンバージョン率の高いサイトを作るための方法といえます。
以下のようなコツを把握して、適切なA/Bテストを実施しましょう。
2.A/Bテストはアクセスの多いページから始めるほうが結果を得やすい
A/Bテストは、アクセス数の多いページで実施するほうが結果を得やすいといえるでしょう。
A/Bテストは、一定期間中の訪問者をA、Bそれぞれのページに振り分けて行うテストですので、ある程度のアクセス数がなければ計測が成立しません。
たとえば、広告を出稿していてトップページよりもランディングページのほうがアクセスが多いという場合には、ランディングページにてA/Bテストを実施するほうが効果的でしょう。
もちろん、ほかのページでも、ある程度のアクセスがあるならば問題ありません。
商品の個別ページのほうが検索順位が高く、アクセス数が多いという場合に、商品ページにてテストを実施するとよい結果が得られるかもしれません。
ECサイトによってアクセスが集中しているページはさまざまですので、テストを開始する前にどのページから手をつけていくべきかを確認することも重要です。
また下記の資料では、顧客の購買心理に基づいて顧客が求めているニーズを解説し、購買導線ごとにECサイトのCVRを改善するチェック項目をご紹介します。
ECサイトで離脱率を減少させて、CVRを改善し売上を向上させたい方はぜひこの機会に閲覧ください。
ECサイトでA/Bテストを活用する2つのメリット

ECサイトにおいてA/Bテストを活用することで、コンバージョン率の上昇や離脱率の低下といったメリットが得られるでしょう。
1.A/Bテストに基づきよりよいページを作成することでコンバージョン率が上昇する
A/Bテストの結果に基づきサイトを改善することで、コンバージョン率の上昇が期待できます。
コンバージョン率の高いサイトを作れば、アクセス数が少なくても効率よく商品が売れていきます。
逆にアクセス数が多くてもコンバージョン率が低いと、あまり意味がありません。
コンバージョン率を改善できれば、集客に割いていた広告費を削減することも可能です。
その分の費用をリピート顧客の育成に回したりもできるので、積極的にテストを実施し、サイトを改善していきましょう。
2.A/Bテストにより直帰率の低下も期待できる
A/Bテストに基づいてサイトの改善を図ることで、直帰率の低下も期待できます。
たとえば、テスト結果を参考にして商品ページのデザインや購入ボタンの位置などを改善すれば、ボタンが押される可能性もアップします。
それにより、直帰してしまうユーザーも減り、売上アップも期待できます。
直帰率が低いということは、ユーザーのニーズにマッチしているともいえます。
SEOにおいて、ユーザーのニーズに応える価値がある情報の提供は重要な要素です。
そのため、A/Bテストによる直帰率低下はSEO対策としての効果も見込めます。
また下記の資料では、顧客の購買心理に基づいて顧客が求めているニーズを解説し、購買導線ごとにECサイトのCVRを改善するチェック項目をご紹介します。
ECサイトで離脱率を減少させて、CVRを改善し売上を向上させたい方はぜひこの機会に閲覧ください。
ECサイトでA/Bテストをするときの3つの注意点
さまざまなメリットがあるA/Bテストですが、実施する際の注意点もあります。順番に見ていきましょう。
1.明確な仮説を立てなければ結果を正確に読み取ることができない
A/Bテストにおいてパターンを作る際に重要なのは、明確な仮説を持ってパターンを作るということです。
A/Bテストの結果から見えることは「AとBのどちらのパターンがよい結果(数値)を出したか」ということだけです。
仮説を持たずに結果を見ても数値の意味が読み取れず、サイトの改善にもつながりません。
テストを行う前に、たとえば以下のような仮説を立て、AとBのパターンを作成しましょう。
- ・ターゲットユーザーが女性なので、モデル写真も女性のほうが購入ボタンが押されやすいのではないか?
(A:男性モデルのパターン、B:女性モデルのパターンを作る) - ・実際に商品を使っている場面が想像できるような写真にしたほうがよいのではないか?
(A:商品のみのパターン、B:商品を使っている人物のパターンを作る)
このような仮説を立てて検証を行い、なぜこのパターンが優れていたのかということを把握することが大切です。
2.一度に複数の要素を変えてテストを行うと結果の検証がしにくい
A/Bテストは、一定期間継続してデータを集めるため、どうしても時間がかかってしまいます。
そのため一気に結果を出したいと思い、複数の項目を変えてA/Bパターンを作ってテストを行うという事例を見かけることがあります。
たとえば、商品ページのA/Bテストを行う場合、
- 画像を変える
- 文言を変える
- ボタンのカラーを変える
- 背景のカラーを変える
といったテストの仕方がありますが、2つ以上の要素を組み合わせて行うと、テスト結果に対してどの施策が要因になっているのかの判断が難しいでしょう。
A/Bテストは細かい変更を重ねていく施策になので、「文言はこういう言い回しにしたほうがよい」「ボタンはこの色がよい」といった小さなノウハウを蓄積するためにも、一度のテストで複数要素の検証を行わないようにしてください。
3.長期的な結果を見失わないようにするべき
たとえば、商品カートのデザイン変更のような、利用者の操作性を左右するA/Bテストを行う場合、操作方法が変わったことにより離脱する人が増えることがあります。
これは、操作がスムーズになりユーザーの導線が向上したとしても、「これまでと違う」という拒否反応が発生してしまうことが1つの原因です。
こういったテストの場合は、通常のテストのような1週間や10日間でテストを行うのではなく、数ヵ月のような長期間のテストで行うことをおすすめします。
そして、A/Bテストの結果だけで判断するのではなく、さまざまな観点から判断することで長期的に見てコンバージョン率の高いECサイトが完成していきます。
可能であれば訪問者へのアンケートなどで利用者の生の声を聞くこともよい判断材料になるかもしれません。
大幅な変更を伴うものの場合には、A/Bテストの結果はあくまで指標の1つとして考えるようにしましょう。 W2 Unifiedは、商材ジャンルを問わず多様な商品の販売に対応した中大規模事業者向けのECプラットフォームです。実店舗とECの在庫・顧客情報のリアルタイム連携や、消費者向け・法人向けが混在するEC運営も一元管理できます。

さらに、柔軟なカスタマイズ性により、事業戦略や運用フローに合わせた理想的なECサイト構築を実現します。
ECサイトの成長にはA/Bテストの繰り返しが必要

1回のテストで把握できる内容は限られています。随時、テストを行いECサイトを成長させていきましょう。
サイト内のさまざまな箇所のA/Bテストを行うことが大切
A/Bテストを行ううえでは、テストする場所を変えたりテストの目的を変えたりして続けていくことが大切です。
一度目のテストでよい結果が出た箇所であっても、そのほかの箇所でテストを続けていった結果、もう一度ここを改善しなければいけないということも十分に起こりえます。
ECサイトの利用者が脱落することなく商品を購入するために何をしたらよいのかを常に考え続けなければいけない、という意味ではA/Bテストは永遠に終わらない作業といえます。
コンバージョン率や月あたりの新規会員登録数など、目標とする数字を決めてそれに向かってテストを行っていくことで、失速することなく安定してテストを続けることができるでしょう。
また下記の資料では、顧客の購買心理に基づいて顧客が求めているニーズを解説し、購買導線ごとにECサイトのCVRを改善するチェック項目をご紹介します。
ECサイトで離脱率を減少させて、CVRを改善し売上を向上させたい方はぜひこの機会に閲覧ください。
同じテストでも時期を変えて行うと違う結果が出ることもある
A/Bテストを繰り返し行って優れたサイトを作っても、そのときの流行や利用者の変化によりコンバージョンが徐々に落ちてしまうことがあるかもしれません。
そのような場合は、もう一度数字を戻すためにA/Bテストをやり直すということも大切です。
過去の結果に捉われず、柔軟な思考をもってテストを行い続けていくことでECサイトの改善を目指しましょう。