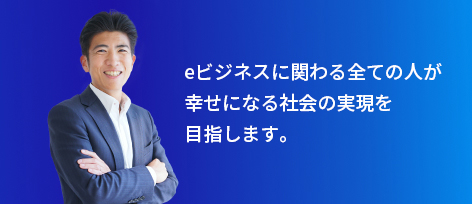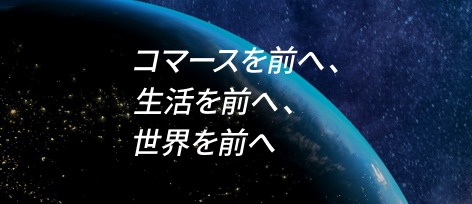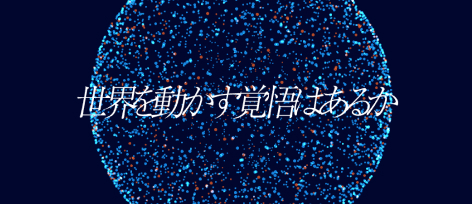【勉強期間1か月!】基本情報技術者試験(FE)に独学で合格する方法
1. IT知識ゼロからのスタート
はじめまして!W2で長期インターンをしている横江です。
私は2022年11月に受験した基本情報技術者試験(FE)において、
「科目A試験(午前)が81%」「科目B試験(午後)が84%」で合格することができました。
※合格基準:科目AB(午前午後)ともに60%以上
私の場合、過去にITパスポートは取得していましたが
その知識もほとんど抜け落ちていて、実務で触れることもほぼなかったため
「ゼロからのスタート」 と言っても差し支えないほどでした。
初めて過去問を解いてみたときには、「こんなの無理すぎる…やめよ」と感じるレベルでした。
そんな私が、今回は1か月という短期間で、合格できたポイントを解説したいと思います。
2. 基本情報技術者試験を取得するメリット
まず基本情報技術者試験とは、ICTや情報処理分野の国家資格の一つで、
「情報処理技術者試験」の区分のひとつです。
試験ではシステムの開発・運用・設計など、IT全般の知識が問われます。
この資格を受験するメリットとしては、以下のようなものがあります。
① IT技術者としての基本が身につく!
学習を通じて情報処理分野のみならず、ビジネスパーソンとして必要な知識を体系的に身につけることができます。
IT人材としてだけではなく、ビジネスパーソンとしてのレベルアップも図れます!
② IT系の業種への就職が有利に!
基本情報技術者試験に合格していれば、一定の知識があることを国家資格として証明できるので就職にも有利になる可能性が高いです。
IT業界を目指す方にとっては、情報処理分野に興味があり、一定の勉強をしてきたアピールにもなります。
③ 企業から資格手当がもらえることもある!
企業によっては、合格者に資格手当を支給する場合があります。
資格手当は、試験学習において、大きなモチベーションにもつながります。
3. 基本情報技術者試験を受験した理由
僕が基本情報技術者試験を受験した理由は以下の2つです。
① 幅広いIT知識をつけたい
「この用語ってどういう意味だろう?」
「ここの仕組みってどうなっているの?」
と日々の業務の中で思うことが多く、業務を中断して調べることが多々ありました。
この先IT業界で働いていく上では、IT分野における網羅的な知識が必要だなと感じていました。
② 技術に強い総合職に憧れがあった
IT業界といっても、ビジネスサイドにはITリテラシーの高くない方も一定数います。
そんな中で「技術に強い総合職」ってかっこよくないですか?笑
ITに強い人材という肩書きにずっと憧れがあったこともあり、受験を決意しました。
4. 学習の進め方とオススメの選択問題
●学習時間
2023年10月に試験申し込みをして、一か月後に本試験というスケジュールでした。
短期間での挑戦だったので、細かいところまで突き詰めるというよりは、
「広く知識をインプットして、試験問題に合わせてそれをアウトプットできる状態」
を目指して勉強を進めました。
1か月という短期間でも、効率的に学習を進めれば、十分に合格ラインに到達することができます。
ここからは、短期間で合格できた学習方法について解説します。
学習の期間としては、科目A/科目B(午前/午後)それぞれ2週間ずつとって
幅広く範囲を網羅できるように参考書とネットを組み合わせて学習しました。
時間も「空き時間を見つけては学習」というスタイルにして、
「1日●時間!」と決め打ちせずに、結果的に多くの時間を取れるように日々のスケジュール調整をしました。
●科目A(午前)試験対策
結論、科目A(午前)試験は「過去問を周回する」につきます。
基礎的な知識をインプットする、出題形式に慣れる、
出題傾向を知るためにも、過去問を解くことが合格への近道になります。
ここで、過去問を解く中で私が意識していたのは、
「なぜこの選択肢が正解なのか」
というところまで理解するということです。
鬼門と言われている科目B(午後)試験においても、
科目A(午前)試験で問われるような基礎的な知識をベースに問題が作成されています。
「なんとなく正解できる状態」
では不十分で、正解の背景にある構造や仕組みまで理解することが、
科目B(午後)試験対策をスムーズに進めるためにも必要になってきます。
●科目B(午後)試験対策
科目B(午後試験)は、出題される11問のうち
情報セキュリティに関する1問とデータ構造及びアルゴリズムに関する1問は必須解答問題となります。
そのため、残りの9問から3問を選んで解答する形になります。
私が選択した問題は以下のとおりです。
・情報セキュリティ(必須回答)
・データ構造及びアルゴリズム(必須回答)
・ソフトウェア・ハードウェア
・データベース
・ソフトウェア問題(表計算)
科目B(午後)試験対策においても、
結論「過去問を周回する」につきます。
過去問を解いていると気づくことだとは思いますが、
各設問出題パターンは5つほどしかなく、過去問と類似した問題が出題されることになります。
「問題を読んで解法を思い出せる状態」
を目指して、苦手分野を重点的に解きまくりましょう。
また、選択問題に関してですが、IT未経験で挑戦するのであれば、
私も選択した以下の3分野がオススメです。
① ソフトウェア・ハードウェア
この分野は問題文の中に答えが隠されていて、それを読解していくような問題構成になっています。
正直なところ文章読解の問題なので、IT未経験者でも比較的簡単に解くことができます。
② データベース
他分野と比べると問題パターンが非常に少なく、毎回似たような問題が頻出しています。
過去問周回数と得点率が比例しやすい分野です。
③ ソフトウェア問題(表計算)
Excelに関する知識で解くことができます。
「垂直照合」「表引き」などのいくつかの関数を覚えておくことで、
ある程度の問題に対応することができます。
5. 学習に使用した教材/サイト
私が試験対策で使用した教材は以下の一冊のみです。
ニュースペックテキスト 基本情報技術者 2023年度 [科目A 科目B 一冊でしっかり対策!](TAC出版)
文字数が比較的少なく、イラスト多めで読みやすいです。
使い方としては、過去問に取り組む前に知識のインプットのために一読して、
その後は過去問を解いていて分からない単語、概念が出てきたら都度ネットで調べる
といったように、辞書代わりに使っていました。
上記の教材と併せて、以下のサイトも非常に参考になりました。
「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典
こちらのサイトでは、複雑な概念や構造を平易な表現で解説してくれたり、
身近な例で分かりやすく解説してくれています。
IT知識ほぼゼロの状態から始める方にとっては、学習の入り口として非常に参考になるはずです。
最後に、試験の過去問は以下のサイトで確認することができます。
科目A(午前)試験、科目B(午後)試験ともに問題と解答、解説がセットになっているので、
効率的に学習を進めることができました。
6. これから受験する皆さんへ
今回は基本情報技術者試験の短期間で合格する方法について解説しました。
1か月で合格!とは言いつつも、試験が近づくにつれて
「もっと早くから取り組んでいれば…」
と思うことが何度もあったので、早め早めの試験対策をお勧めします。
基本情報技術者試験は適切に対策すれば、必ず合格できる資格です。
選択式の回答なので、諦めなければラッキーパンチで合格することもできるかもしれません。
また、試験時間に関しては科目A(午前)が90分、科目Bが100分と長丁場になるため、
集中力を切らさないと練習も事前に取り組んでおくことが必要です。
試験当日まで何が起こるか分からないので、ぜひ諦めずに頑張ってください!